гӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮў
гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўжӨҚж°‘ең°пјҲгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ—гӮҮгҒҸгҒҝгӮ“гҒЎгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўиӘһ: Colonia EritreaпјүгҒҜгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўзҺӢеӣҪгҒҢзҸҫеңЁгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ«жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹжӨҚж°‘ең°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1869е№ҙгҒ«гғ«гғҗгғғгғҶгӮЈгғјгғҺжө·йҒӢдјҡзӨҫгҒҢгӮўгғғгӮөгғ–гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®жңҖеҲқгҒ®йҖІеҮәгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ1882е№ҙгҒ«гҒҜж”ҝеәңгҒ®з®ЎзҗҶдёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹгҖӮ1885е№ҙгҒ«гғһгғғгӮөгғҜгӮ’еҚ й ҳгҒ—гҒҰд»ҘйҷҚеҫҗгҖ…гҒ«й ҳеңҹгӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҖҒ1889е№ҙгҒ«гҒҜгӮҰгғғгғҒгғЈгғӘжқЎзҙ„гҒ§гӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўеёқеӣҪгҒЁгҒ®еӣҪеўғгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒ1890е№ҙгҒ«гҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўжӨҚж°‘ең°гҒҢжӯЈејҸгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ 1936е№ҙгҖҒгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўз·ҸзқЈеәңгҒЁгҒ—гҒҰгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳжқұгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ«зөұеҗҲгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒҜгҖҒ1941е№ҙгҒ«з¬¬дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ®жқұгӮўгғ•гғӘгӮ«жҲҰз·ҡгҒ§гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҢгҒ“гҒ®ең°еҹҹгӮ’еӨұгҒҶгҒҫгҒ§з¶ҡгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒҜгӮӨгӮ®гғӘгӮ№и»ҚгҒ®зөұжІ»дёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҖҒ1951е№ҙгҒ«гҒҜеӣҪйҡӣйҖЈеҗҲгҒ®зӣЈзқЈдёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹгҖӮ1952е№ҙ9жңҲгҒ«гӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®иҮӘжІ»й ҳгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ1991е№ҙгҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгҖӮ жӯҙеҸІгӮўгғғгӮөгғ–гҒ®зҚІеҫ—гҒЁжӨҚж°‘ең°гҒ®иЁӯз«ӢвҶ’и©ізҙ°гҒҜгҖҢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўжҲҰдәүгҖҚгӮ’еҸӮз…§
 зҙ…жө·гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәӢжҘӯгҒ®еҲқжңҹгҒ®жӯҙеҸІгӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢдәәзү©гҒҢгӮёгғҘгӮјгғғгғҡгғ»гӮөгғҡгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜиӢҘгҒ„дҝ®йҒ“еЈ«гҒ§гҖҒгӮ«гӮӨгғӯгҒ§еёғж•ҷгҒ®жә–еӮҷгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒ1837е№ҙгҒ«гӮўгғ“гӮ·гғӢгӮўгҒ«жҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒз©ҚжҘөзҡ„гҒ«гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒёгҒ®йҖІеҮәгӮ’дё»ејөгҒ—гҖҒеҪ“еҲқгҒҜгғ•гғ©гғігӮ№дәәгҒ®йҖІеҮәгӮ’еӢ§гӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҢзөұдёҖгҒ•гӮҢгҒҹ1866е№ҙд»ҘйҷҚгҒҜгҖҒд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹгҖӮгӮ№гӮЁгӮәйҒӢжІігҒ®е®ҢжҲҗгҒҢиҝ‘гҒҘгҒҸгҒЁгҖҒеҪјгҒҜзҙ…жө·гҒ«гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®и’ёж°—иҲ№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зөҰжІ№жүҖгҒЁеҜ„жёҜең°гӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж§ӢжғігҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгӮөгғҡгғҲгҒҜгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўеӨ–еӢҷеӨ§иҮЈгӮ„еӣҪзҺӢгғҙгӮЈгғғгғҲгғјгғӘгӮӘгғ»гӮЁгғһгғҢгӮЁгғјгғ¬2дё–гӮ’еҸ–гӮҠиҫјгҒҝгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®иҖғгҒҲгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгҖӮ  1869е№ҙгҒ®з§ӢгҖҒеҪјгҒҜгӮўгӮҜгғҲгғіжҸҗзқЈгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ж”ҝеәңгҒӢгӮүзҙ…жө·гҒ«жҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘжёҜгӮ’йҒёгҒігҖҒгҒқгҒ®еЈІеҚҙгҒ®жүӢй…ҚгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҪјгҒҜгҖҒгӮўгғғгӮөгғ–ж№ҫгҒ®гғҖгғҠгӮӯгғ«ж—ҸгҒ®йҰ–й•·гҒ«е°‘йЎҚгҒ®дҝқиЁјйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒ„гҖҒгҒқгҒ®иҰӢиҝ”гӮҠгҒЁгҒ—гҒҰеё°еӣҪеҫҢгҒ«й ҳеңҹгӮ’еЈІеҚҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҙ„жқҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ“гӮҢгӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҖж–№гҖҒж”ҝеәңгҒҜгғ©гғ•гӮЎгӮЁгғ¬гғ»гғ«гғҗгғғгғҶгӮЈгғјгғҺгҒЁйҖЈзөЎгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҪјгҒ®дјҡзӨҫгҒҜгҖҒж–°гҒ—гҒҸй–ӢйҖҡгҒ—гҒҹгӮ№гӮЁгӮәйҒӢжІігҒЁзҙ…жө·гӮ’йҖҡгҒЈгҒҰгӮӨгғігғүгҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶи’ёж°—иҲ№и·Ҝз·ҡгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁиЁҲз”»гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгғ«гғҗгғғгғҶгӮЈгғјгғҺзӨҫгҒҢиҮӘеӣҪеҗҚгҒЁиҮӘеӣҪиіҮйҮ‘гҒ§й ҳеңҹгӮ’иіје…ҘгҒ—гҖҒеӣҪзӣҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҗҲж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгӮөгғҡгғҲгҒҜдјҡзӨҫгӮ’д»ЈиЎЁгҒ—гҒҰзҙ…жө·гҒ«жҲ»гӮҠгҖҒиіје…ҘгӮ’е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еҚ—еҒҙгҒ®еңҹең°гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹгҖӮ 1870е№ҙ3жңҲгҒҫгҒ§гҒ«гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®иҲ№дјҡзӨҫгҒҜгҖҒеҢ—гҒ®гӮўгғҚгӮ№гғ¬гғјж№ҫгҒЁеҚ—гҒ®гӮӘгғңгғғгӮҜгҒ®гҒ»гҒјдёӯй–“гҒ«гҒӮгӮӢгҖҒгҒ•гҒігӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢеәғгҒ„гӮўгғғгӮөгғ–ж№ҫгҒ®еҢ—з«ҜгӮ’й ҳжңүгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹ[1]гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒҜгӮӘгӮ№гғһгғіеёқеӣҪгҒЁгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ«ж”Ҝй…ҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒ[2]гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҢе…ҘжӨҚгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜ1880е№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮгҒқгҒ®2е№ҙеҫҢгҖҒе•ҶжҘӯзҡ„гҒӘжүҖжңүиҖ…гҒ«гҒҷгҒҺгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–°иҲҲгҒ®жӨҚж°‘ең°гӮ’жӯЈејҸгҒ«жүҖжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ зҙ…жө·гҒ®иҘҝжө·еІёгҒ®еӨ§йғЁеҲҶгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгӮЁгӮёгғ—гғҲеүҜзҺӢй ҳпјҲжқұеІёгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӘгӮ№гғһгғіеёқеӣҪгҒ®жғіе®ҡзөұжІ»дёӢпјүгҒҢжӯЈејҸгҒ«й ҳжңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгғ»гӮЁгӮёгғ—гғҲжҲҰдәүгҒ§гҒ®гӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®еӨ§ж•—гҒЁгӮ№гғјгғҖгғігҒ®гғһгғ•гғҮгӮЈгғјгҒ®еҸҚд№ұгҒ®жҲҗеҠҹгҒ«гӮҲгӮҠгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒҜж··д№ұгҒ«йҷҘгҒЈгҒҹгҖӮ1884е№ҙгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®гӮўгғүгғҜжқЎзҙ„гҒҜгҖҒзҡҮеёқгғЁгғҸгғігғҚгӮ№4дё–гҒҢгӮ№гғјгғҖгғігҒӢгӮүи»ҚйҡҠгӮ’ж’ӨйҖҖгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жқЎд»¶гҒ«гҖҒгғңгӮҙгӮ№пјҲзҸҫеңЁгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўй«ҳең°пјүгҒЁгғһгӮөгғҜгғіжө·еІёгҒёгҒ®иҮӘз”ұгҒӘгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гӮ’зҙ„жқҹгҒ—гҒҹ[4]гҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®еӨ–дәӨе®ҳгҒҜгҖҒгӮҝгӮёгғҘгғ©ж№ҫжІҝгҒ„гҒ®гғ•гғ©гғігӮ№жӨҚж°‘ең°гҒ§гҒӮгӮӢгғ•гғ©гғігӮ№й ҳгӮҪгғһгғӘгғ©гғігғүгҒҢгӮЁгӮёгғ—гғҲж’ӨйҖҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ§гҒҚгҒҹз©әзҷҪең°еёҜгҒ«жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҮёеҝөгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒЁгҒ®жқЎзҙ„гӮ’з„ЎиҰ–гҒ—гҖҒ公然гҒЁгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®еҢ—ж–№йҖІеҮәгӮ’дҝғгҒ—гҖҒгғһгғғгӮөгғҜгҒҜгӮЁгӮёгғ—гғҲи»ҚгҒ«дёҖзҷәгӮӮзҷәз ІгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸеҚ й ҳгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзңҹзҸ гҒ®еҘҪжјҒе ҙгҒ«еӣІгҒҫгӮҢгҒҹзҸҠз‘ҡзӨҒгҒ®еі¶гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒ®е„ӘгӮҢгҒҹжёҜгҒҜ[5][6]гҖҒиҰҒеЎһеҢ–гҒ•гӮҢгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўз·ҸзқЈгҒ®йҰ–йғҪгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹ[5]гҖӮдёҖж–№гҖҒгӮўгғғгӮөгғ–гҒҜеј•гҒҚз¶ҡгҒҚзөҰжІ№жүҖгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹ[7]гҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҜгӮўгғүгғҜжқЎзҙ„гҒ«еҠ зӣҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒзӣҙгҒЎгҒ«жӯҰеҷЁијёйҖҒгҒ®еҲ¶йҷҗгҒЁгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўиЈҪе“ҒгҒёгҒ®й–ўзЁҺгҒ®иіҰиӘІгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҖӮ 1889е№ҙгҒ®зҡҮеёқгғЁгғҸгғігғҚгӮ№4дё–гҒ®жӯ»еҺ»гҒ«дјҙгҒҶж··д№ұгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгӮӘгғ¬гӮ№гғҶгғ»гғҗгғ©гғҶгӮЈгӮЁгғӘе°Ҷи»ҚгҒҢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўжІҝеІёгҒ®й«ҳең°гӮ’еҚ й ҳгҒ—гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҜгғһгӮөгғҜгҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰгӮўгӮ№гғһгғ©гӮ’йҰ–йғҪгҒЁгҒҷгӮӢж–°жӨҚж°‘ең°гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўпјҲзҙ…жө·гҒ®гғ©гғҶгғіиӘһеҗҚгҒӢгӮүпјүгҒ®иЁӯз«ӢгӮ’е®ЈиЁҖгҒ—гҒҹгҖӮ еҗҢе№ҙиӘҝеҚ°гҒ•гӮҢгҒҹгӮҰгғғгғҒгғЈгғ¬жқЎзҙ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҚ—йғЁгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўзҺӢеӣҪгӮ·гӮ§гғҜгҒ®гғЎгғҚгғӘгӮҜ2дё–гҒҜгҖҒиІЎж”ҝжҸҙеҠ©гҒ®дҝқиЁјгҒЁгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®жӯҰеҷЁгғ»ејҫи–¬гҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„е…ҘжүӢгӮ’еј•гҒҚжҸӣгҒҲгҒ«гҖҒгғ©гӮӨгғҗгғ«гҒ§гҒӮгӮӢгғңгӮҙгӮ№гҖҒгғҸгғһгӮ·гӮўгғігҖҒгӮўгғғгӮұгғ¬гӮ°гӮ¶гӮӨгҖҒгӮ»гғ©гӮӨгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ«гӮҲгӮӢеҚ й ҳгӮ’жүҝиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғЎгғҚгғӘгӮҜ2дё–пјҲеңЁдҪҚ1889гҖң1913е№ҙпјүгҒҢгғ©гӮӨгғҗгғ«гҒ®еӣҪзҺӢгҒ«еӢқеҲ©гҒ—гҖҒзҡҮеёқгҒ«еҚідҪҚгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жқЎзҙ„гҒҜжӯЈејҸгҒ«еӣҪе…ЁдҪ“гӮ’жӢҳжқҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиЁӯз«Ӣд»ҘжқҘгғЎгғҚгғӘгӮҜгҒҜеҢ—йғЁгҒ®гғҶгӮЈгӮ°гғ©гӮӨе·һгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒ®й–ўдёҺгҒ«еҗҰе®ҡзҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[8]гҖӮдёҖж–№гӮӨгӮҝгғӘгӮўеҒҙгҒҜгҖҒгғҶгӮЈгӮ°гғ©гӮӨдәәгҒҢжӨҚж°‘ең°гҒ®дҝқиӯ·й ҳеҶ…гҒ®йғЁж—ҸгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«иҘІж’ғгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒй–ўдёҺгҒӣгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲ[6]гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҶгӮЈгӮ°гғ©гӮӨдәәгҒ®жҢҮе°ҺиҖ…гҒҜгҖҒзҸҫеңЁгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®й ҳең°гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе·һгҒ®й ҳжңүгӮ’дё»ејөгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ®дёӯгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№гҒЁгҒ®йү„йҒ“е»әиЁӯдәӨжёүгҒҜдәӢж…ӢгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸйҖІеұ•гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўиӘһзүҲпјҲгӮўгғ гғҸгғ©иӘһзүҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„пјүгҒ®гӮҰгғғгғҒгғЈгғ¬жқЎзҙ„гҒ§гҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӨгӮҝгғӘгӮўгӮ’йҖҡгҒ•гҒӘгҒ„еӨ–еӣҪгҒЁгҒ®дәӨжёүгӮ’зҰҒжӯўгҒ—гҖҒдәӢе®ҹдёҠгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгӮ’гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®дҝқиӯ·й ҳгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮеӣҪеҶ…зҡ„гҒ«гӮӮи»ҚдәӢзҡ„гҒ«гӮӮе®үе®ҡгҒ—гҒҹгғЎгғҚгғӘгӮҜгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жқЎзҙ„гӮ’е…Ёйқўзҡ„гҒ«з ҙжЈ„гҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҜгӮўгғүгғҜжҲҰдәүгҒ§жғЁж•—гҒ—гҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўдҪөеҗҲгҒ®жңӣгҒҝгҒҜдёҖж—Ұзө¶гҒҹгӮҢгҒҹгҖӮ 20дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҖҒгӮўгғғгӮөгғ–гҒҜгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®дё»иҰҒжёҜгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒиҝ‘йҡЈгҒ®гӮёгғ–гғҒгҒҢйү„йҒ“пјҲ1902е№ҙгҒ«гғҮгӮЈгғ¬гғ»гғҖгғҜгҒҫгҒ§е®ҢжҲҗпјүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгӮўгғғгӮөгғ–[6]гӮ„гӮјгӮӨгғ©гҒёгҒ®еҫ“жқҘгҒ®гӮӯгғЈгғ©гғҗгғіиҲӘи·ҜгҒ«еҸ–гҒЈгҒҰд»ЈгӮҸгӮҠгҖҒй•·гҒ„й–“еҪұгӮ’жҪңгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹ[9][10][11]гҖӮгғһгғғгӮөгғҜгҒҜдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўеҢ—йғЁгҒ®дё»иҰҒжёҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжҜ”ијғзҡ„й«ҳгҒ„й–ўзЁҺгҖҒгӮӯгғЈгғ©гғҗгғігҒёгҒ®дҫқеӯҳгҖҒж”ҝжІ»зҡ„еҜҫз«ӢгҒӢгӮүгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒЁгҒ®иІҝжҳ“йҮҸгҒҜйҷҗгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[6]гҖӮ гӮӨгӮҝгғӘгӮўж”ҝеәңгҒҜиҮӘеӣҪгҒ®еңҹең°гҒ®й–ӢзҷәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒ1880е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҒ«ж–°жӨҚж°‘ең°гҒ§гҒ®жңҖеҲқгҒ®й–ӢзҷәдәӢжҘӯгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҖӮ1888е№ҙгҒ«гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўйү„йҒ“гҒҢгӮөгғјгғҶгӮЈгҒҫгҒ§е®ҢжҲҗгҒ—[12]гҖҒ1911е№ҙгҒ«гҒҜй«ҳең°гҒ®гӮўгӮ№гғһгғ©гҒ«еҲ°йҒ”гҒ—гҒҹ[13]гҖӮ  гӮўгӮ№гғһгғ©-гғһгғғгӮөгғҜй–“гҒ®зҙўйҒ“пјҲ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ§гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒҢжҲҰдәүиі е„ҹйҮ‘гҒЁгҒ—гҒҰи§ЈдҪ“пјүгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮдё–з•ҢжңҖй•·гҒ®и·Ҝз·ҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ«гӮҲгӮӢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўзөұжІ»гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўзӨҫдјҡгҒ®еҢ»зҷӮгҒЁиҫІжҘӯгҒ®еҲҶйҮҺгҒ«гӮӮж”№е–„гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹгҖӮдәәзЁ®е·®еҲҘжі•гҒ®ж–ҪиЎҢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒйғҪеёӮйғЁгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒҜгҒҝгҒӘиҝ‘д»Јзҡ„гҒӘиЎӣз”ҹиЁӯеӮҷгҒЁз—…йҷўгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҜзҸҫең°гҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгӮ’иӯҰеҜҹгӮ„е…¬е…ұдәӢжҘӯгҒӘгҒ©гҒ®е…¬еӢҷгҒ«еҫ“дәӢгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮж–ҮеҢ–зҡ„гҖҒиЁҖиӘһзҡ„гҖҒе®—ж•ҷзҡ„гҒӘеӨҡж§ҳжҖ§гӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәз·ҸзқЈгҒҜзӣёж¬ЎгҒ„гҒ§зөұдёҖгҒЁе…¬гҒ®з§©еәҸгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҒҹгҖӮ гҒӮгҒҫгӮҠзҷәеұ•гҒ—гҒҰгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳгӮҪгғһгғӘгғ©гғігғүгӮ„гғӘгғ“гӮўгҒЁеҜҫз…§зҡ„гҒ«гҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒҜгӮігғӯгғӢгӮўгғ»гғ—гғӘгғўгӮёгӮ§гғӢгӮҝпјҲгҖҢжңҖеҲқгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹжӨҚж°‘ең°гҖҚпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢ[14]гҖҒд»–гҒ®еңҹең°гӮҲгӮҠгӮӮеӨҡгҒҸгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәе…ҘжӨҚиҖ…гӮ’иӘҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ20дё–зҙҖеҲқй ӯгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўж”ҝеәңгҒ®жҸҙеҠ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжңҖеҲқгҒ®ж•°еҚҒ家ж—ҸгҒҢгӮўгӮ№гғһгғ©гӮ„гғһгғғгӮөгғҜе‘ЁиҫәгҒ«е®ҡдҪҸгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҖҒ第дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰдёӯгҒ«гҒҜ4,000дәәзЁӢеәҰгҒ гҒЈгҒҹгӮӨгӮҝгғӘгӮўзі»гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒҜгҖҒ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҪ“еҲқгҒ«гҒҜ10дёҮдәәиҝ‘гҒҸгҒҫгҒ§жӢЎеӨ§гҒ—гҒҹ[15]гҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҜгӮӨгӮ№гғ©гғ ж•ҷгҒ®дҝЎд»°гӮ’е®№иӘҚгҒҷгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜгҒ®еӨ§жӢЎејөгӮ’ж”ҜжҢҒгҒ—гҖҒйҰ–йғҪгҒ®гғӯгӮ¶гғӘгӮӘгҒ®иҒ–жҜҚж•ҷдјҡгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒгӮўгӮ№гғһгғ©гӮ„гӮұгғ¬гғіе‘ЁиҫәгҒ®й«ҳең°гҒ«еӨҡгҒҸгҒ®ж•ҷдјҡгӮ’е»әгҒҰгҒҹгҖӮ 1940е№ҙд»ЈеҲқй ӯгҒ«гҒҜгҖҒгӮ«гғҲгғӘгғғгӮҜгҒҜжӨҚж°‘ең°гҒ®дәәеҸЈгҒ®зҙ„28пј…гҖҒгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгҒҜеҚҠж•°д»ҘдёҠгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®е®—ж•ҷгҒЁгҒ—гҒҰе…¬иӘҚгҒ•гӮҢгҒҹ[16][17]гҖӮ гғ•гӮЎгӮ·гӮ№гғҲжҷӮд»Ј   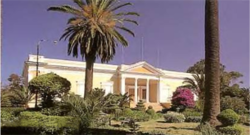 1922е№ҙгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ§гғҷгғӢгғјгғҲгғ»гғ гғғгӮҪгғӘгғјгғӢгҒҢжЁ©еҠӣгӮ’жҸЎгӮӢгҒЁгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®жӨҚж°‘ең°ж”ҝеәңгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҹгҖӮ1936е№ҙ5жңҲгҒ«гғүгӮҘгғјгғҒгӮ§гҒҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўеёқеӣҪгҒ®иӘ•з”ҹгӮ’е®ЈиЁҖгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒЁгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳгӮҪгғһгғӘгғ©гғігғүгҒҜгҖҒеҫҒжңҚгҒ—гҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®гӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒЁеҗҲдҪөгҒ—гҒҰгҖҒж–°гҒҹгҒ«гӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳжқұгӮўгғ•гғӘгӮ«пјҲAfrica Orientale ItalianaпјүгҒ®иЎҢж”ҝеҢәеҹҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғ•гӮЎгӮ·гӮ№гғҲжҷӮд»ЈгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒгҖҢж–°гғӯгғјгғһеёқеӣҪгҖҚгҒ®еҗҚгҒ®дёӢгҒ«еёқеӣҪгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўж”ҝеәңгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳжқұгӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®е·ҘжҘӯгҒ®дёӯеҝғең°гҒЁгҒ—гҒҰйҒёгҒ°гӮҢгҒҹ[18]гҖӮ
гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®йҰ–йғҪгҒ®дәәеҸЈгҒҜеӨ§е№…гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҹгҖӮ1935е№ҙгҒ«гҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҢ4,000дәәгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒҢ12,000дәәгҒ—гҒӢгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ1938е№ҙгҒ«гҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҢ48,000дәәгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒҢ36,000дәәгҒ«гҒҫгҒ§еў—гҒҲгҒҹгҖӮжӯҙеҸІе®¶гҒ®гӮёгғЈгғігғ»гғ«гӮ«гғ»гғқгғҮгӮ№гӮҝгҒҜгҖҒгҖҢгӮўгӮ№гғһгғ©гҒҜе®ҹиіӘзҡ„гҒ«гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®йғҪеёӮгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹпјҲ"in pratica Asmara era diventata una citta' italiana"пјүгҖҚгҒЁиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[20]гҖӮ гӮӨгӮҝгғӘгӮўж”ҝеәңгҒҜиҫІжҘӯж”№йқ©гӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдё»гҒ«гӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәе…ҘжӨҚиҖ…гҒҢжүҖжңүгҒҷгӮӢиҫІе ҙгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹпјҲ1930е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜгӮігғјгғ’гғјгҒ®ијёеҮәгҒҢеҘҪиӘҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјүгҖӮгӮўгӮ№гғһгғ©е‘ЁиҫәгҒ«гҒҜгҖҒ1940е№ҙжҷӮзӮ№гҒ§2,000зӨҫд»ҘдёҠгҒ®дёӯе°Ҹе·ҘжҘӯдјҡзӨҫгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе»әиЁӯгҖҒж©ҹжў°гҖҒз№Ҡз¶ӯгҖҒйЈҹе“ҒеҠ е·ҘгҖҒйӣ»ж°—гҒӘгҒ©гҒ®еҲҶйҮҺгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒ1939е№ҙгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®з”ҹжҙ»гҒҜгҖҒең°е…ғгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒЁгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәе…ҘжӨҚиҖ…гҒ®еҸҢж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгӮўгғ•гғӘгӮ«еӨ§йҷёгҒ§жңҖгӮӮиүҜгҒ„ж°ҙжә–гҒ«йҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[21]гҖӮ гғ гғғгӮҪгғӘгғјгғӢж”ҝжЁ©гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгӮ’е°ҶжқҘгҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘжӢ зӮ№гҒЁиҖғгҒҲгҖҒ1935е№ҙгҒӢгӮү1936е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®еҫҒжңҚгҒЁжӨҚж°‘ең°еҢ–гӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жӢ зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҖӮ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ§гӮӮгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒӢгӮүгӮ№гғјгғҖгғігӮ’ж”»ж’ғгҒ—гҖҒгӮ«гғғгӮөгғ©ең°ж–№гӮ’еҚ й ҳгҒ—гҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®жӨҚж°‘ең°и»ҚгҒ§жңҖгӮӮе„Әз§ҖгҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®гӮўгӮ№гӮ«гғӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гғӯгғүгғ«гғ•гӮ©гғ»гӮ°гғ©гғ„гӮЈгӮўгғјгғӢгӮ„дјқиӘ¬гҒ®еЈ«е®ҳгӮўгғЎгғҮгӮӘгғ»гӮ®гғ¬гҒҜиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢ[22]гҖӮгҒ•гӮүгҒ«з¬¬дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҖҒгӮўгӮ№гӮ«гғӘгҒёгҒ®еҫ“и»ҚгҒҜгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўй ҳгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®е…ҲдҪҸж°‘з”·жҖ§гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдё»гҒӘжңүзөҰйӣҮз”ЁгҒ®жәҗгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ1936е№ҙгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўи»ҚгҒ®гӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўдҫөж”»гҒ«дјҙгҒҶи»ҚеӮҷжӢЎејөгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®40%гҒҢгҒ“гҒ®жӨҚж°‘ең°и»ҚгҒ«е…ҘйҡҠгҒ—гҒҹ[23]гҖӮ 1939е№ҙгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®еӣҪеӢўиӘҝжҹ»гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгӮўгӮ№гғһгғ©еёӮгҒ®дәәеҸЈгҒҜ98,000дәәгҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎ53,000дәәгҒҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢе®ҹгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮўгӮ№гғһгғ©гҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўеёқеӣҪгҒ®гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё»иҰҒгҒӘгҖҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәиЎ—гҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮўгӮ№гғһгғ©гҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўйўЁе»әзҜүгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҖҢгғ”гғғгӮігғ©гғ»гғӯгғјгғһпјҲе°ҸгҒ•гҒӘгғӯгғјгғһпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹ[24]гҖӮгҒ“гҒ®е№ҙгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўе…ЁеңҹгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒ®з·Ҹж•°гҒҜ7дёҮ5еҚғдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[25]гҖӮ гӮўгӮ№гғһгғ©гҒҜгҖҒе»әзҜүзү©гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒйғҪеёӮе»әиЁӯжҷӮгҒ«гғӯгғјгғһгӮҲгӮҠгӮӮеӨҡгҒҸгҒ®дҝЎеҸ·ж©ҹгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒдҫӢеӨ–зҡ„гҒ«иҝ‘д»Јзҡ„гҒӘйғҪеёӮгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮиЁҲз”»йғҪеёӮгҒ®зү№еҫҙгӮ’еӨҡгҒҸеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹйғҪеёӮгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгӮ№гғһгғ©гҒҜгҖҒе»әзҜү家гҒ«гӮҲгӮӢзҗҶжғізҡ„гҒӘиҝ‘д»ЈйғҪеёӮгӮ’гҒ„гҒЎж—©гҒҸе®ҹзҸҫгҒ—гҖҒгғ–гғ©гӮёгғӘгӮўгҒӘгҒ©дё–з•ҢгҒ®еӨҡгҒҸгҒ®йғҪеёӮгҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒе®Ңе…ЁгҒӘжҷ®еҸҠгҒ«гҒҜгҒ„гҒҹгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®зү№еҫҙгҒҜгҖҒйғҪеёӮиЁҲз”»гҖҒеәғгҒ„дёҰжңЁйҒ“гҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒӘең°еҹҹгҒЁзү№еҢәгҖҒзҷәеұ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з©әй–“гҒЁзҜ„еӣІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгӮ№гғһгғ©гҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е»әиЁӯгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҢиҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«е»әиЁӯгҒ—гҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®гӮ«гғјгғ¬гғјгӮ№пјҲгӮўгӮ№гғһгғ©гӮөгғјгӮӯгғғгғҲпјүгӮ’й–ӢеӮ¬гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгӮүгҒ—гҒ„йғҪеёӮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ е»әзҜүзү©гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеәғгҒ„иЎ—и·ҜгӮ„еәғе ҙгҖҒгӮігғјгғ’гғјгғҗгғјгҒӘгҒ©гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®зңҹй«„гӮ’ж„ҹгҒҳгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒ®иЎ—гҒҜгҖҒгҖҢж–°гғӯгғјгғһгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӨгӮ·гҒ®жңЁгӮ„гӮ·гғҗгҒ®жңЁгҒҢдёҰгҒ¶еӨ§йҖҡгӮҠгҒ«гҒҜгҖҒгғ”гғғгғ„гӮ§гғӘгӮўгӮ„гӮ«гғ—гғҒгғјгғҺгӮ„гғ©гғҶгҒ®гӮігғјгғ’гғјгғҗгғјгҖҒгӮўгӮӨгӮ№гӮҜгғӘгғјгғ гғ‘гғјгғ©гғјгҒӘгҒ©гҒҢж•°еӨҡгҒҸз«ӢгҒЎдёҰгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гӮўгӮ№гғһгғ©гӮ„гғһгғғгӮөгғҜе‘ЁиҫәгҒ§гҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒ®жҺЁиіһгҒ«гӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®е·ҘжҘӯжҠ•иіҮгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®е·ҘжҘӯеҢ–гҒ®й–ӢиҠұгҒҜгӮ№гғҲгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹ[26]гҖӮ гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢи»Қж”ҝгҒЁжӨҚж°‘ең°гҒ®зөӮдәҶ
1941е№ҙ1жңҲгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№и»ҚгҒҢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгӮ’еҫҒжңҚгҒ—гҒҹйҡӣгҖҒгӮӨгғігғ•гғ©гӮ„е·ҘжҘӯең°еёҜгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҢи‘—гҒ—гҒҸжҗҚеӮ·гҒ—гҖҒж®ӢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®пјҲгӮўгӮ№гғһгғ©-гғһгӮөгғҜзҙўйҒ“гҒӘгҒ©пјүгҒҜжҲҰеҲ©е“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгӮӨгғігғүгӮ„гӮўгғ•гғӘгӮ«гҒ®гӮӨгӮ®гғӘгӮ№й ҳгҒ®ж–№гҒёй Ҷж¬Ўж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ з¶ҡгҒҸгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гӮІгғӘгғ©жҲҰгҒҜгҖҒ1943е№ҙ9жңҲгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўи»Қдј‘жҲҰгҒҫгҒ§гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўжӨҚж°‘ең°и»ҚпјҲгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўзӢ¬з«ӢгҒ®гҖҢиӢұйӣ„гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгғҸгғҹгғүгғ»гӮӨгғүгғӘгғјгӮ№гғ»гӮўгғҜгғҶгҒӘгҒ©пјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж”ҜжҸҙгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ§гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҢйҷҚдјҸгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒҜгӮӨгӮ®гғӘгӮ№и»ҚгҒ®зөұжІ»дёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгҒҹгҖӮ гӮӨгӮҝгғӘгӮўзҺӢеӣҪгҒҢйҖЈеҗҲеӣҪгҒ«ж•—еҢ—гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒҜеӣҪеӨ–гҒ«з§»дҪҸгҒ—е§ӢгӮҒгҖҒ1949е№ҙгҒ®гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®еӣҪеӢўиӘҝжҹ»гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгӮўгӮ№гғһгғ©гҒ®з·ҸдәәеҸЈ127,579дәәгҒ®гҒҶгҒЎгӮӨгӮҝгғӘгӮўзі»гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒҜгӮҸгҒҡгҒӢ17,183дәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәе…ҘжӨҚиҖ…гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒёгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®дәәгҖ…гҒҜгӮўгғЎгғӘгӮ«гҖҒдёӯжқұгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒёж—…з«ӢгҒЈгҒҹгҖӮ гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒҜеҪ“еҲқгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўзөұжІ»гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮ„гҒҢгҒҰгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒҜжҝҖгҒ—гҒ„зӢ¬з«ӢйҒӢеӢ•пјҲ40е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҒҜгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒӢгӮүгҖҒ1952е№ҙд»ҘйҷҚгҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгӮ’дҪөеҗҲгҒ—гҒҹгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒӢгӮүпјүгҒ«е·»гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ 第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰжң«жңҹгҒ«гҒҜгҖҒгғҙгӮЈгғігғҒгӮ§гғігғ„гӮ©гғ»гғҮгӮЈгғ»гғЎгӮ°гғӘгӮӘеҚҡеЈ«гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӨгӮҝгғӘгӮўзі»гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒҢгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгҒ®еӯҳеңЁгӮ’ж”ҝжІ»зҡ„гҒ«ж“Ғиӯ·гҒ—гҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®зӢ¬з«ӢгӮ’ж¬ЎгҖ…гҒЁжҺЁйҖІгҒ—гҒҹгҖӮеҪјгҒҜгғӯгғјгғһгҒ«иЎҢгҒҚгҖҒгғҗгғҒгӮ«гғігҒҢжҺЁйҖІгҒҷгӮӢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўзӢ¬з«Ӣдјҡиӯ°гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮ жҲҰеҫҢгҖҒгғҮгӮЈгғ»гғЎгӮ°гғӘгӮӘгҒҜгҖҢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўд»ЈиЎЁгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәә委員дјҡгҖҚпјҲCRIEпјүгҒ®зҗҶдәӢгҒ«д»»е‘ҪгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ1947е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ«жңүеҲ©гҒӘгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒЁгҒ®еҗҢзӣҹгӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҖҢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгғ»гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўеҚ”дјҡгҖҚгҒЁгҖҢгғҙгӮ§гғҶгғ©гғігғ»гӮўгӮ№гӮ«гғӘеҚ”дјҡгҖҚгҒ®иЁӯз«ӢгӮ’ж”ҜжҢҒгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒ1947е№ҙ9жңҲгҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®еӯҳеңЁгҒ«еҘҪж„Ҹзҡ„гҒӘгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгҒ®ж”ҝе…ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢPartito Eritrea Pro ItaliaгҖҚпјҲгӮ·гғЈгғ©гғ»гӮӨгӮҝгғӘгӮўе…ҡпјүгӮ’е…ұеҗҢиЁӯз«ӢгҒ—гҖҒ1гғ¶жңҲгҒ§20дёҮдәәд»ҘдёҠгҒ®дјҡе“ЎеҠ е…ҘгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ 1947е№ҙгҒ«гӮўгӮ№гғһгғ©гҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгӮ·гғЈгғ©гғ»гӮӨгӮҝгғӘгӮўе…ҡгҖҚгҒҜгҖҒгғЎгғігғҗгғјгҒ®еӨ§еҚҠгҒҢе…ғгӮӨгӮҝгғӘгӮўе…өгҒ§гҖҒгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®гӮўгӮ№гӮ«гғӘгӮӮеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹпјҲгӮӨгӮҝгғӘгӮўж”ҝеәңгӮӮгғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹпјүгҖӮ гҒ“гҒ®е…ҡгҒ®дё»гҒӘзӣ®зҡ„гҒҜгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгҒ®иҮӘз”ұгҒ®зҚІеҫ—гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзӢ¬з«ӢеүҚгҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ15е№ҙй–“гҒҜгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ«зөұжІ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗжқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ 1947е№ҙгҒ®е№іе’ҢжқЎзҙ„гҒ§гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒҜжӨҚж°‘ең°гҒ®зөӮз„үгӮ’жӯЈејҸгҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒдё»гҒ«гӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўж”ҝеәңгҒҢгӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўдәәгӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒҜж¶Ҳж»…гҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ1962е№ҙгҒ®гӮўгғ•гғӘгӮ«гғҚгӮӨгӮ·гғ§гғігӮәгӮ«гғғгғ—гҒ§е„ӘеӢқгҒ—гҒҹгӮөгғғгӮ«гғјгҒ®гғҒгғЈгғігғ”гӮӘгғігҖҒгӮӨгӮҝгғӯгғ»гғҙгӮЎгғғгӮөгғӯгҒЁгғ«гғҒгӮўгғјгғҺгғ»гғҙгӮЎгғғгӮөгғӯе…„ејҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўж”ҝеәңгҒӢгӮүжӯ“иҝҺгҒ•гӮҢгҒҹгӮӨгӮҝгғӘгӮўзі»гӮЁгғӘгғҲгғӘгӮўдәәгӮӮгҒ„гҒҹгҖӮ   й–ўйҖЈй …зӣ®и„ҡжіЁ
еҸӮиҖғж–ҮзҢ®еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia

















