„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺԺàËã±Ë™û: Three-Pointed StarÔºâ„Å®„ÅØ„ÄÅ„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„ÅÆËá™Âãï˪ä„Å™„Å©„Å´‰ΩøÁÅï„Çå„ÇãÊ®ôÁ´Ý„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ 1909Âπ¥„Å´ÊúÄÂàù„ÅÆ„Éá„Ç∂„ǧ„É≥„Åå‰Ωú„Çâ„Çå„ÄÅÁèæÂú®„ÅØ„Éâ„ǧ„ÉÑ„ÅÆËá™Âãï˪ä„É°„ɺ„Ç´„ɺ„Åß„ÅÇ„Çã„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„Éфɪ„Ç∞„É´„ɺ„ÉóÁ§æ„Å®„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éà„É©„ÉÉ„ÇØÁ§æ„Å´„Çà„Å£„Ŷ‰ΩøÁÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ Ê¶Ç˶ńÇπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆÂü∫„Å®„Å™„ÇãÊ®ôÁ´Ý„ÅØ„ÄÅ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„É¢„Éà„ɺ„ɨ„É≥„ɪ„Ç≤„Ǻ„É´„Ç∑„É£„Éï„ÉàÁ§æÔºàDMG„Äljª•‰∏ã„Äå„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÄçÔºâ„Å´„Çà„Å£„Ŷ„ÄÅÂêåÁ§æ„ÅÆËá™Âãï˪ä„Åß„ÅÇ„Çã„Äå„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„Äç„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„Å®„Åó„ŶËÄÉÊ°à„Åï„Çå„Åü„ÄÇÊúÄÂàù„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„ÅØ1909Âπ¥6Êúà24Êó•„Å´ÂïÜÊ®ô„Å®„Åó„ŶÊÑèÂåÝÁôªÈå≤„ÅÆÁî≥Ë´ã„ÅåÂá∫„Åï„Çå„ÄÅ1910Âπ¥10Êúà10Êó•„Å´ÁôªÈå≤„Åï„Çå„Åü„ÄÇ ‰∏âÊú¨„ÅÆÂÖâËäí„ÅØÈô∏„ɪʵ∑„ɪÁ©∫„ÇíÊåá„Åó„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ„Åù„Çå„Åû„Çå„ÅƉ∏ñÁïå„Åß„ÅÆ„É¢„Éì„É™„ÉÜ„Ç£„ɺ„ÅÆÁô∫±ï„ÇíÊÑèÂë≥„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã[1][2]„ÄÇ 1926Âπ¥6Êúà28Êó•„Å´„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅØ„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„Å®Âêà‰Ωµ„Åó„Ŷ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„Å®„Å™„Çä„ÄÅ˪ä‰∏°„ÅÆÂêç„ÅØ„Äå„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„Äç„ÅåÁÅÑ„Çâ„ÇåÂßã„ÇÅ„Åü„ÄÇÂêà‰Ωµ„Å´Èöõ„Åó„Ŷ‰∏°Á§æ„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„ÇíËûçÂêà„Åï„Åõ„ÇãÂΩ¢„Åß„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ˪ä„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„Å®„Åó„Ŷ„ÅÆ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅåÂÆåÊàê„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„ÅØ„É©„Ƕ„É≥„Éá„É´„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Äå„Ç®„É≥„Éñ„ɨ„ÉÝ„Äç„Å®„ÄÅ˪ä‰∏°„ÅÆ„Éï„ɺ„Éâ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„ÇÑ„Ç∞„É™„É´„Å߉ΩøÁÅï„Çå„ÇãÈäÄËâ≤„ÅÆ„É≠„Ç¥„Éû„ɺ„ÇØÔºàÁèæÂú®„ÅÆÊ≠£Âºè„Å™„Éñ„É©„É≥„Éâ„É≠„Ç¥Ôºâ„Åå„ÅÇ„Çä„ÄÅ„Å©„Å°„Çâ„ÇljΩøÁÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ ÂëºÁß∞„ÄåËã±Ë™û: Three-pointed star„Äç[3]„ÇÑ„Äå„Éâ„ǧ„ÉÑË™û: Dreizack-Stern„Äç[4]„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´„Äʼn∏â„ŧ„ÅÆÈÝÇÁÇπ„ÇíÊåńŧÊòüÔºà„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺԺâ„Å®„ÅÑ„ÅÜÂêç„ÅßÂ뺄Å∞„Çå„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅ„Äå„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÄçÔºàËã±Ë™û: Mercedes-Star[3]„ÄÅ„Éâ„ǧ„ÉÑË™û: Mercedes-Stern[4]Ôºâ„Å®„ÅÑ„ÅÜÂ뺄Å≥Êñπ„Åå„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÄÅ„Å©„Å°„Çâ„ÅÆÂ뺄Å≥Êñπ„ÇÇ„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„Éфɪ„Ç∞„É´„ɺ„ÉóÁ§æ„Å´„Çà„Å£„ŶÁÅÑ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ Ê≤øÈù©„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆÂéüÂûã (1909Âπ¥)„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„Å´„Çà„Å£„Ŷ‰ΩøÁÅåÂßã„ÇÅ„Çâ„Çå„ÅüÊúÄÂàù„ÅÆ„Éá„Ç∂„ǧ„É≥„Å؉∏âËäíÊòü„ÅÆ„Éá„Ç∂„ǧ„É≥„ÅÆ„Åø„Åß„ÄÅÂÜÜÂΩ¢„ÅÆÁ∏ÅÂèñ„Çä„ÅØ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Å™„Åã„Å£„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆÊÑèÂåÝ„ÅØ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅÆÂâµÊ•≠ËÄÖ„Ç¥„ÉÉ„Éà„É™„ɺ„Éó„ɪ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ÅÆÊÅØÂ≠ê„ÅßÂêåÁ§æ„ÅÆÈáçÂΩπ„ÇíÂãô„ÇńŶ„ÅÑ„Åü„Éë„Ƕ„É´„Å®„Ç¢„Éâ„É´„Éï„ÅÆ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÂÖѺü„Å´„Çà„Å£„ŶËÄÉÊ°à„Åï„Çå„Åü[5]„ÄÇ „ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅØ1901Âπ¥„Å´ÊúÄÂàù„ÅÆ„Äå„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„Äç„Åß„ÅÇ„Çã„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ35PS„ÇíÂÆåÊàê„Åï„Åõ„ÄÅÂêåÂπ¥„Å´„ÄåM√©rc√®des„Äç„ÅÆÂïÜÊ®ôÁôªÈå≤„ÇíË°å„Å£„Åü„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ˪ä‰∏°„Å´‰ªò„Åë„ÇãÊ®ôÁ´ÝÔºà„É≠„Ç¥„Éû„ɺ„ÇØÔºâ„ÅØ„ÄåMercedes„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊñáÂ≠ó„ÅÆ„Åø„ÅÆÁ∞°Êòì„Å™„ÇÇ„ÅÆÔºà‰∏äÊé≤Ôºâ„Åå„ÅÇ„Çã„ÅÆ„Åø„ÅÝ„Å£„Åü„ÄÇ„Åù„Åì„Åß„ÄÅ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÂÖѺü„ÅØ1900Â𥉪£Âçä„Å∞„Å´Ê®ôÁ´Ý„Çí‰Ωú„Çã„Åì„Å®„Å´„Åó„ÄÅÁà∂„Ç¥„ÉÉ„Éà„É™„ɺ„Éó„Å嶪„Å´ÂÆõ„Ŷ„ŶÊõ∏„ÅÑ„ÅüÊâãÁ¥ô„ÅÆ„Äå„Åì„Åì„Åã„ÇâÊòü„ÅåÊòá„Çä„ÄÅ„Åù„Çå„ÅåÁßÅ„Åü„Å°„Å®Â≠ê‰æõ„Åü„Å°„Å´Á•ùÁ¶è„Çí„ÇÇ„Åü„Çâ„Åô„Åì„Å®„ÇíÈ°ò„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Äç„Å®„ÅÑ„Å܉∏ÄÁØÄ„Å´ÁùÄÊÉ≥„ÇíÂæó„ŶÂõ≥Ê°à„ÇíËÄÉÊ°à„Åó„Åü„ÄÇÂêåÊôÇ„Å´„ÄÅ4„ŧ„ÅÆÈÝÇÁÇπ„ÇíÊåńŧ„Äå„Éï„Ç©„ɺ„ɪ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„Äç„ÇÇËÄÉÊ°à„Åó„ÄÅÂïÜÊ®ô„ÅÆÁî≥Ë´ã„ÇíË°å„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åå„ÄÅÈô∏„ɪʵ∑„ɪÁ©∫„ÇíÁ§∫„Åô„Çπ„É™„ɺ„ɪ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅåÊ®ôÁ´Ý„Å®„Åó„ŶÈÅ∏„Å∞„Çå„Åü[5][Ê≥®Èáà 1]„ÄÇ „Åì„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„ÅØ1916Âπ¥„Å´Êâã„ÅåÂäÝ„Åà„Çâ„Çå„ÄÅ„É©„Ƕ„É≥„Éá„É´„Å®„Å™„Çä„ÄÅ4„ŧ„ÅÆÂ∞è„Åï„Å™Êòü„ÅåÂäÝ„Åà„Çâ„Çå„Åü[2]„ÄÇÊñáÂ≠ó„ÅÆÈÉ®ÂàÜ„ÅØËá™Âãï˪ä„ÅÆ„Éñ„É©„É≥„Éâ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄåMERCEDES„Äç„ÅƉªñ„ÄÅÂΩìÊôÇ„ÅÆ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ÅÆÂ∑•ÂÝ¥„Åß„ÅÇ„Çã„ÄåUntert√ºrkheim„ÄçÔºà„Ƕ„É≥„Çø„ɺ„ÉÜ„É•„É´„ÇØ„Éè„ǧ„ÉÝÔºâ„ÄÅ„ÄåBerlin-Marienfelde„ÄçÔºà„Éô„É´„É™„É≥„ɪ„Éû„É™„Ç®„É≥„Éï„Çß„É´„ÉáÔºâ„Å®„ÅÑ„ÅÜÊñáÂ≠ó„ÅåÂÖ•„Çå„Çâ„Çå„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Å£„Åü[2]„ÄÇ „Åì„ÅÆ„É©„Ƕ„É≥„Éá„É´Âåñ„Åï„Çå„ÅüÊ®ôÁ´Ý„ÅØ1921Âπ¥„Å´ÂïÜÊ®ô„Å®„Åó„Ŷ„ÅÆÁî≥Ë´ã„Åå„Åï„Çå„Åü[2]„ÄÇ
ÊúàÊ°ÇÂÜÝ„ÅÆÂéüÂûã (1909Âπ¥)„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„ÅØ1885Âπ¥„Åã„ÇâËá™Âãï˪äË£ΩÈÄÝ„ÇíÂßã„ÇńŶ„Åä„Çä„ÄÅ1900Âπ¥„Å´„ÅØÂΩìÊôÇ„ÅÆËá™Âãï˪ä„É°„ɺ„Ç´„ɺ„ÅƉ∏≠„Åß„ÇÇÊúħ߄ÅÆÁîüÁî£Êï∞„ÇíË™á„Çã„Åæ„Åß„Å´„Å™„Å£„Åü„ÄÇ ÊúÄÂàù„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„ÅÆÂà∂ÂÆö„ÅØ„Åù„ÅÆÂæå„ÅÆ1903Âπ¥„Åß„ÄÅ„ÄåOriginal BENZ„Äç„ÅÆÊñáÂ≠ó„ÇíȪí„ÅÑ„É™„É≥„Ç∞„ÇÆ„Ç¢„ÅßÂõ≤„ÇÄ„Å®„ÅÑ„ÅÜ„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Å£„Åü[7][5]„ÄÇ1900Â𥉪£„ÅÆ„Éô„É≥„ÉÑ˪ä„ÅØËá™Âãï˪ä„ɨ„ɺ„Çπ„ÅßÊï∞§ö„Åè„ÅÆÂãùÂà©„ÇíÊåô„Åí„ÄÅ„Åù„ÅÆ„Åì„Å®„Å´ÂõÝ„Çì„Åß„ÄÅ1909Âπ¥„Å´ÂãùÂà©„ÅÆË®º„Åß„ÅÇ„ÇãÊúàÊ°ÇÊ®π„ÅÆÁí∞ÔºàÊúàÊ°ÇÂÜÝÔºâ„Çí„ÅÇ„Åó„Çâ„Å£„Åü„É©„Ƕ„É≥„Éá„É´„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„ÇíÊñ∞„Åü„Å´Âà∂ÂÆö„Åó„Åü[7][6][5]„ÄÇ „ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅÆ„Äå„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„Äç„Å®„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„ÅÆ„ÄåÊúàÊ°ÇÂÜÝ„Äç„ÅåÂêåÂπ¥„Å´Âà∂ÂÆö„Åï„Çå„Åü„ÅÆ„ÅØÔºà„Åã„ŧ„Ŷ„Ç¥„ÉÉ„Éà„É™„ɺ„Éó„ɪ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„Å®„Ç´„ɺ„É´„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„Åå„Ū„źÂêåÊôÇ„Å´„Ǩ„ÇΩ„É™„É≥Ëá™Âãï˪ä„ÇíÂÆåÊàê„Åï„Åõ„ÅüÊôÇ„Å®Âêå„Åò„ÅèÔºâÂÅ∂ÁÑ∂„ÅƉ∏ÄË᥄Ů„Å™„Çã[6]„ÄÇ
メルセデス・ベンツ誕生 (1926年)
2010Â𥉪£„Åã„ÇâÁÅÑ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Ç®„É≥„Éñ„ɨ„ÉÝ„ÄÇËÉåÊôØËâ≤„Å؉ª•Ââç„ÅØÊøÉÁ¥∫„ÅÝ„Å£„Åü„Åå„ÄÅȪí„Ŵ§âÊõ¥„Åï„Çå„Åü[5]„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØ„ÄÅÂéüÂûã„ÅÆË™ïÁîüÊôÇ„ÅÆÈÄ∏Ë©±„ÇíË∏è„Åæ„Åà„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÄŧúÁ©∫„ÄÅ„Åô„Å™„Çè„Å°ÂÆáÂÆô„ÅÆʺÜȪí„ÇíË°®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã[5]„ÄÇ
Á¨¨‰∏Äʨ°‰∏ñÁïå§ßÊà¶Ôºà1914Âπ¥ - 1918Âπ¥Ôºâ„ÅÆÁµÇÊà¶Âæå„ÄÅÊïóÊà¶ÂõΩ„Å®„Å™„Å£„Åü„Éâ„ǧ„ÉÑ„Åß„Å؄ǧ„É≥„Éï„ɨ„Å´„Çà„ÇäÁµåÊ∏à„Å؉ΩéËø∑„Åó„ÄÅËá™Âãï˪äË≤©Â£≤„ÇÇËã¶Â¢É„Å´„ÅÇ„Å£„Åü[8]„ÄÇ1900Â𥉪£„Åã„ÇâÁ´∂Âêà„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„Å®„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„ÅØÁîü„ÅçÊÆã„Çä„ÇíÂõ≥„Çã„Åü„ÇÅ„Å´ÂçîÂäõÈñ¢‰øÇ„ÇíÁµê„Å≥„ÄÅ1924Âπ¥ÈÝÉ„Åã„Çâ‰∏°Á§æ„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„Çí‰ΩøÁÅó„ÅüÂÖ±ÂêåÂ∫ÉÂëä„ÇíÈݪÁπÅ„Å´Âá∫„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü[8]„ÄÇ 1926Âπ¥6Êúà28Êó•„Äʼn∏°Á§æ„ÅØÂêà‰Ωµ„Åó„Ŷ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„Å®„Å™„Çä„ÄÅÊ®ôÁ´Ý„Å´„ŧ„ÅфŶ„Çlj∏°ËÄÖ„ÅÆÈáç˶ńř˶ÅÁ¥Ý„ÇíÊÆã„Åó„ŶËûçÂêà„Åï„Åõ„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅåËÄÉÊ°à„Åï„Çå„Åü[8]„ÄÇ„Åô„Å™„Çè„Å°„ÄÅ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„Åã„Çâ„ÅØ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÇíÊÆã„Åó„ÄÅ„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„Åã„Çâ„ÅØÊúàÊ°ÇÂÜÝ„ÇíÊÆã„Åô„Å®„ÅÑ„ÅÜÂΩ¢„Å®„Å™„Å£„Åü[8]„ÄÇÂêà‰Ωµ„Å´Èöõ„Åó„Ŷ„ÄÅ˪ä‰∏°„ÅÆ„Éñ„É©„É≥„ÉâÂêç„ÅØ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅÆ„Äå„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„Äç„Å®„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„ÅÆ„Äå„Éô„É≥„ÉÑ„Äç„ÇíÂêà„Çè„Åõ„Ŷ„Äå„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„Äç„Å®„Å™„Çä„ÄÅÊñ∞„Åü„Å™„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„Åå„ÄÅ„Ç®„É≥„Éñ„ɨ„ÉÝ„ÇÑ„Éï„ɺ„Éâ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Å®„Åó„ŶÁÅÑ„Çâ„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü[1]„ÄÇ „ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÊôljª£„ÅÆ1921Âπ¥11Êúà„Åã„Çâ„ÄÅ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„Å®ÂÜÜ„ÅÆ„Åø„Çí‰ΩøÁÅó„ÅüÂΩ¢„ÅÆ„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Åå‰ΩøÁÅï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„ÄÅ„Åì„Çå„ÅØ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ˪ä‰∏°„Å´„ÇǺï„ÅçÁ∂ô„Åå„Çå„ÄÅ„Éï„ɺ„Éâ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Å®„Åó„ŶÈï∑„Åè‰Ωø„Çè„Çå„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çã[5]Ôºà‚Üí#Ëá™Âãï˪ä„Å´„Åä„Åë„Çã‰ΩøÁî®Ôºâ„ÄÇ1989Âπ¥„Å´„ÅØ„Åì„ÅÆÊÑèÂåÝ„Å´Âü∫„Å•„ÅÑ„ÅüÊ®ôÁ´Ý„Åå„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„ÅÆÊ≠£Âºè„řʮôÁ´Ý„Å®„Å™„Å£„Åü„Älj∏ÄÊñπ„ÄÅ1926Â𥉪•Êù•„ÅÆ„É©„Ƕ„É≥„Éá„É´„ÇíÁÅÑ„ÅüÊ®ôÁ´Ý„ÅØ„Åù„ÅÆÂæå„ÇDŽŪ„Å®„Çì„ũ§âÊõ¥„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Å™„Åè„ÄÅ2020Â𥉪£„ÅƉªäÊó•„Åæ„Åß˪ä‰∏°„ÅÆ„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„ÉàÂâçÁ´Ø„Å´Êé≤„Åí„Çâ„Çå„ÄʼnΩøÁÅåÁ∂ö„Åë„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[8]„ÄÇ
Ëá™Âãï˪ä„Å´„Åä„Åë„Çã‰ΩøÁÉû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„ÅÆË™ïÁîü„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÁ§æ„ÅÆÊúÄÂàù„ÅÆ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅØ1909Âπ¥ÈÝÉ„Åã„Çâ„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„ÅÆË£ÖÈ£æ„Å®„Åó„ŶÂ∞éÂÖ•„Åï„Çå„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÆÂæå„ÄÅ„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Ç≠„É£„ÉÉ„Éó„ÅÆË£ÖÈ£æ„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Åå„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ‰∏ä„Å´Áõ¥Á´ã„Åó„ŶÊé≤„Åí„Çâ„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„ÄÇ1930Â𥉪£‰ª•Ââç„Å´Ëá™Âãï˪䉺öÁ§æ„ÅåÁã¨ËᙄÅÆ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Ç퉪ò„Åë„Çã„ÅÆ„ÅØÂΩìÊôlj∏ÄËà¨ÁöÑ„Å´Ë°å„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ „ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„Å®„Å™„Å£„ÅüÂæå„ÇÇ„ÄÅ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÊôljª£„Å®„Ū„źÂêå„ÅòÊÑèÂåÝ„ÅÆ„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Åå‰ΩøÁÅï„ÇåÁ∂ö„Åë„Åü„ÄÇ„Éô„É≥„ÉÑÁ§æ„Å®„ÅÆÂêà‰Ωµ„Å´‰º¥„ÅÑ„ÄÅ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Å´„ÇÇÊúàÊ°ÇÂÜÝ„ÇíË∂≥„ÅôË©¶Ê°à„ÇÇʧúË®é„Åï„Çå„Åü„Åå„ÄÅÊé°ÁÅØ„Åï„Çå„Å™„Åã„Å£„Åü[5]„ÄÇ
Á¨¨‰∫åʨ°‰∏ñÁïå§ßÊඉª•Èôç Á¨¨‰∫åʨ°‰∏ñÁïå§ßÊà¶Âæå„ÄÅ„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„Å´„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Ç≠„É£„ÉÉ„Éó„ÇíÁΩÆ„Åè„Åì„Å®„Åå„Å™„Åè„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„Åì„Å®„Å´‰º¥„ÅÑ„ÄÅËá™Âãï˪䉺öÁ§æÂêÑÁ§æ„ÅØ„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„ÅÆ„Äå„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Äç„ÇíÊí§Â骄Åó„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü[Ê≥®Èáà 5]„ÄÇ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÄÅ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅØ„ÉĄǧ„ÉÝ„É©„ɺÂÖѺü„ÅƉ∏äË®ò„ÅÆÁùÄÊÉ≥„Åã„ÇâÂà∂ÂÆö„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅ„ÄåÂπ∏ÈÅã„ÅÆÊòü„ÅƉ∏ã„ÅßÂÆâÂÖ®„ÇíÈ°ò„ÅÜ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜ„É°„ÉɄǪ„ɺ„Ç∏„ÅåË溄ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[9]„ÄÇ„Åù„ÅÆ„Åü„ÇÅ„ÄÅ„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Ç≠„É£„ÉÉ„Éó„ÅåÂøÖ˶ńř„Åè„Å™„Å£„ÅüÂæå„ÇÇ„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„Å´„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„ÉàÔºà„Éï„ɺ„Éâ„Ç؄ɨ„Çπ„Éà„Éû„ɺ„ÇØÔºâ„ÇíÁΩÆ„Å艺ùÁµ±„ÅØÁ∂ö„Åë„Çâ„Çå„Åü[9]„ÄÇ „Åì„ÅÜ„Åó„Åü„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„ÅÆ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„ÅØ„ÄÅË°ùÁ™Å‰∫ãÊïÖ„ÅåÁô∫Áîü„Åó„ÅüÊôÇ„ÅÆÊ≠©Ë°åËÄÖ„ÅÆÂÆâÂÖ®ÊÄß„ÇíÈ´ò„ÇÅ„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅ1957Âπ¥„Åã„Çâ„ÅØ„Éê„Éç„ÅåÂÖ•„Çå„Çâ„Çå„ÄÅË°ùÁ™ÅÊôÇ„Å´Ëá™ÂãïÁöÑ„Å´Êõ≤„Åå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„ÄÇ 2010Â𥉪£„Åæ„Åß„ÅØ„ÄÅ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅƉΩøÁÅØ˪ä‰ΩìÂâçÈÉ®„Å´ÈÖçÁΩÆ„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅƄŪ„Åã„ÅØ„Äʼnªñ„É°„ɺ„Ç´„ɺ„ÅÆÊ®ôÁ´Ý„Å®Âêå„Åò„Åè„ÄÅ˪ä‰ΩìÂæåÈÉ®„ÇÑ„ÄÅ„Éõ„ǧ„ɺ„É´„Ç≠„É£„ÉÉ„ÉóÁ®ãÂ∫¶„Å´Èôê„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ2020Â𥉪£„Å´ÂÖ•„Çã„Å®„ÄÅ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆÂΩ¢Áä∂„ÅØ„Éï„É≠„É≥„Éà„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Ç∞„É™„É´„ÅÆÊ®°Êßò„ÇÑ„ÄÅ„Éï„É≠„É≥„Éà„É©„ǧ„Éà„ÄÅ„É™„Ç¢„É©„ǧ„Éà„ÅÆÁÇπÁÅØÈÉ®„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÁÆáÊâÄ„ÅÆÊÑèÂåÝ„Å®„Åó„Ŷ„ÇljΩøÁÅï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ
ª∫ÈÄÝÁâ©„Å´„Åä„Åë„Çã‰ΩøÁî®Ëá™Âãï˪äÈñ¢ÈÄ£„É°„ɺ„Ç´„ɺ„Åß„ÅØ„ÄÅ„É≠„Ç¥„Éû„ɺ„ÇØ„ÅÆ„Ç™„Éñ„Ç∏„Çß„ÇíË≤©Â£≤Â∫ó„Å™„Å©„Å´Êé≤„Åí„Çã„Åì„Å®„ÅØÂ∫É„ÅèË°å„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åå„ÄÅ„Çπ„É™„ɺ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅË≤©Â£≤Â∫ó„ÅåÂ≠òÂú®„Åó„Å™„ÅѪ∫Áâ©„Å´„ÇÇÂ∫ÉÂëä°î„Å®„Åó„Ŷ„Åó„Å∞„Åó„Å∞Êé≤„Åí„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[10]„ÄÇ„Åù„ÅÆÁ∑èÊï∞„ÅØ„É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„Éфɪ„Ç∞„É´„ɺ„ÉóÁ§æ„Åß„ÇÇÊ≠£Á¢∫„Å™„Å®„Åì„Çç„ÅØÊääÊè°„Åó„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ„ÄÅË≤©Â£≤Â∫ó„Å´Êé≤„Åí„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÇÇ„ÅÆ„ÇÇÂê´„ÇÅ„Çå„Å∞„ÄÅ600„ÇíË∂Ö„Åà„Çã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[10]„ÄÇ „ÅÇ„Åæ„Çä„Å´„ÇÇÊï∞„Åå¢ó„Åà„Åü„Åü„ÇÅ„ÄÅ1995Âπ¥„Å´„ÅØ„Äå„Åì„ÅÜ„Åó„ÅüÁõÆÁ´ã„ŧÂΩ¢„Åß„ÅƉΩøÁÅØÊú¨Á§æ„ÅåÊåáÂÆö„Åó„ÅüË≤©Â£≤Â∫ó„Å´Èôê„Çã„Åπ„Åç„ÅÝ„Äç„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÊñ∞˶è„ÅÆË®≠ÁΩÆ„ÅåÂà∂Èôê„Åï„Çå„Åü„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Çã„Åå„ÄÅÊñπÈáù„ÅƧâÊõ¥„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Åì„ÅÆÂà∂Èôê„ÅØ1999Âπ¥„Å´ËߣÈô§„Åï„Çå„Åü[10]„ÄÇ „É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„ÉÑ˪ä„ÅÆË≤©Â£≤Â∫ó„Å™„Å©„ÇíÈô§„Åè„Å®„ÄŪ∫ÈÄÝÁâ©„ÅƉ∏ä„Å´„Ç™„Éñ„Ç∏„Çß„Å®„Åó„ŶÁΩÆ„ÅÑ„ÅüËëóÂêç„Å™‰ΩøÁæã„Å®„Åó„Ŷ„Äʼn∏ãË®ò„ÅƉæã„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇ
ÈÅéÂ骄Ŵ„Ç™„Éñ„Ç∏„Çß„ÇíÊé≤„Åí„Ŷ„ÅÑ„Åüª∫ÈÄÝÁâ©
脚注注釈
出典
参考資料
外部リンク
|
Portal di Ensiklopedia Dunia
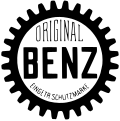






![1909年の最初のスリーポインテッド・スター[注釈 2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Mercedes_brand_logo_1909.png/250px-Mercedes_brand_logo_1909.png)

![2010Â𥉪£„Åã„ÇâÁÅÑ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Ç®„É≥„Éñ„ɨ„ÉÝ„ÄÇËÉåÊôØËâ≤„Å؉ª•Ââç„ÅØÊøÉÁ¥∫„ÅÝ„Å£„Åü„Åå„ÄÅȪí„Ŵ§âÊõ¥„Åï„Çå„Åü[5]„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØ„ÄÅÂéüÂûã„ÅÆË™ïÁîüÊôÇ„ÅÆÈÄ∏Ë©±„ÇíË∏è„Åæ„Åà„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÄŧúÁ©∫„ÄÅ„Åô„Å™„Çè„Å°ÂÆáÂÆô„ÅÆʺÜȪí„ÇíË°®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã[5]„ÄÇ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/2018_Mercedes_logo.jpg/330px-2018_Mercedes_logo.jpg)
![1926Âπ¥„ÅÆÊ®ôÁ´Ý[Ê≥®Èáà 4]„ÄÇ„Ç®„É≥„Éñ„ɨ„ÉÝ„Å®„Åó„ŶÁÅÑ„Çâ„Çå„ÄÅÁèæÂú®„ÇDŽŪ„źÂêå„ÅòÊÑèÂåÝ„Åß„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„ÉàÂâçÁ´Ø„Å´‰ªò„Åë„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Mercedes_benz_logo_1926.png/120px-Mercedes_benz_logo_1926.png)
![1933Âπ¥„Å´ËøΩÂäÝ„Åï„Çå„ÅüÊ®ôÁ´Ý[3]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Mercedes-Benz_free_logo.svg/120px-Mercedes-Benz_free_logo.svg.png)


![1910Âπ¥ÈÝÉ: „É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„ÉÄ„Éñ„É´„Éï„Ç߄ɺ„Éà„É≥Ôºà„ǧ„Çø„É™„Ǣ˙ûÁâàÔºâ„ÄÇ„Çπ„É™„ɺ„ɪ„Éù„ǧ„É≥„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„ÇíÊé≤„ÅíÂßã„ÇÅ„ÅüÈÝÉ„ÅÆ˪ä‰∏°[1]„ÄÇ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Mercedes_Douple-Phaeton_Type_28-50_%281909%29_jm63936.jpg/250px-Mercedes_Douple-Phaeton_Type_28-50_%281909%29_jm63936.jpg)



![1934年: W23(英語版)(130)。初期の例外で、リアエンジン車であるため車体前部にラジエーターがないため、マスコットを直立させずボンネット表面に沿って置いている[9]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/MHV_MB_W23_130_1935_01.jpg/250px-MHV_MB_W23_130_1935_01.jpg)

![1930Â𥉪£: O 10000Ôºà„Éï„É©„É≥„ÇπË™ûÁâàÔºâ„ÄÇ„Éú„É≥„Éç„ÉÉ„Éà„Éê„Çπ/„Éà„É©„ÉÉ„ÇØ„Åß„ÇÇ„É©„Ç∏„Ç®„ɺ„Çø„ɺ„Éû„Çπ„Ç≥„ÉÉ„Éà„Åå‰ΩøÁÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÜ„Åó„Åü˪ä‰∏°„ÅÆ„Éï„É≠„É≥„Éà„Ç∞„É™„É´„Åß„ÅØ„ÄåDIESEL„Äç„ÅÆÊñáÂ≠ó„Å®ÂÖ±„Å´‰ΩøÁÅô„Çã„Åì„Å®„Åå‰∏ÄËà¨ÁöÑ„ÅÝ„Å£„Åü[9]„ÄÇ„Åì„ÅÆ˪ä‰∏°„Åß„ÅØ˪ä‰ΩìÊ≠£Èù¢„ÅÆ3„É∂ÊâÄ„Å´Ê®ôÁ´Ý„ÅåÁÅÑ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Mobiles_Postamt.jpg/250px-Mobiles_Postamt.jpg)
![1952Âπ¥: „É°„É´„Ǫ„Éá„Çπ„ɪ„Éô„É≥„Éфɪ300SLÔºàËã±Ë™ûÁâàÔºâÔºàW194Ôºâ„ÄljπóÁî®Ëªä„Åß„ÅØ„Äńɨ„ɺ„Ç∑„É≥„Ç∞„Ç´„ɺ„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„ÅÆ„É¢„Éá„É´„Åã„Çâ„Éï„É≠„É≥„Éà„Ç∞„É™„É´„Å´Ê®ôÁ´Ý„ÇíÈÖç„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü[5]„ÄÇ](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Mercedes_300_SL_W194_at_RMMR_2022.jpg/250px-Mercedes_300_SL_W194_at_RMMR_2022.jpg)
![ウニモグ。スポーツカーやトラックでフードマスコットは基本的に用いず、フロントグリルに大きなスリーポインテッド・スターが用いられている[5]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/2006_07_15_W%C3%B6rth_0074_%288585783050%29_%282%29.jpg/250px-2006_07_15_W%C3%B6rth_0074_%288585783050%29_%282%29.jpg)
![1998年: メルセデス・ベンツ・CLK-LM。最高時速300 km以上で走るレーシングカーにフードマスコットを装着した珍しい例[注釈 6]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Mercedes_Benz_CLK_LM_-_Flickr_-_andrewbasterfield.jpg/250px-Mercedes_Benz_CLK_LM_-_Flickr_-_andrewbasterfield.jpg)
![2010年代: Eクラス(W213)。フードマスコットを装着。1990年代以降、フードマスコットは省略されることが増え[9]、限られた車種やグレードのみに用いられるようになった。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/0_Mercedes-Benz_W213_Facelift_0.jpg/250px-0_Mercedes-Benz_W213_Facelift_0.jpg)












![六本木ファーストビル[注釈 10]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Roppongi_First_Building_Tokyo.jpg/250px-Roppongi_First_Building_Tokyo.jpg)













