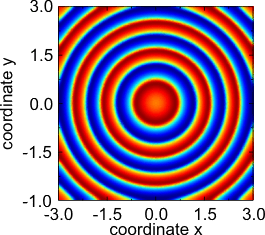هڈچه؟œو‹،و•£ç³» هڈچه؟œو‹،و•£ç³»ï¼ˆمپ¯م‚“مپ®مپ†مپ‹مپڈمپ•م‚“مپ‘مپ„م€پ英: reaction-diffusion system)مپ¨مپ¯م€پç©؛é–“مپ«هˆ†ه¸ƒمپ•م‚Œمپںن¸€ç¨®مپ‚م‚‹مپ„مپ¯è¤‡و•°ç¨®مپ®ç‰©è³ھمپ®و؟ƒه؛¦مپŒم€پ物è³ھمپŒمپٹن؛’مپ„مپ«ه¤‰هŒ–مپ—هگˆمپ†م‚ˆمپ†مپھه±€و‰€çڑ„مپھهŒ–ه¦هڈچه؟œمپ¨م€پç©؛é–“ه…¨ن½“مپ«ç‰©è³ھمپŒه؛ƒمپŒم‚‹و‹،و•£مپ®م€پن؛Œمپ¤مپ®مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ®ه½±éں؟مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه¤‰هŒ–مپ™م‚‹و§کهگم‚’و•°çگ†مƒ¢مƒ‡مƒ«هŒ–مپ—مپںم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚ و¦‚è¦پهڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپ¯م€پهŒ–ه¦مپ®هˆ†é‡ژمپ«مپٹمپ„مپ¦è‡ھ然مپھه½¢مپ§ه؟œç”¨مپ•م‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پهŒ–ه¦çڑ„مپ§مپ¯مپھمپ„ه‹•هٹ›ه¦éپژ程م‚’è،¨çڈ¾مپ™م‚‹ن¸ٹمپ§م‚‚م€پهڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپ¯ه؟œç”¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پç”ں物ه¦م‚„هœ°è³ھه¦م€پ物çگ†ه¦م‚„ç”ںو…‹ه¦مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پمپمپ®م‚ˆمپ†مپھه؟œç”¨ن¾‹مپ¯è¦‹م‚‰م‚Œم‚‹م€‚و•°ه¦çڑ„مپ«è¨€مپ†مپ¨م€پهڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپ¯هچٹç·ڑه½¢و”¾ç‰©ه‹هپڈه¾®هˆ†و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ®ه½¢م‚’هڈ–م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚ ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯و¬،مپ®م‚ˆمپ†مپ«è¨کè؟°مپ•م‚Œم‚‹م€‚ مپ“مپ“مپ§مƒ™م‚¯مƒˆمƒ« q(x,t) مپ®هگ„وˆگهˆ†مپ¯مپ‚م‚‹ç‰©è³ھمپ®و؟ƒه؛¦م‚’è،¨مپ—م€پ مپ¯و‹،و•£ن؟‚و•°مپ‹م‚‰مپھم‚‹ه¯¾è§’è،Œهˆ—م‚’è،¨مپ—م€پR مپ¯مپ™مپ¹مپ¦مپ®ه±€و‰€çڑ„مپھهڈچه؟œم‚’è،¨مپ™م€‚هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ®è§£مپ¯م€پ進è،Œو³¢مپ®ه½¢وˆگم‚„و³¢مپ«ن¼¼مپںçڈ¾è±،م€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯ه¸¯م‚„ه…角ه½¢مپ®م‚ˆمپ†مپھè‡ھه·±çµ„ç¹”مƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³م€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯و•£é€¸م‚½مƒھمƒˆمƒ³مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚ˆم‚ٹ複雑مپھو§‹é€ م‚’هگ«م‚€م€په¹…ه؛ƒمپ„範ه›²مپ®وŒ™ه‹•م‚’見مپ›م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚ ن¸€وˆگهˆ†مپ®هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈوœ€م‚‚ç°،هچکمپھهڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ¯م€پç©؛é–“ن¸€و¬،ه…ƒمپ«مپٹمپ‘م‚‹هچکن¸€ç‰©è³ھمپ®و؟ƒه؛¦ u مپ«é–¢مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§م€پ مپ¨è¨کè؟°مپ•م‚Œم€پمپ“م‚Œمپ¯KPPو–¹ç¨‹ه¼ڈ(Kolmogorov-Petrovsky-Piskounov مپ®ç•¥ï¼‰مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹[1]م€‚هڈچه؟œé …مپŒç„،مپ„ه ´هگˆم€پو–¹ç¨‹ه¼ڈمپ¯ç´”粋مپھو‹،و•£éپژ程مپ®مپ؟م‚’è،¨مپ™م€‚مپمپ®م‚ˆمپ†مپھو–¹ç¨‹ه¼ڈمپ¯مƒ•م‚£مƒƒم‚¯مپ®ç¬¬ن؛Œو³•ه‰‡مپ«é–¢ن؟‚مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚هڈچه؟œé …مپŒ R(u) = u(1-u) مپ§مپ‚م‚‹ه ´هگˆم€پç”ں物ه¦çڑ„مپھن؛؛هڈ£مپ®ه؛ƒمپŒم‚ٹم‚’è،¨çڈ¾مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«ه…ƒم€…用مپ„م‚‰م‚Œمپںم€پمƒ•م‚£مƒƒم‚·مƒ£مƒ¼مپ®و–¹ç¨‹ه¼ڈمپŒه¾—م‚‰م‚Œم‚‹[2]م€‚R(u) = u(1 − u2) مپ§مپ‚م‚‹ه ´هگˆم€پمƒ¬م‚¤مƒھمƒ¼ï¼مƒ™مƒٹمƒ¼مƒ«ه¯¾وµپم‚’è،¨مپ™مپںم‚پمپ®مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¦م‚§مƒ«ï¼مƒ›مƒ¯م‚¤مƒˆمƒکمƒƒمƒ‰ï¼م‚·مƒ¼م‚²مƒ«و–¹ç¨‹ه¼ڈمپŒه¾—م‚‰م‚Œم‚‹[3][4]م€‚R(u) = u(1 − u)(u − خ±) مپٹم‚ˆمپ³ 0 < خ± < 1 مپ§مپ‚م‚‹ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پ燃焼çگ†è«–مپ«çڈ¾م‚Œم‚‹م‚ˆم‚ٹن¸€èˆ¬çڑ„مپھم‚¼مƒ«مƒ‰مƒ“مƒƒمƒپو–¹ç¨‹ه¼ڈمپŒه¾—م‚‰م‚Œم‚‹[5]م€‚مپمپ—مپ¦مپمپ®ç‰¹هˆ¥مپھ退هŒ–çڑ„مپھن¾‹مپ¯ R(u) = u2 − u3 مپ®ه ´هگˆمپ«ه¾—م‚‰م‚Œم€پمپمپ®و–¹ç¨‹ه¼ڈم‚‚مپ¾مپںم‚¼مƒ«مƒ‰مƒ“مƒƒمƒپو–¹ç¨‹ه¼ڈمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹[6]م€‚ ن¸€وˆگهˆ†مپ®ç³»مپ®مƒ€م‚¤مƒٹمƒںم‚¯م‚¹مپ¯م€پمپ‚م‚‹ç‰¹ه®ڑمپ®هˆ¶é™گمپ«é–¢مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپھمپœمپھم‚‰مپ°م€پمپمپ®ç™؛ه±•و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ¯ه¤‰هˆ†ç³» مپ¨مپ—مپ¦م‚‚و›¸مپ‹م‚Œم€پمپ—مپںمپŒمپ£مپ¦مپ“م‚Œمپ¯و¬،ه¼ڈمپ§ن¸ژمپˆم‚‰م‚Œم‚‹م€Œè‡ھç”±م‚¨مƒچمƒ«م‚®مƒ¼م€چ مپ®و°¸ç¶ڑçڑ„مپھو¸›ه°‘م‚’و„ڈه‘³مپ™م‚‹مپ‹م‚‰مپ§مپ‚م‚‹م€‚ مپ“مپ“مپ§ V(u) مپ¯ R(u)=dV(u)/du مپ§مپ‚م‚‹م‚ˆمپ†مپھمƒمƒ†مƒ³م‚·مƒ£مƒ«م‚’è،¨مپ™م€‚  ن¸€مپ¤ن»¥ن¸ٹمپ®ه®ڑه¸¸هگŒو¬،解م‚’ه‚™مپˆم‚‹ç³»مپ«مپٹمپ„مپ¦م€په…¸ه‹çڑ„مپھ解مپ¯م€پمپمپ®هگŒو¬،çٹ¶و…‹م‚’مپ¤مپھمپگ進è،Œو³¢مپ¨مپ—مپ¦ن¸ژمپˆم‚‰م‚Œم‚‹م€‚مپمپ®م‚ˆمپ†مپھ解مپ¯م€پمپمپ®ه½¢çٹ¶م‚’ه¤‰مپˆمپڑمپ«ن¸€ه®ڑمپ®é€ںه؛¦مپ§ç§»ه‹•مپ—م€پu(x, t) = أ»(خ¾) مپ¨è¨کè؟°مپ•م‚Œم‚‹م€‚مپ“مپ“مپ§ خ¾ = x − ct مپ§مپ‚م‚ٹ c مپ¯مپمپ®é€²è،Œو³¢مپ®é€ںه؛¦م‚’è،¨مپ™م€‚مپ“مپ“مپ§م€پ進è،Œو³¢مپ¯ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«ه®‰ه®ڑمپھو§‹é€ م‚’ه‚™مپˆم‚‹مپŒم€پéهچکèھ؟مپھه®ڑه¸¸è§£ï¼ˆن¾‹مپˆمپ°م€په‰چ進مپ¨هڈچه‰چ進مپ®مƒڑم‚¢مپ§و§‹وˆگمپ•م‚Œم‚‹ه±€و‰€هŒ–مپ•م‚Œمپںé کهںں)مپ¯ن¸چه®‰ه®ڑمپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپ«و³¨و„ڈمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§مپ‚م‚‹م€‚c = 0 مپ®ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پمپ“مپ®è¨کè؟°ه†…ه®¹مپ«مپ¯و¬،مپ®م‚ˆمپ†مپھç°،هچکمپھ証وکژمپŒهکهœ¨مپ™م‚‹[7]ï¼ڑu0(x) مپŒه®ڑه¸¸è§£م€پu=u0(x) + إ©(x, t) مپŒç„،é™گه°ڈو‘‚ه‹•è§£مپ§مپ‚م‚‹مپھم‚‰م€پç·ڑه‹ه®‰ه®ڑو€§è§£وگمپ«م‚ˆمپ£مپ¦و¬،مپ®و–¹ç¨‹ه¼ڈمپŒه°ژمپ‹م‚Œم‚‹م€‚ مپ“مپ®è§£ إ© = دˆ(x)exp(−خ»t) مپ«ه¯¾مپ—م€پم‚·مƒ¥مƒ¬مƒ‡م‚£مƒ³م‚¬مƒ¼ه‹مپ®ه›؛وœ‰ه€¤ه•ڈé،Œ مپŒه¾—م‚‰م‚Œم‚‹م€‚مپںمپ مپ—م€پمپمپ®è² مپ®ه›؛وœ‰ه€¤مپŒè§£مپ®ن¸چه®‰ه®ڑو€§مپ«ه¸°çµگمپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚ه¹³è،Œç§»ه‹•ن¸چه¤‰و€§مپ«م‚ˆم‚ٹم€پدˆ = ∂xu0(x) مپ¯ه›؛وœ‰ه€¤ خ» = 0 مپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹ن¸ç«‹çڑ„مپھه›؛وœ‰é–¢و•°مپ§مپ‚م‚ٹم€پمپمپ®ن»–مپ®مپ™مپ¹مپ¦مپ®ه›؛وœ‰é–¢و•°مپ¯م€پم‚¼مƒè§£مپ®و•°مپ«مپ¤مپ„مپ¦هچکèھ؟مپ«ه¢—هٹ مپ™م‚‹ه®ںه›؛وœ‰ه€¤مپ®çµ¶ه¯¾ه€¤مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€په¢—هٹ مپ™م‚‹çµگمپ³ç›®مپ®و•°مپ«ه¾“مپ£مپ¦هˆ†é،مپ•م‚Œم‚‹م€‚ه›؛وœ‰é–¢و•° دˆ = ∂x u0(x) مپ¯ه°‘مپھمپڈمپ¨م‚‚ن¸€مپ¤مپ®م‚¼مƒè§£م‚’وŒپمپ،م€پéهچکèھ؟مپھه®ڑه¸¸è§£مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹ه›؛وœ‰ه€¤ خ» = 0 مپ¯وœ€ه°ڈمپ®م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€پمپ—مپںمپŒمپ£مپ¦ن¸چه®‰ه®ڑو€§م‚’و„ڈه‘³مپ™م‚‹م€‚ 進è،Œو³¢مپ®é€ںه؛¦ c م‚’و±؛ه®ڑمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€پ移ه‹•ه؛§و¨™ç³»م‚’考مپˆم€په®ڑه¸¸è§£م‚’وژ¢مپ™مپ“مپ¨مپŒه‡؛و¥م‚‹م€‚ مپ“مپ®و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ¯م€پن½چç½® أ»م€پو™‚é–“ خ¾م€پهٹ› Rم€پو¸›è،°ن؟‚و•° c مپ«ه¯¾مپ™م‚‹è³ھé‡ڈ D مپ®ه‹•مپچمپ«ه¯¾مپ™م‚‹و©ںو¢°çڑ„مپھé،ن¼¼و€§م‚’ه‚™مپˆم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚ ç©؛é–“ن¸€و¬،ه…ƒمپ‹م‚‰م‚ˆم‚ٹé«کو¬،مپ®ç©؛é–“و¬،ه…ƒمپ«è°è«–م‚’移مپ—مپ¦م‚‚م€پن¾ç„¶مپ¨مپ—مپ¦وœ‰هٹ¹مپ¨مپھم‚‹ه†…ه®¹مپ¯و•°ه¤ڑمپڈهکهœ¨مپ™م‚‹م€‚ه¹³م‚‰مپھم€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯و›²مپŒمپ£مپں進è،Œو³¢مپ¯ه…¸ه‹çڑ„مپھو§‹é€ مپ§م€پو›²مپŒمپ£مپںو³¢مپ®ه±€و‰€é€ںه؛¦مپŒه±€و‰€و›²çژ‡هچٹه¾„مپ«ن¾هکمپ™م‚‹مپ«ه¾“مپ„م€پو–°مپںمپھهٹ¹وœمپŒç”ںمپکم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹ï¼ˆمپ“مپ®مپ“مپ¨مپ¯و¥µه؛§و¨™ç³»م‚’考مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ§هˆ†مپ‹م‚‹ï¼‰م€‚مپ“مپ®çڈ¾è±،مپ¯م€پمپ„م‚ڈم‚†م‚‹و›²çژ‡é§†ه‹•ن¸چه®‰ه®ڑو€§م‚’ه°ژمپڈ[8]م€‚ ن؛Œوˆگهˆ†مپ®هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈن؛Œوˆگهˆ†مپ®ç³»مپ¯م€پن¸€وˆگهˆ†مپ®ç³»مپ¨و¯”較مپ—مپ¦م‚ˆم‚ٹه¹…ه؛ƒمپ„çڈ¾è±،م‚’許مپ™م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚م‚¢مƒ©مƒ³مƒ»مƒپمƒ¥مƒ¼مƒھمƒ³م‚°مپ«م‚ˆمپ£مپ¦هˆم‚پمپ¦وڈگه”±مپ•م‚Œمپںمپ‚م‚‹é‡چè¦پمپھم‚¢م‚¤مƒ‡م‚¢مپ«م€په±€و‰€çڑ„مپھç³»مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯ه®‰ه®ڑمپ§مپ‚مپ£مپ¦م‚‚و‹،و•£مپ®هکهœ¨مپ™م‚‹çٹ¶و³پمپ§مپ¯ن¸چه®‰ه®ڑمپ¨مپھم‚‹çٹ¶و…‹مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚‹[9]م€‚و‹،و•£مپ¯ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯ه®‰ه®ڑهŒ–هٹ¹وœمپ¨é–¢é€£مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹مپ®مپ§م€پن¸€èپ´مپ™م‚‹مپ¨مپ“مپ®م‚¢م‚¤مƒ‡م‚¢مپ¯ç›´و„ںمپ«هڈچمپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ®م‚ˆمپ†مپ§م‚‚مپ‚م‚‹م€‚ مپ—مپ‹مپ—مپھمپŒم‚‰م€پç·ڑه‹هŒ–ه®‰ه®ڑو€§è§£وگمپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پن¸€èˆ¬çڑ„مپھن؛Œوˆگهˆ†ç³» م‚’ç·ڑه‹هŒ–مپ™م‚‹مپ¨مپچم€په®ڑه¸¸هگŒو¬،解مپ®ه¹³é¢و³¢و‘‚ه‹• مپ¯و¬،م‚’و؛€مپںمپ™مپ“مپ¨مپŒهˆ†مپ‹م‚‹م€‚ مƒپمƒ¥مƒ¼مƒھمƒ³م‚°مپ®م‚¢م‚¤مƒ‡م‚¢مپ¯م€پهڈچه؟œه‡½و•°مپ®مƒ¤م‚³مƒ“م‚¢مƒ³ R' مپ®ç¬¦هڈ·مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ç‰¹ه¾´ن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپںç³»مپ®ه››مپ¤مپ®هگŒه€¤é،مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ®مپ؟م€پçگ†è§£مپ•م‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚特مپ«م€پوœ‰é™گمپ®و³¢مƒ™م‚¯مƒˆمƒ« k مپŒوœ€م‚‚ن¸چه®‰ه®ڑمپھم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹مپ¨ن»®ه®ڑمپ•م‚Œمپںمپ¨مپچم€پمپمپ®مƒ¤م‚³مƒ“م‚¢مƒ³مپ¯ç¬¦هڈ· م‚’ه‚™مپˆم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„م€‚مپ“مپ®ç³»مپ®é،مپ¯م€پمپمپ®ç¬¬ن¸€مپ®وڈڈه†™مپ«مپ،مپھمپ؟و´»و€§ه› هگمƒ»وٹ‘هˆ¶ه› هگ系(activator-inhibitor system)مپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم‚‹م€‚مپ™مپھم‚ڈمپ،م€پهں؛ه؛•çٹ¶و…‹مپ®è؟‘مپڈمپ§مپ¯مپ‚م‚‹وˆگهˆ†مپ¯ن¸،وˆگهˆ†مپ®ç”ں産م‚’ن؟ƒé€²مپ™م‚‹مپŒم€پن¸€و–¹مپ§هˆ¥مپ®وˆگهˆ†مپ¯مپم‚Œم‚‰مپ®وˆگé•·م‚’éک»ه®³مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپمپ®وœ€م‚‚ه‚‘ه‡؛مپ—مپںن»£è،¨ن¾‹مپ¯م€پمƒ•م‚£مƒƒمƒ„مƒ•مƒ¥مƒ¼ï¼هچ—雲و–¹ç¨‹ه¼ڈ مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ“مپ“مپ§ ئ’(u) = خ»u − u3 − خ؛ مپ¯و´»ه‹•é›»ن½چمپŒمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ç¥çµŒم‚’移ه‹•مپ™م‚‹مپ‹م‚’è،¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹ [10][11]م€‚مپ¾مپں duم€پdvم€پد„م€پدƒ مپٹم‚ˆمپ³ خ» مپ¯و£ه®ڑو•°مپ§مپ‚م‚‹م€‚ و´»و€§ه› هگمƒ»وٹ‘هˆ¶ه› هگç³»مپ«مƒ‘مƒ©مƒ،مƒ¼م‚؟مپ®ه¤‰هŒ–مپŒو–½مپ•م‚Œمپںمپ¨مپچم€په‡è³ھمپھهں؛ه؛•çٹ¶و…‹مپŒه®‰ه®ڑمپ§مپ‚م‚‹م‚ˆمپ†مپھو،ن»¶مپ‹م‚‰م€پمپم‚ŒمپŒç·ڑه‹ن¸چه®‰ه®ڑمپ§مپ‚م‚‹م‚ˆمپ†مپھو،ن»¶مپ¸مپ¨ç§»م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹م€‚مپمپ®ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹هˆ†ه²گمپ¯م€پو”¯é…چçڑ„مپھو³¢و•° k = 0 م‚’ه‚™مپˆم‚‹ه¤§هںںçڑ„مپھوŒ¯ه‹•ه‡è³ھçٹ¶و…‹مپ¸مپ®مƒ›مƒƒمƒ—هˆ†ه²گمپ§مپ‚م‚‹مپ‹م€پو”¯é…چçڑ„مپھوœ‰é™گمپ®و³¢و•°م‚’ه‚™مپˆم‚‹ه¤§هںںçڑ„مپھمƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³çٹ¶و…‹مپ¸مپ®مƒپمƒ¥مƒ¼مƒھمƒ³م‚°هˆ†ه²گمپ®مپ„مپڑم‚Œمپ‹مپ§مپ‚م‚ٹه¾—م‚‹م€‚ç©؛é–“ن؛Œو¬،ه…ƒمپ«مپٹمپ‘م‚‹ه¾Œè€…مپ®هˆ†ه²گمپ¯م€پé€ڑه¸¸م€پم‚¹مƒˆمƒ©م‚¤مƒ—م‚„ه…角ه½¢مپ®مƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³م‚’ه°ژمپڈم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚
مƒ•م‚£مƒƒمƒ„مƒ•مƒ¥مƒ¼ï¼هچ—雲مپ®ن¾‹مپ«ه¯¾مپ—م€پمپمپ®مƒپمƒ¥مƒ¼مƒھمƒ³م‚°هˆ†ه²گمپٹم‚ˆمپ³مƒ›مƒƒمƒ—هˆ†ه²گمپ®مپںم‚پمپ®ç·ڑه‹ه®‰ه®ڑé کهںںمپ®ه¢ƒç•Œم‚’ن½œم‚‹ن¸ç«‹ه®‰ه®ڑو›²ç·ڑمپ¯م€پو¬،ه¼ڈمپ§ن¸ژمپˆم‚‰م‚Œم‚‹م€‚ هˆ†ه²گمپŒن؛œè‡¨ç•Œمپ§مپ‚م‚‹مپھم‚‰م€پهں؛ه؛•çٹ¶و…‹مپ¨مƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³مپŒه…±هکمپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپھمƒ’م‚¹مƒ†مƒھم‚·م‚¹مپھé کهںںمپ«مپٹمپ„مپ¦م€پمپ—مپ°مپ—مپ°ه±€و‰€çڑ„مپھو§‹é€ (و•£é€¸م‚½مƒھمƒˆمƒ³ï¼‰مپŒè¦³و¸¬مپ•م‚Œم‚‹م€‚مپمپ®ن»–م€پé »ç¹پمپ«çڈ¾م‚Œم‚‹و§‹é€ مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پمƒ‘مƒ«م‚¹هˆ—(ه‘¨وœں進è،Œو³¢مپ¨مپ—مپ¦م‚‚çں¥م‚‰م‚Œم‚‹ï¼‰م€پè؛و—‹و³¢م€پم‚؟مƒ¼م‚²مƒƒمƒˆمƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³مپŒمپ‚م‚‹م€‚مپم‚Œم‚‰ن¸‰مپ¤مپ®è§£مپ®م‚؟م‚¤مƒ—مپ¯م€په±€و‰€çڑ„مپھمƒ€م‚¤مƒٹمƒںم‚¯م‚¹مپŒه®‰ه®ڑمپھمƒھمƒںمƒƒمƒˆم‚µم‚¤م‚¯مƒ«م‚’ه‚™مپˆم‚‹م‚ˆمپ†مپھن؛Œوˆگهˆ†ï¼ˆمپ‚م‚‹مپ„مپ¯م‚ˆم‚ٹه¤ڑمپڈمپ®وˆگهˆ†ï¼‰مپ®هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ®م€پن¸€èˆ¬çڑ„مپھو§‹é€ مپ§مپ‚م‚‹[12]م€‚
ن¸‰وˆگهˆ†مپٹم‚ˆمپ³مپم‚Œن»¥ن¸ٹمپ®وˆگهˆ†مپ®هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈو§کم€…مپھç³»مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€پن؛Œمپ¤م‚ˆم‚ٹم‚‚ه¤ڑمپ„وˆگهˆ†مپ®هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈمپŒوڈگه”±مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پمƒ™مƒم‚¦م‚½مƒ•مƒ»م‚¸مƒ£مƒœمƒپمƒ³م‚¹م‚مƒ¼هڈچه؟œمپ®مƒ¢مƒ‡مƒ«[13]م€پè،€و¶²ه‡ه›؛مپ®مƒ¢مƒ‡مƒ«[14]مپ‚م‚‹مپ„مپ¯ه¹³é¢مپ®و°—ن½“و”¾é›»ç³»[15]مپھمپ©مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œم‚‹م€‚ م‚ˆم‚ٹه¤ڑمپڈمپ®وˆگهˆ†م‚’هگ«م‚€ç³»مپ§مپ¯م€پن¸€وˆگهˆ†مپ‚م‚‹مپ„مپ¯ن؛Œوˆگهˆ†مپ®ç³»مپ§مپ¯èµ·مپ“م‚ٹه¾—مپھمپ„مپ•مپ¾مپ–مپ¾مپھçڈ¾è±،(ن¾‹مپˆمپ°م€په¤§هںںçڑ„مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯مپ®مپھمپ„ç©؛é–“ه¤ڑو¬،ه…ƒمپ«مپٹمپ‘م‚‹ه®‰ه®ڑمƒ©مƒ³مƒ‹مƒ³م‚°مƒ‘مƒ«م‚¹مپھمپ©ï¼‰مپŒèµ·مپ“م‚‹مپ“مپ¨مپŒçں¥م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[16]م€‚و‰±مپ†ç³»مپ®و€§è³ھمپ«ن¾هکمپ—مپ¦èµ·مپ“م‚ٹه¾—م‚‹çڈ¾è±،مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ه°ژه…¥مپ¨ç³»çµ±çڑ„مپھو¦‚è¦پمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پ[17]مپ§ن¸ژمپˆم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ ه؟œç”¨مپ¨و™®éپچو€§è؟‘ه¹´م€پهڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپ¯مƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³ه½¢وˆگمپ«ه¯¾مپ™م‚‹هں؛وœ¬çڑ„مپھمƒ¢مƒ‡مƒ«مپ¨مپ—مپ¦م€په¤ڑمپڈمپ®é–¢ه؟ƒم‚’集م‚پمپ¦مپ„م‚‹م€‚ن¸ٹè؟°مپ®مƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³ï¼ˆé€²è،Œو³¢م€پم‚¹مƒ‘م‚¤مƒ©مƒ«م€پم‚؟مƒ¼م‚²مƒƒمƒˆم€په…角ه½¢م€پم‚¹مƒˆمƒ©م‚¤مƒ—م€پو•£é€¸م‚½مƒھمƒˆمƒ³ï¼‰مپ¯و§کم€…مپھم‚؟م‚¤مƒ—مپ®هڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپ«مپٹمپ„مپ¦è¦‹م‚‰م‚Œم‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—مپمپ“مپ«مپ¯ه¤ڑمپڈمپ®çں›ç›¾م€پن¾‹مپˆمپ°م€په±€و‰€هڈچه؟œé …مپ«مپٹمپ„مپ¦مپم‚Œم‚‰مپŒè¦‹م‚‰م‚Œم‚‹مپھمپ©م€پمپŒهکهœ¨مپ™م‚‹م€‚هڈچه؟œو‹،و•£éپژ程مپ¯م€پç”ں物ه¦مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه½¢و…‹ه½¢وˆگمپ¨é–¢é€£مپ™م‚‹éپژ程مپ«ه¯¾مپ™م‚‹وœ¬è³ھçڑ„مپھهں؛盤مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚‚م€پè؟°مپ¹م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[18] م€‚مپمپ—مپ¦م€پمپم‚Œمپ¯ه‹•ç‰©مپ®و¯›çڑ®م‚„م€پçڑ®è†ڑمپ®è‰²ç´ و²ˆç€مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م‚‚関連ن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[19][20]م€‚ →م€Œen:The chemical basis of morphogenesisم€چم‚‚هڈ‚ç…§
هڈچه؟œو‹،و•£و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ®مپ•م‚‰مپھم‚‹ه؟œç”¨ن¾‹مپ¯م€پç”ںو…‹مپ®ن¾µه…¥[21]م‚„و„ںوں“ç—‡مپ®و‹،مپŒم‚ٹ[22]م€پè…«çکچمپ®وˆگé•·[23][24][25]م‚„م€په‚·مپ®و²»ç™’[26]مپھمپ©مپ«è¦‹م‚‰م‚Œم‚‹م€‚هڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپŒé–¢ه؟ƒم‚’集م‚پم‚‹هˆ¥مپ®çگ†ç”±مپ«مپ¯م€پمپم‚Œم‚‰مپŒéç·ڑه‹هپڈه¾®هˆ†و–¹ç¨‹ه¼ڈمپ§مپ‚م‚‹مپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پ解وگçڑ„مپھو‰±مپ„مپŒمپںمپ³مپںمپ³هڈ¯èƒ½مپ¨مپھم‚‹مپ“مپ¨مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œم‚‹[7][8][27][28][29]م€‚ ه®ں験هŒ–ه¦مپ«مپٹمپ‘م‚‹هڈچه؟œو‹،و•£ç³»مپ®م‚ˆمپڈç®،çگ†مپ•م‚Œمپںه®ں験مپ«مپ¯م€پçڈ¾هœ¨ن¸‰مپ¤مپ®و–¹و³•مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒçں¥م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚第ن¸€مپ«م€پم‚²مƒ«ه‹مƒھم‚¢م‚¯م‚؟مƒ¼[30]مپ‚م‚‹مپ„مپ¯م‚مƒ£مƒ”مƒ©مƒھمƒ¼مƒپمƒ¥مƒ¼مƒ–[31]مپŒç”¨مپ„م‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م€‚第ن؛Œمپ«م€پم‚مƒ£م‚؟مƒھمƒ†م‚£مƒƒم‚¯è،¨é¢ن¸ٹمپ®و¸©ه؛¦مƒ‘مƒ«م‚¹مپŒèھ؟مپ¹م‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨[32][33]م€‚第ن¸‰مپ«م€پهڈچه؟œو‹،و•£ç³»م‚’用مپ„مپ¦ç¥çµŒمƒ‘مƒ«م‚¹مپ®é€²è،ŒمپŒمƒ¢مƒ‡مƒ«هŒ–مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨[10][34]م€پمپ§مپ‚م‚‹م€‚ مپم‚Œم‚‰مپ®ن¸€èˆ¬çڑ„مپھن¾‹مپ¨مپ¯هˆ¥مپ«م€پéپ©هˆ‡مپھç’°ه¢ƒن¸‹مپ§مپ¯مƒ—مƒ©م‚؛مƒ[35]م‚„هچٹه°ژن½“[36]مپ®م‚ˆمپ†مپھé›»و°—輸é€پç³»م‚‚م€پهڈچه؟œو‹،و•£مپ®و‰‹و³•مپ«م‚ˆمپ£مپ¦è،¨çڈ¾مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒه‡؛و¥م‚‹مپ“مپ¨مپŒهˆ¤وکژمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپم‚Œم‚‰مپ®ç³»مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€پمƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³ه½¢وˆگمپ«é–¢مپ™م‚‹و§کم€…مپھه®ں験مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ é–¢é€£é …ç›®هڈ‚考و–‡çŒ®
ه¤–部مƒھمƒ³م‚¯
|
Portal di Ensiklopedia Dunia





![{\displaystyle {\mathfrak {L}}=\int \limits _{-\infty }^{\infty }\left[{\frac {D}{2}}(\partial _{x}u)^{2}-V(u)\right]{\text{d}}x}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c90197c12d2ff8dee1afc274f08e0c5d632b7b3f)











![{\displaystyle {\begin{aligned}q_{\text{n}}^{H}(k):&{}\quad {\frac {1}{\tau }}+(d_{u}^{2}+{\frac {1}{\tau }}d_{v}^{2})k^{2}&=f^{\prime }(u_{h}),\\[6pt]q_{\text{n}}^{T}(k):&{}\quad {\frac {\kappa }{1+d_{v}^{2}k^{2}}}+d_{u}^{2}k^{2}&=f^{\prime }(u_{h}).\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6fa5f0d7344114fdbd83fdb79ce83296ae151a75)