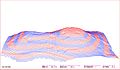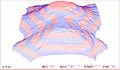жЏесЂ«т««тЈцтб│уЙц
 тЈцтб│уЙцтѕєтИЃтЏ│№╝ѕуЕ║СИГтєЎуюЪсЂФжЄЇсЂГтљѕсЂЏсђЂ1975т╣┤№╝Ѕ тЏйтюЪС║цжђџуюЂ тЏйтюЪтю░уљєжЎб тю░тЏ│сЃ╗уЕ║СИГтєЎуюЪжќ▓УдДсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«уЕ║СИГтєЎуюЪсѓњтЪ║сЂФСйюТѕљсђѓ тЈцтб│уЙцСИ╗УдЂжЃесЂ«уЕ║СИГтєЎуюЪ№╝ѕ2009т╣┤№╝Ѕ тЏйтюЪС║цжђџуюЂ тЏйтюЪтю░уљєжЎб тю░тЏ│сЃ╗уЕ║СИГтєЎуюЪжќ▓УдДсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«уЕ║СИГтєЎуюЪсѓњтЪ║сЂФСйюТѕљсђѓжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙц№╝ѕсЂѓсѓЂсЂ«сЂ┐сѓёсЂЊсЂхсѓЊсЂљсѓЊ№╝ЅсЂ»сђЂУЃйуЎ╗тЇіт│ХСИГтц«жЃесђЂуЪ│тиЮуюїж╣┐т│ХжЃАСИГУЃйуЎ╗ућ║сЂФсЂѓсѓІтЈцтб│сЂ«жЏєсЂЙсѓісѓњсЂёсЂєсђѓтЏйсЂ«тЈ▓УиАсЂФТїЄт«џсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсђѓ 1тЈитб│№╝ѕтЅЇТќ╣тЙїТќ╣тб│№╝ЅсђЂ2тЈитб│№╝ѕтЅЇТќ╣тЙїтєєтб│№╝ЅсѓњСИГт┐ЃсЂесЂЌсЂдсђЂуюЅСИѕт▒▒т▒▒СИГсЂФу┤ё40тЪ║сЂ«уЙцсѓњтйбТѕљсЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓ1тЈитб│тб│жаѓсЂФсЂ»тЏйтюЪтю░уљєжЎбсЂ«СИЅуГЅСИЅУДњуѓ╣№╝ѕжЏет««т▒▒сЂетЉйтљЇ№╝ЅсЂїсЂѓсѓісђЂТеЎжФў187.95сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсѓњТИгсѓІсђѓсЂЊсЂ«тб│жаѓжЃесЂ»жђџуД░сђЂжЏисЃХт│░№╝ѕсѓЅсЂёсЂїсЂ┐сЂГ№╝ЅсЂесѓѓтЉ╝сЂ░сѓїсѓІсђѓ1тЈитб│сЃ╗2тЈитб│сЂ»ую║ТюЏсЂФтёфсѓїсђЂСИЃт░ЙТ╣ЙсЃ╗уЪ│тІЋт▒▒у│╗сЃ╗жѓЉуЪЦТйЪтю░Т║ЮтИ»сЃ╗ТЌЦТюгТхисѓњСИђТюЏсЂДсЂЇсѓІсђѓ 1тЈитб│сЃ╗2тЈитб│сЂ»сђЂжЏїжЏёСИАС║ђсЂ«ТйюсѓђТЅђсЂДсђЂтцЕТЌЦжЎ░Т»ћтњЕуЦъсЂ«тЙАжЎхсЂесЂёсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЪ[1]сђѓ1тЈитб│сЂ«тЅЇТќ╣жЃесЂФсЂ»сЂІсЂцсЂдтцЕТЌЦжЎ░Т»ћтњЕуЦъуцЙ№╝ѕС┐ЌсЂФжЏесЂ«т««сЂесЂёсЂє[1]№╝ЅсЂ«уцЙТ«┐сЂїт╗║сЂдсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЪсђѓтцЕТЌЦжЎ░Т»ћтњЕуЦъуцЙсЂ»т╗Хтќют╝ЈсЂ«уЦътљЇтИ│сЂФУеўУ╝ЅсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂїсђЂсЂЮсЂ«т╝ЈтєЁуцЙсЂїсЂЮсЂ«сЂЙсЂЙуЈЙтГўсЂ«уЦъуцЙсЂФуЏИтйЊсЂЎсѓІсЂІсЂ»ТќГт«џсЂДсЂЇсЂфсЂё№╝ѕСИГУЃйуЎ╗ућ║С║їт««сЂФсѓѓтљїтљЇсЂ«уЦъуцЙсЂїсЂѓсѓІ№╝ЅсђѓсЂЙсЂЪ1тЈитб│тЙїТќ╣жЃетб│жаѓсЂФсЂ»сЂІсЂцсЂдуЏИТњ▓сЂ«тюЪС┐хсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсђЂтЦЅу┤ЇуЏИТњ▓сЂїУАїсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЪсђѓ ТДІТѕљтєЁт«╣сђјуЪ│тиЮуюїжЂ║УиАтю░тЏ│сђЈ[2]сЃ╗сђјуЪ│тиЮУђЃтЈцтГдуаћуЕХС╝џсђЁУфїсђЈ[3]сЂеТЌДж╣┐УЦ┐ућ║сЃ╗СИГУЃйуЎ╗ућ║СйюТѕљсЂ«У│ЄТќЎсЂФтЈцтб│сЂ«уиЈТЋ░сЃ╗ТДІТѕљтєЁт«╣сЂФжБЪсЂёжЂЋсЂёсЂїсЂѓсѓІсђѓТЌДж╣┐УЦ┐ућ║сЃ╗СИГУЃйуЎ╗ућ║СйюТѕљсЂ«У│ЄТќЎсЂФсЂ»36тЪ║сЂ«тЈцтб│сЂїсЂѓсѓІсЂесЂЌсЂдсЂёсѓІсЂїсђЂсЂЮсЂ«36тЪ║сЂ«тЁиСйЊуџёТДІТѕљсѓњТўјуц║сЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёсђѓТюгжаЁсЂДсЂ»СЙ┐т«юСИісђЂсђјжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсЂ«Уф┐ТЪ╗сђЈ[4]уЪ│тиЮУђЃтЈцтГдуаћуЕХС╝џсђЁУфїсђЈ[3]УеўУ╝ЅтѕєсѓњТ»ЇСйЊсЂесЂЌсђЂсђјтЈ▓УиАжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсђЈ[5]УеўУ╝ЅсЂДсЃісЃ│сЃљсЃфсЃ│сѓ░сЂїжЄЇУцЄсЂЌсЂдсЂёсѓІтЈцтб│сѓњRРЌІРЌІтЈитб│сЂеУеўУ┐░сЂЎсѓІсђѓ сЂфсЂіС╗ўУ┐ЉсЂФсЂѓсѓІТБ«сЂ«т««тЈцтб│уЙцсЃ╗УЦ┐ждгта┤тЈцтб│уЙцсЂ»сђЂсђјуЪ│тиЮУђЃтЈцтГдуаћуЕХС╝џсђЁУфїсђЈ[3]сЂДжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсЂ«Тћ»уЙцТЅ▒сЂёсЂесЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂїсђЂТюгжаЁсЂДсЂ»УДдсѓїсЂфсЂёсђѓ
СИ╗сЂфтЈцтб│1тЈитб│1990т╣┤С╗БсЂФтб│СИўУАежЮбсЂ«тЁежЮбуЎ║ТјўсЂесђЂугг1тЪІУЉгТќйУеГсЂ«уЎ║ТјўУф┐ТЪ╗сѓњт«ЪТќйсђѓ тб│СИў тЈцтб│уЙцтєЁсЂ«ТюђжФўТЅђсђЂжЏисЃХт│░сЂФСйЇуй«сЂЎсѓІтЅЇТќ╣тЙїТќ╣тб│сђѓтЁежЋи64сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЙїТќ╣жЃет╣Ё43.6сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЅЇТќ╣жЃет╣Ё31сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЙїТќ╣жЃежФўсЂЋ8.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсѓњТИгсѓІ[6]сђѓ сЂфсЂісђЂсђјжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсЂ«Уф┐ТЪ╗сђЈ[4]С╗ЦтЅЇсЂ«ТќЄуї«сЂДсЂ»сђЂтЁежЋи70сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂеУеўУ╝ЅсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЪсђѓ1990т╣┤С╗БсЂ«уЎ║ТјўУф┐ТЪ╗уЏ┤тЅЇсЂ«уЈЙтю░УАесЂФт»ЙсЂЎсѓІТИгжЄЈ№╝ѕ1991т╣┤сђЂУѕфуЕ║тєЎуюЪТИгжЄЈсЂФсѓѕсѓІ№╝ЅсЂДсѓѓтЁежЋи69сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсѓњТИгсЂБсЂдсЂёсЂЪ[7]сђѓсЂЌсЂІсЂЌсЂфсЂїсѓЅ1992т╣┤С╗ЦжЎЇсЂ«уЎ║ТјўУф┐ТЪ╗сЂДсђЂУЉ║уЪ│сЂїУЉ║сЂІсѓїсЂдсЂёсѓІу»ётЏ▓сЂїуб║т«џсЂЌсђЂсђїУЉ║уЪ│сЂїТќйсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІу»ётЏ▓сЂїсЂЎсЂфсѓЈсЂАтб│СИўсЂДсЂѓсѓІсђЇ[8]сЂесЂёсЂБсЂЪТќ░сЂЪсЂфуљєУДБсЂїсЂЊсЂ«тЈцтб│сЂФСИјсЂѕсѓЅсѓїсЂЪсђѓсЂЊсЂ«уљєУДБсЂДсЂ»сђЂУЉ║уЪ│сЂїУЉ║сЂІсѓїсЂдсЂёсЂфсЂёжЃетѕєсЂ»сђїУЉ║уЪ│тЪ║т║ЋсѓњТЈЃсЂѕсѓІсЂЪсѓЂсЂ«тЪ║тЈ░сђЇ[8]сЂесЂЌсђЂсђїтб│СИўтцќТќйУеГсђЇ[8]сЂДсЂѓсѓІсЂесЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓсЂЊсЂ«ухљТъютЙЊТЮЦсЂ«уљєУДБсЂФт»ЙсЂЌсђЂуЅ╣сЂФтЅЇТќ╣жЃесЂ«тйбуіХсЂїтцДсЂЇсЂЈтЅісѓЅсѓїсѓІухљТъюсЂесЂфсЂБсЂЪсђѓ тб│СИўтЁеСйЊсЂ»сђЂтб│СИўУЦ┐тЂ┤сЂФу»ЅжђатЈ»УЃйсЂфсѓ╣сЃџсЃ╝сѓ╣сѓњТ«ІсЂЌсЂфсЂїсѓЅсѓѓсђЂсЂѓсЂѕсЂдтЅЇТќ╣жЃесѓѓтЙїТќ╣жЃесѓѓт░ЙТа╣тЇЌТЮ▒уФ»сЂјсѓісЂјсѓісЂФУ┐ФсЂБсЂЪтйбсЂ«тЇатю░сЂДсЂѓсѓІсђѓ тб│СИўсЂ»тю░т▒▒сѓњтЅісѓітЄ║сЂЌсђЂУ░ижЃесЂФсЂ»тюЪсѓњУБюсЂБсЂдТЋ┤тйбсЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓТЋ┤тйбТЎѓсЂ«уЏЏтюЪсЂФсЂ»2уе«жАъсЂ«тюЪсѓњС║цС║њсЂФуфЂсЂЇтЏ║сѓЂсЂЪуЅѕу»ЅТіђТ│ЋсѓёсђЂтюЪсЂФжбетїќт┤ЕтБісЂЌсЂЪУі▒т┤Ќт▓ЕсЂ«у▓њсѓњТиисЂюУЙ╝сѓЊсЂаТЮљТќЎсЂфсЂЕсѓњСй┐ућесЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓ УЉ║уЪ│сЂїУЉ║сЂІсѓїсЂдсЂёсѓІу»ётЏ▓сЂ»2Т«ху»ЅТѕљсЂДсђЂСИГТ«хсЂ«сЃєсЃЕсѓ╣сЂїсЂ╗сЂ╝Т░┤т╣│сЂФтб│СИўсѓњтЁетЉесЂЎсѓІсђѓ УЉ║уЪ│уЎ║ТјўУф┐ТЪ╗ТЎѓсЂ«УЉ║уЪ│сЂ«Т«ІтГўуіХТ│ЂсЂ»УЅ»тЦйсђѓуЪ│ТЮљсЂ»ТюђтцДтЙёсЂї40-60сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂ20-30сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂ10сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФтЅЇтЙїсЂ«3уе«жАъсѓњСй┐ућесђѓ тЪ║ТюгуџёсЂфУЉ║сЂЇТќ╣сЂ»сђЂтб│СИўсЂ«СИІТ«хсЂ«УБЙуЪ│сЂФсЂ»40-60сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂ«сѓѓсЂ«сѓњсђЂтб│СИўСИіТ«хсЂ«УЉ║уЪ│УБЙсЂісѓѕсЂ│тї║ућ╗уЪ│тѕЌсЂФсЂ»20-30сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂ«сѓѓсЂ«сѓњСй┐ућесЂЌсђЂтї║ућ╗сЂ«СИГсѓњ20-30сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂісѓѕсЂ│10сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФтЅЇтЙїсЂ«уЪ│ТЮљсЂДтЁЁтАФсЂЎсѓІТќ╣Т│ЋсЂДсЂѓсѓІсђѓ С╗ЦСИісЂ«3уе«жАъсЂ«УЉ║уЪ│сЂесЂ»тѕЦТа╝сЂФсђЂуЏ┤тЙё1сЃАсЃ╝сЃѕсЃФтЅЇтЙїсЂ«СИЇТЋ┤тєєтйбсЂ«тцДтъІт▓ЕуЪ│2тђІсѓњсђЂсЂЈсЂ│сѓїжЃесЂФУ┐ЉсЂётЙїТќ╣жЃеСИіТ«хСИГСйЇсЂФтхїсѓЂУЙ╝сѓЊсЂДсЂёсѓІ[6][9]сђѓ Сй┐ућеуЪ│ТЮљсЂ«60%сЂ»уЅЄж║╗т▓ЕжАъсђЂ22%сЂїуЈфУ│фт▓ЕсђЂ15%сЂїУі▒т┤Ќт▓ЕжАъсђЂ1.6%сЂїУ╝ЮуЪ│т«Ѕт▒▒т▓ЕжАъсђЂТ«ІсѓісЂёсЂџсѓїсѓѓ1%ТюфТ║ђсЂДуЪ│уЂ░т▓ЕжАъсђЂуЂФуаЋт▓ЕжАъсђЂухљТЎХУ│фуЪ│уЂ░т▓ЕсђЂсЃЄсѓцсѓхсѓцсЃѕсЂїуХџсЂЈсђѓ сЂЊсѓїсѓЅсЂ«сЂєсЂАсђЂСИ╗сЂЪсѓІуЅЄж║╗т▓ЕжАъсђЂуЈфУ│фт▓ЕсђЂУі▒т┤Ќт▓ЕжАъсђЂуЂФуаЋт▓ЕжАъсђЂухљТЎХУ│фуЪ│уЂ░т▓ЕсЂ«5уе«сЂ»сђЂтЈцтб│уЙцсЂїсЂѓсѓІуюЅСИѕт▒▒СИђтИ»сЂФтѕєтИЃсЂЎсѓІТќ░уггСИЅу┤ђСИГТќ░СИќсЂ«уцФт▓Ет▒цсѓёуЂФуаЋт▓ЕжАъсЂІсѓЅТ┤ЌсЂётЄ║сЂЋсѓїсЂЪуцФсЂїтЈцтб│С╗ўУ┐ЉсЂ«У░итиЮсЂФТЋБтюесЂЌсђЂсЂЮсѓїсѓЅсѓњТјАуЪ│сЂЌсЂЪсѓЅсЂЌсЂёсђѓУ╝ЮуЪ│т«Ѕт▒▒т▓ЕсЂ»сђЂтЈцтб│уЙцсЂІсѓЅжЏбсѓїсЂЪт┐ЌУ│ђућ║сЃ╗уЂўТхдтю░тЪЪсЂ«Тхит▓ИсЂ«Т╝ѓуцФсѓётјЪт▓ЕсѓњТјАуЪ│сЂЌсЂЪсѓЅсЂЌсЂёсђѓсЃЄсѓцсѓхсѓцсЃѕсЂ»сђЂУЃйуЎ╗тЇіт│ХтїЌжЃесЂФтѕєтИЃсЂЎсѓІТќ░уггСИЅу┤ђСИГТќ░СИќтЅЇТюЪсЂ«уЕ┤Т░┤у┤»т▒цтєЁсЂ«сѓѓсЂ«сѓњТјАуЪ│сЂЌсЂЪсѓЅсЂЌсЂё[10]сђѓ тЪІУЉгТќйУеГ тЪІУЉгТќйУеГсЂ»тЙїТќ╣жЃежаѓт╣│тЮджЮбсЂФ2тЪ║уб║УфЇсђѓтЙїТќ╣жЃежаѓт╣│тЮджЮбсЂ«сЂ╗сЂ╝СИГтц«сЂФСйЇуй«сЂЎсѓІугг1тЪІУЉгТќйУеГсЂесђЂсЂЮсЂ«УЦ┐тЂ┤сЂФСйЇуй«сЂЎсѓІугг2тЪІУЉгТќйУеГсЂДсЂѓсѓісђЂтЪІУЉгжаєт║ЈсЂ»угг1тЪІУЉгТќйУеГсЂїтЁѕУАїсђѓ
угг1тЪІУЉгТќйУеГсЂФС╝┤сЂєтбЊтБЎсЂ»сђЂСИђТЌдтб│жаѓжЃесЂЙсЂДтб│СИўсѓњСйюсѓіСИісЂњсЂЪтЙїсЂФТјўсѓіУЙ╝сѓЊсЂаТјўсѓіУЙ╝сЂ┐тбЊтБЎсЂДсЂѓсѓІсђѓсЂЮсЂ«УдЈТеАсЂ»тЇЌтїЌ8.6сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂТЮ▒УЦ┐4.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФС╗ЦСИісђЂТи▒сЂЋ1.2сЃАсЃ╝сЃѕсЃФтЅЇтЙїсђѓ угг1тЪІУЉгТќйУеГсЂ»у▓ўтюЪТДесЂДсЂѓсѓісђЂтЁежЋи7.2сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂт╣Ё2сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЅ▓уФ╣тйбТюеТБ║сѓњтєЁУћхсЂЎсѓІсђѓтЅ▓уФ╣тйбТюеТБ║сЂ»жЋисЂЋ6.2сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂт╣Ё80сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂДсЂѓсѓІсђѓтбЊтБЎт║ЋсѓѕсѓісЂЋсѓЅсЂФ70сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФТјўсѓіУЙ╝сѓЊсЂДУеГуй«сђѓтЅ▓уФ╣тйбТюеТБ║сЂ«т░ЈтЈБсЂФсЂ»сђЂУЊІсЃ╗У║ФсЂесѓѓсЂФуИёТјЏуфЂУхисЂїсЂѓсЂБсЂЪсђѓ сЂЙсЂЪуИёТјЏуфЂУхисЂ«СйЇуй«сЂІсѓЅТБ║У║ФсЂїТи▒сЂЈсђЂТБ║УЊІсЂїУќёсЂёТДІжђасЂеУђЃсЂѕсЂдсЂёсѓІсђѓ тЅ»УЉгтЊЂсЂ«СйЇуй«сЂІсѓЅсђЂТБ║тєЁсЂ»3сЂцсЂ«тї║ућ╗сЂФС╗ЋтѕЄсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЪсЂеТјет«џсђѓ у▓ўтюЪТДесЂ«УбФУдєу▓ўтюЪтцќжЮбсЂФсЂ»сђЂСИИтцфуіХсЂ«жЂЊтЁисЂФсѓѕсѓІсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІтЈЕсЂЇуиасѓЂсЂ«уЌЋУиАсЂїТ«ІсѓІсђѓ угг1тЪІУЉгТќйУеГСИГтц«сЂФуЏ┤тЙё2.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂуЈЙтб│жаѓжЮб№╝ѕТЋ┤тѓЎтЅЇ№╝Ѕсѓѕсѓі1.8сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂ«Ти▒сЂЋсЂФсЂісѓѕсЂХуЏЌТјўуЕ┤сЂїсЂѓсѓісђЂТБ║тєЁсЂ«СИђжЃесЂФсѓѓтЈісЂХсђѓ
угг2тЪІУЉгТќйУеГсЂФС╝┤сЂєтбЊтБЎсЂ»сђЂтЇЌтїЌ10сЃАсЃ╝сЃѕсЃФС╗ЦСИісђЂТЮ▒УЦ┐4.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФС╗ЦСИісЂДсђЂугг1тЪІУЉгТќйУеГсѓѕсѓітцДсЂЇсЂёсђѓ тбЊтБЎСИіт▒цжЃесѓњТцютЄ║сђЂСИђжЃесЂ«сЃѕсЃгсЃ│сЃЂуЎ║ТјўС╗ЦтцќсЂ»тєЁжЃеТюфуЎ║ТјўсђЂТюеТБ║уЏ┤УЉгсѓњТЃ│т«џ[6]сђѓ сЂфсЂісђЂтЅЇТќ╣жЃесЂФуцЙТ«┐сѓњСйюсѓІсЂЪсѓЂтЅЇТќ╣жЃесѓњтЅіт╣│сЂЌсЂЪжџЏсђЂт«Ѕт▒▒т▓ЕУ│фТЮ┐уЪ│сѓњт░ЈтЈБуЕЇсЂФу»ЅсЂёсЂЪуФфуЕ┤т╝ЈуЪ│т«цсЂ«СИђжЃесЂїжю▓тЉѕсЂЌсђЂтЅЇТќ╣жЃесЂФсѓѓтЪІУЉгТќйУеГсЂїсЂѓсѓІсЂесЂЌсЂдсЂёсЂЪ[4]сЂїсђЂ1990т╣┤С╗БсЂ«уЎ║ТјўУф┐ТЪ╗сЂДсЂ»ТцютЄ║сЂДсЂЇсЂфсЂІсЂБсЂЪсђѓ ТБ║тєЁтЅ»УЉгтЊЂугг1тЪІУЉгТќйУеГсЂ«тЅ▓уФ╣тйбТюеТБ║тєЁсЂ«3сЂцсЂ«тї║ућ╗сЂІсѓЅжЂ║уЅЕсЂїтЄ║тюЪсђѓ
У╗іУ╝фуЪ│сЃ╗уЪ│жЄДсѓњтљѕсѓЈсЂЏсЂд19тђІтЄ║тюЪсЂЌсђЂуЋ┐тєЁсѓњжЎцсЂЉсЂ░уфЂтЄ║сЂЌсЂЪТЋ░сЂесЂёсЂєсђѓжіЁжЈЃсЂ»52ТюгтЄ║тюЪсЂЌсђЂсЂЎсЂ╣сЂдТЪ│УЉЅтйбсђѓ жіЁжЈАсЂ»уЏ┤тЙё17сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЇітєєТќ╣Та╝тИ»сѓњТїЂсЂцсђѓсЂ╗сЂ╝т«їтйбсђѓжЈАжЮбсЂ«СИђжЃесЂФт╣│у╣ћсѓісЂ«ух╣сЂ«у╣ћуЅЕуЅЄсЂїС╗ўуЮђсђѓсЂЙсЂЪжЈАсЂ«СИІсЂІсѓЅУЁљТюйсЂЌсЂЪТюеуЅЄсЂїтЄ║тюЪсђѓУбФУЉгУђЁсЂ«жаГжЃеТЮ▒тЂ┤сЂФСйЇуй«сђѓ сЂЙсЂЪтЅЇТюЪтЈцтб│сЂДсЂ«Тќ╣тйбТЮ┐жЮЕуХ┤уЪГућ▓сЂ«тЄ║тюЪСЙІсЂ»тЁетЏйуџёсЂФсѓѓт░ЉсЂфсЂё[6]сђѓ тЄ║тюЪтюЪтЎетюЪтЎеуЅЄсЂїСИІУеўтђІСйЊтѕєсђЂтб│СИўСИісЂІсѓЅтЄ║тюЪсђѓ тЙїТќ╣жЃеУЦ┐УБЙсЂесЂЈсЂ│сѓїжЃесЂДС║їжЄЇтЈБуИЂтБ║2тђІСйЊсђЂтЙїТќ╣жЃетЇЌУБЙсЂІсѓЅжЏєСИГтЄ║тюЪсЂЌсЂЪСИГтъІуЏ┤тЈБтБ║1тђІСйЊсђЂт░ЈтъІСИИт║ЋжЅб4тђІСйЊсђЂућЋ1тђІСйЊсђЂТЅІТЇЈтюЪтЎе1тђІСйЊсђЂжФўтЮЈ15тђІСйЊС╗ЦСИісђЂтБ║т║ЋжЃе7тђІСйЊсђѓТЉЕТ╗ЁсЂїУЉЌсЂЌсЂёу┤░уЅЄсЂїсЂ╗сЂесѓЊсЂЕсЂДсЂѓсѓІ[6]сђѓ у»Ѕжђат╣┤С╗БсђјтЈ▓УиАжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсђЈ[6]сЂДсЂ»тЈцтб│ТЎѓС╗БтЅЇТюЪсѓњ4ТюЪсЂФтѕєсЂЉсѓІУђЃсЂѕ[11][12]сЂФтЙЊсЂёсђЂ3ТюЪтЙїтЇісЂІсѓЅ4ТюЪтѕЮсѓЂжаЃсЂеухљУФќС╗ўсЂЉсЂдсЂёсѓІсђѓсЂЮсЂ«Та╣ТІасЂ»СИІУеўУђЃт»ЪсЂФсѓѕсЂБсЂдсЂёсѓІсђѓ
2тЈитб│ 3DCGсЂДТЈЈућ╗сЂЌсЂЪ2тЈитб│ ТЅІтЅЇсЂ«жџєУхисЂ»7тЈитб│   1990т╣┤С╗БсЂФУЉ║уЪ│у»ётЏ▓уб║УфЇсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«8сЂІТЅђсЂ«сЃѕсЃгсЃ│сЃЂуЎ║Тјўсѓњт«ЪТќйсђѓ тб│СИў1тЈитб│сЂ«тїЌТЮ▒Тќ╣сЂФСйЇуй«сЂЌсђЂ1тЈитб│сЂесЂ«Т»ћжФў4.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФ№╝ѕтб│жаѓжЃесЂЕсЂєсЂЌсЂ«Т»ћУ╝Ѓ№╝ЅсЂДСйјсЂЈсђЂтЅЇТќ╣жЃесѓњ1тЈитб│сЂФтљЉсЂЉсЂЪтйбсѓњсЂфсЂЎсђѓ тЁежЋи65.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЙїтєєжЃетЙё42сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂтЅЇТќ╣жЃетЅЇуФ»т╣Ё28сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂсЂЈсЂ│сѓїжЃет╣Ё25.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсѓњТИгсѓІ[8]сђѓ 1тЈитб│сЂетљїТДўсЂФсђЂсђјжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсЂ«Уф┐ТЪ╗сђЈ[4]С╗ЦтЅЇсЂ«ТќЄуї«сЂДсЂ»сђЂтЁежЋи70сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсЂеУеўУ╝ЅсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЪсђѓ1990т╣┤С╗БсЂ«уЎ║ТјўУф┐ТЪ╗уЏ┤тЅЇсЂ«уЈЙтю░УАесЂФт»ЙсЂЎсѓІТИгжЄЈ№╝ѕ1991т╣┤сђЂУѕфуЕ║тєЎуюЪТИгжЄЈсЂФсѓѕсѓІ№╝ЅсЂДсЂ»тЁежЋи72-74сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсѓњТИгсЂБсЂдсЂёсЂЪ[7]сђѓсЂЌсЂІсЂЌсЂфсЂїсѓЅ1тЈитб│сЂетљїсЂўсЂЈсђїУЉ║уЪ│сЂїТќйсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІу»ётЏ▓сЂїсЂЎсЂфсѓЈсЂАтб│СИўсЂДсЂѓсѓІсђЇсЂесЂёсЂєуљєУДБсЂ«сѓѓсЂесђЂС┐«ТГБсЂЌсЂЪсЂ«сЂїСИіУеўсЂ«тђцсЂДсЂѓсѓІсђѓ УЉ║уЪ│сЂїУЉ║сЂІсѓїсЂдсЂёсѓІу»ётЏ▓сЂ»2Т«ху»ЅТѕљсЂДсђЂСИГТ«хсЂ«сЃєсЃЕсѓ╣сЂїсЂ╗сЂ╝Т░┤т╣│сЂФтб│СИўсѓњтЁетЉесЂЎсѓІсђѓтЅЇТќ╣жЃетЅЇжЮбсЂФ3Т«хуЏ«сЂ«Т«хсЂїСйюсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂїсЂЊсѓїС╗ЦтцќсЂФ3Т«хуЏ«сЂ»уб║УфЇсЂДсЂЇсЂџсђѓ УЉ║уЪ│сѓѕсѓіСИІт▒цсЂ»Уф┐ТЪ╗сЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёсЂЪсѓЂсђЂтб│СИўсЂ«ТДІжђауГЅсЂ»СИЇТўјсђѓ УЉ║уЪ│тЙїтєєжЃесЃ╗тЅЇТќ╣жЃесЂесѓѓТўјуъГсЂфУБЙуЪ│сѓњуб║УфЇсђѓУЉ║уЪ│уЪ│ТЮљсЂ«тцДсЂЇсЂЋсЂ»1тЈитб│сЂетљїТДўсѓЅсЂЌсЂёсђѓсЂЌсЂІсЂЌсЂфсЂїсѓЅтЅЇТќ╣жЃетЅЇжЮбсЂ«УБЙуЪ│сЃ╗УЉ║уЪ│сЂ»сђЂтЙїтєєжЃесЂ«сЂЮсѓїсѓѕсѓіт░ЈсЂЋсЂфуЪ│сЂїтцџсЂёсѓѕсЂєсЂДсЂѓсѓІ[8]сђѓ тЪІУЉгТќйУеГтЙїтєєжЃетб│жаѓсЂФуЏ«уФІсЂБсЂЪС╣▒сѓїсЂ»сЂфсЂЈсђЂуЏЌТјўсѓњтЈЌсЂЉсЂдсЂёсЂфсЂётЈ»УЃйТђДсЂїжФўсЂёсђѓ тЇЌтїЌТќ╣тљЉсЂФУ╗ИсѓњТїЂсЂцу▓ўтюЪТДесЂЙсЂЪсЂ»ТюеТБ║уЏ┤УЉгсѓњТЃ│т«џсђѓ№╝ѕТЋ┤тѓЎС║ІТЦГсЂ«СИђуФ»сЂДУеГуй«сЂЌсЂЪУДБУфгТЮ┐сЂ«сЂЪсѓЂсЂ«т║іТјўсѓісЂ«жџЏсЂФж╗њсЂёсѓисЃЪсЂ«сѓѕсЂєсЂфт▒цсѓњуб║УфЇсђѓтЪІУЉгТќйУеГсЂ«жЎЦТ▓АсЂФсѓѕсѓІж╗њУЅ▓тюЪсЂ«тЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓІ№╝Ѕ[8]сђѓ
3тЈитб│ 1тЈитб│сЂІсѓЅтЇЌсЂФсђїТќ░жђџУ░итєЁсђЇсЂетЉ╝сЂ░сѓїсѓІуІГт░ЈсЂфТћ»т░ЙТа╣сЂїтѕєт▓љсЂЌт╣│жЄјтЂ┤сЂФСИІжЎЇсЂЎсѓІсђѓ3тЈитб│сЂ»сЂЊсЂ«т░ЙТа╣СИісЂФтѕєтИЃсЂЎсѓІтЈцтб│СИГсЂДТюђтцДУдЈТеАсЂ«тєєтб│сђѓт░ЙТа╣сЂїт░ЈжаѓжЃесѓњСйюсЂБсЂдТђЦжЎЇСИІсЂЎсѓІт░ЙТа╣уГІСИісЂ«ТюђжЂЕТЅђсѓњтЇасѓЂсѓІсђѓсЂІсЂцсЂдтб│жаѓжЃесЂФТёЏт«ЋуЦъсЂ«уцЙуЦасЂїсЂѓсЂБсЂЪсЂеС╝ЮсЂѕсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂїсђЂтб│СИўсЂ«т┤ЕсѓїсЂ»сЂ╗сЂесѓЊсЂЕсЂфсЂЈсђЂТЋ┤уЙјсЂфтЇіТѕфтєєжїљтйбсѓњтЉѕсЂЎсѓІсђѓУБЙжЃесЂФтю░т▒▒сѓњтЅіт╣│сЂЌсЂЪсЃєсЃЕсѓ╣жЮбсЂїсѓЂсЂљсѓІсђѓУЉ║уЪ│сЃ╗тЪ┤У╝фуГЅсЂ«уб║УфЇсЂфсЂЌ[4]сђѓ 5сЃ╗6сЃ╗7тЈитб│ 1990т╣┤С╗БсЂФуЎ║ТјўУф┐ТЪ╗сѓњт«ЪТќйсђѓ2тЈитб│сЂ«ТЮ▒сЂ«тб│УБЙсЂФС║њсЂёсЂФт»ёсѓіТи╗сЂєсѓѕсЂєсЂФСйЇуй«сЂЎсѓІсђѓ2тЈитб│Рєњ7тЈитб│Рєњ5тЈитб│Рєњ6тЈитб│сЂ«жаєсЂФу»Ѕжђасђѓ№╝ѕсЃѕсЃгсЃ│сЃЂуЎ║ТјўсЂФсѓѕсѓІС║њсЂёсЂ«т▒цт║ЈсЂІсѓЅтѕцТўј) 5тЈитб│т░ЙТа╣сѓњтЅісѓітЄ║сЂЌсђЂСИђжЃесЂФуЏЏтюЪсѓњТќйсЂЌсЂду»Ѕжђасђѓ тЪІУЉгТќйУеГсЂ»ТюеТБ║уЏ┤УЉгсѓњТЃ│т«џсђѓтб│СИўСИГтц«сЂФСйЇуй«сЂЌсђЂжЋисЂЋ5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂт╣Ё1.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓтЇЌтїЌТќ╣тљЉсЂФУ╗ИсѓњТїЂсЂцсђѓ жЂ║уЅЕсЂ«тЄ║тюЪсЂфсЂЌ[15]сђѓ 6тЈитб│т░ЙТа╣сѓњтЅісѓітЄ║сЂЌсђЂСИђжЃесЂФуЏЏтюЪсѓњТќйсЂЌсЂду»Ѕжђасђѓтб│жаѓжЃет╣│тЮджЮбуЏ┤тЙё6сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓ тЪІУЉгТќйУеГсЂ»ТюеТБ║уЏ┤УЉгсѓњТЃ│т«џсђѓтб│СИўСИГтц«сЂФСйЇуй«сЂЌсђЂжЋисЂЋ4сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂт╣Ё2.3сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓN50┬░WТќ╣тљЉсЂФУ╗ИсѓњТїЂсЂцсђѓ жЂ║уЅЕсЂ«тЄ║тюЪсЂфсЂЌ[15]сђѓ 7тЈитб│т░ЙТа╣сѓњтЅісѓітЄ║сЂЌсђЂуЏЏтюЪсѓњТќйсЂЌсЂду»ЅжђасЂЎсѓІсЂїсђЂ5сЃ╗6тЈитб│сѓѕсѓіуЏЏтюЪсЂїтцџсЂёсђѓтб│СИўсЂ»УЦ┐№йътїЌ№йъТЮ▒сЂ«сЂ┐сѓњТЋ┤тйбсЂЌсђЂ5тЈитб│тЂ┤сЂ«ТЋ┤тйбсѓњуюЂуЋЦсђѓтб│жаѓжЃет╣│тЮджЮбуЏ┤тЙё5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓ тЪІУЉгТќйУеГсЂ»ТюеТБ║уЏ┤УЉгсѓњТЃ│т«џсђѓтб│СИўСИГтц«сЂФСйЇуй«сЂЌсђЂжЋисЂЋСИЇТўј№╝ѕтђњТюетјЪтЏасЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІТћфС╣▒уЕ┤сЂ«сЂЪсѓЂ№╝ЅсђЂт╣Ё1.5сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓN50┬░WТќ╣тљЉсЂФУ╗ИсѓњТїЂсЂцсђѓТБ║сЂ»тЅ▓уФ╣тйбТюеТБ║сЂесЂ┐сѓЅсѓїсђЂТБ║сЂ«т╣Ё50сѓ╗сЃ│сЃЂсЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓ жЂ║уЅЕсЂ«тЄ║тюЪсЂфсЂЌ[15]сђѓ 17тЈитб│ 1990т╣┤С╗БсЂФуЎ║ТјўУф┐ТЪ╗сѓњт«ЪТќйсђѓ тб│СИў1тЈитб│сЂІсѓЅтЇЌУЦ┐сЂФсЂ«сЂ│сѓІуІГсЂёт░ЙТа╣СИісЂФуФІтю░сђѓуЈЙТ│ЂТеЎжФўсЂ»180.75сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓтб│тйбсЂ»сЂёсЂ│сЂцсЂфтєєтйбсЂДсђЂтб│жаѓжЃет╣│тЮджЮбсЂ»т║ЃсЂІсЂБсЂЪсѓЅсЂЌсЂёсђѓУхцТхдуаѓсЂ«тю░т▒▒№╝ѕТўјж╗ёУцљУЅ▓уаѓУ│фтюЪ№╝ЅсѓњтЅісѓітЄ║сЂЌсђЂуЏЏтюЪ№╝ѕУі▒т┤Ќт▓ЕсЂ«жбетїќуцФсЂїТиитЁЦсЂЎсѓІж╗ёУцљУЅ▓у▓ўУ│фтюЪсђЂсЂЌсЂЙсѓіт╝исЂё№╝ЅсѓњУАїсЂєсЂЊсЂесЂДтб│СИўсѓњу»ЅТѕљсђѓтб│СИўсЂ«ТЮ▒тЂ┤сЃ╗тЇЌУЦ┐тЂ┤сЂДсђЂт░ЙТа╣уГІсѓњсѓФсЃЃсЃѕсЂЌсЂЪтЉеТ║ЮсѓњТцютЄ║сђѓт╣Ё1.1-2.2сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђЂТи▒сЂЋ0.4-0.8сЃАсЃ╝сЃѕсЃФсђѓсЂЊсЂ«тЉеТ║ЮсЂ»тб│СИўсѓњтЁетЉесЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёсђѓ УЉ║уЪ│сЃ╗Т«ху»ЅсЂ«уб║УфЇсЂфсЂЌсђѓ тЪІУЉгТќйУеГуФфуЕ┤т╝ЈуЪ│т«цсѓњуб║УфЇсђѓтб│СИўсЂ«СИГт┐ЃсЂІсѓЅжЏбсѓїсЂЪСйЇуй«сЂФсЂѓсѓІсђѓтєЁжЃесЂ»ТюфУф┐ТЪ╗сђѓсЂфсЂітб│СИўСИГт┐ЃсЂФТќ╣тйбсЂ«тюЪтЮЉсѓњТцютЄ║сЂЌсЂЪсЂїсђЂТђДТа╝сЂ»СИЇТўјсђѓ у»Ѕжђат╣┤С╗Б1тЈитб│сЂФтЁѕУАїсЂЌсЂду»Ѕжђа№╝ѕтЉеТ║ЮсЂ«тюЪт▒цтаєуЕЇуіХТ│ЂсЂІсѓЅ№╝ЅсђѓТЎѓТюЪсЂїтѕцтѕЦсЂДсЂЇсѓІтЄ║тюЪжЂ║уЅЕсЂфсЂЌ[16]сђѓ R36тЈитб│СИГУЃйуЎ╗ућ║сЃ╗ТЌДж╣┐УЦ┐ућ║сЂї36тЈитб│сЂесЂЎсѓІтЈцтб│сђѓ 1990т╣┤С╗БсЂФуЎ║ТјўУф┐ТЪ╗сѓњт«ЪТќйсђѓ т░ЙТа╣сЂ«ТїЅжЃесЂФуФІтю░сђѓуЏЏтюЪсѓњсѓЈсЂџсЂІсЂФУфЇсѓЂсѓІсђѓТ«ху»ЅсЃ╗УЉ║уЪ│сЂ«уб║УфЇсЂфсЂЌсђѓтЉеТ║ЮсЂ»тѕцуёХсЂесЂЌсЂфсЂёсђѓжЏєуЪ│сЃ╗тѕЌуЪ│сЂѓсѓісђѓ тЪІУЉгТќйУеГсЂ»ТюеТБ║сЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІсЂїсђЂтйбуіХСИЇТўјсђѓ тЄ║тюЪжЂ║уЅЕсЂ»сђЂжЅёУБйтЊЂсЂеу«АујЅсЃ╗тІЙујЅсЃ╗УЄ╝ујЅсђѓ т╣┤С╗БсЂ»сђЂтЈцтб│ТЎѓС╗БСИГТюЪСИГУЉЅтЅЇтЙї№╝ѕујЅжАъсЂ«ТЮљУ│фсЂїу▓ўТЮ┐т▓ЕсЃ╗уЪ│уЂ░т▓ЕсЂДсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂІсѓЅ№╝Ѕсђѓ тЈцтб│сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂСйЋсѓЅсЂІсЂ«уЦГуЦђжЂ║УиАсЂ«тЈ»УЃйТђДсѓѓсЂѓсѓІ[17]сђѓ жЏесЂ«т««1сЃ╗2тЈитб│сѓњтЈќсѓіти╗сЂЈТГ┤тЈ▓уџёуњ░тбЃ 1тЈитб│сЂе2тЈитб│сЂесЂ»тб│тйбсЂїтЅЇТќ╣тЙїТќ╣тб│сЂетЅЇТќ╣тЙїтєєтб│сЂесЂ«жЂЋсЂёсЂ»сЂѓсѓІсЂїсђЂтЁежЋисђЂтб│жаѓт╣│тЮджЮбсђЂтЅЇТќ╣жЃет╣│тЮджЮбсђЂТ«ху»ЅсЂ«СйЇуй«сђЂтЅЇТќ╣жЃесЂ«жќІсЂЇсЂфсЂЕжАъС╝╝ТђДсЂїт╝исЂЈсђЂтљїсЂўУеГУеѕУдЈТа╝сѓѕсѓІсѓѓсЂ«сЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІ[8]сђѓ сЂЙсЂЪ2тЈитб│сЂ»сђЂуЋ┐тєЁсЂ«тцДтъІтЈцтб│сЂДсЂѓсѓІтЦѕУЅ»тИѓСйљу┤ђуЪ│тАџт▒▒тЈцтб│сЂесЂ«жќЊсЂФ1:3сђЂтЦѕУЅ»тИѓС║ћуцЙуЦътЈцтб│сЂесЂ«жќЊсЂФ1:4сЂесЂёсЂБсЂЪТЋ┤ТЋ░Т»ћсЂДуЏИС╝╝жќбС┐ѓсЂїсЂѓсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїТїЄТЉўсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІ[4][18]сђѓ сЂЙсЂЪ2тЈитб│сЂ»сђЂтљїсЂўУЃйуЎ╗сЂ«тЈцтб│сЂДсѓѓсђЂСИЃт░ЙтИѓТИЕС║Ћ15тЈитб│[19]№╝ѕ6СИќу┤ђтѕЮжаГ№╝ЅсЂесЂ«жќЊсЂФсђЂт╣┤С╗БсѓњУХісЂѕсЂд4:1сЂ«уЏИС╝╝жќбС┐ѓсЂїсЂѓсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїТїЄТЉўсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІ[18]сђѓ СИђТќ╣сђЂжѓЉуЪЦТйЪтю░Т║ЮтИ»сѓњТїЪсѓЊсЂДсђЂжЏесЂ«т««тЈцтб│уЙцсЂет»Йт│ЎсЂЎсѓІСйЇуй«сЂФсЂѓсѓІСИГУЃйуЎ╗ућ║т░Јућ░СИГсЂ«УдфујІтАџтЈцтб│№╝ѕтЙё67mсЂ«тєєтб│№╝ЅсђЂС║ђтАџтЈцтб│№╝ѕтЁежЋи61mсЂ«тЅЇТќ╣тЙїТќ╣тб│№╝Ѕ[20][21]сЂ»сђЂжЏесЂ«т««1сЃ╗2тЈитб│сЂеу»ЅжђаТЎѓТюЪсЂїУ┐ЉсЂёсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІсЂЊсЂесђЂтљїсЂўсЂЈтєєу│╗сЂеТќ╣у│╗сЂ«тЈцтб│сЂїт»ЙсЂФсЂфсЂБсЂЪТДІТѕљсЂДсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂІсѓЅсђЂтЈцсЂЈсѓѕсѓіТ»ћУ╝ЃТцюУејсЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсђѓ жЏесЂ«т««тЈцтб│тЁгтюњ  2010т╣┤ 1994т╣┤сЂІсѓЅТќЄтїќт║ЂсЂ«тЈ▓УиАуГЅТ┤╗ућеуЅ╣тѕЦС║ІТЦГсЂФсѓѕсѓісђЂТюгТа╝уџёТЋ┤тѓЎсѓњжќІтДІсђѓСИ╗сЂфтєЁт«╣сЂ»СИІУеўсђѓ
1тЈитб│сЂ»у»ЅжђатйЊТЎѓсЂ«тб│СИўсЂ«жФўсЂЋсѓњтєЇуЈЙсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсђЂуЎ║ТјўУф┐ТЪ╗тЅЇсЂ«тю░УАежЮбсЂФуЏЏтюЪсѓњТќйсЂЌсЂЪсђѓсЂЮсЂ«сЂЙсЂЙсЂДсЂ»тб│жаѓжЃесЂФсЂѓсѓІСИЅУДњуѓ╣ТеЎуЪ│сЂїтЪІсЂЙсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂЪсѓЂсђЂТеЎуЪ│сЂФуГњуіХсЂ«УдєсЂёсѓњсЂІсЂХсЂЏсЂдт»ЙуГќсЂЌсЂдсЂёсѓІсђѓсђђ Уф┐ТЪ╗сЂеТЋ┤тѓЎт░ЈтЈ▓
тЈцтб│уЙцсѓњУѕътЈ░сЂФсЂЌсЂЪУ│ЏжіўжЏисЃХт│░сЂ«жЏїжЏёуЦъС║ђ№╝ѕ2тЈитб│сЃ╗1тЈитб│№╝ЅсЂФсЂцсЂёсЂдсђЂТќЄТћ┐19С╣ЎС║Цт╣┤сђЂућ▓жЎйжи║т▒▒жђИтБФжю▓ТЏЅсЂФсѓѕсЂБсЂдтЦЅсѓЅсѓїсЂЪсЂесЂЎсѓІСИІУеўсЂ«У│ЏжіўсЂїТ«ІсѓІ[1]сђѓ Т╗ІТГ│тцЈУЕБТќ╝уЋХуцЙуЪБсђЂТЅ┐уЦъС╣Іт╣┤УГюУђїтЦЅтЁЕжЪ╗ ТќЄтїќУ▓АжЄЇУдЂТќЄтїќУ▓А№╝ѕтЏйТїЄт«џ№╝Ѕ
тЏйсЂ«тЈ▓УиА
уЪ│тиЮуюїТїЄт«џТќЄтїќУ▓А
С║цжђџсѓбсѓ»сѓ╗сѓ╣
УёџТ│е
жќбжђБжаЁуЏ«тцќжЃесЃфсЃ│сѓ»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia