„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ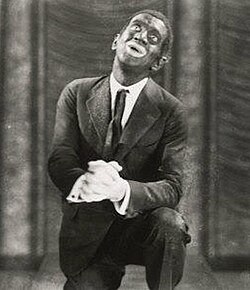 „Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ (Ëã±Ë™û: blackface) „ÅØ„ÄÅȪí‰∫∫‰ª•Â§ñ„ÅÆʺîËÄÖ„ÅåȪí‰∫∫„Çíʺî„Åò„Çã„Åü„ÇÅ„Å´ÊñΩ„ÅôËàûÂè∞ÂåñÁ≤ß„ÄÅ„Åù„Çå„Ŵ˵∑ÂõÝ„Åô„ÇãʺîËÄÖ„Åä„Çà„Å≥ʺîÁõÆ„ÄÇ19‰∏ñÁ¥Ä„ŴʵÅË°å„Åó„ÄÅ„Äå„Éó„É©„É≥„É܄ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÅÆ„Éè„ÉÉ„Éî„ɺ„ɪ„Ç¥„ɺ„ɪ„É©„ÉÉ„Ç≠„ɺ„ɪ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„Äç(„ÅÆ„Çì„Åç„řȪí‰∫∫„ÄÇ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅØËîëÁß∞)„ÄÅ„Äå„ÉÄ„É≥„Éá„Ç£„ɪ„Ç؄ɺ„É≥„Äç(„Ç؄ɺ„É≥„ÅØȪí‰∫∫„ÇíË°®„ÅôËîëÁß∞)„Å™„Å©‰∫∫Á®ÆÁöÑ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„ÇíÂ∫É„ÇÅ„ÇãÁµêÊûú„Å®„Å™„Å£„Åü[1]„ÄÇ1848Âπ¥„Åæ„Åß„Å´„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅåÂÖ®Á±≥„ÅßʵÅË°å„Åó„ÄÅ„Ç™„Éö„É©„Å™„Å©„ÅÆ„Éï„Ç©„ɺ„Éû„É´„Å™‰ΩúÂìÅ„Çí‰Ωú„ÇäÊõø„Åà„Ŷ‰∏ÄË਄ŴʵÅË°å„Åï„Åõ„Åü[2]„ÄÇ20‰∏ñÁ¥ÄÂàùÈÝ≠„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅÆÊûÝ„Åã„Çâ§ñ„Çå„ŶÁã¨ËᙄÅÆ„Çπ„Çø„ǧ„É´„Å®„Å™„Å£„Åü„Åå„ÄÅ1960Â𥉪£„ÄÅ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫ÂÖ¨Ê∞ëÊ®©ÈÅãÂãï„Å´„Çà„ÇäÁµÇÁÑâ„Åó„Åü[3]„ÄÇ  1830Âπ¥ÈÝÉ„Åã„ÇâÁ¥Ñ100Âπ¥„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÅÆÂäáÂÝ¥„Å´„Åä„ÅфŶ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÈáç˶ńř‰ºùÁµ±ÁöÑʺîÁõÆ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ„Åô„Åê„ŴʵÅË°å„ÅØÂ∫É„Åæ„Çä„Äńǧ„ÇÆ„É™„Çπ„Åß„ÅØ1978Âπ¥„Åæ„ÅßÁ∂ö„ÅÑ„Åü„ÄéThe Black and White Minstrel Show„Äè[4]„ÄÅ1976Âπ¥„Å®1981Âπ¥„ÅÆ„ÄéAre You Being Served?„Äè„ÅÆ„ÇØ„É™„Çπ„Éû„Çπ„ɪ„Çπ„Éö„Ç∑„É£„É´„ÅåÊîæÈÄÅ„Åï„Çå„Çã„Å™„Å©„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Çà„ÇäÈï∑Á∂ö„Åç„Åó„Åü[5][6]„ÄÇ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åß„ÇDŽǧ„ÇÆ„É™„Çπ„Åß„ÇÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„Å´„Åä„ÅфŶ„ÇÇ„Å£„Å®„ÇÇ„Çà„ÅèÁÅÑ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇÁôΩ‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ÅØÂàùÊúü„Å´„ÅØÁѺ„Åç„Ç≥„É´„ÇØ„ÄÅÂæåÊúü„Å´„ÅØ„Éâ„ɺ„É©„É≥„ÇÑÈù¥Â¢®„ÅßÈ°î„ÇíȪí„Åè°ó„Çä„ÄÅÂîá„Çí˙ẵ„Åó„ÄÅ„Åæ„ÅüÁ∏Æ„Çå„Åü„Ç´„ÉÑ„É©„ÄÅÊâãË¢ã„ÄÅÁáïÂ∞æÊúç„ÅÇ„Çã„ÅÑ„Å؄ź„ÇçÊúç„ÇíÁùÄÁÅô„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ„ÅÆ„Å°„ŴȪí‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ÇÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åßʺî„Åò„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ „Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅÆ„Çπ„Éà„ÉÉ„ÇØ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÇíÂÖ∑˱°Âåñ„Åó„Åü„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Å؉∫∫Á®ÆÁöфǧ„É°„ɺ„Ç∏„ÄÅË°åÂãï„ÄÅÊÑü˶ö„Çí‰∏ñÁïå‰∏≠„Ŵʧç„Åà‰ªò„Åë„Åü„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅȪí‰∫∫ÊñáÂåñ„ÅƉ∫∫Ê∞ó„Å´Êãç˪ä„Çí„Åã„Åë„Åü[7]„ÄÇÁèæÂú®„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Ç´„É™„Ç´„ÉÅ„É•„Ç¢„ÅØË≠∞Ë´ñ„Çíºï„Åç˵∑„Åì„Åô„Älj∏ÄÊñπ„Åß„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÂçò„Å´Ëá™ÂàÜ„Å®ÈÅï„ÅÜÊÄßÂà•„ÄÅË∫´ÂàÜ„Äʼn∫∫Á®Æ„ÇíË°®„ÅôÁï∞ÊÄßË£Ö„Å®ÂêåÁæ©„ÅÝ„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÑè˶ã„ÇÇ„ÅÇ„Çã[8]„ÄÇ 20‰∏ñÁ¥ÄÂçä„Å∞„Åæ„Åß„Å´‰∫∫Á®Æ„Åä„Çà„Å≥‰∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„Å´ÂØæ„Åô„ÇãËÄÉ„ÅàÊñπ„Åå§â„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åç„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å´„Çà„ÇãʺîÁõÆ„ÅØ„Å™„Åè„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÇÁèæÂú®„Åß„ÅØʺîÁõƉ∏äÂøÖ˶ńřÊôÇ„Å´Èôê„Çä„ÄÅ„Åæ„ÅüÁ§æ‰ºöÁöщ∏ªÂºµ„ÇÑÈ¢®Âà∫„Å´„ÅÆ„Åø‰ΩøÁÅï„Çå„Çã„ÄÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÊÅí‰πÖÁöÑÂΩ±Èüø„ÅØËâØ„Åè„ÇÇÊÇ™„Åè„ÇÇ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫ÊñáÂåñ„Çí‰∏ñÁïå„Å´Â∫É„ÇÅ„Çã„Åç„Å£„Åã„Åë„Å®„Å™„Å£„Åü„Åì„Å®„Å®„Åï„Çå„Çã[9][10]„ÄÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´ÊñáÂåñ„ÅÆÁõóÁî®[9][10][11]„ÄÅÊêæÂèñ„ÄÅÂêåÂåñ[9]„ÅÆÂÖàÈßÜ„Åë„Å®„ÇÇ„Å™„Çä„ÄÅÁÑ°Êï∞„Å´Ê¥æÁîü„Åó„Ŷ‰∏ñÁïå„ÅÆ„Éù„Éî„É•„É©„ɺ„ɪ„Ç´„É´„ÉÅ„É£„ɺ„ÅƉ∏ÄÈÉ®„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã[10][12][13]„ÄÇ Ê≠¥Âè≤Ȫí„Åï„ÅÆË°®Áèæ„Åä„Çà„Å≥Â∑ÆÂà•„Å∏„ÅÆÊàê„ÇäÁ´ã„Å° „Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ˵∑Ê∫ê„ÅØ„ÅØ„Å£„Åç„Çä„Åó„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„ÄÇÊñáÂåñ„Ç≥„É°„É≥„É܄ǧ„Çø„ɺ„ÅÆ„Ç∏„Éß„É≥„ɪ„Çπ„Éà„É©„Çπ„Éú„Ƕ„ÅØÈÅÖ„Åè„Å®„ÇÇË•ø„Ç¢„Éï„É™„Ç´‰∫∫„Åå„Éù„É´„Éà„Ǩ„É´„Å´ÈÄ£„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åã„Çå„Åü1441Âπ¥ÈÝÉ„Åã„Ç≺ùÁµ±ÁöÑ„Å´„ÄåÁôΩ‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„ÅÆÊ•Ω„Åó„Åø„Åä„Çà„Å≥ÂïìËíô„ÅÆ„Åü„ÇÅȪí„Åï„ÇíË°®Áèæ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Äç„Ů˙û„Å£„Åü[14]„ÄÇÁôΩ‰∫∫„Åü„Å°„ÅØ„Ç®„É™„Ç∂„Éô„ÇπÊúù„ÇÑ„Ç∏„É£„Ç≥„Éì„Ç¢„É≥Êôljª£„ÅƄǧ„ÇÆ„É™„Çπ„ɪ„É´„Éç„ǵ„É≥„ÇπʺîÂäá„Åß„Äé„Ç™„Ǫ„É≠„Äè(1604Âπ¥)„Å™„Å©„ÅßȪí‰∫∫ÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„Çíʺî„Åò„Ŷ„ÅÑ„Åü[4]„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„Äé„Ç™„Ǫ„É≠„Äè„Å™„Å©„Åì„ÅÆÊôljª£„ÅÆʺîÂäá„Åß„ÅØȪí‰∫∫„ÅÆÈü≥Ê•Ω„ÇÑË°åÂãï„Å™„Å©„ÅÆÊ®°ÂÄ£„ÇÑ˙ẵ„ÅØ„Å™„Åã„Å£„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã[14]„ÄÇ1769Âπ¥5Êúà29Êó•„ÄÅ„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„ÇØ„ÅÆ„Ç∏„Éß„É≥„ɪ„Çπ„Éà„É™„ɺ„ÉàÂäáÂÝ¥„Åß„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„É≥„ɪ„Ç´„É≥„Éë„Éã„ɺ„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÁôΩ‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„Å®„Åó„ŶÊúâÂêç„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„É´„ǧ„Çπ„ɪ„Éè„É©„É݄ɪ„Ç∏„É•„Éã„Ç¢„Åå„ǧ„ÇÆ„É™„Çπ„ÅÆ„Ç™„Éö„É©„ÄéThe Padlock„Äè„ÅÆÈÖî„Å£Êâï„ÅÑ„ÅÆȪí‰∫∫„Éû„É≥„Ç¥„ɺÂΩπ„Çíʺî„Åò„Ŷ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÂéüÂûã„Å®„Å™„Å£„Åü[15]„ÄÇ„Åì„ÅÆʺîÊäÄ„ÅØ•ΩË©ï„Åß„Äʼnªñ„ÅÆÂΩπËÄÖ„Åü„Å°„ÇÇ„Åì„ÅÆ„Çπ„Çø„ǧ„É´„ÇíÂèñ„ÇäÂÖ•„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„ÄÇÈÅÖ„Åè„Å®„ÇÇ1810Â𥉪£„Å´„ÅØ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„ÇπÈÅìÂåñÂ∏´„Åå‰∫∫Ê∞ó„Å®„Å™„Å£„Åü[16]„ÄÇ1822Âπ¥„Åã„Çâ1823Âπ¥„Äńǧ„ÇÆ„É™„Çπ‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ÉÅ„É£„ɺ„É´„Ç∫„ɪ„Éû„Ç∑„É•„Ƕ„Ç∫„ÅØÂÖ®Á±≥„ÉÑ„Ç¢„ɺÂ֨ʺî„ÇíË°å„Å™„ÅÑ„ÄÅʨ°„ÅÆÂ֨ʺî„ÄéA Trip to America„Äè„ŴȪí‰∫∫„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÇíÂäÝ„Åà„ÄÅ•¥Èö∑„ÅÆÊ≠å„ÄéPossum up a Gum Tree„Äè„ÇíÊ≠å„Å£„Åü[17]„ÄÇ1823Âπ¥„ÄÅ„Ç®„Éâ„Ƕ„Ç£„É≥„ɪ„Éï„Ç©„ɨ„Çπ„Éà„ÅØ„Éó„É©„É≥„É܄ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÅÆȪí‰∫∫„Çíʺî„Åò[17]„ÄÅ1828Âπ¥„Å´„ÅØ„Ç∏„É߄ɺ„Ç∏„ɪ„ÉØ„Ç∑„É≥„Éà„É≥„ɪ„Éá„Ç£„ÇØ„ÇΩ„É≥„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åß„ÅÆ„Ç≠„É£„É™„Ç¢„ÇíÁ¢∫Á´ã„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü[18]„ÄÇ„Åó„Åã„Åó1828Âπ¥„Äʼnªñ„ÅÆÁôΩ‰∫∫„Ç≥„É°„Éá„Ç£‰ø≥ÂÑ™„Éà„ɺ„Éû„Çπ„ɪD„ɪ„É©„ǧ„Çπ„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åß„ÄéJump Jim Crow„Äè„ÇíË∏ä„Çä„Å™„Åå„ÇâÊ≠å„Åщ∫∫Ê∞ó„ÅåÁàÜÁô∫„Åó[19]„ÄÅ1832Âπ¥„Åæ„Åß„Å´„Çπ„Çø„ɺ„ÉÄ„ÉÝ„Å´„ÅÆ„Åó‰∏ä„Åå„Å£„Åü[20]„ÄÇ  „É©„ǧ„Çπ„ÅØ„Äå„ÉÄ„Éá„Ç£„ɪ„Ç∏„É݄ɪ„ÇØ„É≠„Ƕ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜËä∏Âêç„ÅßÂÖ®Á±≥„Çí„ÉÑ„Ç¢„ɺÂ֨ʺî„Åó„Åü„ÄDŽɨ„Ç≥„É≥„Çπ„Éà„É©„ÇØ„Ç∑„Éß„É≥Âæå„Äʼn∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„ÅÆÊí§ÂªÉ„ÇíÁ§∫„Åô„Äå„Ç∏„É݄ɪ„ÇØ„É≠„ǶÊ≥ï„Äç„Å´Âê牪ò„Åë„Çâ„Çå„Åü[21]„ÄÇ 1830Â𥉪£„Åã„Çâ1840Â𥉪£ÂàùÈÝ≠„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Çπ„DZ„ÉÉ„Éńɪ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„ɺ„Å®„Ç≥„Éü„ÉÉ„ÇØ„ÇΩ„É≥„Ç∞„ÄÅ„Åù„Åó„ŶÊøÄ„Åó„ÅÑ„ÉÄ„É≥„Çπ„Çí„Éü„ÉÉ„ÇØ„Çπ„Åó„Ŷʺî„Åò„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇÂΩìÂàù„É©„ǧ„Çπ„Å®„Åù„ÅÆÂêåÂÉö„Åü„Å°„ÅØÂÆâÂäáÂÝ¥„Åß„ÅÆ„Åøʺî„Åò„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅƉ∫∫Ê∞ó„Åå‰∏ä„Åå„Çã„Å®‰∏äʵÅÈöéÁ¥ö„ÅåÂá∫ÂÖ•„Çä„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å™ÂäáÂÝ¥„Åß„ÅÆÂá∫ʺî„Åå¢ó„Åà„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅÆ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„ÅØ„ÄÅ„Åä„Å©„Åë„Ŷ„ÅфŶ„ÄÅÊÄÝ„ÅëËÄÖ„Åß„ÄÅËø∑‰ø°Ê∑±„Åè„ÄÅËáÜÁóÖ„Åß„ÄÅ•ΩËâ≤„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÊ≥•Ê£í„Åß„ÄÅÁóÖÁöÑ„Å´Âòò„ŧ„Åç„Åß„ÄÅËã±Ë™û„Åå‰∏ãÊâã„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇÂàùÊúü„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅØÂÖ®„ŶÁî∑ÊÄß„ÅÝ„Å£„Åü„Åü„ÇÅ„ÄÅÁï∞ÊÄßË£Ö„ÅßȪí‰∫∫•≥ÊÄß„Çíʺî„Åò„Ŷ„Ç∞„É≠„ÉÜ„Çπ„ÇØ„Å´Áî∑„Çâ„Åó„ÅèÈ≠ÖÂäõ„Åå„Å™„Åè„ÄÅÂÖ∏ÂûãÁöÑÂçóÈÉ®„ÅÆ„Éû„Éü„ɺ(Ȫí‰∫∫„ÅÆËÇù„Å£ÁéâÊØç„Åï„Çì)„Çø„ǧ„Éó„Åã„ÄÅÊÄßÁöÑ„Å´„Å®„Ŷ„ÇÇÊåëÁô∫ÁöфřʺîÊäÄ„Çí „Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ1830Â𥉪£„ÅÆ„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÅÆËàûÂè∞„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅƉ∫∫Ê∞ó„Åå‰∏ä„Åå„Çä„ÄÅË≥¢„Åфɧ„É≥„Ç≠„ɺ„Å®‰ºùË™¨ÁöÑÈñãÊãìËÄÖ„ÅÆ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Åå„Ç≥„Éü„Ç´„É´„Ŵʺî„Åò„Çâ„Çå„Åü[22]„ÄÇ19‰∏ñÁ¥ÄÂæåÊúü„Åã„Çâ20‰∏ñÁ¥ÄÂàùÈÝ≠„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Å®„ǧ„ÇÆ„É™„Çπ„ÅÆËàûÂè∞„ÅØÁπÅÁõõ„ÅóÁ∂ö„Åë[23]„Äź∑ʨ≤„Å™„ɶ„ÉĄɧ‰∫∫[24][25]„ÄÅÈÖî„Å£Êâï„ÅÑ„ÅßÂñßÂò©Êó©„ÅÑ„Åä„Åπ„Å£„Åã‰Ωø„ÅÑ„ÅÆ„Ç¢„ǧ„É´„É©„É≥„Éâ‰∫∫;[25][26][27]„ÄÅÊ≤π„Åæ„Åø„Çå„ÅƄǧ„Çø„É™„Ç¢‰∫∫[25]„ÄÅÈù¢ÁôΩ„Åø„ÅÆ„Å™„ÅÑ„Éâ„ǧ„Éщ∫∫[25]„ÄÅÈ®ô„Åï„Çå„ÇÑ„Åô„ÅÑÁî∞ËàéËÄÖ[25]„Å™„Å©‰∏ª„Å´Ê∞ëÊóèÁöÑ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Åå„Ç≥„Éü„Ç´„É´„Ŵʺî„Åò„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ 1830Â𥉪£„Åä„Çà„Å≥1840Â𥉪£ÂàùÈÝ≠„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅƉø≥ÂÑ™„Åü„Å°„ÅØ„ÇΩ„É≠„ÄÅ„Éá„É•„Ç™„ÄÅÊôÇ„ÄÖ„Éà„É™„Ç™„Åßʺî„Åò„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„ÅÆ„Å°„Å´„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Å®„Åó„ŶÊÄßÊݺ‰ªò„Åë„Çâ„Çå„ÇãÂ∑°Ê•≠Â֨ʺî„ÅØ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„Å®„Åó„Ŷ„ÅÆ„Åøʺî„Åò„Çâ„Çå„Åü[28]„ÄÇ1843Âπ¥„ÄÅ„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„ÇØ„Åß„ÉÄ„É≥„ɪ„Ç®„É°„ÉÉ„Éà„Åä„Çà„Å≥„É¥„Ç°„ɺ„Ç∏„Éã„Ç¢„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Ç∫„ÅØÊñ¨Êñ∞„Åï„Çщ∏äʵńÅÆ„Çπ„É܄ɺ„Çø„Çπ„ÇíÊéíÈô§„Åó„ÄÅÊú¨ÊݺÁöÑ„Å™„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„ÇπʺîÂäá„Çí‰∏äʺî„Åó„Åü„ÄÇÂêåÊôÇÊúü„ÄÅ„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„ÇØÂ∑û„Éê„ÉÉ„Éï„Ç°„É≠„ɺ„ÅßE„ɪP„ɪ„ÇØ„É™„Çπ„ÉÜ„Ç£„ÅåË°å„Å™„Å£„ÅüÂ֨ʺî„ÅÆÊñπ„ÅåÊó©„ÅÑ„Å®„Åô„ÇãË™¨„ÇÇ„ÅÇ„Çã[29]„ÄÇ„Ç®„É°„ÉÉ„Éà„Çâ„ÅØÂçäÂÜÜÂΩ¢„ÅÆ„Ç™„ɺ„DZ„Çπ„Éà„É©„ɪ„Éî„ÉÉ„Éà„Ŵʺî•èÂÆ∂„Åü„Å°„ÇíÂ∫ß„Çâ„Åõ„ÄÅ„ÉÄ„É≥„Éê„É™„É≥•èËÄÖ„ÇíÁâáÂÅ¥„Å´„ÄÅ„Éú„ɺ„É≥„Ç∫•èËÄÖ„ÇíÈÄÜÂÅ¥„Å´ÈÖçÁΩÆ„Åó„ÄÅÂâçÂ∫ß„Å®„Åó„Ŷʺî„Åò„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„Åô„Åê„Å´3Âπï„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ1ÂπïÁõÆ„Å®„Å™„Å£„Åü[30]„ÄÇ1852Âπ¥„Åæ„Åß„Å´„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Çπ„DZ„ÉÉ„Éńɪ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„ÅØ1Âπï„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆÁ¨ëÂäá„Å´Êã°Â§ß„Åó„ÄÅ„Åü„Åæ„Å´3Âπï„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ„Éà„É™„Å®„Å™„Çã3ÂπïÁõÆ„Å´ÁôªÂÝ¥„Åó„Åü[31]„ÄÇ „Åì„ÅÆÈÝÉ„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´ÂêàË°ÜÂõΩÂåóÈÉ®„ÅƉΩúÊõ≤ÂÆ∂„Çπ„ÉÜ„Ç£„ɺ„Éñ„É≥„ɪ„Éï„Ç©„Çπ„Çø„ɺ„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅßÊ¥ªË∫ç„Åó„Åü„ÄÇÊ≠åË©û„ÅØÊñπˮĄÅßÊõ∏„Åã„Çå„ÄÅÁèæÂú®„ÅÆ„Çπ„Çø„É≥„ÉĄɺ„Éâ„Å® „Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Éù„É™„ÉÜ„Ç£„Ç´„É´„ɪ„Ç≥„ɨ„ÇØ„Éà„Éç„Çπ„Åã„Çâ§ßÂπքŴ§ñ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„ÄÅÂΩº„ÅÆÂæåÊúü„ÅÆÊõ≤„ÅØÂò≤Á¨ë„ÇÑÈú≤È™®„ÅßÂ∑ÆÂà•ÁöÑ„Å™„Ç´„É™„Ç´„ÉÅ„É•„Ç¢„ÅØ„Å™„Åè„Å™„Ç䉪ñ„ÅÆ„Ç∏„É£„É≥„É´„ÅÆÊõ≤„ÅÆÊâãÊú¨„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇ„Éï„Ç©„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆÊõ≤„ÅØ•¥Èö∑„ÇÑÂçóÈÉ®„Çí„É܄ɺ„Éû„Å´„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå§ö„Åè„ÄÅ„Åù„ÅÆÁîò„ÅфǪ„É≥„ÉÅ„É°„É≥„Çø„É´„Å™Êõ≤Ë™ø„ÅØÁè扪£‰∫∫„ÅÆÂøÉ„Å´„ÇÇÈüø„Åã„Åõ„Çã.[32]„ÄÇ ÁôΩ‰∫∫„Å´„Çà„Çã„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅØÁôΩ‰∫∫ÂΩπËÄÖ„ÅåȪí‰∫∫„Å´„Å™„Çä„Åô„Åæ„Åô„Åì„Å®„ÇíÁâπÂ楄Ů„Åó„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éü„É•„ɺ„Ç∏„ÉÉ„ÇØ„Çíʺî•è„ÅóȪí‰∫∫Ëã±Ë™û„ÅÆÁúü‰ºº„ÅßË©±„Åó„Åü„ÄÇ1890Â𥉪£„Åæ„Åß„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅØ„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÅÆ„Ç∑„É߄ɺ„ɪ„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„ÅƉ∏ªÊµÅ„Åß„ÅÇ„Çä„Äńǧ„ÇÆ„É™„Çπ„ÇÑ„É®„ɺ„É≠„ÉÉ„Éë„ÅƉªñ„ÅÆÂú∞Âüü„Åß„Çǧ߉∫∫Ê∞ó„Åß„ÅÇ„Å£„Åü[33]„ÄÇ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅÆÂ㢄ÅÑ„Åå‰∏ãÈôç„Åô„Çã„Å®„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÂéüÁÇπÂõûÂ∏∞„Åó„É¥„Ç©„ɺ„Éâ„É¥„Ç£„É´„ÅƉ∏ÄÈÉ®„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü[23]„ÄÇÈÅÖ„Åè„Å®„ÇÇ1930Â𥉪£„Å´„ÅØÊòÝÁŴÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„ÄÅ1950Â𥉪£„Å´„ÅØ„É©„Ç∏„Ç™Áï™ÁµÑ„ÄéAmos 'n' Andy„Äè„Å´ÁôªÂÝ¥„Åó„Ŷ„ÄåËÄ≥„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Äç„Å®Â뺄Å∞„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü[34]„ÄÇ„Åæ„ÅüÈÅÖ„Åè„Å®„ÇÇ1950Â𥉪£„Å´„ÅØ„Ç¢„Éû„ÉÅ„É•„Ç¢„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅƉ∫∫Ê∞ó„ÅåÁ∂ö„ÅфŶ„ÅÑ„Åü[35]„ÄÇ1950Â𥉪£„Äńǧ„ÇÆ„É™„Çπ„Å´„Åä„ÅфŶ‰∫∫Ê∞ó„ÅÝ„Å£„Åü„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Ç´„É≥„Éñ„É™„Ç¢Âá∫Ë∫´„ÅÆ„É™„Ç´„É´„Éâ„ɪ„Ƕ„Ç©„ɺ„É™„ɺ„ÅßÁåø„ÅÆ„Éì„É´„Éú„ÇíÈÄ£„Çå„Ŷ„ǧ„É≥„Ç∞„É©„É≥„ÉâÂåóÈÉ®„ÇíÂ∑°Ê•≠„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü[36]„ÄÇ „Åù„ÅÆÁµêÊûú„ÄÅȪí‰∫∫„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÂÅè˶ã„Çí‰Ωú„Çä‰∏ä„Åí„Çã„ÅÆ„Å´Èáç˶ńřÂΩπÂâ≤„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇÁ§æ‰ºöÊ¥æ„Ç≥„É°„É≥„É܄ǧ„Çø„ɺ„ÅƉ∏≠„Å´„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÁôΩ‰∫∫„ÅÆÊú™Áü•„ÅÆÊÅê„Çå„ÅÆÊçå„ÅëÂ裄Äʼn∫∫Á®Æ„ÇÑÊîØÈÖç„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅÆÊÑüÊÉÖ„ÇÑÊÅê„Çå„ÇíË°®Áèæ„Åô„ÇãÊñπÊ≥ï„Å®„Å™„Å£„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÑè˶ã„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇ„ÄéLove and Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working Class„Äè„ÅƉ∏≠„Åß„Ç®„É™„ÉÉ„Ç؄ɪ„É≠„ÉÉ„Éà„ÅØ„ÄåȪí„ÅщªÆÈù¢„Å؉æÆË汄ÇÑËÑÖËø´„Åù„Åó„Ŷ‰∫∫Èñì„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÊÅê„Çå„ÇíË°®Áèæ„Åß„Åç„Çã„ÄÇ„Åù„Çå„Å®ÂêåÊôÇ„Å´„Åù„Çå„Çâ„Çí„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„Åß„Åç„Çã„Äç„Ůˮò„Åó„Åü[37]„ÄÇ „Åó„Åã„ÅóÂ∞ë„Å™„Åè„Å®„ÇÇÊúÄÂàù„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÁ§æ‰ºöÁöÑ„Å´Â∞Å„ÅòË溄ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„ÅüÂèçÂØæÂã¢Âäõ„ÅÆ£∞„Çí±ä„Åë„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åü„ÄÇÊó©„Åè„ÇÇ1832Âπ¥„Å´„ÅØ„ÄÅȪí°ó„Çä„ÅÆ„Éà„ɺ„Éû„Çπ„ɪD„ɪ„É©„ǧ„Çπ„Åå„ÄåÁôΩ‰∫∫Á¥≥£´„Åü„Å°„Çà„ÄÅÁßÅ„ÅÆÈÅì„Å´Ë∏è„ÅøË溄ÇÄ„Å™„ÄÇ„ÇÇ„ÅóÁßÅ„Çí‰æÆË汄Åô„Çã„Å™„Çâ„ÇÑ„Å£„ŧ„Åë„Çã„Äç„Å®Ê≠å„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Åæ„Åü„É©„ǧ„Çπ„Å؄Ƕ„Ç£„É™„Ç¢„É݄ɪ„Ç∑„Ç߄ǧ„ÇØ„Çπ„Éî„Ç¢„ÅÆ„Éë„É≠„Éá„Ç£„Åß„ÄåÁßÅ„ÅØȪí‰∫∫„ÅÝ„Åå„ÄÅÁôΩ‰∫∫„ÅØÂÖѺü„Å®Â뺄Å∂„Äç„Å®Ê≠å„ÅÑ„Äʼn∏㱧ÁôΩ‰∫∫„Å®‰∏㱧Ȫí‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„ÅåÂêåÁ≠â„Å®„Åø„Å™„Åï„Çå„ÇãÊ©ü‰ºö„Åß„ÇÇ„ÅÇ„Å£„Åü[38]„ÄÇ ÊòÝÁîª 1930Â𥉪£„ÄÅÊï∞§ö„ÅÑÂêç„ÅÆÁü•„Çå„ÅüËàûÂè∞„ÇÑÊòÝÁÅÆ„Ç®„É≥„Çø„É܄ǧ„Éä„ɺ„Åü„Å°„ÇÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü[39]„ÄÇÊòÝÁÅß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÅüÁôΩ‰∫∫„ÅØ„Ç¢„É´„ɪ„Ç∏„Éß„É´„ÇΩ„É≥[40]„ÄÅ„Ç®„Éá„Ç£„ɪ„Ç´„É≥„Çø„ɺ[41]„ÄÅ„Éì„É≥„Ç∞„ɪ„ÇØ„É≠„Çπ„Éì„ɺ[40]„ÄÅ„Éï„ɨ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Ç¢„Çπ„ÉÜ„Ç¢„ÄÅ„Ç¢„ǧ„É™„ɺ„É≥„ɪ„ÉÄ„É≥„ÄÅ„Éü„ÉÉ„Ç≠„ɺ„ɪ„É´„ɺ„Éã„ɺ„ÄÅ„Ç∑„É£„ɺ„É™„ɺ„ɪ„ÉÜ„É≥„Éó„É´„ÄÅ„Ç∏„É•„Éá„Ç£„ɪ„Ǩ„ɺ„É©„É≥„Éâ„ÄÅ„ÉÅ„Çß„Çπ„Çø„ɺ„ɪ„É¢„É™„Çπ„ÄÅ„Äå„Éú„Çπ„Éà„É≥„ɪ„Éñ„É©„ÉÉ„Ç≠„ɺ„ɪ„É©„É≥„Éá„Éñ„ɺ„Äç„ÅÆ„Ç∏„É߄ɺ„Ç∏„ɪE„ɪ„Çπ„Éà„ɺ„É≥„Å™„Å©„Åß„ÅÇ„Å£„Åü[41]„ÄÇ1940Â𥉪£„Å´„ÅØ„É؄ɺ„Éä„ɺ„ɪ„Éñ„É©„Ç∂„ɺ„ÇπË£Ω‰Ωú„ÅÆ„ÄéThis is the Army„Äè(1943Âπ¥)„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅÆ„Ç∑„ɺ„É≥„ÄÅ„Äé„ǵ„É©„Éà„ǨÊú¨Á∑ö„Äè(1945Âπ¥)„Åß„Éè„ǧ„ÉÅ„ÅÆ„É°„ǧ„ÉâÂΩπ„ÅÆ„Éï„É≠„ɺ„É©„ɪ„É≠„Éñ„ÇΩ„É≥„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Çí‰ΩøÁÅó„Åü[42]„ÄÇ ÊòÝÁîªÈªéÊòéÊúü„ÄÅȪí‰∫∫ÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„ÅØÁôΩ‰∫∫„Å´„Çà„Çä„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åßʺî„Åò„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ1903Âπ¥„ÄÅ„Äé„Ç¢„É≥„ÇØ„É´„ɪ„Éà„ÉÝ„ÅÆÂ∞è±ã„ÄèÊòÝÁîªÁ¨¨1‰ΩúÁõÆ„Åß„Å؉∏ªË¶Å„řȪí‰∫∫ÂΩπÂÖ®„Ŷ„ÅåÁôΩ‰∫∫„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü[43]„ÄÇ1914Âπ¥„ÄÅ„Äé„Ç¢„É≥„ÇØ„É´„ɪ„Éà„ÉÝ„Äè„ÅØ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ǵ„É݄ɪ„É´„ɺ„Ç´„Çπ„Åå‰∏ªÊºî„Åó„Åü„Åå„ÄÅÁôΩ‰∫∫„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åå„Éà„Éó„Ç∑„ɺÂΩπ„Çíʺî„Åò„Åü[44]„ÄÇD„ɪW„ɪ„Ç∞„É™„Éï„Ç£„ÇπÁõ£Áù£„ÅÆÊòÝÁÄéÂúãÊ∞ë„ÅÆÂâµÁîü„Äè(1915Âπ¥)„Åß„Å؉∏ªË¶Å„řȪí‰∫∫ÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„ÅÆÂÖ®„Ŷ„ÇíÁôΩ‰∫∫„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åßʺî„Åò„Ŷ„ÅÑ„Åü[45]„ÄÇ„Åó„Åã„ÅóÊòÝÁÅƉ∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„Å∏„ÅÆÂèçÁô∫„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Éâ„É©„Éû„ÉÜ„Ç£„ÉÉ„ÇØ„Å™ÊòÝÁÅß„ÅÆ„Åì„ÅÆÊâãÊ≥ï„ÅØÁµÇ„Çè„Å£„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÆÂæå„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÁôΩ‰∫∫„ÅØÊòÝÁÅƉ∏≠„ÅÆ„É¥„Ç©„ɺ„Éâ„É¥„Ç£„É´„ÇÑ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅÆ„Ç∑„ɺ„É≥„ÅÆ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„ÇÑËÖπË©±Ë°ì„Å´„ÅÆ„ÅøÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü[46][47]„ÄÇ„Åó„Åã„Å󉪕Èôç‰ΩïÂçÅÂπ¥„ÇÇÂêåÊßò„Å´„Éç„ǧ„ÉÜ„Ç£„É¥„ɪ„Ç¢„É°„É™„Ç´„É≥„ÄÅ„Ç¢„Ç∏„Ç¢‰∫∫„ÄÅ„Ç¢„É©„Éñ‰∫∫„Å™„Å©„ÅåÁôΩ‰∫∫„Å´„Çà„Çäʺî„Åò„Çâ„ÇåÁ∂ö„Åë„Åü[48]„ÄÇ 1930Â𥉪£ÁµÇÁõ§‰ª•Èôç„Äʼn∫∫Á®Æ„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊÑü˶ö„Åå§â„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åç„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅƉ∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„ÇÑÂÅè˶ã„Å®„ÅÆÈñ¢‰øÇÊÄß„Åå¢ó§߄Åó„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„É©„ǧ„É¥„ɪ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„Åß„Åï„Åà„ÇDŽŪ„Å®„Çì„Å©„Å™„Åè„Å™„Å£„Åü[41]„ÄÇ„Åü„ÅÝ„ÅóÁ™ÅÁÑ∂„Å™„Åè„Å™„Å£„ÅüË®≥„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅ„É©„Ç∏„Ç™Áï™ÁµÑ„ÄéAmos 'n' Andy „Äè(1928Âπ¥‚Äì1960Âπ¥)„ÅÆ„ÄåËÄ≥„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Äç„ÅØÁ∂ôÁ∂ö„Åó„ÄÅÁôΩ‰∫∫„Å´„Çà„ÇäȪí‰∫∫„ÅÆ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„ÅßȪí‰∫∫ÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„Ååʺî„Åò„Çâ„ÇåÁ∂ö„Åë„Åü[49]„ÄÇ1950Â𥉪£ÈÝÉ„ÄÅ„Ç¢„Éã„É°„Åß„Å؉øÆÊ≠£„Åï„Çå„Åö„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅåÁîü„ÅçÁ∂ö„Åë„Åü„ÄÇ„Çπ„Éà„É©„Çπ„Éú„Ƕ„ÅØ1940Â𥉪£„ÅÆ„É°„Éà„É≠„ɪ„Ç¥„ɺ„É´„Éâ„Ƕ„Ç£„É≥„ɪ„É°„ǧ„ɧ„ɺ„ÅÆ„Ç¢„Éã„É°„ÅÆÁ¥Ñ3ÂàÜ„ÅÆ1„ÅØ„Äå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÄÅ„Ç؄ɺ„É≥„ÄÅ„Éû„Éü„ɺ„ÅåÂê´„Åæ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Äç„Ů˙û„Å£„Åü[50]„ÄÇ„Éê„ÉÉ„Ç∞„Çπ„ɪ„Éê„Éã„ɺ„Åß„ÅØÈÅÖ„Åè„Å®„ÇÇ1953Âπ¥„ÅÆ„Äé„ǵ„ÉÝ„Å®ÂÖ±„Å´Â骄Çä„Ũ„Äè„Åæ„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅåÁôªÂÝ¥„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü[51]„ÄÇ „Éê„ɨ„Ç®1910Âπ¥„ÄÅ„Éü„Éè„ǧ„É´„ɪ„Éï„Ç©„ɺ„Ç≠„É≥Êå؉ªò„ÅÆ„Éê„ɨ„Ç®„ÅÆ„Äé„Ç∑„Çß„Éò„É©„Ç∂„ɺ„Éâ„Äè„Åå„É≠„Ç∑„Ç¢„ÅßÂàùʺî„Åï„Çå„Åü„ÄÇ„Éã„Ç≥„É©„ǧ„ɪ„É™„ÉÝ„Çπ„Ç≠„ɺԺù„Ç≥„É´„ǵ„Ç≥„Éï„ÅÆÈü≥Ë©©„ÇíÂü∫„Å´„Åó„Åü„Éê„ɨ„Ç®‰ΩúÂìÅ„Åß„ÅÇ„Çã„Älj∏ªË¶ÅÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„ÅÆ•≥ÊÄß„Ç∫„Éê„ǧ„ÉÄ„ÅØÈáë„ÅÆ•¥Èö∑„Åã„ÇâË™òÊÉë„Åï„Çå„Çã„ÄÇ„É¥„Ç°„ɺ„ÉÑ„É©„Éï„ɪ„Éã„Ç∏„É≥„Çπ„Ç≠„ɺ„ÅåÂàùʺî„Åó„ÅüÈáë„ÅÆ•¥Èö∑„Çíʺî„Åò„Çã„ÉÄ„É≥„ǵ„ɺ„ÅØÈ°î„Å®‰Ωì„ÇíËå∂Ëâ≤„Ŵ°ó„Çã„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„Çà„Çä•¥Èö∑„Å®„ÅÑ„ÅÜ„ÇÇ„ÅÆ„ÅØËÇå„ÅÆËâ≤„ÅåÊøÉ„ÅÑ„Å®„ÅÆË™çË≠ò„Çíʧç„Åà‰ªò„Åë„Åü„ÄÇ1912Âπ¥ÁµÇÁõ§„ÄÅ„Éï„Ç©„ɺ„Ç≠„É≥„ÅØ„Äé„Éö„Éà„É´„ɺ„Ç∑„É•„Ç´„Äè„ÇíÊåØ„Ç䉪ò„Åë„Åü„ÄÇÁîü„ÇíÂèó„Åë„Åü„Éö„Éà„É´„ɺ„Ç∑„É•„Ç´„ÄÅ„Éê„ɨ„É™„ɺ„Éä„ÄÅ„É݄ɺ„Ç¢„ÅÆ3‰Ωì„ÅƉ∫∫ÂΩ¢„Çí‰∏≠ÂøÉ„Å®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÂàùʺîÊôÇ„ÄÅ„Ç¢„ɨ„Ç؄ǵ„É≥„ÉĄɺ„ɪ„Ç™„É´„É≠„Éï„Å´„Çà„ÇäÂàùʺî„Åï„Çå„Åü„É݄ɺ„Ç¢ÂΩπ„ÅØÂÆåÂÖ®„Å™„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ„É݄ɺ„Ç¢„ÅØ„Ç≥„Ç≥„Éä„ÉÑ„ÇíÊåÅ„Å£„ŶÁôªÂÝ¥„Åó„ÄÅÂàÄ„Åß„Åï„Å∞„Åì„ÅÜ„Å®„Åô„Çã„ÄÇÂãï„Åç„ÅØÁåø„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ„É݄ɺ„Ç¢„ÅØ„Éê„ɨ„É™„ɺ„Éä„ÇíË™òÊÉë„Åó„ÄÅ„Éö„Éà„É´„ɺ„Ç∑„É•„Ç´„ÅÆȶñ„ÇíÊÆãÂøç„Å´Âàá„Çã„ÄÇ„Äé„Éö„Éà„É´„ɺ„Ç∑„É•„Ç´„Äè‰∏äʺîÊôÇ„ÄÅ„É݄ɺ„Ç¢ÂΩπ„ÅØÁèæÂú®„Åß„ÇÇÂÆåÂÖ®„Å™„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åæ„Åü„ÅØ„Éñ„É´„ɺ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åßʺî„Åò„Çâ„Çå„Çã„ÄÇ„Éê„ɨ„Ç®Áïå„Åß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÊâπÂৄÅÆÂØæ˱°„Å®„ÅØ„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„ÄÇÁèæÂú®„Åß„ÇÇ„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÇÑ„É®„ɺ„É≠„ÉÉ„Éë„ÅÆ„Éê„ɨ„Ç®Áïå„Åß„ÅØ„Äé„É©„ɪ„Éê„ɧ„Éá„ɺ„É´„Äè„ÄÅ„Äé„Ç™„Ǫ„É≠„Äè„Å™„Å©„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇÑ„Éñ„É©„Ƕ„É≥„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åå„Å™„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Çã[52]„ÄÇ „Éñ„É©„ÉÉ„Ç؄ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ  ‚Üí„Äå„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„Äç„ÇÇÂèÇÁÖß
1840Âπ¥„Åæ„Åß„ÄÅȪí‰∫∫„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÇÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆËàûÂè∞ÂåñÁ≤ß„ÅßÂá∫ʺî„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Éï„ɨ„Éá„É™„ÉÉ„Ç؄ɪ„ÉÄ„Ç∞„É©„Çπ„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Çí´åÊÇ™„Åó„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Å´ÂØæ„ÅóÂèçÂØæÊÑè˶ã„ÇíËø∞„Åπ„ÅüÊúÄÂàù„ÅÆ1‰∫∫„Å®„Åï„Çå„Äʼn∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„Å®ÈùûÈõ£„Åó„Åü[54]„ÄÇ„ÉÄ„Ç∞„É©„Çπ„ÅØ„Äå„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÂΩ¢„Åß„ÅÇ„ÇåÊúâËâ≤‰∫∫Á®Æ„ÇíÁôΩ‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„ÅÆÂâç„Å´ÁôªÂÝ¥„Åï„Åõ„Çå„Å∞Èáë„Å´„Å™„Çã„Äç„Ů˙û„Å£„Åü[55]„ÄÇ 1860Â𥉪£„ÄÅȪí‰∫∫„Åå„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„Å´Âá∫ʺî„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„Å®„ÄÅ„ÄåÊ≠£ÁúüÊ≠£Èäò„Äç„ÄÅ„ÄåÊú¨Áâ©„Äç„Å®ÂÆ£‰ºù„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆ„Äå„Ç´„É©„ɺ„Éâ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Äç„ÅØ[56]„ÄÅËߣÊîæ„Åï„Çå„Ŷ„Åæ„ÇÇ„Å™„ÅÑÂÖÉ•¥Èö∑„ÅƉ∫∫„ÄÖ„Åã„ÇâÂ∏∏„ÄÖÊâπÂৄÇíÂèó„Åë„Ŷ„ÅÑ„Åü[57]„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„Åì„ÅÆÂÆ£‰ºù„Å´„ÅØÊÇ™ÊÑè„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÄÅÁôΩ‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„ÅØÁÜüÁ∑¥„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„Åß„ÅØ„Å™„ÅèÂãïÁâ©Âúí„ÅÆ„Çà„Å܄ř˶ã‰∏ñÁâ©Â∞è±ã„ÅƄŧ„ÇÇ„Çä„Åß˶ã„Å´Êù•„Ŷ„ÅÑ„Åü[58]„ÄljΩé‰∫àÁÆó„ÄÅÂ∞è˶èÊ®°ÂäáÂÝ¥„Åå§ö„ÅÑ„Å´„ÇÇ„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅÂÆ¢Âèó„Åë„ÅØÁôΩ‰∫∫„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´ÂäáÂõ£„Å®ÂØæÁ≠â„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ1886Âπ¥3Êúà„ÄÅÂÖ®Á±≥„Åß„ÇÇ„Å£„Å®„Çlj∫∫Ê∞ó„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã„Éñ„ÉÉ„Ç´„ɺ&„Ç؄ɨ„ǧ„Éà„É≥„ɪ„Ç∏„É߄ɺ„Ç∏„Ç¢„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Ç∫„ÅØÊâπË©ïÂÆ∂„Åã„Çâ„ÅÆÁß∞Ë≥õ„ÇÇÂæó„Åü[59]„ÄÇ „Åì„Çå„Çâ„ÅÆ„Ç´„É©„ɺ„Éâ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅØ„ÄÅÂåóÈÉ®„ÅÆȪí‰∫∫„ÅÆÁ§æ‰ºöÁöщ∏ªÂºµ„Å®„ÅØÈÅï„ÅÑ„ÄÅ„Éó„É©„É≥„É܄ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Å™„Å©„Çí„Éç„Çø„Å´„Åó„ÄÅ„Äå„Ç∏„É߄ɺ„Ç∏„Ç¢„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Ç∫„Äç„Å®Â뺄Å∞„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü[60][61]„ÄÇÊâìÊ•ΩÂô®„ÇíÁÅфŶÊú¨Áâ©„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„Ç؄ɪ„Éü„É•„ɺ„Ç∏„ÉÉ„ÇØ„Çíʺî•è„Åó„ÄÅ„Éù„É™„É™„Ç∫„ÉÝ„ÇíÂèñ„ÇäÂÖ•„Çå„Åü‰ºùÁµ±ÁöÑ„Å™„ÉÄ„É≥„Çπ„Çí„Åó„ÄÅ„Åù„Ç剪•Â§ñ„ÅÆÊ•ΩÂô®„Çí‰ΩøÁÅõ„ÅöÊâãË∂≥„Çí‰Ωø„Å£„Ŷ‰Ωì„ÇíÂè©„ÅÑ„Åü„ÇäË∂≥„ÇíË∏è„ÅøÈ≥¥„Çâ„Åó„Ŷ„É™„Ç∫„ÉÝ„ÇíÂèñ„Çä„ÄÅȪí‰∫∫„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅÆÊñπ„ÅåÂÑ™Â㢄Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇȪí‰∫∫„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Åß„ÇÇ„Å£„Å®„ÇÇÊàêÂäü„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ1„ŧ„ÅØ„Äńǵ„É݄ɪ„Éò„ǧ„Ç∞„ÅÆ„Çπ„ɨ„ǧ„É¥„ɪ„Éà„É´„ɺ„Éó„ɪ„Ç™„Éñ„ɪ„Ç∏„É߄ɺ„Ç∏„Ç¢„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Ç∫(•¥Èö∑ÂäáÂõ£„ÄÅ„ÅÆÊÑè)„Åß„ÄÅ„ÉÅ„É£„ɺ„É´„Ç∫„ɪ„Éí„ÉÉ„ÇØ„Çπ„ÅåÁÆ°ÁêÜ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„ÄÅÊúÄÁµÇÁöÑ„Å´„ÉÅ„É£„ɺ„É´„Ç∫„ɪ„Ç´„ɨ„É≥„ÉĄɺ„Ŵºï„ÅçÁ∂ô„ÅÑ„ÅÝ„ÄÇ„Ç∏„É߄ɺ„Ç∏„Ç¢„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Ç∫„ÅØÂÖ®Á±≥„Åä„Çà„Å≥ʵ∑§ñ„Å´„ÉÑ„Ç¢„ɺÂ֨ʺî„Åó„ÄÅ„ÅÆ„Å°„Å´„Éè„É¥„Ç°„É™„ɺ„ɪ„Ç´„É©„ɺ„Éâ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Ç∫„Å®„Å™„Å£„Åü[59]„ÄÇ 1870Â𥉪£‰∏≠Êúü„ÄÅÁôΩ‰∫∫„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅØ„Çà„Çä˱™ËèØ„Å´„Å™„Çä„ÄÅȪí‰∫∫„Å´„Çà„Çã„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Å®ÈÄ܄ŴȪí‰∫∫ÊñáÂåñ„Åã„ÇâÈÅÝ„Åñ„Åã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü[62]„ÄÇ„Éï„Ç£„Çπ„Ç؄ɪ„Ç∏„É•„Éì„É™„ɺ„ɪ„Ç∑„É≥„Ǩ„ɺ„Ç∫„Å™„Å©„ÅÆ„Ç∏„É•„Éì„É™„ɺ„ɪ„Ç∑„É≥„Ǩ„ɺ„Ç∫„ÅÆʵÅË°å„Å´„Çà„Çä„ÄÅÈúäÊ≠å„Å™„Å©„ÅÆȪí‰∫∫Èü≥Ê•Ω„ÇíÁôΩ‰∫∫„ÅÆÂÆóÊïôÈü≥Ê•Ω„Å®„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´ÂåóÈÉ®„ÅÆÁôΩ‰∫∫„ÅåËààÂë≥„ÇíÁ§∫„Åó„Åü„ÄÇ˧áÊï∞„ÅÆ„Ç∏„É•„Éì„É™„ɺ„ɪ„Ç∑„É≥„Ǩ„ɺ„Ç∫„ÅØÁñ뉺º„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Å®„Åó„Ŷ£≤„ÇäË溄Çì„Åß„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅÆÊõ≤„ÇÇʺî•è„Åó„ÄÅÈÄÜ„Å´„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅØËÅñÊ≠å„Çíʺî•è„ÅóÂßã„ÇÅ„ÄÅ„Åù„ÅÆÂæåÂçóÈÉ®„ÅÆȪí‰∫∫ÂÆóÊïôÈü≥Ê•Ω„Å´Êâã„ÇíÂ∫É„Åí„Åü„ÄÇ„Éï„Ç£„Çπ„Ç؄ɪ„Ç∏„É•„Éì„É™„ɺ„ɪ„Ç∑„É≥„Ǩ„ɺ„Ç∫„Å´„Çà„Çä„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å®‰∏ÄÁ∑ö„ÇíÁÅô„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Åæ„ÅüÂÆóÊïôÈü≥Ê•Ω„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„Çíº∑Ë™ø„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„Å´‰ΩøÁÅï„ÇåÂßã„ÇÅ„Åü„Äå„Ç∏„É•„Éì„É™„ɺ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÂçòË™û„ÅØÊï∞Âπ¥„ÅÆ„ÅÜ„Å°„ŴȪí‰∫∫ÊñáÂåñ„Å´„Åä„ÅфŶ„Äå„Éñ„É©„É≥„É܄ɺ„Ç∑„Éß„É≥„Ä牪•‰∏ä„ÅÆÊÑèÂë≥„ÇíÊåńŧ„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü[63]„ÄÇ„Ç∏„É•„Éì„É™„ɺ„ɪ„Ç∑„É≥„Ǩ„ɺ„Ç∫„ÅØÁôΩ‰∫∫Â∏ÇÂÝ¥„Å´Âêë„ÅëÂçóÈÉ®„ÅÆȪí‰∫∫ÂÆóÊïôÈü≥Ê•Ω„ÇíÊ¥óÁ∑¥„Åï„Åõ„Äʼn∏ÄÊñπ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Çà„ÇäÁï∞ÂõΩÈ¢®„ÅÆ˶ã„Åã„Åë„Ŵ˙ẵ„Åó„Åü[64]„ÄÇ „Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éó„É≠„ÉÄ„ÇØ„Ç∑„Éß„É≥„ÇÇËá™Â∑±È¢®Âà∫„Å´„Çà„ÇãÈÅìÂåñ„ÇÑ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„ÇíÂê´„Çì„Åß„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„ÅåËàûÂè∞„Å´Á´ã„Å°Âßã„ÇÅ„ÅüÈÝÉ„ÄÅȪí‰∫∫„ÅØËÇå„ÅÆËâ≤„ÅÆÊøÉÊ∑°„Å´„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ1860Â𥉪£„Äʼn∏ÄÊôÇÁöÑ„Å´ÊúâËâ≤‰∫∫Á®Æ„ÅÆÂäáÂõ£„ÅØ„Åì„ÅÆÊÖ£Áøí„ÇíÁÝ¥„Çä„ÄÅ„Ç≥„É°„Éá„Ç£ÂøóÂêë„ÅÆ„Äå„Ç≥„É´„ÇØ„ÅßÊÝì„Çí„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„ÄçÊäëÂúß„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„Äʼnªñ„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„Åü„Å°„ÅØ„Åù„ÅÆËâ≤Ë™ø„ÅƧöÊßòÊÄß„Åß„Ç≥„É°„É≥„É܄ǧ„Çø„ɺ„Åü„Å°„ÇíÈ©ö„Åã„Åõ„Åü[65]„ÄÇ„Åì„ÅÆÈÝÉ„ÇÇ„Åæ„ÅÝ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Åßʺî„Åò„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü[66]„ÄÇ Èªí‰∫∫„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„Åü„Å°„ÅØ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„Ç≥„Éü„É•„Éã„ÉÜ„Ç£„Åß„Çπ„Çø„ɺ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„ÄÅ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„ÅƉ∏äʵÅÈöéÁ¥ö„Åã„Çâ„ÅØÁѰ˶ñ„ÅÇ„Çã„ÅÑ„ÅØÈùûÈõ£„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ1882Âπ¥„Äʼn∏≠ʵÅÈöéÁ¥ö„ÅÆ„Ç∏„Ç߄ǧ„ÉÝ„Ç∫„ɪ„É¢„É≥„É≠„ɺ„ɪ„Éà„É≠„ÉÉ„Çø„ɺ„ÅØ„ÄåÊúĉΩé„Å™„Ç´„É™„Ç´„ÉÅ„É•„Ç¢„Äç„Å®„Åó„Ŷ˪ΩËîë„Åó„ŧ„ŧ„ÄÅȪí‰∫∫„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÇíÈùûÈõ£„Åô„Çã‰∫∫„ÇÇÂΩº„Çâ„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éü„É≥„Ç∞„Çí˶ã„Çå„Å∞„Åù„ÅÆ„ÄåÈ´ò„ÅÑÈü≥Ê•ΩÊñáÂåñ„Äç„Å®ÊÑüÂòÜ„ÅóÊÖãÂ∫¶„Çí˪üÂåñ„Åô„Çã„Ů˙û„Å£„Åü[67]„ÄÇÁôΩ‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„Å®ÈÅï„ÅÑ„ÄÅȪí‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„ÅØ„Ç´„É™„Ç´„ÉÅ„É•„Ç¢„Å®„Åó„ŶÊçâ„Åà„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅÁ¥Ñ50Âπ¥Âæå„Å´„Éû„ÉÝ„Ç∫„ɪ„Éû„Éñ„É™„ɺ„ÅåÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Åæ„ÅßËá™ÂàÜ„Åü„Å°„ÅÆÊñáÂåñ„Çí˶ã„Çã„ÅÆ„ÇíÊ•Ω„Åó„Çì„Åß„ÅÑ„Åü[68]„ÄÇ Â∑ÆÂà•ÁöÑ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Åå¢óº∑„Åï„Çå„Ŷ„Åç„Åü„Å´„ÇÇ„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅØÂÆüÂãôÁöÑ„Åß„ÄÅȪí‰∫∫„ÅƧö„Åè„ÅåÂ∞±„ÅфŶ„ÅÑ„ÅüÂçòÁ¥îÂä¥ÂÉç„Å´ÊØî„Åπ„ŶÁîüÊ¥ª„Å´Âõ∞„Çâ„Å™„ÅфŪ„Å©„ÅÆÂà©Áõä„ÇíÂæó„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åü„Älj∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„ÅÆÊôljª£„ÄÅ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„Éü„É•„ɺ„Ç∏„Ç∑„É£„É≥„Äʼnø≥ÂÑ™„ÄÅ„ÉÄ„É≥„ǵ„ɺ„Å´„Çà„Å£„ŶȪí°ó„Çä„Åß„ÅÆËàûÂè∞Âá∫ʺî„ÅØËá™ÂàÜ„ÅÆÊâçËÉΩ„ÇíÊä´Èú≤„Åô„Çã„Ū„źÂî؉∏Ä„ÅÆÊ©ü‰ºö„Åß„ÅÇ„Å£„Åü[69]„ÄÇ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅØÂçóÈÉ®‰ª•Â§ñ„Å߉∏äʺî„Åï„Çå„Äʼn∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„ÇíÂæƶô„Å´„Åã„Çâ„Åã„ÅÑ„ÄÅÁôΩ‰∫∫Á§æ‰ºö„ٕ¥Èö∑Âà∂Â∫¶ÂªÉÊ≠¢Ë´ñÊé®ÈÄ≤„ÅÆ„ÉÄ„Éñ„É´„Çπ„Çø„É≥„ÉĄɺ„Éâ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÁôΩ‰∫∫„ÄÅȪí‰∫∫„Å´„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„É≥„Çπ„Å´„Åä„ÅфŶ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éü„É•„ɺ„Ç∏„ÉÉ„ÇØ„Äńɶ„ɺ„É¢„Ç¢„ÄÅ„ÉÄ„É≥„Çπ„ÅÆ˱ä„Åã„Åï„Åå„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÇѧñÂõΩ„ÅÆÁôΩ‰∫∫„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„Å´ÊúÄÂàù„Å´Âèó„Åë„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü[10]„ÄÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Åå„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÅÆ„Ç∑„É߄ɺ„ɪ„Éì„Ç∏„Éç„Çπ„Å´„Åä„Åë„Çã„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÅÆÁôªÁ´úÈñÄ„Å®„Å™„Å£„Åü[70]„ÄÇȪí‰∫∫„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„É≥„Çπ„ÇíÁôΩ‰∫∫„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÁöÆËÇâ„Å®„Åó„ŶÂà©ÁÅó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇÊÄßÁöÑÈßÑÊ¥íËêΩ„ÅåÊä´Èú≤„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÄÅÁôΩ‰∫∫„ÅÆÈÅìÂæ≥‰∏ªÁæ©ËÄÖ„Åã„Çâ´åÊÇ™„Åï„Çå„Åü„ÄÇ„É¥„Ç©„ɺ„Éâ„É¥„Ç£„É´„ÅƉæÆËæ±ÁöфřʺîÁõÆ„Å´„ÅØÂæƶô„Å™„É°„ÉɄǪ„ɺ„Ç∏„ÅåË溄ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇ „É¥„Ç©„ɺ„Éâ„É¥„Ç£„É´„ÅƉ∫∫Ê∞ó‰∏äÊòá„Å´‰º¥„ÅÑ„ÄÅ„Éê„Éè„ÉûÁîü„Åæ„Çå„ÅƉø≥ÂÑ™„Åä„Çà„Å≥„Ç≥„É°„Éá„Ç£„Ç¢„É≥„ÅÆ„Éê„ɺ„Éà„ɪ„Ƕ„Ç£„É™„Ç¢„ÉÝ„Ç∫„ÅØ„Éï„É≠„ɺ„ɨ„É≥„Éфɪ„Ç∏„ɺ„Ç∞„Éï„Çß„É´„Éâ„ɪ„Ç∏„É•„Éã„Ç¢„ÅÆÂî؉∏Ä„ÅÆ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„Çπ„Çø„ɺ„Å®„Å™„Çä„ÄÅ„Ç∏„ɺ„Ç∞„Éï„Çß„É´„ÉâÊúÄÈ´òÈ°ç„ÅÆÁµ¶Êñô„ÇíÁç≤Âæó„Åó„Åü[53][71]„ÄÇ 1909Âπ¥„ÄÅÂäáÂÝ¥ÊâÄÊúâËÄÖÂá∫ʺî•ëÁ¥ÑÂçö(TOBA)„ÅØ„ÄÅÂÖ®Âì°Èªí‰∫∫„Å´„Çà„Çã„É¥„Ç©„ɺ„Éâ„É¥„Ç£„É´Â∑°Ê•≠Â֨ʺî„ÇíÁµÑÁπî„Åó„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å؉∫∫Ê∞óÂ֨ʺî„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„Çâ„ÅØÁµ¶Êñô„Åå‰Ωé„Åè„ÄÅ„Äå„Çø„Éï„ɪ„Ç™„É≥„ɪ„Éñ„É©„ÉÉ„Ç؄ɪ„Ç¢„ÇØ„Çø„ɺ„Äç(TOBA„ÄÅÂé≥„Åó„ÅÑÁä∂Ê≥Å„ÅÆȪí‰∫∫‰ø≥ÂÑ™)Áï•„Åó„Ŷ„Äå„Éà„Éì„ɺ„Äç„Å®Â뺄Å∞„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇTOBA„ÅØ„ÉÜ„Ç£„É݄ɪ„É݄ɺ„Ç¢„ÇÑ„Ç∏„Éß„Éã„ɺ„ɪ„Éè„ÇÆ„É≥„Çπ„Å™„Å©„Çí‰∏ªÂΩπ„Å´„Åó„ÄÅ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅØÂ∞ë„Å™„Åã„Å£„Åü„Åå„Å®„Ŷ„ÇÇËâØ„ÅÑÁîüÊ¥ª„ÇíÈÄÅ„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Åó„ÄÅTOBA„Å؉ªñÊâÄ„Å®ÊØî„Åπ„Ŷ„Çà„ÇäÈ≠ÖÂäõÁöÑ„Å™‰ªï‰∫ã„ÇíÂÝÖË™ø„Å´‰∏é„Åà„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇÁôΩ‰∫∫„ÄÅȪí‰∫∫„Å´„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å؉ΩïÁôæ‰∫∫„ÇÇ„ÅÆ„Ç¢„ɺ„ÉÜ„Ç£„Çπ„Éà„ÇÑ„Ç®„É≥„Çø„É܄ǧ„Éä„ɺ„ÅƧö„Åè„Åå„ÅÆ„Å°„Å´‰ªñ„ÅÆÂ֨ʺî„ÅƉªï‰∫ã„Çí˶ã„ŧ„Åë„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÁ™ÅÁÝ¥Â裄Ů„Å™„Å£„Åü„Äljæã„Åà„Å∞„Éò„ǧ„É¥„Ç°„É™„ɺ„ɪ„É®„ɺ„É≠„Éî„Ç¢„É≥„ɪ„Éü„É≥„Çπ „Éà„ɨ„É´„ÅÆÊúÄ„ÇÇÊúâÂêç„Å™„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆ1‰∫∫„ÅØ„ÅÆ„Å°„Å´„Äå„Ç∞„É©„É≥„Éâ„ɪ„Ç™„ɺ„É´„Éâ„ɪ„Éû„É≥„ɪ„Ç™„Éñ„ɪ„Ç∂„ɪ„Éã„Ç∞„É≠„ɪ„Çπ„É܄ɺ„Ç∏„Äç„Å®„Åó„ŶÁü•„Çâ„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„ǵ„É݄ɪ„É´„ɺ„Ç´„Çπ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü [72]„ÄÇ1914Âπ¥„ÄÅ„É´„ɺ„Ç´„Çπ„ÅØ„Éè„É™„Ç®„ÉÉ„Éà„ɪ„Éì„ɺ„ÉÅ„É£„ɺ„ɪ„Çπ„Éà„ǶÂéü‰Ωú„ÅÆÊòÝÁÄé„Ç¢„É≥„ÇØ„É´„ɪ„Éà„ÉÝ„ÅÆÂ∞è±ã„Äè„Å߉∏ªÊºî„Åó„Åü [73]„ÄÇ1930Â𥉪£ÂàùÈÝ≠„Åã„Çâ1940Â𥉪£ÁµÇÁõ§„ÄÅ„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„ÇØ„ÅÆ„Éè„ɺ„ɨ„ÉÝ„Å´„ÅÇ„ÇãËëóÂêç„Å™„Ç¢„Éù„É≠„ɪ„Ç∑„Ç¢„Çø„ɺ„ÅØÂÖ®Á±≥Ȫí‰∫∫Âú∞‰ΩçÂêë‰∏äÂçö(NAACP)„Åã„Çâ„ÅÆÊäóË≠∞„Å´„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄńŪ„źÂÖ®„Ŷ„ÅÆȪí‰∫∫„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„Åó„ÄÅÂîá„Çí§߄Åç„ÅèÁôΩ„Åß°ó„Çä„Çπ„DZ„ÉÉ„Éńɪ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„ÇíË°å„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Ç≥„É°„Éá„Ç£„ÅƉ∏≠„Åß„ÄÅÂΩº„Çâ„ÅØ„Åù„ÅÆ„É°„ǧ„ÇØ„Åå„Å™„Åë„Çå„Å∞Ë£∏„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´ÊÑü„Åò„Çã„Ů˙û„Å£„Åü[74]:4, 1983 ed.„ÄÇ „Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅØÂΩìÂàù„ÅÆÁôΩ‰∫∫„Å´„Çà„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åã„ÇâȪí‰∫∫„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„Å´„Çà„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Å´Áߪ˰å„Åó„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÇȪí‰∫∫„Åü„Å°„ÅØ„Åù„ÅÆÊßòºè„ÇíÁÅфŶËá™ÂàÜ„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„Å´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÇȪí‰∫∫ÂäáÂÝ¥„Åã„Çâ„Éó„É≠„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„É≥„Çπ„Åå„Åß„Åç„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„ÄÇȪí‰∫∫„Å´„Çà„Çã„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Å´„ÅØÁôΩ‰∫∫„Åü„Å°„Å´„ÅØ„Å™„ÅÑ„Éê„ǧ„Çø„É™„ÉÜ„Ç£„Çфɶ„ɺ„É¢„Ç¢„ÇíÊåÅ„Å°Âêà„Çè„Åõ„Ŷ„ÅÑ„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÑè˶ã„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇ Èªí‰∫∫„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅØËá™Ë∫´„Çí„Åã„Çâ„Åã„ÅÜ„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅÊÝπÂ∫ï„Åß„ÅØÁôΩ‰∫∫„Çí„Åã„Çâ„Åã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄDŽDZ„ɺ„Ç؄Ƕ„Ç©„ɺ„ÇØ„ÅØÁôΩ‰∫∫„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅÆÈñì„Åß„ÅØȪí‰∫∫„ÅÆ„ÉÄ„É≥„Çπ„ÇíÈ¢®Âà∫„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åå„ÄÅȪí‰∫∫„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„Åß„ÅØÁôΩ‰∫∫„ÅÆÁîüÊ¥ªÁøíÊÖ£„ÇíÈ¢®Âà∫„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ „Äå„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„Äç„Å®„Åó„Ŷ„ÅÆÊèè„Åã„ÇåÊñπ„Äå„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„Äç(darky)„ÅØȪí‰∫∫„ÇíË°®„ÅôËîëÁß∞„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÊó•Êú¨Ë™û„Åß„ÅØ„ÄåȪí„Çì„ź„Äç„Å™„Å©„Ůˮ≥„Åï„Çå„Çã„ÄÇ „Ç®„É≥„Çø„ɺ„É܄ǧ„É°„É≥„ÉàÁïå„ÄÅÂÖêÁ´•ÊñáÂ≠¶„ÄÅË≤ØÈáëÁƱ„ÇÑ„Åä„ÇÇ„Å°„ÇÉ„ÄÅÊßò„ÄÖ„Å™„Ç≤„ɺ„ÉÝ„ÄÅ„Ç´„ɺ„Éà„Ç•„ɺ„É≥„ÄÅ„Ç≥„Éü„ÉÉ„Ç؄ɪ„Çπ„Éà„É™„ÉÉ„Éó„ÄÅÂ∫ÉÂëä™í‰Ωì„ÄÅË£ÖÈ£æÂìÅ„ÇÑË°£È°û„ÄÅÁµµËëâÊõ∏„ÄÅÊ•ΩË≠ú„ÄÅÈ£≤È£üÁâ©„ÅÆ„Éñ„É©„É≥„Éâ„ÇÑ„Éë„ÉɄDZ„ɺ„Ç∏„Å™„Å©Êßò„Äքř™í‰Ωì„Åß„ÄÅ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„Å®„Åó„ŶÂãïÁúº„ÄÅ¢®Â°ó„Çä„ÅÆËÇå„Äŧ߄Åç„Å™ÁôΩ„ÄÅ„Éî„É≥„ÇØ„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØ˵§„ÅÑÂîá„ÄÅ˺ù„ÅèÁôΩ„ÅÑÊ≠Ø„ÅåÊèè„Åã„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„ÄÇ 1895Âπ¥„Äńǧ„ÇÆ„É™„Çπ„ÅßÂÖêÁ´•Êõ∏ÁîªÂÆ∂„Éï„É≠„ɺ„ɨ„É≥„Çπ„ɪ„DZ„ǧ„Éà„ɪ„Ç¢„Éó„Éà„É≥„ÅåÊèè„ÅÑ„Åü„Ç¥„É™„Ƕ„Ç©„ɺ„Ç∞„ÅåÁôªÂÝ¥„Åó„Åü„ÄÇÂ≠ê‰æõÊôljª£„Å´ÈÅé„Åî„Åó„Åü„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åã„ÇâÊåÅ„Å£„Ŷ„Åç„Åü„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´‰∫∫ÂΩ¢„Åß„ÅÇ„Çã„Ũ„ÅÑ„Åê„Çã„Åø„Çí„É¢„Éá„É´„Å®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Äå„Ç¥„É™„ɺ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÊÑõÁß∞„ÇíÊåńŧÂΩº„ÅØʺÜȪí„ÅÆÈ°î„ÄÅÈáéÊÄßÁöÑ„Å™Á∏Æ„ÇåÊØõ„ÄÅ˵§„ÅÑÂîá„Å™„Å©ÂÖ∏ÂûãÁöÑ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅÆÊßòÁõ∏„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÆÂæå‰∫∫ÂΩ¢„ÄÅ„Åä„ÇÇ„Å°„ÇÉ„ÅÆ„ÉÜ„Ç£„ɺ„Ǫ„ÉÉ„Éà„ÄÅȶôÊ∞¥„Å™„Å©Êßò„ÄÖ„Å™ÂïÜÂìÅ„ÅåË£ΩÈÄÝ„Åï„Çå„Äńǧ„ÇÆ„É™„Çπ„Åã„Çâ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Å´ÈÄÜ˺∏ÂÖ•„Åï„Çå„Åü„ÄÇ„Äå„Ç¥„É™„Ƕ„Ç©„ɺ„Ç∞„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜË®ÄËëâ„ÅØËâ≤Ȫí§ñÂõΩ‰∫∫„ÇíË°®„ÅôËîëÁß∞„Äå„Ƕ„Ç©„Ç∞„Äç(wog)„Åã„Çâ„Åç„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å®„Åï„Çå„Çã[75]„ÄÇ   1930Â𥉪£„Åã„Çâ1940Â𥉪£„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„ÅÆ„Ç´„ɺ„Éà„Ç•„ɺ„É≥„Åß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Éç„Çø„Çщªñ„ÅƉ∫∫Á®Æ„ÇÑÊ∞ëÊóè„ÅÆÈ¢®Âà∫„Åå„Åó„Å∞„Åó„Å∞Êèè„Åã„Çå„Åü„ÄÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Éü„ÉÉ„Ç≠„ɺ„Éû„Ƕ„Çπ„Å™„Å©„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅÆÁô∫±ï„Å∏„ÅÆÂΩ±Èüø„ÅÆ1„ŧ„Å®„Å™„Å£„Åü[76]„ÄÇ1933Âπ¥„ɶ„Éä„ǧ„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Ç¢„ɺ„ÉÜ„Ç£„Çπ„ÉÑ„ÅØ„ÄÅ„Äé„Éü„ÉÉ„Ç≠„ɺ„ÅÆËѱÁ∑öËäù±քÄè(ÂéüÈ°å„ÅØÂàùÊúü„ÅÆ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„Å∏„ÅÆÂõûÈ°ß„ÇíÊÑèÂë≥„Åô„Çã„É°„É≠„Éâ„É©„Éû„ÅÆÊîπ§â)„ÅØ„Äé„Ç¢„É≥„ÇØ„É´„ɪ„Éà„ÉÝ„ÅÆÂ∞è±ã„Äè„Çí„Éá„Ç£„Ç∫„Éã„ɺ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅßʺîÂá∫„Åï„Çå„ÅüÁü≠Á∑®ÊòÝÁÅß„ÅÇ„Çã„ÄÇÂäáÂÝ¥„Éù„Çπ„Çø„ɺ„Åß„ÅØ„ÄÅÂÖÉ„ÄÖȪí„ÅÑËÇå„ÅÆ„Éü„ÉÉ„Ç≠„ɺ„ÅÝ„Åå§߄Åç„Å™„Ç™„ɨ„É≥„Ç∏Ëâ≤„ÅÆÂîá„Çí„Åó„ÄÅÁ∏Æ„Çå„ÅüÁôΩ„ÅÑÈݨ„Å≤„Åí„Åå„ÅÇ„Çä„ÄÅÁèæÂú®„Åß„ÅØ„Éà„ɨ„ɺ„Éâ„Éû„ɺ„ÇØ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„ÇãÁôΩ„ÅÑÊâãË¢ã„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã[77]„ÄÇ  1950Âπ¥„Åæ„Åß„Å´„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åß„ÅØÂÖ®Á±≥Ȫí‰∫∫Âú∞‰ΩçÂêë‰∏äÂçö(NAACP)„Åå„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„ÅÆÊèè„Åã„ÇåÊñπ„Å™„Å©„Å´Ê≥®ÊÑè„Çí‰øÉ„Åô„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å´„Çà„Çã„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„É≥„Çπ„ÇÑÊèèÂÜô„Çí‰∏≠Ê≠¢„Å´ËøΩ„ÅÑË溄ÇÄ„Ç≠„É£„É≥„Éö„ɺ„É≥„Çí§߄Åç„ÅèË°å„Å™„Å£„Åü„ÄÇÊï∞ÂçÅÂπ¥„ÅÆÈñì„ÄÅ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅØ„Ç¢„ǧ„Çπ„ÅÆ„Éî„Ç´„Éã„Éã„ɺ„ɪ„Éï„É™„ɺ„Ç∫„Äńɨ„Çπ„Éà„É©„É≥„ɪ„ÉÅ„Ç߄ɺ„É≥„ÅÆ„Ç؄ɺ„É≥„ɪ„ÉÅ„Ç≠„É≥„ɪ„ǧ„É≥[78]„ÄÅ„Éã„Ǩ„ɺ„ɪ„Éò„Ç¢„ɪ„Çø„Éê„Ç≥„ÄÅ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺÊ≠ØÁ£®„ÅçÁ≤â(„ÉĄɺ„É™„ɺ„Å®ÊîπÂêç)„Å™„Å©„Åß˶ãÂèó„Åë„Çâ„Çå„Åü„ÄÇ „Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫ÂÖ¨Ê∞ëÊ®©ÈÅãÂãï„ÅÆÊàêÂäü„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´ÂõΩÂÜÖ„Åß„ÅØ„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÊòéÁôΩ„Å™Â∑ÆÂà•ÁöÑÊèèÂÜô„ÅØÁµÇÁÑâ„ÇíËøé„Åà„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÅÆ„Çø„Éñ„ɺ„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇ 1960Â𥉪£ÂàùÈÝ≠„ÄÅÊó•Êú¨„Åß„ÅØ„ÉÄ„ÉÉ„Ç≥„Å°„ÇÉ„Çì‰∫∫ÂΩ¢„Åå§߉∫∫Ê∞ó„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇ„ÉÄ„ÉÉ„Ç≥„Å°„ÇÉ„Çì„Åا߄Åç„ř˵§„ÅÑÂîá„Å®Ëçâ„Åß„Åß„Åç„Åü„Çπ„Ç´„ɺ„Éà„Çí±•„ÅÑ„ÅüȪí‰∫∫„ÅÆÂ≠ê‰æõ„ÇíÊ®°„Åó„Åü‰∫∫ÂΩ¢„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇÁî∑„ÅÆÂ≠ê„ٕ≥„ÅÆÂ≠ê„ÅƉ∫∫ÂΩ¢„Åå„ÅÇ„Çä„ÄÅ•≥„ÅÆÂ≠ê„ÅØ„É™„Éú„É≥„Çí„ŧ„Åë„Ŷ„ÅÑ„Åü„Älj∫∫ÂΩ¢„ÅÆȪí„ÅÑËÇå„ÅØ„Ç∏„É£„Ç∫„ÅƉ∫∫Ê∞ó„ÅƉ∏äÊòá„Åã„ÇâÈÅ∏ÂÆö„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Å®„Åï„Çå„Çã„ÄÇÂ∞èË™¨ÂÆ∂Ê≤≥ÈáéÂÖ∏Áîü„ÅØ„ÄåÁßÅ„Åü„Å°„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™Ëã•„Åщ∏ñ‰ª£„ÅØÊîøÊ≤ª„ÇÑÁ§æ‰ºö„Åã„ÇâÁñé§ñ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Éã„Ç∞„É≠„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´ÁßÅ„Åü„Å°„ÅØÊäëÂúß„ÄÅÁÑ°ÁêÜËߣ„Å´Èï∑„ÅÑÈñì„Åï„Çâ„Åï„Çå„ÄÅÁßÅ„Åü„Å°„ÅØÂΩº„Çâ„Å®ÂêåÊßò„Å´ÊÑü„Åò„Ŷ„ÅÑ„Çã„Äç„Ů˙û„Å£„Åü[79]„ÄÇ Áè扪£„ÅÆË°®ÁèæÈï∑„ÅÑÈñì„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åä„Çà„Å≥„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅÆÊèèÂÜô„ÅØ„Ç¢„ɺ„É´„ɪ„Éá„Ç≥„ÇÑ„Ç∏„É£„Ç∫„ɪ„Ç®„ǧ„Ç∏„Å®Èñ¢ÈÄ£„Åó„ŶËä∏Ë°ìÁöÑ„ÄÅÊßòºèÁöÑ„Éá„Éê„ǧ„Çπ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ1950Â𥉪£„Åä„Çà„Å≥1960Â𥉪£„Åæ„Åß„Å´„ÄÅÁâπ„Å´„É®„ɺ„É≠„ÉÉ„Éë„Åß„ÅØÈùûÂ∏∏„Å´ÂØõ§߄Åß„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØËä∏Ë°ìÂÆ∂„Åü„Å°„ÅÆÈñì„ÅßÈ¢®Â§â„Çè„Çä„Åß„Ç≠„É£„É≥„Éó„ř˰®ÁèæÊ≥ï„ÅƉ∏ÄÁ®Æ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄDŽǧ„ÇÆ„É™„Çπ„Åß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„ÄéThe Black and White Minstrel Show„Äè„ÅåÈü≥Ê•Ω„Éê„É©„Ç®„ÉÜ„Ç£Áï™ÁµÑ„Å®„Åó„Ŷ‰∫∫Ê∞ó„Åå„ÅÇ„Çä„ÄÅ1978Âπ¥„Åæ„ÅßÁ∂ö„ÅÑ„Åü„ÄÇÊõ≤„ÅƧö„Åè„ÅØ„Éü„É•„ɺ„Ç∏„ÉÉ„ÇØ„Éõ„ɺ„É´„ÄÅ„Ç´„É≥„Éà„É™„ɺ„ɪ„Ç¢„É≥„Éâ„ɪ„Ƕ„Ç®„Çπ„Çø„É≥„ÄʼnºùÁµ±ÁöÑ„Éï„Ç©„ɺ„ÇØ„ÇΩ„É≥„Ç∞„Åã„ÇâÈÅ∏Êõ≤„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü[80]„ÄÇ„Åæ„Åü„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Ç∞„ɨ„ǧ„Çπ„ɪ„Ç∏„É߄ɺ„É≥„Ç∫„ÅÆ„ÄéSlave to the Rhythm„Äè(1980Âπ¥),[81]„ÄÅ„Ç´„É´„ÉÅ„É£„ɺ„ɪ„ÇØ„É©„Éñ„ÅÆ„ÄéDo You Really Want to Hurt Me„Äè(1982Âπ¥)[82]„ÄÅ„Çø„Ç≥„ÅÆ„ÄéPuttin' On the Ritz„Äè(1983Âπ¥)„Å™„Å©„ÅÆ„Éü„É•„ɺ„Ç∏„ÉÉ„Ç؄ɪ„Éì„Éá„Ç™„Å´ÁôªÂÝ¥„Åó„Åü[83]„ÄÇ ‰∫§Êòì„ÅÆÁô∫±ï„ÇÑʵ∑§ñÊóÖË°å„ÅƉ∏ÄËà¨Âåñ„Å´„Çà„Çä„Åï„Çâ„Å™„ÇãÊñáÂåñ„ÅÆËûçÂêà„Åå˵∑„Åì„Çä„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÁï∞„Å™„ÇãÂïèÈ°å„Ååºï„Åç˵∑„Åì„Åï„Çå„Åü„ÄÇËøëÁè扪£„Å´„Åä„ÅфŶ„ÇÇÊó•Êú¨„Åß„ÅØ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅÆÊèèÂÜô„Å؉∫∫Ê∞ó„Åß„ÅÇ„Çã„Åå„ÄÅ1990Â𥉪£„Äńǵ„É≥„É™„Ç™„Åå„Éî„É≥„ÇØ„ÅÆÂéö„ÅÑÂîá„ÄÅËÄ≥„Ŵ˺™„Çí„Åó„Åü„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅÆ„Éì„Éì„É≥„Éê„ÅƉ∫∫ÂΩ¢„ÇíÁô∫Ë°®„Åó„ÅüÈöõ[84]Ë≠∞Ë´ñ„Çíºï„Åç˵∑„Åì„ÅóË£ΩÈÄ݉∏≠Ê≠¢„Å®„Å™„Å£„Åü[85]„ÄÇ „Çπ„Éö„ǧ„É≥„ÅÆ„É©„Ç´„ǵÁ§æ„ÅÆËèìÂ≠ê„Ç≥„É≥„ÇƄɺ„Éà„Çπ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅØ[86]„Åö„Çì„Åê„Çä„Åó„ÅüÂ∞è„Åï„Å™Ëå∂Ëâ≤„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Åå„ÄÅÂéö„ÅÑ˵§„ÅÑÂîá„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄDŽǧ„ÇÆ„É™„Çπ„ÅÆ„Ç¥„É™„Ƕ„Ç©„ɺ„Ç∞„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Åß„ÅÇ„Çã„Ç¥„ɺ„É™„ɺ„ÅØ[87]„ÄÅ100Âπ¥Ëøë„Åè„Ç∏„Ç߄ǧ„ÉÝ„Ç∫„ɪ„É≠„Éê„ɺ„Éà„ÇΩ„É≥&„ǵ„É≥„Ç∫„ÅÆ„Ç∏„É£„ÉÝ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Åå„ÄÅ2001Âπ¥„ÄʼnΩøÁ∏≠Ê≠¢„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇ„Åó„Åã„ÅóÂïÜÂìÅ„ÄűïÁ§∫„ÄÅ„Åù„Åó„ŶÂ≠ê‰æõ„Å´‰∫∫Ê∞ó„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Å®„Åó„Ŷ„ÅÆÂ≠òÁ∂ö„ÇíÁ¶ÅÊ≠¢„Åô„Åπ„Åç„Å™„ÅÆ„Åã„Å®„ÅÑ„ÅÜË≠∞Ë´ñ„ÅØ„Åæ„ÅÝÁ∂ö„ÅфŶ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Éï„É©„É≥„Çπ„Åß„ÅØ„Ç≥„Ç≥„Ç¢„ÅÆ„Éê„Éä„Éã„Ç¢„Åß„Åæ„Åݧ߄Åç„ř˵§„ÅÑÂîá„Çí„Åó„ÅüȪí‰∫∫Â∞ëÂπ¥„Åå„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Å®„Åó„Ŷ‰ΩøÁÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[88]„ÄÇ Áè扪£„Å´„Åä„ÅфŶ„Çlj∏ñÁïå‰∏≠„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÂïÜÂìÅ„ÇÑÂ∫ÉÂëä„Å™„Å©„Å߉ΩøÁÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ „Éá„Ç∏„Çø„É´„ɪ„É°„Éá„Ç£„Ç¢„Éá„Ç∏„Çø„É´„ɪ„É°„Éá„Ç£„Ç¢„Åß„ÅØÂÆüÈöõ„Å´È°î„ÇíȪí„Åè°ó„Çã„Åì„Å®„Åå„Å™„Åè„Å®„ÇÇȪí‰∫∫„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅåÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇ1999Âπ¥„ÄÅ„Ç¢„ÉÄ„É݄ɪ„Ç؄ɨ„ǧ„Éà„É≥„ɪ„Éë„Ƕ„Ç®„É´3‰∏ñ„ÅØ„Éì„Éá„Ç™„ɪ„Ç≤„ɺ„ÉÝ„ÅÆȪí‰∫∫ÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„ÅÆ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Åß„ÅÆÊèè„Åã„ÇåÊñπ„Å´Ë®ÄÂèä„Åô„Çã„Äå„Éè„ǧ„ÉÜ„Ç؄ɪ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜË®ÄËëâ„Çí‰Ωú„Å£„Åü[89]„ÄÇ„Éá„ǧ„É¥„Ç£„ÉÉ„Éâ„ɪ„ɨ„Éä„ɺ„Éâ„ÅØ„Äå„Éê„ɺ„ÉÅ„É£„É´„ɪ„É™„Ç¢„É™„ÉÜ„Ç£„ÅÆ„Çπ„Éù„ɺ„Éфɪ„Ç≤„ɺ„ÉÝ„Å´„Åä„ÅфŶ‰ΩìÂäõ„ÄÅÈÅãÂãïËÉΩÂäõ„ÄÅ„Éë„É؄ɺ„Å™„Å©„Å´„Åä„Åë„Çã„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„ÅÆȪí‰∫∫„Å´„Å™„Çä„Åü„ÅÑ„Å®ÊÄù„ÅÜ„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Äç„Ů˙û„Å£„Åü„ÄDŽɨ„Éä„ɺ„Éâ„ÅÆË´ñÊãÝ„ÅØ„Çπ„Éù„ɺ„Éфɪ„Ç≤„ɺ„ÉÝ„ÅÆ„Éó„ɨ„ǧ„ɧ„ɺ„ÅØȪí‰∫∫„Ç¢„Éê„Çø„ɺ„Çí„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åô„Çã„Åì„Å®„Å´„Çà„Çä„Ç¢„ǧ„Éá„É≥„ÉÜ„Ç£„ÉÜ„Ç£„ɪ„Éфɺ„É™„Ç∫„ÉÝ„Çí„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„Åì„Å®„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„Åó„Åü[90]„ÄÇ„Éï„Ç£„É™„ÉÉ„Éó„Çπ„Å®„É™„ɺ„Éâ„ÅØ„Åì„ÅÆ„Çø„ǧ„Éó„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„ÄåÁôΩ‰∫∫„ÅåȪí‰∫∫ÂΩπ„ÇíÂçò„Ŵʺî„Åò„Çã„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„ÄÅÂ∑ÆÂà•ÁöÑ˶≥ÂÆ¢„ÇíÂñú„Å∞„Åõ„Çã„Çà„ÅÜ˙ẵ„Åó„ÅüʺîÊäÄ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Åù„ÅÆȪí„Åï„Å´„Çà„Å£„ŶÁôΩ‰∫∫Ëá≥‰∏ä‰∏ªÁæ©„ÇíÊòéÁôΩ„Å´Âº∑˶ńÅó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Äç„Ů˙û„Å£„Åü[91]„ÄÇ „ÇΩ„Éº„Ç∑„É£„É´„ɪ„É°„Éá„Ç£„Ç¢„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÂÆπÊòì„Å´Êã°ÊÅô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„ÄÇ2016Âπ¥„ÄÅSnapchat„Å´„Åä„ÅфŶÊíÆÂΩ±ËÄÖËá™Ë∫´„ÅÆÈ°î„Å´„Éú„Éñ„ɪ„Éû„ɺ„É™„ɺ„ÅÆ„Éï„Ç£„É´„Çø„ɺ„ÇíÈáç„Å≠„Çã„Å®„ÉĄɺ„ÇØ„Å™ËÇåËâ≤„ÄÅ„Éâ„ɨ„ÉÉ„Éâ„É≠„ÉÉ„ÇØ„Çπ„ÄÅ„Éã„ÉÉ„ÉàÂ∏Ω„ÅåË°®Á§∫„Åï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü[92][93]„ÄÇÂÖ®Á±≥„ÅƧßÂ≠¶Áîü„ÅåËá™Ë∫´„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÁîªÂÉè„ÇíÂÖ±Êúâ„Åó„Åü„Åì„Å®„Å®ÂÖ±„Ŵ§ß˶èÊ®°„řȮíÂãï„Å´Áô∫±ï„Åó„Åü[94][95][96][97]„ÄÇ „Ç¢„É°„É™„Ç´20‰∏ñÁ¥Ä1936Âπ¥„ÄÅ„Ç™„ɺ„ÇΩ„É≥„ɪ„Ƕ„Çß„É´„Ç∫„ÅÆ„ÄéVoodoo Macbeth„ÄèÂ∑°Ê•≠Â֨ʺî„ÅƉ∏ªÂΩπ„É¢„ɺ„É™„Çπ„ɪ„Ç®„É™„Çπ„ÅåÁóÖÊ∞ó„Å´„Çà„ÇäÈôçÊùø„Åó„ÅüÊôÇ„ÄńǶ„Çß„É´„Ç∫„ÅåÊÄ•ÈÅΩ‰ª£ÂΩπ„ÇíÂãô„ÇÅ„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åßʺî„Åò„Åü[98]„ÄÇ ‰∫∫Á®Æ„ÅÆ¢ÉÁïå„Åä„Çà„Å≥ËÇå„ÅÆËâ≤„Å´„Çà„ÇãÂ∑ÆÂà•„Åå„ÅÇ„Çã„Ç¢„É°„É™„Ç´ÊñáÂåñ„ÅØ2‰∫∫„ÅÆÁôΩ‰∫∫Áî∑ÊÄß„Å´„Çà„Çã„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅƉ∫∫Ê∞ó„Éá„É•„Ç™„Åß„ÅÇ„Çã„Ç¢„É¢„Çπ&„Ç¢„É≥„Éá„Ç£„Å´„Çà„Å£„ŶÂÆüË®º„Åï„Çå„Åü„ÄÇ1929Âπ¥„ÅÆÂ֨ʺî‰∏≠„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Çí„ÇÑ„ÇÅ„Åü„ÅåȪí‰∫∫Ë®õ„Çä„ÅÆ„Åæ„Åæ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ20‰∏ñÁ¥ÄÂàùÈÝ≠„Åã„ÇâÂçóÂåóÊඉ∫âÂâç„Åæ„Åß„Å´‰∫∫Á®Æ„ÅÆ¢ÉÁïå„ÅÆ„ÅÇ„Çã„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„É≥„Çπ„ÅØÁ¢∫Á´ã„Åï„Çå„Åü[99]„ÄÇ 20‰∏ñÁ¥ÄÂàùÈÝ≠„ÄÅ„Éã„É•„ɺ„Ç™„ɺ„É™„É≥„Ç∫„ÅßÊØéÂπ¥Ë°å„Çè„Çå„Çã„Éû„É´„Éá„Ç£„Ç∞„É©„ÅÆ„Éë„ɨ„ɺ„Éâ„Å´„Åä„ÅфŶ„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫Âä¥ÂÉçËÄÖ„Åü„Å°„Åå„Äå„Éà„É©„É≥„Éó„Çπ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Ç∞„É´„ɺ„Éó„ÇíÁµêÊàê„Åó„Ŷ„Éõ„ɺ„Éú„ɺ„ÅÆÊÅ∞Â•Ω„ÅßË°åÈÄ≤„Åó„Åü„ÄÇÁõÆÁ´ã„Åü„Åõ„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Äå„Ç∫„ɺ„É´„ɺ„Äç„Å®ÊîπÂêç„Åó„ÄÅÂú∞ÂÖÉ„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„Ç؄ɪ„Ç∏„É£„Ç∫„ɪ„ÇØ„É©„Éñ„ÇÑ„Ç≠„É£„Éê„ɨ„ɺ„Åßʺî„Åò„Çâ„Çå„Çã„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ɪ„É¥„Ç©„ɺ„Éâ„É¥„Ç£„É´„ÅÆË°£Ë£≥„ÇíÁúü‰ºº„Åü[100]„ÄÇ„Åù„ÅÆÁµêÊûú„ɨ„ÉÉ„ÇØ„Çπ„ɪ„Éë„ɨ„ɺ„Éâ„Å®„Åó„Ŷ„Éû„É´„Éá„Ç£„Ç∞„É©„ÅßÊúÄ„ÇÇÁü•„Çâ„ÇåÊúÄ„ÇÇÁõÆÁ´ã„Å£„Åü„ÇØ„É´„ɺ„ÅÆ1„ŧ„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇËçâ„ÅÆ„Çπ„Ç´„ɺ„Éà„ÄÅ„Ç∑„É´„ÇØ„Éè„ÉÉ„Éà„ÄÅ˙ẵ„Åó„Åü„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„Åó„ÄÅ„Éã„É•„ɺ„Ç™„É™„É≥„Ç∫„ÅÆ„Ç∫„ɺ„É´„ɺ„Å؉∫∫Ê∞ó„Å®ÂÖ±„Å´Ë≠∞Ë´ñ„ÇíÂ∑ª„Åç˵∑„Åì„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã[101]„ÄÇ „Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÂåñÁ≤ß„ÅØ„Éö„É≥„Ç∑„É´„Éô„Éã„Ç¢Â∑û„Éï„Ç£„É©„Éá„É´„Éï„Ç£„Ç¢„ÅßÊØéÂπ¥Ë°å„Çè„Çå„Çã„Éû„Éû„ɺ„Ç∫„ɪ„Éë„ɨ„ɺ„Éâ„ÅƉºùÁµ±„ÅÆ1„ŧ„Å®„ÇÇ„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åü„Älj∫∫Ê®©Âõ£‰Ωì„ÇÑȪí‰∫∫„Ç≥„Éü„É•„Éã„ÉÜ„Ç£„Åã„Çâ„ÅÆÊäóË≠∞„Åå¢ó§߄Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„ÄÅ1964Âπ¥„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØÂ֨ºè„Å´Á¶ÅÊ≠¢„Å®„Å™„Å£„Åü[102]„ÄÇ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆÁ¶ÅÊ≠¢„Å´„ÇÇ„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅ2016Âπ¥„ÅÆ„Éë„ɨ„ɺ„Éâ„Åß„ÇÇ„É°„Ç≠„Ç∑„Ç≥‰∫∫„ÇíË°®„Åô„Åü„ÇÅ„Å´„Éñ„É©„Ƕ„É≥„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅåÊñΩ„Åï„Çå„Äʼn∫∫Ê®©Âõ£‰Ωì„Åã„ÇâÊäóË≠∞„Åï„Çå„Åü„ÄÇ1964Âπ¥„ÄÅ„Ç≥„Éç„ÉÅ„Ç´„ÉÉ„ÉàÂ∑û„Éé„ɺ„Éï„Ç©„ɺ„ÇØ„Åß„Éû„ɺ„Éńɪ„Ç™„Éñ„ɪ„ÉĄǧ„ÉÝ„Ç∫„ÅÆË≥áÈáëÈõÜ„Çńǧ„Éô„É≥„Éà„Å߉ºùÁµ±ÁöÑ„Å´Â≠¶Áîü„Åü„Å°„Å´„Çà„Çã„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÅåË°å„Å™„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åå„ÄŪÉÊ≠¢„Å´ËøΩ„ÅÑË溄Åæ„Çå„Åü[103]„ÄÇ 1980Âπ¥„ÄÅ„É™„ÉÅ„É£„ɺ„Éâ„ɪ„Ç®„É´„Éï„Éû„É≥Áõ£Áù£„ÄÅ„Éê„É≥„Éâ„ÅÆ„Ç™„ǧ„É≥„Ç¥„ɪ„Éú„ǧ„É≥„Ç¥‰∏ªÊºî„Å´„Çà„Çã„Ç¢„É≥„ÉĄɺ„Ç∞„É©„Ƕ„É≥„ÉâÊòÝÁÄé„Éï„Ç©„ɺ„Éì„Éá„É≥„ɪ„Çæ„ɺ„É≥„Äè„ÅåÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åå‰ΩøÁÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„ÅßË≠∞Ë´ñ„Åå˵∑„Åì„Å£„Åü[104]„ÄÇ 1988Âπ¥„ÄÅÂÖɄǧ„É™„Éé„ǧÂ∑û‰∏ãÈô¢Ë≠∞Âì°„ÄÅÂÖ±ÂíåÂÖöÈô¢ÂÜÖÁ∑èÂãô„Éú„Éñ„ɪ„Éû„ǧ„DZ„É´„ÅØ„ÄéUSA„Éà„Ç•„Éá„ǧ„Äè„É܄ɨ„ÉìÁâà„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅËã•„ÅÑÈÝÉ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„Å´Âá∫ʺî„Åó„Åü„Åì„Å®„ÇíÂæåÊÇî„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Ů˙û„ÇäË©±È°å„Å´„Å™„Å£„Åü[105][106]„ÄÇ 1993Âπ¥„ÄÅÁôΩ‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ÉÜ„ÉÉ„Éâ„ɪ„ÉÄ„É≥„ÇΩ„É≥„Åå„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„ÇØ„Å´„ÅÇ„Çã„Éï„É©„ǧ„Ç¢„ɺ„Ç∫„ɪ„ÇØ„É©„Éñ„Å´„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÁôªÂÝ¥„Åó„ÄÅÂΩìÊôÇÊÅã‰∫∫„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„Ç≥„É°„Éá„ǣ•≥ÂÑ™„Ƕ„ɺ„Éî„ɺ„ɪ„Ç¥„ɺ„É´„Éâ„Éê„ɺ„Ç∞„ÅåÊõ∏„ÅÑ„Åü„Éç„Çø„ÇíÊä´Èú≤„Åó„Ŷ§ßÂïèÈ°å„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇÁôΩ‰∫∫„ÅßÂêåÊÄßÊÑõËÄÖ„ÅÆ„Éë„Éï„Ç©„ɺ„Éû„ɺ„ÅÆ„ÉÅ„É£„ÉÉ„Ç؄ɪ„Éã„ÉÉ„Éó„ÅØËá™Ë∫´„ÅåÂá∫ʺî„Åô„Çã„Ç≠„É£„Éê„ɨ„ɺ„ÅßÁôΩ‰∫∫„ÅÆ„Åø„ÅÆ˶≥ÂÆ¢„ÅÆÂâç„ÅßÁï∞ÊÄßË£Ö„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Äå„Ç∑„É£„ɺ„É™„ɺ„ɪQ„ɪ„É™„Ç´„ɺ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Çíʺî„Åò„Äʼn∫∫Á®ÆÁöÑÈ¢®Âà∫„ÇíÊä´Èú≤„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇ„Éã„ÉÉ„Éó„ÅÆÊÇ™Ë≥™„Å™„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅØÊâπÂৄÅï„Çå„ÄÅȪí‰∫∫„ÄÅÂêåÊÄßÊÑõËÄÖ„ÇÑ„Éà„É©„É≥„Çπ„Ç∏„Çß„É≥„ÉĄɺ„ÅÆÊ¥ªÂãïÂÆ∂„Åã„Çâ„Éá„ɢʥªÂãï„Çí„Åï„Çå„Åü[107]„ÄÇ 2000Âπ¥„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åä„Çà„Å≥„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ÅØ„Çπ„Éë„ǧ„Ç؄ɪ„É™„ɺ„ÅÆÊòÝÁÄéBamboozled„Äè„ÅÆ„É܄ɺ„Éû„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇȪí‰∫∫„ÅÆ„É܄ɨ„Éì±ÄÈáçÂΩπ„Å؉∏çÊ∫Ä„Çí„Åü„ÇÅË溄ÅøËߣÈõá„Åï„Çå„Çã„Åü„ÇÅ„Å´„Çè„Åñ„Å®„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„Åô„Åå„ÄÅÊÄùÊÉë„Å®„ÅØÈÄÜ„ÅÆÊñπÂêë„Å´Âêë„Åã„ÅÑÊÅê„Çå„Çã[108]„ÄÇ 21‰∏ñÁ¥Ä„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„ÇØ„ÇíÊãÝÁÇπ„Å®„Åô„Çã„É°„Éà„É≠„Éù„É™„Çø„É≥„ɪ„Ç™„Éö„É©„ÅØ„Äé„Ç™„Ǫ„É≠„Äè„Çíʺî„Åò„ÇãÈöõ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü[109][110][111][112]„ÄÇ„ÉĄɺ„ÇØ„Å™Ëâ≤„ÅÆËàûÂè∞ÂåñÁ≤ß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å®„ÅÑ„Å܄Ū„Å©„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„Å®„ÅÑ„Å܉∏ªÂºµ„ÇÇ„ÅÇ„Å£„Åü„Åå2015Âπ¥„ÅߪÉÊ≠¢„Åó„Åü[113]„ÄÇ ÁôΩ‰∫∫§ßÂ≠¶Áîü„Çâ„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„ÅóË≠∞Ë´ñ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÊØéÂπ¥„Éè„É≠„Ƕ„Ç£„É≥„ÅÆÈÝÉ„Å´„Ç®„Çπ„Ç´„ɨ„ɺ„Éà„Åó„ÄÅ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„ÇíÊèèÂÜô„Åô„Çã[114][115][116][117]„ÄÇ „Éù„DZ„ÉÉ„Éà„É¢„É≥„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Åß„ÅÇ„Çã„É´„ɺ„Ç∏„É•„É©„ÅÆÂΩìÂàù„ÅÆ„Éá„Ç∂„ǧ„É≥„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅÆ„Ç´„É™„Ç´„ÉÅ„É•„Ç¢„Å®‰ºº„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å®„Åó„ŶË≠∞Ë´ñ„ÇíÂ∑ª„Åç˵∑„Åì„Åó„Åü„Äljª•ÈôçËÇå„ÅÆËâ≤„ÅØÁ¥´Ëâ≤„Ŵ§âÊõ¥„Åï„Çå„Åü„ÄÇ 2005Âπ¥11Êúà„ÄÅȪí‰∫∫„Ç∏„É£„ɺ„Éä„É™„Çπ„Éà„ÅÆ„Çπ„ÉÜ„Ç£„ɺ„É¥„ɪ„ÇÆ„É™„Ç¢„ɺ„Éâ„ÅåËá™Ë∫´„ÅÆ„Éñ„É≠„Ç∞„Å´ÂÜôÁúü„ÇíÊé≤˺â„Åó„Åü„Åì„Å®„Åã„ÇâË≠∞Ë´ñ„ÅåÂô¥Âá∫„Åó„Åü„ÄÇÂΩìÊôÇ„Ç¢„É°„É™„Ç´ÂêàË°ÜÂõΩ‰∏äÈô¢Ë≠∞Âì°ÂÄôË£úËÄÖ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Ç¢„Éï„É™„Ç´Á≥ª„Ç¢„É°„É™„Ç´‰∫∫„ÅÆÊîøÊ≤ªÂÆ∂„Éû„ǧ„DZ„É´„ɪ„Çπ„ÉÜ„Ç£„ɺ„É´„ÅÆÁîªÂÉè„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇÁ∏Æ„Çå„ÅüÁôΩ„ÅÑÁúâÊØõ„Äŧ߄Åç„ř˵§„ÅÑÂîá„Å´ÂäÝÂ∑•„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇȪí‰∫∫Ë®õ„Çä„Åß„ÄåÁßÅ„ÅØ„Åü„ÅÝ„ÅƄǵ„É≥„Éú(Ȫí‰∫∫„ÅÆËîëÁß∞)„ÅÝ„Åë„ũ§߄Åç„Å™„Éè„Ƕ„Çπ„Å´Á´ãÂÄôË£ú„Åô„Çã„Äç„Å®„ÅÆÊ≥®Èáà„Åå„ŧ„ÅфŶ„ÅÑ„Åü(Ëã±Ë™û„Åß„Äå„Éè„Ƕ„Çπ„Äç„ÅØ„ÄåË≠∞‰ºö„Äç„ÅÆÊÑèÂë≥„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÄÅ„Äå„Éì„ÉÉ„Ç∞„ɪ„Éè„Ƕ„Çπ„Äç„ÅØÂàëÂãôÊâÄ„ÇÑȪí‰∫∫•¥Èö∑„Åå„ÅÑ„Åü„Éó„É©„É≥„É܄ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ÅÆ„Çà„Å܄ř§ßÈÇ∏ÂÆÖ„ÅÆ„Åì„Å®„ÇÇË°®„Åô)„ÄÇ„ÇÆ„É™„Ç¢„ɺ„Éâ„ÅØÊîøÊ≤ªÁöщøùÂÆàÊ¥æ„Å®Ëá™Â∑±ÂºÅË≠∑„Åó„ÄÅ„Çπ„ÉÜ„Ç£„ɺ„É´„ÅØ„ÄåÂΩº„Çâ„ÅÆÂë≥Êñπ„Å´„Å™„Çã„ÅÆ„ÇíÊãíÂ궄Åô„Çã„Äç„Ů˙û„Å£„Åü[118]„ÄÇ 2008Âπ¥„ÄÅ„Éô„Éç„Ç∫„Ç®„É©„Å®Êó•Êú¨„ÅÆʵńÇå„Çíʱ≤„ÇÄÁôΩ‰∫∫„Ç≥„É°„Éá„Ç£„Ç¢„É≥„ÅÆ„Éï„ɨ„ÉÉ„Éâ„ɪ„Ç¢„ɺ„Éü„Ǫ„É≥„Å؉∫∫Ê∞ó„É܄ɨ„ÉìÁï™ÁµÑ„Äé„ǵ„Çø„Éá„ɺ„ɪ„Éä„ǧ„Éà„ɪ„É©„ǧ„Éñ„Äè„Åß„Éê„É©„Ç؄ɪ„Ç™„Éê„Éû„ÅÆÁúü‰ºº„Çí„ÅóË≠∞Ë´ñ„ÇíÂ∑ª„Åç˵∑„Åì„Åó„Åü„ÄÇ„Äé„Ǩ„ɺ„Éá„Ç£„Ç¢„É≥„ÄèÁ¥ô„ÅÆË®òËÄÖ„ÅØÁï™ÁµÑ„Å´„Å™„ÅúȪí‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ÇíÈõá„Çè„Å™„Åã„Å£„Åü„ÅÆ„ÅãÂÖ¨ÈñãË≥™Âïè„Åó„ÄÅÁï™ÁµÑ„ÅØÂΩìÊôÇȪí‰∫∫„É°„É≥„Éê„ɺ„ÅØ1‰∫∫„Åó„Åã„ÅÑ„Å™„Åã„Å£„Åü„Åü„ÇÅ„Å®Á≠î„Åà„Åü[119]„ÄÇ 2010Âπ¥11Êúà„ÄÅ„É܄ɨ„ÉìÁï™ÁµÑ„ÄéIt's Always Sunny In Philadelphia„Äè„ÅÆ„Ç®„Éî„ÇΩ„Éº„Éâ„ÄéDee Reynolds: Shaping America's Youth„Äè„Åß„Ç≥„Éü„Ç´„É´„Å´„Åæ„Çã„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅåÊ≠£„Åó„ÅÑ„Åì„Å®„Åß„ÅÇ„Çã„Åã„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´Ë°®Áèæ„Åï„Çå„Åü„ÄÇÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„ÅÆ1‰∫∫„Åå1965Âπ¥„ÅÆ„Äé„Ç™„Ǫ„É≠„Äè„ÅÆ„É≠„ɺ„ɨ„É≥„Çπ„ɪ„Ç™„É™„É¥„Ç£„Ç®„ÅÆ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åß„ÅÆʺîÊäÄ„ÅØÂ∑ÆÂà•ÁöÑ„Åß„ÅØ„Å™„Åã„Å£„Åü„Ů˙û„Å£„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Ç®„Éî„ÇΩ„Éº„Éâ„ÅƉ∏≠„Åß„ÄÅÊòÝÁÄé„É™„ɺ„ǵ„É´„ɪ„Ƕ„Çß„Éù„É≥„Äè„ÅÆ„Éï„Ç°„É≥„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„Åó„ŶÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÂá∫ʺî„Åó„Åü[120]„ÄÇÁ¨¨9„Ç∑„ɺ„Ç∫„É≥„ÅÆ„Ç®„Éî„ÇΩ„Éº„Éâ„ÄéThe Gang Makes Lethal Weapon 6„Äè„ÅßÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„ÅåÂÜçÂ∫¶„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÁôªÂÝ¥„Åó„Åü„ÄÇ 2012Âπ¥„ÄÅ„Éù„ÉÉ„Éó„ÉÅ„ÉÉ„Éó„Çπ„ÅÆ„Ç≥„Éû„ɺ„Ç∑„É£„É´„ÅßÁôΩ‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„Ç¢„Ç∑„É•„Éà„É≥„ɪ„Ç´„ÉÉ„ÉÅ„É£„ɺ„Åå„Éñ„É©„Ƕ„É≥„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Å߄ǧ„É≥„Éâ‰∫∫„ÅÆ„Çπ„É܄ɨ„Ç™„Çø„ǧ„Éó„Çíʺî„Åò„ÄÅË≠∞Ë´ñ„ÇíÂ∑ª„Åç˵∑„Åì„Åó„Äʼn∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜÊâπÂৄÇíÂèó„Åë„Ŷ„Åì„ÅÆ„Ç≥„Éû„ɺ„Ç∑„É£„É´„Å؉∏≠Ê≠¢„Å®„Å™„Å£„Åü[121]„ÄÇ 2013Âπ¥10Êúà„ÄÅ•≥ÂÑ™„Ç∏„É•„É™„Ç¢„É≥„ɪ„Éè„Éï„ÅØ„Éè„É≠„Ƕ„Ç£„É≥„Åß„Äé„Ç™„ɨ„É≥„Ç∏„ɪ„ǧ„Ç∫„ɪ„Éã„É•„ɺ„ɪ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Äè„ÅÆ„Ç؄ɨ„ǧ„Ç∏„ɺ„ɪ„Ç¢„ǧ„Ç∫(„Ƕ„Çæ„ɪ„Ç¢„Éâ„Ç•„ɺ„Éê)„Å´‰ªÆË£Ö„Åó„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÇíÊñΩ„Åó„ŶÊâπÂৄÅÆÂØæ˱°„Å®„Å™„Å£„Åü[122][123]„ÄÇ„Åù„ÅÆÂæå„Éè„Éï„ÅØ˨ùÁΩ™„Åó„ÄÅTwitter„Åß„ÄåÁßÅ„ÅÆË°£Ë£≥„Åå‰∫∫„ÄÖ„ÇíÂÇ∑„ŧ„ÅëÊîªÊíÉ„Åó„Ŷ„Åó„Åæ„Å£„Åü„Åì„Å®„ÇíË™ç„ÇÅ„ÄÅÂøÉ„Åã„Çâ˨ùÁΩ™„Åó„Åæ„Åô„Äç„Ůˮò„Åó„Åü[124]„ÄÇ ‰ΩúÂÆ∂„É¥„Ç£„ÇØ„Éà„É™„Ç¢„ɪ„Éï„Ç©„ǧ„Éà„ÅØËá™Ë∫´„ÅÆÂ∞èË™¨„ÄéSave the Pearls: Revealing Eden„Äè„ÅÆÂ∫ÉÂëä„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åå‰ΩøÁÅï„Çå„Åü„Åì„Å®„Å´ÊäóË≠∞„Åó„Åü[125][126]„ÄÇ „Ç¢„É°„É™„Ç´ÂÜÖ§ñ„ÅßÈ£üÂô®„ÄÅÁü≥Èπ∏„ÄÅ„Åä„ÇÇ„Å°„ÇÉ„Åã„ÇâÂƧÂÜÖË£ÖÈ£æÂìÅ„ÄÅT„Ç∑„É£„ÉÑ„Å™„Å©„ÅÆÂïÜÂìÅ„Å´Ëá≥„Çã„Åæ„Åß„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„ÅåÊèè„Åã„ÇåÁ∂ö„Åë„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Åù„ÅƉ∏ÄÈÉ®„ÅØÊ≠¥Âè≤ÁöÑ„Å™ÊñáÂåñÁöÑÂ∑•Ëä∏ÂìÅ„Å®„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åå„ÄÅ„Åù„Ç剪•Â§ñ„ÅØ„ÅÑ„Çè„ÇÜ„Çã„Äå„Éï„Ç°„É≥„Çø„Ç∏„ɺ„Äç(Á©∫ÊÉ≥„ÅÆÁî£Áâ©)„Å®Â뺄Å∞„ÇåËøëÂπ¥Êñ∞„Åü„Å´„Éá„Ç∂„ǧ„É≥„Åä„Çà„Å≥Ë£ΩÈÄÝ„Åï„ÇåÂ∏ÇÂÝ¥„Å´Âá∫Âõû„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åß„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÂïÜÂìÅ„ÅØ„Ç™„É™„Ç∏„Éä„É´„ÅÆ„ÉĄɺ„Ç≠„ɺ„ÅÆ„Ç≠„É£„É©„ÇØ„Çø„ɺ„Å®ÂÖ±„Å´„Éã„ÉÉ„ÉÅÂ∏ÇÂÝ¥„ÅßÁπÅÁõõ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ1970Â𥉪£„Åã„Çâ„Äå„Éã„Ç∞„É≠„Éì„É™„Ç¢„Äç„ÅÆ„É¥„Ç£„É≥„É܄ɺ„Ç∏„Å®„Åó„Ŷ„ÅƉæ°Âħ„ÅØ„Å©„Çì„Å©„Çì‰∏ä„Åå„Å£„Ŷ„Åç„Ŷ„ÅÑ„Çã[127]„ÄÇ „É܄ɨ„Éì„Éâ„É©„Éû„Äé„Éû„ÉÉ„Éâ„É°„É≥„Äè„ÅÆÁôªÂÝ¥‰∫∫Áâ©„É≠„Ç∏„É£„ɺ„ɪ„Çπ„Çø„ɺ„É™„É≥„Ç∞„ÅØÁ¨¨3„Ç∑„ɺ„Ç∫„É≥„ÅÆ„Ç®„Éî„ÇΩ„Éº„Éâ„ÄéMy Old Kentucky Home„Äè(„Çπ„ÉÜ„Ç£„ɺ„Éñ„É≥„ɪ„Éï„Ç©„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆ„Äé„DZ„É≥„Çø„ÉÉ„Ç≠„ɺ„ÅÆÊàë„ÅåÂÆ∂„Äè„Å®ÂêåÂêç)„Åß„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÁôªÂÝ¥„Åó„Åü„ÄÇ 2008Âπ¥„ÅÆÊòÝÁÄé„Éà„É≠„Éî„ÉÉ„Ç؄ɪ„ǵ„É≥„ÉĄɺ/Âè≤‰∏äÊúĉΩé„ÅƉΩúÊ඄Äè„ÅƉ∏≠„Å߉ø≥ÂÑ™„É≠„Éê„ɺ„Éà„ɪ„ÉĄǶ„Éã„ɺ„ɪJr„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÈ¢®Âà∫ÁöÑ„Å™„Ç™„ɺ„Çπ„Éà„É©„É™„Ç¢‰ø≥ÂÑ™ÂΩπ„Çíʺî„Åò„Åü„ÄÇ Êó•Êú¨‚Üí„ÄåÊó•Êú¨„ÅÆ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„Éó„Äç„ÇÇÂèÇÁÖß
Êó•Êú¨„Åß„ÅØ„ÄÅ„Ç¢„É°„É™„Ç´„Åã„ÇâÊù•Ëà™„Åó„Åü„Éû„Ç∑„É•„ɺ„ɪ„Éö„É™„ɺ„ÅåÈÖç‰∏ã„ÅÆÁôΩ‰∫∫„Çí‰Ωø„Å£„Ŷ„Éü„É≥„Çπ„Éà„ɨ„É´„ɪ„Ç∑„É߄ɺ„ÇíË°å„Å£„Åü„ÅÆ„ÅåÂ规Åщæã„Åß„ÅÇ„Çã[128]„ÄÇ Êó•Êú¨„ÅÆ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„Éó„Åß„ÅØ„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„ÄåȪí°ó„Çä„Äç„Å™„Å©„Å®Â뺄Å∞„Çå„ÄÅ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„Éë„ɺ„ÅƄǵ„Éñ„Ç´„É´„ÉÅ„É£„ɺ„ÅØ„Äå„Éñ„É©„Éë„É≥„Äç„Çπ„Çø„ǧ„É´„Å®„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[129]„ÄÇÊñáÂåñÁöÑ„Å´Â∑ÆÂà•ÁöÑʵńÇå„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å´„ÇÇ„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅÊó•Êú¨„Åß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„Éó„ÅÆʵÅË°å„ÅÆË®º„Å®„Å™„Å£„Åü[130]„ÄÇÊó•Êú¨„ÅÆ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„Éó„ɪ„Éï„Ç°„É≥„ÅƉ∏ÄÈÉ®„ÅØ„Åì„Çå„Çí„Åç„Åæ„ÇäÊÇ™„ÅèÊÑü„Åò„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Çí„Åó„Ŷ„Åç„ÅüËÄÖ„ÅØ„Åù„ÅÆ„Çπ„Çø„ǧ„É´„Çí§â„Åà„Çã„Åπ„Åç„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„Å®ÊÑü„Åò„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÂ∑ÆÂà•ÁöÑÊßòÁõ∏„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çã„Åå„ÄÅÊó•Êú¨„ÅƧö„Åè„ÅÆËã•ËÄÖ„Åü„Å°„ÅØ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„Éó„ÅÆÊñáÂåñ„ÅØ„Åì„ÅÜ„ÅÑ„ÅÜ„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Å®ÊÄù„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã[131]„ÄÇÊó•Êú¨„Åß„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØË°®Èù¢ÁöÑ„Å™ÊñáÂåñ„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÂèçÈÄÜËÄÖ„Å®„Åó„Ŷ˶ã„Çâ„Çå„ÇãÂêë„Åç„ÇÇ„ÅÇ„Çã[132]„ÄÇ „Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅØ„Éí„ÉÉ„Éó„Éõ„ÉÉ„É󉪕§ñ„Åß„ÇÇÂïèÈ°å„ÅåÊÆã„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[133]„ÄÇÊó•Êú¨„ÅÆ„É™„Ç∫„É݄ɪ„Ç¢„É≥„Éâ„ɪ„Éñ„É´„ɺ„Çπ„ɪ„Ç∞„É´„ɺ„Éó„ÅÆ„É©„ÉÉ„ÉÑ&„Çπ„Çø„ɺ„ÅØ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅßÁü•„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[134]„ÄÇ2015Âπ¥3Êúà„ÄÅ„Éï„Ç∏„É܄ɨ„Éì„Ç∏„Éß„É≥„ÅØÈü≥Ê•ΩÁï™ÁµÑ„Åß„É©„ÉÉ„ÉÑ&„Çπ„Çø„ɺ„Å®„ÇÇ„ÇÇ„ÅÑ„Çç„ÇØ„É≠„ɺ„Éê„ɺZ„Åå„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„ÅßÁôªÂÝ¥„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇíË®àÁÅó„Åü„ÄÇÂèéÈå≤Âæå„ÄÅ„É©„ÉÉ„ÉÑ&„Çπ„Çø„ɺ„ÅÆ„É°„É≥„Éê„ɺ„ÅÆ1‰∫∫„ÅåÁîªÂÉè„Çí„Ç™„É≥„É©„ǧ„É≥„Å´Êé≤˺â„Åó„ÄÅ„Éñ„É©„ÉÉ„ÇØ„Éï„Ç߄ǧ„Çπ„Åß„ÅÆÂá∫ʺîÂÝ¥Èù¢„ÅÆÊîæÈÄÅ„Å´ÂèçÂØæ„Åô„Çã„Ç≠„É£„É≥„Éö„ɺ„É≥„Åå˵∑„Åì„Å£„Åü„ÄÇ3Êúà7Êó•„Å´Áï™ÁµÑ„ÅåÊîæÈÄÅ„Åï„Çå„Åü„Åå„ÄÅ„ÄåÁä∂Ê≥Å„ÇíËÄÉÊÖÆ„Åó„ÅüÁµêÊûú„ÄçÁ∑®ÈõÜ„Åß„Åì„ÅÆ„Ç∑„ɺ„É≥„ÅØ„Ç´„ÉÉ„Éà„Åï„Çå„Åü[135]„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„Åì„ÅÆÊäóË≠∞ÂÜÖÂÆπ„Å´„ÅØË߶„Çå„Çâ„Çå„Å™„Åã„Å£„Åü[136]„ÄÇ„É©„ÉÉ„ÉÑԺ܄Çπ„Çø„ɺ„ÅØËá™ÂàÜ„Åü„Å°„ÅÆȪí°ó„Çä„ÅØȪí‰∫∫„Å∏„ÅÆ„É™„Çπ„Éö„ÇØ„Éà„Åã„ÇâÊù•„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å®„Åó„Åü‰∏ä„Åß„ÄÅÈÅéÂ骄ŴȪí‰∫∫„Éê„É≥„Éâ„ÅÆ„Éï„Ç£„ÉÉ„Ç∑„É•„Éú„ɺ„É≥„Å®Âֱʺî„Åó„ÅüÈöõ„ÄÅÁõ∏Êâã„Åå‰∏çÂø´ÊÑü„ÇíÈú≤„Çè„Å´„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÅÆ„Çí˶ã„Åü„Å®Ëø∞„Åπ„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Å؉∏çÈÅ©Âàá„Åï„ÇíË™çË≠ò„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„ÄÅ„Åù„ÅƉ∏ä„Åß„Åù„ÅÆÂæå„ÇÇȪí°ó„Çä„ÇíÊ≠¢„ÇÅ„Å™„Åã„Å£„Åü„Åì„Å®„ÇíÊÑèÂë≥„Åô„Çã[137]„ÄÇ „Éï„Ç°„ÉÉ„Ç∑„Éß„É≥„ÅÆÈÝòÂüü„Åß„ÅØ„ÄÅ90Â𥉪£‰∏≠Áõ§„Çà„Çä‰∏ª„Å´10‰ª£„Åã„Çâ20‰ª£„ÅÆ•≥ÊÄß„ÅÆÈñì„ÅßʵÅË°å„Åó„Åü„Äå„Ǩ„É≥„Ç∞„É≠„Äç„É°„ǧ„ÇØ„ÅåÂïèÈ°åÊèê˵∑„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ[138]Ȫí°ó„Çä„É°„ǧ„ÇØ„ÅØÊó•Êú¨„Å´„Åä„Åë„ÇãÂ∑ÆÂà•„Å´ÂØæ„Åô„ÇãË™çË≠ò„ÅƉΩé„Åï„Å´„Çà„Å£„ŶÂïèÈ°å„Å´„Å™„Çâ„Åö„Å´Ê∏à„Çì„ÅÝ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„ÅÆÊâπÂৄÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇ[139] 2017Âπ¥12Êúà31Êó•„Åã„ÇâÁøåÂπ¥1Êúà1Êó•„Å´„Åã„Åë„ŶÊó•Êú¨„É܄ɨ„ÉìÁ≥ªÂàó„ÅßÊîæÈÄÅ„Åï„Çå„Åü„Éê„É©„Ç®„ÉÜ„Ç£Áï™ÁµÑ„Äé„ÉĄǶ„É≥„Çø„Ƕ„É≥„ÅƄǨ„Ç≠„ÅƉΩø„ÅÑ„ÇÑ„ÅÇ„Çâ„Å∏„Çì„Åß!„Äè„ÅƉºÅÁÄåÁµ∂ÂØæ„Å´Á¨ë„Å£„Ŷ„ÅØ„ÅÑ„Åë„Å™„ÅÑ„Ç¢„É°„É™„Ç´„É≥„Éù„É™„Çπ24ÊôÇ!„Äç„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅÂá∫ʺîËÄÖ„ÅÆʵúÁî∞ÈõÖÂäü„ÅåȪí‰∫∫‰ø≥ÂÑ™„ÅÆ„Ç®„Éá„Ç£„ɪ„Éû„ɺ„Éï„Ç£„Å´ÊâÆ„Åô„Çã„Åü„ÇÅÈ°î„ŴȪí°ó„Çä„ÇíÊñΩ„Åó„ŶÁôªÂÝ¥„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅÊîæÈÄÅÁõ¥Âæå„Åã„Çâ§ñÂõΩ‰∫∫˶ñËÅ¥ËÄÖ„Çí‰∏≠ÂøÉ„Å´ÊâπÂà§ÊÑè˶ã„ÅåÁõ∏ʨ°„ÅÑ„Å݄Ū„Åã„ÄÅBBC„ÇÑ„Éã„É•„ɺ„É®„ɺ„Ç؄ɪ„Çø„ǧ„ÉÝ„Ç∫„Å™„Å©„ÅÆʵ∑§ñ§ßÊâã„É°„Éá„Ç£„Ç¢„ÇÇ„Åì„ÅÆÂïèÈ°å„ÇíÂèñ„Çä‰∏ä„Åí„Äʼn∫∫Á®ÆÂ∑ÆÂà•ÁöÑ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÅÊñáÂåñÁöÑÈÖçÊÖÆ„ÅåË∂≥„Çä„Å™„ÅÑ„Å®„ÅÆÊÑè˶ã„Å®Áï™ÁµÑÂÜÖÂÆπ„ÇíÊìÅË≠∑„Åô„ÇãÊÑè˶ã„ÅÆÂèåÊñπ„ÇíÁ¥π‰ªã„Åó„Åü[140][141]„ÄÇ„Åì„ÅÆÈ®íÂãï„Å´„ŧ„ÅфŶÂèñÊùê„Åó„ÅüÁï™ÁµÑ„Äé„Åë„ÇÑ„Åç„Éí„É´„Ç∫„Äè„Å´ÂØæ„ÅóÊó•Êú¨„É܄ɨ„Éì„ÅØ„ÄåÂ∑ÆÂà•„Åô„ÇãÊÑèÂõ≥„Å؉∏ÄÂàá„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„Äç„Å®„Åó„ÄÅ„ÄåÊßò„ÄÖ„Å™„ÅîÊÑè˶ã„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅØÊâøÁü•„Åó„Ŷ„Åä„Çä„ÄʼnªäÂæå„ÅÆÁï™ÁµÑ‰Ωú„Çä„ÅÆÂèÇËÄÉ„Å´„Åï„Åõ„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÅÝ„Åç„Åæ„Åô„Äç„Å®ÂõûÁ≠î„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã[142]„ÄÇ„Å™„Åä„ÄÅÂêåÂπ¥1Êúà5Êó•„Å´ÊîæÈÄÅ„Åï„Çå„ÅüÂêåÁï™ÁµÑÂÜÖ„Å´„Åä„ÅфŶ„ÇÇʵúÁî∞„ÅåȪí°ó„Çä„Çí„Åó„Åü„Ç∑„ɺ„É≥„ÅåÂÜç„Å≥ÁÅÑ„Çâ„Çå„Åü[142]„ÄÇ Èñ¢ÈÄ£‰∫ãÈÝÖ
脚注
参考文献
外部リンク
|
Portal di Ensiklopedia Dunia













