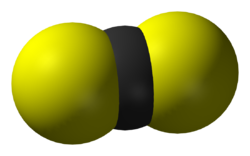| 二硫化炭素
|

|
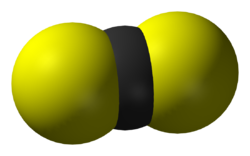
|
|
|
| 識別情報
|
|
|
|
|
|
|
| ECHA InfoCard
|
100.000.767 
|
| EC番号
|
|
| KEGG
|
|
|
|
|
| RTECS number
|
|
| 国連/北米番号
|
1131
|
|
|
|
|
|
| 特性
|
| 化学式
|
CS2
|
| モル質量
|
76.139 g/mol
|
| 外観
|
無色液体(低純度のものは黄色がかっている)
|
| 密度
|
1.261 g/cm3
|
| 融点
|
-110.8 °C, 162 K, -167 °F
|
| 沸点
|
46.3 °C, 319 K, 115 °F
|
| 水への溶解度
|
0.258 g/100 mL (0 °C)
0.239 g/100 mL (10 °C)
0.217 g/100 mL (20 °C)[1]
0.014 g/100 mL (50 °C)
|
| 屈折率 (nD)
|
1.6295
|
| 構造
|
|
|
直線形
|
|
|
0 D
|
| 危険性
|
| GHS表示:
|
|
|
   [2] [2]
|
|
|
Danger
|
|
|
H225, H315, H319, H361, H372[2]
|
|
|
P210, P281, P305+P351+P338, P314[2]
ICSC 0022
|
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド)
|
|
| 引火点
|
-30 ℃
|
| 爆発限界
|
1.3–50 %
|
| 致死量または濃度 (LD, LC)
|
|
|
3188 mg/kg
|
| 関連する物質
|
| 関連物質
|
二酸化炭素
硫化カルボニル
二セレン化炭素
|
| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。
|
二硫化炭素(にりゅうかたんそ、英: carbon disulfide)は代表的な炭素の硫化物で、化学式は CS2。無色で揮発性の液体であり、主にセロハンやレーヨンの製造過程で溶剤として利用されているほか、ゴムの加硫促進剤、有機化学原料や浮遊選鉱剤などに用いられている。二硫炭、硫化炭素、硫炭などと略される。劇物。
化学的性質
純度が高いものはエーテル様の芳香を持つ無色の液体だが、保存中に分解しやすく一般的には硫化カルボニルのような悪臭を持つ夾雑物が含まれ黄色を呈する。
酸素 (O)と硫黄 (S)が同族であることから、二酸化炭素 (CO2)と等電子的な分子であるが、二硫化炭素は非常に燃えやすい。また求核剤と反応しやすく、容易に還元されやすい。この反応性の違いは、硫黄の場合原子核のπ電子供与能が酸素より低く、そのため炭素原子が求電子性を示すためと考えられる。
製造
自然界では火山や沼地から微量に放出されるのみである[3]。
工業的には木炭・コークスなどの固体の炭素源を用いて硫黄蒸気と反応させる固相-気相反応および、天然ガス(メタン)を炭素源として硫黄蒸気と反応させる気相反応の二種類の方法によって製造される。いずれの方法においても硫化水素が副生し、クラウス法で硫黄として再回収される[4]。
固相-気相反応での反応温度は約900°C。この方法は反応装置に鋳鉄で作られたレトルトを持ちいる「レトルト法」と、耐火レンガの炉内で電気加熱を行う「電気炉法」、微粉黒鉛を用いる「流動法」[5]がある[6]。低温で反応させると、一硫化炭素が発生する。

気相反応では二酸化ケイ素や酸化アルミニウムを触媒に用いることで600°Cという低温で製造することができる[4]。このメタンを用いた二硫化炭素の製法はアメリカのFirst Movers Coalition社の技術でありFMC法もしくはメタンガス法と呼ばれる[7]。この製法では石油精製の過程で副生する硫黄とメタンガスを有効利用できるため、石油コンビナートに併設して製造工場が作られるケースもある[3]。このように石油コンビナート内で製造される場合、副生する硫化水素はそのままの形で他の製造工場に移送され別の化合物の合成原料として利用されることもある[3]。

世界の二硫化炭素の生産/消費量は約100万トンで、中国が49%、次いでインドが13%を消費しており、そのほとんどがレーヨン繊維の生産用である[8]。
日本国内での生産量は1967年のピーク時には年間154,000トンであったが[4]、1981年には年間95、000トン[4]、2015年には年間37,000トンとなっている[9]。輸送に困難が伴うことから輸出入はそれほど盛んではない。
反応
燃焼
二硫化炭素は燃焼すると、二酸化硫黄と二酸化炭素が発生する。

塩素化
二硫化炭素の塩素化は四塩化炭素を合成するのに使われる。

この変換は、中間体としてチオホスゲンを経由して進行する。
求核付加
第一級および第二級アミンの付加によりジチオカルバミン酸(英語版)アンモニウムを生じる。

同様にアルコキシドからはキサントゲン酸塩を生じる。この反応はビスコース、レーヨン、セロファンなどの再生セルロース製造の基本となっている。またヨードメタンと反応させてメチルキサンテートとすることでシュガエフ脱離やバートン・マクコンビー脱酸素化(英語版)の基質とすることができる。

硫化ナトリウムの付加によりトリチオ炭酸ナトリウム(英語版)を生じる。

利用
二硫化炭素の主な工業用途は、ビスコース・レーヨンとセロファン・フィルムの製造であり、年間生産量の75%を占めている[10]。
殺虫剤
穀物や果実にたいする殺虫剤として、あるいは土壌の病害性昆虫や線虫の殺滅のために使われる[11][12]。
溶剤
リン、硫黄、セレン、臭素、ヨウ素、脂質、樹脂、ゴムなどの溶剤として用いられる[13]。オクタノール/水分配係数は1.94。
有機化合物を良く溶解してプロトンNMRに検出されないので、重クロロホルムに溶けにくいサンプルの測定を行う際の溶媒に適している。
製造原料
キサントゲン酸塩などの有機硫黄化合物の合成にも広く使用される。医薬品やゴム化学に使用されるジチオカルバメートの前駆体でもある。
毒性
二硫化炭素は、急性中毒と慢性中毒の両方に関連しており、その症状は多岐にわたる[14]。神経系に影響するため、高濃度では致死的である。
二硫化炭素は200 μg/m3以上でも臭いを感じることがあり、WHOは20 μg/m3以下という感覚的指針を推奨している。
環境省によるリスク評価によれば、呼吸による無毒性量は 3.2 mg/m3 、経口摂取による無毒性量は 2.5 mg/kg・day とされている。また、10~15年間暴露した場合、10 mg/m3で健康に害があるという報告もあるが、過去の暴露レベルに関する十分なデータがないため、これらの害と10 mg/m3の濃度との関連は不確かである[15]。
蒸気でなく、皮膚からも吸収されるので取り扱いには注意が必要。誤って皮膚から吸収された場合、急性の二硫化炭素中毒症状は、視覚障害、精神の高揚を伴う興奮発作、次いで意識不明、昏睡、呼吸麻痺として現れる。度々、より長時間の吸引による慢性の中毒症状は、頭痛、不眠、記憶・視覚・聴覚障害、神経炎、血管障害として現れる。変異原性については否定的な報告が多いが肯定的な報告もあって明確に判断できない。発がん性は無いと考えられている。体内で代謝されて主に尿から排泄される。
危険性
揮発性が高く、非常に引火しやすい(引火点-30°C、発火点90°C)。比重が水より大きく水に難溶であることを利用し、二硫化炭素の上に注水し揮発を防ぐ水没貯蔵方法が用いられる。引火した場合は大量の水による消火を行う。燃焼により二酸化硫黄 (SO2)を発生するのでそれに対する注意も必要である。
日本における法規制については下記の通り。
脚注
- ^ Seidell, Atherton; Linke, William F. (1952). Solubilities of Inorganic and Organic Compounds. Van Nostrand
- ^ a b c Sigma-Aldrich Co., Carbon disulfide. Retrieved on 2014-05-27.
- ^ a b c 熊本健志 (2014-05). “二硫化炭素の特殊な貯蔵・取扱い方法について”. Safety & Tomorrow (危険物保安技術協会) 155: 36. https://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/155/contents/155_36.pdf.
- ^ a b c d 岡秀昭「ケミカルス覚書 二硫化炭素」『有機合成化学協会誌』第41巻第5号、有機合成化学協会、1983年、464頁、doi:10.5059/yukigoseikyokaishi.41.464。
- ^ 岸本定吉「木炭の生産と利用の現況と將来」『燃料協会誌』第41巻第9号、日本エネルギー学会、1962年、749頁、doi:10.3775/jie.41.737。
- ^ 芦田一夫「二硫化炭素原料としての木炭-二硫化炭素の性質および用途-」『燃料協会誌』第41巻第9号、日本エネルギー学会、1962年、773頁、doi:10.3775/jie.41.773。
- ^ “Courtaulds to switch CS2 output to F.M.C.methaneroute.”. Chemical Age 88: p.89. (1962).
- ^ “Carbon Disulfide report from IHS Chemical”. 2013年6月15日閲覧。
- ^ 『優先評価化学物質のリスク評価(一次) 人健康影響及び生態影響に係る評価Ⅱ リスク評価書簡易版 二硫化炭素』(レポート)厚生労働省、経済産業省、環境省、2018年9月21日。
- ^ Lay, Manchiu D. S.; Sauerhoff, Mitchell W.; Saunders, Donald R.; "Carbon Disulfide", in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2000 doi: 10.1002/14356007.a05_185
- ^ グリーンウッド, ノーマン; アーンショウ, アラン (1997). Chemistry of the Elements (英語) (2nd ed.). バターワース=ハイネマン(英語版). ISBN 978-0-08-037941-8.
{{cite book2}}: CS1メンテナンス: デフォルトと同じref (カテゴリ)
- ^ British Crop Protection Council (1987). The Pesticide Manual, A World Compendium, 8th Ed.
- ^ http://www.akzonobel.com/sulfurderivatives/products/carbon_disulfide/
- ^ “ATSDR - Public Health Statement: Carbon Disulfide”. www.atsdr.cdc.gov. 2020年1月17日閲覧。
- ^ “Chapter 5.4 : Carbon disulfide”. Air Quality Guidelines (2 ed.). WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark. (2000). オリジナルの18 October 2022時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20221018194943/https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/123058/AQG2ndEd_5_4carbodisulfide.PDF 2021年7月31日閲覧。
関連文献
関連項目
外部リンク