µØÄńź¢ÕĤ
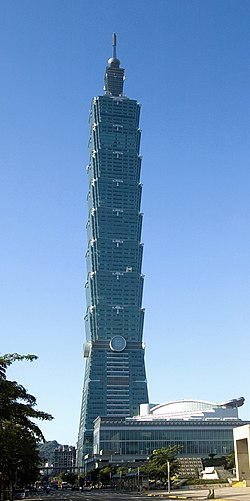 µØÄ ńź¢ÕĤ’╝łŃā¬Ńā╝Ńā╗Ńé║Ńā╝Ńā”Ńé¦Ńā│ŃĆüŃéŖ ŃüØŃüÆŃéōŃĆüĶŗ▒Ķ¬×ÕÉŹ’╝ÜC.Y. Lee / Chu-Yuan Lee / ŃāüŃāźŃā”ŃéĪŃā│Ńā╗Ńā¬Ńā╝ŃĆü1938Õ╣┤12µ£ł30µŚź - ’╝ēŃü»õĖŁĶÅ»µ░æÕøĮÕ║āµØ▒ń£üÕć║Ķ║½Ńü«Õ╗║ń»ēÕ«ČŃĆüńö╗Õ«ČŃĆé õĖŁĶÅ»µ¢ćµśÄõ╝ØńĄ▒Ńü«ńē╣Ķē▓ŃéÆÕÅŚŃüæńČÖŃüäŃüĀńÅŠõ╗ŻÕ╗║ń»ēŃüīńē╣Ķē▓Ńü¦ŃĆüńÅŠõ╗ŻÕ╗║ń»ēŃü¦Ńü»ÕÅ░ÕīŚ101Ńéäķ½śķøä85ŃāōŃā½Ńü¬Ńü®Ńü«ķ½śŃüĢŃü¦ÕÅ░µ╣ŠŃü«õĖŖõĮŹŃéÆÕŹĀŃéüŃéŗĶČģķ½śÕ▒żŃāōŃā½ŃĆüÕ«ŚµĢÖµ¢ĮĶ©ŁŃü¦Ńü»õĖŁÕÅ░ń”ģÕ»║Ńü¬Ńü®Ńü«õ╗ŻĶĪ©õĮ£Ńüīń¤źŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü╗ŃüŗŃĆüńö╗Õ«ČŃü©ŃüŚŃü”µ░┤Õó©ńö╗Ńü«õĮ£ÕōüŃééµēŗŃüīŃüæŃü”ŃüäŃéŗ[1]ŃĆé õ║║ńē® õĖŁĶÅ»µ░æÕøĮµÖéõ╗ŻŃü«õĖŁÕøĮÕ║āµØ▒ń£üµÄ▓ķÖĮń£īŃü¦Õć║ńö¤ŃĆé ÕøĮń½ŗÕÅ░µ╣ŠÕĖ½ń»äÕż¦ÕŁ”ķÖäÕ▒×ķ½śń┤ÜõĖŁÕŁ”ŃéÆńĄīŃü”ŃĆüÕøĮń½ŗµłÉÕŖ¤Õż¦ÕŁ”Õ╗║ń»ēÕŁ”ń│╗’╝łń│╗Ńü»ÕŁ”ķā©Ńü½ńøĖÕĮōŃĆé1961Õ╣┤ÕŹÆµźŁ[2]’╝ēŃĆüń▒│ÕøĮŃāŚŃā¬Ńā│Ńé╣ŃāłŃā│Õż¦ÕŁ”Õ╗║ń»ēÕŁ”ń¦æ’╝łPrinceton University School of Architecture’╝ēŃü½ķĆ▓Ńü┐1966Õ╣┤Master’╝łõ┐«ÕŻ½ÕÅĘ’╝ē[2]ŃĆé 1970Õ╣┤ŃĆüµØ▒µĄĘÕż¦ÕŁ”Õ╗║ń»ēń│╗ÕŖ®ńÉåµĢֵijŃü½Õ░▒õ╗╗ŃüŚÕÉīÕ╣┤Ńü½ŃéżŃé¬Ńā╗Ńā¤Ńā│Ńā╗ŃāÜŃéżŃü«Õ╗║ń»ēõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦µŚźµ£¼õĖćÕøĮÕŹÜĶ”¦õ╝ÜŃĆīõĖŁĶÅ»µ░æÕøĮķż©ŃĆŹŃü«Ķ©ŁĶ©łÕŖ®µēŗ[2]ŃĆé ŃüōŃéīŃüīµØÄŃü«Õ╗║ń»ēÕ«ČŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ«¤ÕŗÖŃāćŃāōŃāźŃā╝Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤[3]ŃĆé 1971Õ╣┤ŃĆüń▒│ÕøĮŃāĢŃéŻŃā®ŃāćŃā½ŃāĢŃéŻŃéóŃü«ŃāÄŃā╝Ńā¼Ńā│Ńā╗Ńé╣Ńé”ŃéŻŃā│ŃāÉŃā╝Ńā│Ńā╗ŃéóŃéĮŃéĘŃé©ŃéżŃāä’╝łNolen-Swinburne & Associates’╝ē[2]ŃĆüŃā£Ńé╣ŃāłŃā│ÕåŹķ¢ŗńÖ║Õģ¼ńżŠ’╝łBoston Planning and Development Agency’╝ēŃüŖŃéłŃü│ŃāŁŃéĄŃā│Ńé╝Ńā½Ńé╣Ńü«Ńé”ŃéŻŃā¬ŃéóŃāĀŃā╗ŃāÜŃā¼ŃéżŃā®’╝łWilliam Pereira’╝ēÕ╗║ń»ēõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¬Ńü®Ńü½µēĆÕ▒×ŃĆéŃāÜŃā¼ŃéżŃā®Ńü«õ║ŗÕŗÖµēĆŃü½Õ£©ń▒ŹŃüŚŃü¤ŃüōŃü©Ńü¦µØÄŃü»ŃāłŃā®Ńā│Ńé╣ŃéóŃāĪŃā¬Ńé½Ńā╗ŃāöŃā®Ńā¤ŃāāŃāē’╝ł1972Õ╣┤Õ«īµłÉ’╝ēŃü«µĪłõ╗ČŃü½ķ¢óŃéÅŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕ╣ĖķüŗŃéÆÕŠŚŃü¤[3]ŃĆéõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ŃāÜŃā¼ŃéżŃā®Ńü½µ¼ĪŃüÉÕ£░õĮŹŃüŠŃü¦õĖŖŃéŖĶ®░ŃéüŃü¤ŃüīŃĆüÕåģÕ┐āŃü¦Ńü»µ£øķāĘŃü«Õ┐ĄŃüīÕ╝ĘŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŻŃü¤[3]ŃĆé 1978Õ╣┤Ńü½ÕÅ░µ╣ŠŃü½µł╗ŃéŗŃü©ŃĆüõ║ŗÕŗÖµēĆŃéÆķ¢ŗĶ©ŁŃĆéĶÅ»õ║║Ńü«Õ«¤µźŁÕ«ČķäŁÕ橵ĢÅŃüīķ¢ŗńÖ║ŃüÖŃéŗńÆ░õ║×õĖ¢ńĢīÕż¦µź╝Ńü«Ķ©ŁĶ©łŃéƵŗģŃüäŃĆüõ╗źÕŠīŃü»ÕÅ░µ╣ŠŃü©õĖŁÕøĮŃü¦ÕżÜŃüÅŃü«õ╗ŻĶĪ©õĮ£ŃéÆõĖ¢Ńü½ķĆüŃéŖÕć║ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆé2003Õ╣┤ŃüŗŃéē2006Õ╣┤ŃüŠŃü¦ÕÅŗõ║║Ńü«ń¤│Õ▒▒õ┐«µŁ”Ńü«Ķ”üĶ½ŗŃü¦µŚ®ń©▓ńö░Õż¦ÕŁ”Õ╗║ń»ēÕŁ”ń¦æµĢֵijŃéÆÕŗÖŃéüŃéŗ[2]ŃĆé2009Õ╣┤ŃĆüµØÄŃü«Õ╗║ń»ēõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»µé▓µāģÕ¤ÄÕĖéŃü¬Ńü®Ńü«Ķł×ÕÅ░Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õ╣Øõ╗ĮĶĆüĶĪŚŃü«µśćÕ╣│µł▓ķÖóŃéƵ¢░ÕīŚÕĖéµö┐Õ║£Ńü½Õ»äĶ┤łŃüŚŃü¤[4][5]ŃĆé ń”ģÕ«ŚŃéÆń»żŃüÅõ┐Īõ╗░ŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü»ŃĆüń”ģõĖā[µ│©ķćł 1]Ńü©Ķ橵ĖłÕ«Śµ│ĢÕĖ½Ńü«ķćłµā¤Ķ”ÜŃü©Ńü«ńĖüŃü½ŃéłŃéŗŃééŃü«[3]ŃĆéµØÄŃüīõĖŁĶÅ»Ńü©Ķź┐µ┤ŗŃü«ÕĘźµ│ĢŃéÆńĄäŃü┐ÕÉłŃéÅŃüøŃü”2001Õ╣┤Ńü½ÕŹŚµŖĢń£īÕ¤öķćīķÄ«Ńü¦Õ«īµłÉŃüĢŃüøŃü¤õĖŁÕÅ░ń”ģÕ»║Ńü»ŃüØŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŚŃüæŃü”ŃüäŃéŗ[3]ŃĆé Ķ©ŁĶ©łµĆصā│Ķ╗Źõ║║Ńü«ÕŁÉŃü©ŃüŚŃü”ńö¤ŃüŠŃéīŃĆüµ▒║ŃüŚŃü”ĶŻĢń”ÅŃü¬Õ«ČÕ║ŁŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃüīŃĆüÕ░ÅÕŁ”5Õ╣┤Ńü¦ńŠÄĶĪōŃü½ńø«Ķ”ÜŃéüŃü¤ŃĆéÕ«Čń│╗Ńü½Ńü»ńŠÄĶĪōŃü«Õż®ÕłåŃüīŃüéŃüŻŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗ[3]ŃĆéÕĖ½ń»äÕż¦õ╗śÕ▒×ķ½śŃü¦ŃééĶć¬Ķ║½Ńü»õ╗¢Ńü«ÕżÜŃüÅŃü«ńö¤ÕŠÆÕÉīµ¦śŃĆüńŠÄĶĪōµĢÖÕĖ½ŃéÆÕ┐ŚŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŃüīŃĆüŃé»Ńā®Ńé╣Ńü¦Õ╗║ń»ēÕ«ČŃéÆńø«µīćŃüŚŃü”ŃüäŃü¤1õ║║Ńü«ÕÉīń┤Üńö¤Ńü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŚŃüæŃü”Ńé»Ńā®Ńé╣Ńü¦Ńü»ńŠÄĶĪōµĢÖÕĖ½Ńü½ŃééÕ╗║ń»ēń│╗Ńü«µīćÕ░ÄŃĆüĶ®”ķ©ōŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤[3]ŃĆé ÕĮōµÖéŃü«ÕÅ░µ╣ŠŃü«Õż¦ÕŁ”Ńü¦Õ╗║ń»ēÕŁ”ķā©ŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü»µłÉÕŖ¤Õż¦ÕŁ”ŃüĀŃüæŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆéķ½śµĀĪŃü¦Ńü«ńŠÄĶĪōµīćÕ░ÄŃüīÕŖ¤ŃéÆÕźÅŃüŚŃü”ŃüŗŃĆüÕÉīÕ╣┤Ńü½µłÉÕŖ¤Õż¦ÕŁ”Õ╗║ń»ēÕŁ”ķā©Ńü½ÕÉłµĀ╝ŃüŚŃü¤50ÕÉŹŃü«ŃüåŃüĪŃĆüÕĖ½Õż¦ķÖäÕ▒×Õć║Ķ║½ĶĆģŃü»µØÄŃéÆÕɽŃéüŃü”5õ║║ŃéÆÕŹĀŃéüŃü¤[3]ŃĆé Õż¦ÕŁ”Ńü¦Ńü»1Õ╣┤ńö¤ŃüŗŃéē4Õ╣┤ńö¤ŃüŠŃü¦õĖĆŃüżŃü«Õż¦Õ«ČÕ║ŁŃü«ŃéłŃüåŃü¬µĀĪķó©Ńü¦µś╝Õż£ŃéÆÕĢÅŃéÅŃüÜÕŁ”ÕåģŃü«ŃéóŃāłŃā¬Ńé©Ńü¦ŃāćŃāāŃéĄŃā│Ńü½µśÄŃüæµÜ«ŃéīŃü”ŃĆüÕÅÄń®½ŃüīÕżÜŃüŗŃüŻŃü¤Ńü©ŃüäŃüå[3]ŃĆé ķØÆÕ╣┤µÖéŃü«µØÄŃü»Ńé╣ŃéżŃé╣Ńü«Õ╗║ń»ēÕ«ČŃā½Ńā╗Ńé│Ńā½ŃāōŃāźŃéĖŃé©’╝ł1887-1965’╝ēŃéÆŃĆīÕ╗║ń»ēõĮ£ÕōüŃü»ĶŖĖĶĪōÕ«ČŃü©ŃüŚŃü”Ńü«µēŹµ░ŚŃü½µ║óŃéīŃĆüµŁ┤ÕÅ▓ŃéÆÕżēŃüłŃü¤õĖĆõ║║Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüńÅŠõ╗ŻÕ╗║ń»ēÕÅ▓Ńü«ÕüēÕż¦Ńü¬õ║║ńē®ŃĆŹŃü©Ķ®ĢŃüŚŃĆüĶć¬Ķ║½Ńü«µēŗµ£¼Ńü½ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤[3]ŃĆé ÕÅ░µ╣ŠŃü½ÕĖ░ÕøĮÕŠīŃééŃĆīõĖŁÕøĮµ¢ćÕī¢ŃéÆń¤źŃéēŃüÜŃüŚŃü”ŃĆüõĖŁÕøĮõ║║Ńü«Õ╗║ń»ēŃéÆĶ©ŁĶ©łŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃĆÄõĖŁĶÅ»Õ╗║ń»ēŃĆÅŃü«µĆØĶĆāŃéƵĘ▒ŃéüŃü”ŃüäŃüÅ[3]ŃĆéõĖŁÕøĮŃü«õ╗ŻĶĪ©ńÜäµĆصā│Õ«ČŃü«ńē¤Õ«ŚõĖēŃü½Õģźķ¢ĆŃüŚŃĆüÕäÆÕŁ”ŃĆüõ╗ÅÕŁ”ŃĆüĶĆüĶŹśµĆصā│ŃéÆÕŁ”ŃéōŃü¦ŃĆīµ£Ćķ½śŃü«µ¢ćÕī¢Ńü»Õ«ŚµĢÖŃü½Ńü╗ŃüŗŃü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕóāÕ£░Ńü½ĶŠ┐ŃéŖńØĆŃüÅ[3]ŃĆé õĖŁĶÅ»Ńü©Ķź┐µ┤ŗŃü«µ¢ćÕī¢ŃéÆŃüČŃüżŃüæŃüéŃüŻŃü¤µłÉµ×£ńē®Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆīµØ▒ńÄŗµ╝óÕ««ŃĆŹŃéäŃĆīÕż¦Õ«ēÕøĮÕ«ģŃĆŹŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüŚŃü¤[3]ŃĆéµØÄŃü»ŃĆīÕ▒ŗõĖŖķā©Ńü½õĖŁÕøĮÕÅżõ╗ŻÕ╗║ń»ēŃü«Õ▒ŗµĀ╣ŃéÆńĮ«ŃüäŃü”Ńü┐Ńü¤ŃĆŹŃü©Ķ¬×ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗ[3]ŃĆé Õ«ÅÕøĮÕż¦µź╝’╝ł1989Õ╣┤’╝ēŃü»µØÄŃüīŃĆīĶć¬ÕĘ▒Ńü«õĖŁÕøĮÕ╗║ń»ēµäÅĶŁśŃéÆõĮ£ÕōüŃü½ÕÅŹµśĀŃü¦ŃüŹŃü¤ŃĆŹŃü©ÕłØŃéüŃü”Ķć¬Ķ¬ŹŃü¦ŃüŹŃéŗŃééŃü«Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õĮ£ÕōüŃü¦ŃĆüÕäÆÕŁ”Ńü½ÕēćŃüŻŃü¤ÕĘ”ÕÅ│Õ»Šń¦░Ńü«Õż¢Ķ”│Ńü©ŃĆüÕż®Ńā╗Õ£░Ńā╗õ║║Ńü«õĖēĶĆģŃü«ķ¢óõ┐éŃéÆńē®Ķ¬×ŃéŗÕĮóńŖČŃü¦ŃĆüõĖŁÕøĮÕ╗║ń»ēŃüīŃééŃüżńē╣Ķē▓ŃéÆŃĆīÕĮóÕ╝ÅÕī¢ŃĆŹŃüŗŃéēŃĆīµ”éÕ┐ĄÕī¢ŃĆŹŃüĖÕżēŃüłŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ®”Ńü┐Ńü¤Ńü©ŃüäŃüå[3]ŃĆé õĖƵ¢╣Ńü¦21õĖ¢ń┤ĆŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŗŃéēŃü»ķøæĶ¬īŃĆÄEGG[µ│©ķćł 2]ŃĆÅŃü©ÕøĮÕåģŃü«ĶŗźµēŗÕ╗║ń»ēÕ«ČŃüīķüĖÕ«ÜŃüÖŃéŗŃĆÄÕÅ░µ╣ŠŃü¦µ£ĆŃééķå£ŃüäÕ╗║ń»ēńē®ŃĆÅŃü½µØÄŃü«õĮ£ÕōüŃüīµĢ░õ╗ČŃā®Ńā│Ńé»ŃéżŃā│ŃüÖŃéŗŃü¬Ńü®ŃĆüõĖ¢õ╗ŻŃü«ķüĢŃüäŃü©Ńü»ŃüäŃüłõĖŹÕÉŹĶ¬ēŃü¬Ķ®ĢõŠĪŃééŃüéŃéŗ[7][8]ŃĆé µĀäÕģĖ
õĖ╗Ńü¬ÕÅŚń½Āńē®õ╗Č
õĖ╗Ńü¬õĮ£ÕōüÕÅ░µ╣Š
ÕÅ░µ╣ŠÕøĮÕż¢
Ķäܵ│©Ķ©╗ķćłÕć║ÕģĖ
ķ¢óķĆŻķĀģńø«
Õż¢ķā©Ńā¬Ńā│Ńé»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia









































