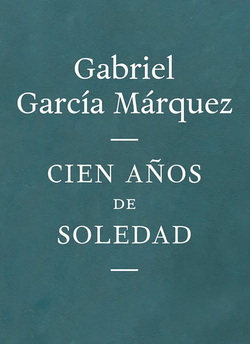百年の孤独
『百年の孤独』(ひゃくねんのこどく、西: Cien Años de Soledad、シエン アニョス デ ソレダッド、英: One Hundred Years of Solitude)は、ガブリエル・ガルシア=マルケスの長編小説。初刊はスペイン語で、1967年に出版された。ガルシア=マルケスは主に本作により1982年秋にノーベル文学賞を受賞した。 紹介世界各国でベストセラーになり、ラテンアメリカ文学ブームを巻き起こした。2002年のノルウェイ:ブッククラブ「世界傑作文学100」や、1999年のフランス:ル・モンド「ル・モンド20世紀の100冊」[1]に選ばれた。『考える人 特集 海外の長編小説ベスト100』(2008年5月号、新潮社)ではベスト1に選ばれている。 邦訳は1972年に刊行された(99年に改訳版刊行)。スペイン語圏では刊行当初から「ソーセージのように売れた」が、日本語版は初版4000部で、重版がかかるまでに5年かかり、その2刷もわずか1000部(アルゼンチンでは初版8000部が2週間で売り切れた)。また、46言語に翻訳され、世界累計5000万部の発行部数があるとされている。[2] 初刊訳から半世紀以上、作家没後10年を経て、2024年に新潮文庫で再刊された。これに合わせ月刊『新潮』2024年8月号では特集「『百年の孤独』と出会い直す」が組まれ、新潮社から池澤夏樹監修による「『百年の孤独』読み解き支援キット」(HTML版とPDF版)が無償配布された[3][4]。 池澤夏樹の著書『ブッキッシュな世界像』(白水社)や『世界文学を読みほどく―スタンダールからピンチョンまで【増補新版】―』(新潮選書)は本書を丁寧に読み解いている。[誰によって?] 日本では1981年に寺山修司により上演[5][6]、1982年、同じ寺山が映画化を進めたが、原作者側と係争となって公開できず、改題(『さらば箱舟』)および原作クレジットの削除などの条件を受諾して、寺山の死(1983年5月)の後、1984年になり公開された[7][8][9]。したがって現在は無関係な作品として扱われるが、ストーリーは共通している[要出典]。 あらすじホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアランを始祖とするブエンディア一族が蜃気楼の村マコンドを創設し、隆盛を迎えながらも、やがて滅亡するまでの100年間を舞台としている。 コロンビアのリオアチャにあるコミュニティでは、近い血縁での婚姻が続いたせいで豚の尻尾が生えた奇形児が生まれてしまった。それを見たウルスラは性行為を拒否するが、そのことを馬鹿にされたため、ウルスラの従兄弟で夫のホセ・アルカディオは彼女を馬鹿にした男を殺してしまう。しかし殺された男がホセとウルスラの前に現れ続けたために、夫妻は故郷を離れてジャングルを放浪した末に、新しい住処「マコンド」を開拓する。そしてウルスラは「豚のしっぽ」が生まれないように、婚姻の相手は血のつながりのない相手に限定するという家訓を残した。さまざまな人間模様や紆余曲折がありながら「マコンド」は繁栄していったが、ウルスラが残した家訓は玄孫の代に叔母と甥の恋愛結婚という形で破られ、「マコンド」は衰退と滅亡へと向かっていく。 登場人物 第1世代
第2世代
第3世代
第4世代
第5世代
第6世代
第7世代
その他の人物
日本語訳
作品論
文庫化いつからか「文庫化されたら、世界が滅びる」と皮肉を込めて日本では言われていたが、『おすすめ文庫王国2024』(本の雑誌編集部)により、2024年の新潮文庫からの文庫化の予定が明かされ、SNSはトレンドにもなるなど騒然とした。 予告通り2024年6月26日に新潮文庫より刊行。品薄状態が長く続くなど約4ヵ月で36万部という大ベストセラーとなり社会現象ともなった。同年、第6回野間出版文化賞を受賞。世界的名作の風化を防ぐのみならず、若い世代の読者獲得にもつながり、多くの人々が海外文学に触れる機会を作った点が特に評価されての受賞。 Netflixによる映像化Netflixでテレビドラマシリーズ『百年の孤独 (2024年12月11日配信)』のシーズン1が(8話)が公開、シーズン2の公開時期は未定[10]。現在の映像化はガルシア=マルケスの息子ロドリゴ・ガルシアとゴンサロ・ガルシア・バルチャが製作総指揮を務めており、撮影主にコロンビアで行われていおり、重要な舞台であるマコンドは54.39平方キロメートルに及ぶ巨大なセット、300トンの鉄製彫刻、1万6000本の植物など、前代未聞の規模で再現された。本作はコロンビア文化省も参加したNetflixがラテンアメリカで展開する最大規模のプロジェクトである。 Netflixの公式アカウントからは世界各国からいくつか公式のアートワークが選ばれ、日本からは新潮文庫版の『百年の孤独』の三宅瑠人の装画を用いて、デザインされたアートワークが公開されている。 原書のデザイン1967年に、アルゼンチンのスダメリカナ社から刊行された『CIEN AÑOS DE SOLEDAD』の初版のデザインは、スペイン出身でメキシコで活動したアーティスト、ビセンテ・ロホ(Vicente Rojo, 1932-2021)担当する予定であったが、期限を守れず、初版のデザインは出版社のスタッフが間に合わせで作ったという逸話が残っている。そのため、よく初版と勘違いされるビセンテ・ロホのデザインは第2版以降のものであり、船をモチーフとした初版のデザインが存在している。 ビセンテ・ロホが担当したこの表紙のタイトル文字では、"SOLEDAD" の "E" が鏡文字になっており、デザインとして施されたものであるが、エクアドルの書店員が誤植だと勘違いし、届いた本をぜんぶ手書きで修正したというエピソードが残っている。 20周年・50年周年デザイン『CIEN AÑOS DE SOLEDAD』の初版のデザインをもとにしたブックカバーバージョンに、アレンジを加えたかたちで、出版社はそれぞれ違うが、20周年バージョン(ハードカバー)、50年周年バージョン(ソフトカバー)が発売されている。20周年バージョンにはガルシア=マルケスが編集者に当てた手紙がタイプライターでうたれた原稿状態のまま収録されている。 また、体裁は各社によるが、各国、節目毎に豪華版や限定版が発売されている。 日本語版のデザイン日本語訳は鼓直、担当編集者である新潮社の塙陽子により、1972年に新潮社より刊行されてから、これまで1回の全面改訳、3回の装幀の変更が行われている。初版は岸健喜による装幀、その後、組版は流用しながら叢書「新潮 現代世界の文学」の1作目として刊行されている。(こちらはシリーズフォーマットをデザイナーの早川良雄が手がけている)。1999年に訳者による全面改訳が行われ、レメディオス・バロの絵画作品を用いた、新潮社装幀室の装幀に変更されている。2006年には、全集のかたちをとった「ガルシア=マルケス全小説」の刊行がスタートし、現在も刊行が続いている。全集のフォーマット、各作品の装幀は新潮社装幀室が手がけている。(装画はシリーズを通して、アーティストのシルヴィア・ベッヒュリの作品より選ばれている)。
2024年に刊行された、文庫版『百年の孤独』の装幀では、特別に黄金色のスピン(栞)が使用されている。通常、天アンカットを採用している、新潮文庫ではこげ茶色のスピンが使用されるが、作中のモチーフで度々登場する黄金色から小説内容に合わせて使用され、装画及び背色にも、黄金色のインキが用いられており、文庫としては珍しく作品世界に合わせた統一感が装幀により実現されている。 また、カバーデザインでは、ビセンテ・ロホのデザインへのオマージュとして、タイトルに"E" の鏡文字を取り入れている。装幀は新潮社装幀室、カバー装画はブエンディア家の年代記にモチーフに三宅瑠人が手がけている。 関連項脚注出典
参考文献
外部リンク |
||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia