йіҙжҲёеҸІйғҺ
йіҙжҲё еҸІйғҺпјҲгҒӘгӮӢгҒЁ гҒ—гӮҚгҒҶгҖҒ1908е№ҙ10жңҲ19ж—Ҙ - жІЎе№ҙдёҚи©іпјүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дҝіе„ӘгҒ§гҒӮгӮӢ[1][2][3][4]гҖӮжң¬еҗҚеҚ—жўқ ж…¶еӨ«пјҲгҒӘгӮ“гҒҳгӮҮгҒҶ гӮҲгҒ—гҒҠпјү[1]гҖӮйіҙжҲё еӣӣйғҺгҖҒйіҙй–Җ еҸІйғҺгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЎЁиЁҳгҒ«жҸәгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҖҢжҶҺгҖ…гҒ—гҒ’гҒӘйқўиІҢгҖҚгӮ’гӮӮгҒЎгҖҒгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»жҷӮд»ЈжңҖжң«жңҹгҒ®еүЈжҲҹжҳ з”»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҒиӢҘжүӢгҒ®жӮӘеҪ№дҝіе„ӘгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢ[1][2]гҖӮ дәәзү©гғ»жқҘжӯҙ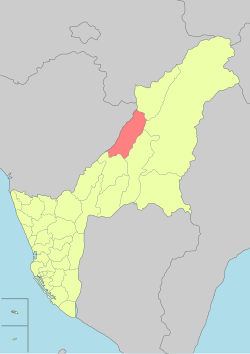 1908е№ҙпјҲжҳҺжІ»41е№ҙпјү10жңҲ19ж—ҘгҖҒж—Ҙжң¬зөұжІ»жҷӮд»ЈгҒ®еҸ°ж№ҫгғ»й«ҳйӣ„е·һеӮҖе„Ўи•ғзӨҫпјҲзҸҫеңЁгҒ®дёӯиҸҜж°‘еӣҪй«ҳйӣ„еёӮз”Ід»ҷеҢәпјүгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгӮӢ[1][2]гҖӮ й•·гҒҳгҒҰдә¬йғҪгҒ«з§»гӮҠгҖҒжәҖ19жӯігӮ’иҝҺгҒҲгӮӢ1927е№ҙпјҲжҳӯе’Ң2е№ҙпјүгҖҒжқұдәңгӮӯгғҚгғһгҒ«е…ҘзӨҫгҖҒеҗҢзӨҫгҒ®иЈҪдҪңгғ»й…ҚзөҰгҒҷгӮӢжҷӮд»ЈеҠҮгҒ«еҮәжј”гҒ—гҒҰжҳ з”»з•ҢгҒ«гғҮгғ“гғҘгғјгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҪ№еҗҚгҒ®гҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒ®з«ҜеҪ№гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[1]гҖӮеӨ§йғЁеұӢгҒ®з«ҜеҪ№дҝіе„ӘгҒӢгӮүиә«гӮ’иө·гҒ“гҒ—гҖҒ1929е№ҙпјҲжҳӯе’Ң4е№ҙпјүгҒ«гҒҜгҖҒеҫҢи—ӨеІұеұұзӣЈзқЈгҒ®гҖҺе№ЎйҡҸйҷўй•·е…өиЎӣ жҷәгҒ®е·»гҖҸгҖҺе№ЎйҡҸйҷўй•·е…өиЎӣ еӢҮгҒ®е·»гҖҸгҒ®йҮ‘жҷӮйҮ‘е…өиЎӣгҖҒеҗҢгҒҳгҒҸгҖҺгҒӢгӮүгҒҸгӮҠиқ¶ еүҚзҜҮгҖҸгҖҺгҒӢгӮүгҒҸгӮҠиқ¶ еҫҢзҜҮгҖҸгҒ®еӨ©е Ӯи§’д№ӢйҖІзӯүгӮ’жј”гҒҳгҒҰгҖҒжӮӘеҪ№гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҹ[1][3]гҖӮеҪ“жҷӮгҒ®еҗҢзӨҫгҒ«гҒҜгҖҒ黒幕зҡ„еӨ§зү©еҪ№гҒЁгҒ—гҒҰзүҮеІЎе·ҰиЎӣй–ҖгӮ„зҖ¬е·қи·Ҝд№Ӣд»ӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӮӘеҪ№гҒ®йҮҚйҺ®гҒҢгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®й…ҚдёӢгҒ§е®ҹйҡӣгҒ«жҶҺгҒҫгӮҢеҪ№гҒ®иЎҢеӢ•гӮ’иө·гҒ“гҒҷеҪ№гӮ’жј”гҒҳгӮӢиӢҘжүӢдҝіе„ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[2]гҖӮжқұдәңгӮӯгғҚгғһгҒҜзөҢе–¶жӮӘеҢ–гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ1931е№ҙпјҲжҳӯе’Ң6е№ҙпјү9жңҲгҖҒжқұдәңгӮӯгғҚгғһгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’д»ЈиЎҢгҒҷгӮӢжқұжҙ»жҳ з”»зӨҫпјҲжқұжҙ»пјүгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒйіҙжҲёгҒҜеҗҢзӨҫгҒ«з¶ҷз¶ҡе…ҘзӨҫгҒҷгӮӢ[1][3]гҖӮ1932е№ҙпјҲжҳӯе’Ң7е№ҙпјү10жңҲгҖҒжқұжҙ»гҒҢи§Јж•ЈгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҗҢе№ҙ11жңҲгҒ«еүҚгғ»жқұдәңгӮӯгғҚгғһдә¬йғҪж’®еҪұжүҖй•·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹй«ҳжқ‘жӯЈж¬ЎгҒҢжқұдәңгӮӯгғҚгғһгӮ’иІ·еҸҺгҒ—гҖҒе®қеЎҡгӮӯгғҚгғһиҲҲиЎҢгӮ’иЁӯз«ӢгҖҒйіҙжҲёгҒҜеҗҢзӨҫгҒ«з§»зұҚгҒҷгӮӢ[1][3]гҖӮ 1934е№ҙпјҲжҳӯе’Ң9е№ҙпјү2жңҲгҖҒе®қеЎҡгӮӯгғҚгғһгҒҢи§Јж•ЈгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйіҙжҲёгҒҜгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰжқұдәңгӮӯгғҚгғһгҒҢдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖҒе…өеә«зңҢиҘҝе®®еёӮз”ІйҷҪең’гҒ®з”ІйҷҪж’®еҪұжүҖгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰеүЈжҲҹжҳ з”»гҒ®иЈҪдҪңгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹжҘөжқұжҳ з”»гҒ«з§»зұҚгҒ—гҒҹ[1][3]гҖӮжҘөжқұжҳ з”»гҒҜгҖҒзҝҢ1936е№ҙпјҲжҳӯе’Ң11е№ҙпјүгҖҒж’®еҪұжүҖгӮ’з”ІйҷҪең’гҒӢгӮүгҖҒеӨ§йҳӘеәңеҚ—жІіеҶ…йғЎеҸӨеёӮз”әзҷҪйіҘең’пјҲзҸҫеңЁгҒ®зҫҪжӣійҮҺеёӮзҝ йіҘең’пјүгҒёгҒЁз§»и»ўгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒзҫ…й–Җе…үдёүйғҺгҖҒеёӮе·қеҜҝдёүйғҺгҖҒз¶ҫе°Ҹи·ҜзөғдёүйғҺгӮүгҒ®дҝіе„ӘйҷЈгҖҒдёӢжқ‘еҒҘдәҢгҖҒең’жұ жҲҗз”·пјҲеҸӨжө·еҚ“дәҢпјүгҖҒе…җдә•з§Җз”·пјҲгҒ®гҒЎгҒ®е…җдә•иӢұз”ҹпјүгӮүзӣЈзқЈйҷЈгҒҢз”ІйҷҪең’гҒ«ж®Ӣз•ҷгҒ—гҖҒз”ІйҷҪжҳ з”»гӮ’иЁӯз«ӢгҖҒйіҙжҲёгҒҜгҒ“гӮҢгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢ[1][3]гҖӮз”ІйҷҪжҳ з”»гҒ®иЈҪдҪңзү©гҒҜгҖҒеҪ“еҲқгҖҒеҚғйіҘиҲҲжҘӯгҒҢй…ҚзөҰгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒйҖ”дёӯгҒӢгӮүгғһгӮӯгғҺгғҲгғјгӮӯгғјиЈҪдҪңжүҖгҒҢиҮӘзӨҫгҒ®иЈҪдҪңзү©гҒЁдәҢжң¬з«ӢгҒҰзӯүгҒ§гҖҒй…ҚзөҰгӮ’и«ӢгҒ‘иІ гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгғһгӮӯгғҺгғҲгғјгӮӯгғјгҒҢ1937е№ҙпјҲжҳӯе’Ң12е№ҙпјү4жңҲгҒ«и§Јж•ЈгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒз”ІйҷҪжҳ з”»гӮӮзҝҢжңҲгҒ«и§Јж•ЈгҒ—гҒҹ[3]гҖӮйіҙжҲёгҒҜгҖҒеӨ§еЎҡз”°й¶ҙеӯҗгӮүгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҘҲиүҜгҒ®гҒӮгӮ„гӮҒжұ гҒ§еёӮе·қеҸіеӨӘиЎӣй–ҖгҒ®е®ҹе…„еұұеҸЈеӨ©йҫҚгҒҢзөҢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹе…ЁеӢқгӮӯгғҚгғһгҒ«з§»зұҚгҒ—гҒҹ[1][3]гҖӮ1940е№ҙпјҲжҳӯе’Ң15е№ҙпјүгҖҒе…ЁеӢқгҒҜжқҫз«№гӮӯгғҚгғһгҒ®еӮҳдёӢгҒ«е…ҘгӮӢгҒҢгҖҒжәҖ32жӯігҒ«гҒӘгӮӢеҗҢе№ҙд»ҘйҷҚгҒ®йіҙжҲёгҒ®еҮәжј”иЁҳйҢІгҒҢиҰӢеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„[3][4]гҖӮеҮәжј”дҪңе“ҒгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҖҒгӮөгӮҰгғігғүзүҲгҖҒи§ЈиӘ¬зүҲгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғҲгғјгӮӯгғјгҒёгҒ®еҮәжј”гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[3]гҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҒҫгӮӮгҒӘгҒҸжҷӮд»ЈгҒҜ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ«зӘҒе…ҘгҒ—гҖҒж¶ҲжҒҜгҒҜдёҚжҳҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжІЎе№ҙдёҚи©ігҖӮ гғ•гӮЈгғ«гғўгӮ°гғ©гғ•гӮЈгҒҷгҒ№гҒҰгӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгҒҜгҖҢеҮәжј”гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮе…¬й–Ӣж—ҘгҒ®еҸіеҒҙгҒ«гҒҜеҪ№еҗҚ[3][4]гҖҒгҒҠгӮҲгҒіжқұдә¬еӣҪз«Ӣиҝ‘д»ЈзҫҺиЎ“йӨЁгғ•гӮЈгғ«гғ гӮ»гғігӮҝгғјпјҲNFCпјүжүҖи”өзӯүгҒ®дёҠжҳ з”Ёгғ—гғӘгғігғҲгҒ®зҸҫеӯҳзҠ¶жіҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮиЁҳгҒҷ[5][6][7]гҖӮеҗҢгӮ»гғігӮҝгғјзӯүгҒ«жүҖи”өгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҒЁгҒҸгҒ«1940е№ҙд»Јд»ҘеүҚгҒ®дҪңе“ҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҒ»гҒјзҸҫеӯҳгҒ—гҒӘгҒ„гғ•гӮЈгғ«гғ гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ жқұдәңгӮӯгғҚгғһдә¬йғҪж’®еҪұжүҖгҒҷгҒ№гҒҰиЈҪдҪңгҒҜгҖҢжқұдәңгӮӯгғҚгғһдә¬йғҪж’®еҪұжүҖгҖҚгҖҒй…ҚзөҰгҒҜгҖҢжқұдәңгӮӯгғҚгғһгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮ
жқұжҙ»жҳ з”»зӨҫзү№зӯҶд»ҘеӨ–гҒҷгҒ№гҒҰиЈҪдҪңгҒҜгҖҢжқұжҙ»жҳ з”»зӨҫгҖҚгҖҒй…ҚзөҰгҒҜгҖҢжқұдәңгӮӯгғҚгғһгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮ
е®қеЎҡгӮӯгғҚгғһиҲҲиЎҢгҒҷгҒ№гҒҰиЈҪдҪңгғ»й…ҚзөҰгҒҜгҖҢе®қеЎҡгӮӯгғҚгғһиҲҲиЎҢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮ
жҘөжқұжҳ з”»гҒҷгҒ№гҒҰиЈҪдҪңгғ»й…ҚзөҰгҒҜгҖҢжҘөжқұжҳ з”»гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮ
з”ІйҷҪжҳ з”»гҒҷгҒ№гҒҰиЈҪдҪңгҒҜгҖҢз”ІйҷҪжҳ з”»гҖҚгҖҒй…ҚзөҰгҒҜгҖҢеҚғйіҘиҲҲжҘӯгҖҚгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҢгғһгӮӯгғҺгғҲгғјгӮӯгғјиЈҪдҪңжүҖгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ«еҠҮдјҙзӯүгҒҢйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгӮөгӮҰгғігғүзүҲгҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮ
е…ЁеӢқгӮӯгғҚгғһгҒҷгҒ№гҒҰиЈҪдҪңгғ»й…ҚзөҰгҒҜгҖҢе…ЁеӢқгӮӯгғҚгғһгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢ[3][4]гҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгӮөгӮӨгғ¬гғігғҲжҳ з”»гҒ«жҙ»еӢ•ејҒеЈ«гҒ®и§ЈиӘ¬гҒҢйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹи§ЈиӘ¬зүҲгҒ§гҒӮгӮӢ[3]гҖӮ
и„ҡжіЁ
еҸӮиҖғж–ҮзҢ®
й–ўйҖЈй …зӣ®
еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ
|
||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia













