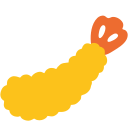Òé½Òé¡ÒâòÒâ®Òéñ
Òé½Òé¡ÒâòÒâ®Òéñ ÞîÂÞë▓ÒüäÒü«ÒüîÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒÇéÒâ¼ÒâóÒâ│´╝ê Òé½Òé¡ÒâòÒâ®Òéñ´╝êÞí¿Þ¿ÿµÅ║Òéî: þëíÞáúÒâòÒâ®ÒéñÒÇüÒüïÒüìÒâòÒâ®Òéñ´╝ëÒü¿Òü»ÒÇüþëíÞáú´╝êÒé½Òé¡´╝ëÒéÆõ©╗ÒüƒÒéïÚúƒµØÉÒü¿ÒüùÒüƒÒâòÒâ®ÒéñÒÇéµ┤ïÚúƒ´╝êµùѵ£¼þöƒÒü¥ÒéîÒü«ÞÑ┐µ┤ïÚó¿µûÖþÉå[µ│¿ 1]´╝ëÒü«õ©Çþ¿«ÒüºÒüéÒéèÒÇüµùѵ£¼Òü«µÅÜÒüÆþ뮵ûÖþÉåÒü«õ©Çþ¿«ÒÇüÞ▓صûÖþÉåÒü«õ©Çþ¿«ÒüºÒüéÒéïÒÇé õ©╗Òü½Òâ×Òé¼Òé¡´╝êþ£ƒþëíÞáúÒÇüÕ¡ªÕÉì: Crassostrea gigas´╝ëÒüîþö¿ÒüäÒéëÒéîÒÇüÕêØþºïÒüïÒéëÕêصÿÑÒü½ÒüïÒüæÒüª[2]´╝êÕêÑÞ│çµûÖÒüºÒü»ÒÇüµÖ®þºïÒüïÒéëÕñÅÒü½ÒüïÒüæÒüª[3]´╝ëÒüîµù¼ÒüºÒüéÒéïÒÇéõ©Çµû╣ÒüºÒÇüÒéñÒâ»Òé¼Òé¡´╝êÕ▓®þëíÞáúÒÇüÒéñÒâ»Òé¼Òé¡Õ▒×ÒÇêÕ¡ªÕÉì: genus SaccostreaÒÇëÒÇüÞï▒ÕÉì: rock oyster´╝ëÒü»ÒÇü5µ£êÒüïÒéë8µ£êÒü½ÒüïÒüæÒüª[2]´╝êµÿÑÒüïÒéëÕñÅÒü½ÒüïÒüæÒüª[4]´╝ëµù¼ÒéÆÞ┐ÄÒüêÒéïÒÇéÒüØÒü«ÒüƒÒéüÒÇüµùѵ£¼ÒüºÒü»Õ╣┤ÚûôÒéÆÚÇÜÒüùÒüªÚúƒÒü╣ÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒüºÒüìÒéïÒÇé µ¡┤ÕÅ▓Òé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒüîÕêØÒéüÒüªõ¢£ÒéëÒéîÒüƒµÖéµ£ƒÒü½ÒüñÒüäÒüªÒü»Þ½©Þ¬¼ÒüéÒüúÒüªÒü»ÒüúÒüìÒéèÒüùÒü¬ÒüäÒüîÒÇüµ»öÞ╝âþÜäµ£ëÕèøÒü¬µâàÕá▒Òü¿ÒüùÒüªõ╗Ñõ©ïÒü«2ÒüñÒüîÒüéÒéïÒÇé õ©ÇÒüñÒü½Òü»ÒÇüµùÑÕêèµû░Þü×ÒÇĵÖéõ║ïµû░Õá▒ÒÇÅÒü«Õ«ÂÕ║¡ÕÉæÒüæÒâ¼ÒéÀÒâöµ¼äÒüºÒüéÒéïÒÇÄõ¢òÒü½ÒüùÒéêÒüåÕ¡É´╝êÒü¡´╝ëÒÇÅÒü«1893Õ╣┤´╝êµÿĵ▓╗26Õ╣┤´╝ë10µ£ê6µùÑõ╗ÿÒüæÞ¿ÿõ║ïÒüºÒüéÒéèÒÇüÒüôÒüôÒü½Òü»ÒÇüÒâíÒâ¬Òé▒Òâ│þ▓ëÒÇüþÄëÕ¡ÉÒÇüÒâæÒâ│þ▓ëÒéÆõ¢┐ÒüúÒüƒÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒü«õ¢£Òéèµû╣ÒüîÒüÖÒüºÒü½µÄ▓Þ╝ëÒüòÒéîÒüªÒüäÒéï[5]ÒÇéõ╗èõ©ÇÒüñÒü½Òü»ÒÇü1895Õ╣┤´╝êµÿĵ▓╗28Õ╣┤´╝ëÒü½ÕëÁµÑ¡ÒüùÒüƒµØ▒õ║¼Òâ╗ÚèÇÕ║ºÒü«µ┤ïÚúƒÕ║ùÒÇîþàëþôªõ║¡ÒÇìÒüºÒüéÒüúÒüªÒÇüÞ▒ÜÒé½ÒâäÒéÆÕºïÒéüÒü¿ÒüÖÒéïµò░ÕñÜÒüÅÒü«µÅÜÒüÆþ뮵ûÖþÉåÒéÆÞÇâµíêÒüùÒüªµÖ«ÕÅèÒüòÒüøÒüªÒüäÒéïÒüôÒü«Õ║ùÒüºÒÇü1901Õ╣┤´╝êµÿĵ▓╗34Õ╣┤´╝ëÒüöÒéìÒü½Òé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒééÒâíÒâïÒâÑÒâ╝Òü½ÕàÑÒüúÒüªÒüäÒéï[6]ÒÇé Òé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒü»þÖ╗Õá┤õ╗ѵØÑÚòÀÒéëÒüŵ┤ïÚúƒÕ║ùÒüáÒüæÒü«ÒâíÒâïÒâÑÒâ╝ÒüºÒüéÒüúÒüƒÒüîÒÇüÒéäÒüîÒüªõ©ÇÞê¼Õ«ÂÕ║¡Òü½ÒééµÖ«ÕÅèÒüùÒüªÒéåÒüìÒÇüµùѵ£¼Òü«Õ«ÂÕ║¡µûÖþÉåÒü«ÒâíÒâïÒâÑÒâ╝Òü½ÒééÕèáÒéÅÒüúÒüƒÒÇéÒü¥ÒüƒÒÇüÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÕ«ÜÚúƒÒü¬Òü®Òü«Õ¢óÒüºÕÆîÚúƒÕ║ùÒéäÕû½ÞîÂÕ║ùÒüºõ¥øÒüòÒéîÒéïÒüôÒü¿ÒééÕñÜÒüÅÒü¬ÒüúÒüªÒüäÒüúÒüƒÒÇé Òü¬ÒüèÒÇüÞÑ┐µ┤ïÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÕÅñõ╗úÒâ¡Òâ╝Òâ×Òü½ÒüèÒüäÒüªÒé½Òé¡Òü»þöƒÚúƒ´╝êÒüøÒüäÒüùÒéçÒüÅ´╝ëÒüÖÒéïÒééÒü«ÒüºÒüéÒéèÒÇüÒüôÒü«ÚúƒµûçÕîûÒéÆÕ╝òÒüìþÂÖÒüÉÕ¢óÒüºõ©ûþòîõ©¡Òü½µïíµòúÒüùÒüªÒüäÒéïµ¼ºþ▒│µûçÕîûգŴ╝êÒâòÒâ®Òâ│Òé╣ÒéÆõ©¡Õ┐âÒü½ÒÇüÒéñÒé┐Òâ¬ÒéóÒÇüÒéóÒâíÒâ¬Òé½ÒÇüÒé¬Òâ╝Òé╣ÒâêÒâ®Òâ¬ÒéóÒü¬Òü®ÒééÕɽÒéÇ[7]´╝ëÒüºÒééÒÇüÒé½Òé¡Òü»þöƒÚúƒÒüÖÒéïÒééÒü«ÒüºÒüéÒüúÒüªÒÇüÒâòÒâ®ÒéñÒüºõ¥øÒüÖÒéïµûÖþÉåÒü»ÞªïÕ¢ôÒüƒÒéëÒü¬ÒüäÒÇé ÚûóÚÇúÒüÖÒéïµûÖþÉåÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒü½ÒééÒüåõ©ÇÒüñµëïÒéÆÕèáÒüêÒüƒµûÖþÉåÒééÒüéÒéïÒÇé Òé½Òé¡ÒâòÒâ®Òéñõ©╝´╝êÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒü®Òéô´╝ë / þëíÞáúÒâòÒâ®Òéñõ©╝Òü»ÒÇüÒé½Òâäõ©╝Òü«ÒéêÒüåÒü½þÄëÞæ▒´╝êÒüƒÒü¥Òü¡ÒüÄ´╝ëÒü¬Òü®õ╗ûÒü«ÕàÀµØÉÒü¿Òé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒéÆÕë▓õ©ïÒüºþà«ÒüƒÕ¥îÒÇüÚÂÅÕìÁÒüºÒü¿ÒüÿÒÇüÒüöÚú»Òü«õ©èÒü½Þ╝ëÒüøÒüƒµûÖþÉåÒüºÒüéÒéï[8][9][10]ÒÇéÚÄîÕÇëõ©╝Òü»ÒÇüÚÄîÕÇëÕ©éÕåàÒü«þë╣Õ«ÜÕ£░ÕƒƒÒü«ÒüöÕ¢ôÕ£░µûÖþÉåÒüºÒüéÒéïÒüîÒÇüÒüôÒüôÒüºÒü»Òé½Òé¡ÒâòÒâ®Òéñõ©╝ÒééÒâÉÒâ¬Òé¿Òâ╝ÒéÀÒâºÒâ│Òü«õ©ÇÒüñÒü½Òü¬ÒüúÒüªÒüäÒéïÒÇé Òü¥ÒüƒÒÇüÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒüîõ╗ûÒü«µûÖþÉåÒü«ÕàÀµØÉÒü½Òü¬ÒüúÒüªÒüäÒéïÒé▒Òâ╝Òé╣ÒééÒüéÒéïÒÇé Òé½Òâ¼Òâ╝Òü«Õá┤ÕÉêÒÇüÒé½ÒâäÒé½Òâ¼Òâ╝Òü«Òé½ÒâäÒü¿ÕÉÿÒÇüÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒüîÒâêÒââÒâöÒâ│Òé░ÕàÀµØÉÒü¿ÒüùÒüªÕê®þö¿ÒüòÒéîÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒüéÒéïÒÇéµäøþƒÑþ£îÒüºÒü»ÒÇüÒüéÒéôÒüïÒüæÒé╣ÒâæÒé▓ÒââÒâåÒéúÒü«ÒâêÒââÒâöÒâ│Òé░ÕàÀµØÉÒü«õ©ÇÒüñÒü½ÒééÒü¬ÒüúÒüªÒüäÒéïÒÇé õ©ëÚçìþ£îÚ│Ñþ¥¢Õ©éÒü«õ©ÄÕÉëÕ▒ïÒü»ÒÇüÒüöÕ¢ôÕ£░ÒâÉÒâ╝Òé¼Òâ╝Òü«ÒÇîÒü¿Òü░Òâ╝ÒüîÒâ╝ÒÇìÒü¿ÒüùÒüªÒÇüÒé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒéƵîƒÒéôÒüáÒâøÒââÒâêÒâëÒââÒé░ÒÇîµÁªµØæÒüïÒüìÒâëÒââÒé░ÒÇìÒéƵÅÉõ¥øÒüùÒüªÒüäÒéï[11]ÒÇé ÚºàÕ╝üÒü«ÕàÀµØÉÒü¿ÒüùÒüªÒü»ÒÇüJRÕ║âÕ│ÂںൺïÕåàÒüºÞ▓®Õú▓ÒüòÒéîÒüªÒüäÒéïÒÇîÒüùÒéâÒééÒüÿÒüïÒüìÒéüÒüùÒÇìÒü½Òé½Òé¡ÒâòÒâ®ÒéñÒéƵÀ╗ÒüêÒüªÒüäÒéïÒâíÒâïÒâÑÒâ╝ÒüîÒüéÒéï[12][13]Òü╗ÒüïÒÇüµ┤ïÚó¿Õ╝üÕ¢ôÒü½ÕàÑÒéîÒéëÒéîÒéïõ¥ïÒééÒüéÒéïÒÇé
ÞíøþöƒÚØóÕÄÜþöƒÕè┤Õâìþ£üÒü»ÒÇü2013Õ╣┤´╝êÕ╣│µêÉ25Õ╣┤´╝ë10µ£ê6µùÑÒü½µö╣µ¡úÒüùÒüƒÒÇîÕñºÚçÅÞ¬┐þÉåµû¢Þ¿¡Þíøþöƒþ«íþÉåÒâ×ÒâïÒâÑÒéóÒâ½ÒÇìÒüºÒÇüÕèáþå▒Þ¬┐þÉåÚúƒÕôüÒü»ÒÇüõ©¡Õ┐âÚâ¿Òüî 75┬░CÒüº 1Õêåõ╗Ñõ©è´╝êõ║îµ×ÜÞ▓ØÒü¬Òü®ÒÇüÒâÄÒâ¡ÒéªÒéñÒâ½Òé╣µ▒ܵƒôÒü«µÇûÒéîÒüîÒüéÒéïÚúƒÕôüÒü«Õá┤ÕÉêÒü»ÒÇü85´¢×90┬░CÒüº 90þºÆõ╗Ñõ©èÒÇé´╝ëÒÇüÒü¥ÒüƒÒü»ÒÇüÒüôÒéîÒü¿ÕÉîþ¡ëõ╗Ñõ©èÒü¥ÒüºÕèáþå▒ÒüòÒéîÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþó║Þ¬ìÒüÖÒéïÒéêÒüåµîçÕ░ÄÒüùÒüªÒüäÒéï[14][15]ÒÇé Úúƒþöƒµ┤╗Õ¡ªÞÇàÒâ╗þòæµ▒ƒµò¼Õ¡ÉÒü»ÒÇüÒâÄÒâ¡ÒéªÒéñÒâ½Òé╣Òü½ÒéêÒéïÚúƒõ©¡µ»ÆÒéÆþÖ║þöƒÒüòÒüøÒü¬Òüäõ©¡Õ┐âÚ⿵©®Õ║ªÒüî 85┬░CÒü«µØíõ╗ÂÒéÆÞÂàÒüêÒéïÒüƒÒéüÒü½Òü» 3Õêå30þºÆõ╗Ñõ©èÒü«Õèáþå▒ÒüîÕ┐àÞªü[16]Òü¿ÒüùÒüªÒüäÒéïÒÇéõ©ÇÞê¼Þ▓íÕøúµ│òõ║║ þÆ░ÕóâµûçÕîûÕëÁÚÇáþáöþ®ÂµëÇÒü»ÒÇüÕ░ÅÕ▒▒þö░ÕëçÕ¡ØÒéë ÚúƒÕôüÞíøþöƒþáöþ®ÂÒÇüVol.53 (2003) ÒéÆÕç║Õà©Òü¿ÒüùÒüªÒÇüµ▓╣µ©® 170┬░Cõ╗Ñõ©èÒüº 3Õêåõ╗Ñõ©èµÅÜÒüÆÒéïÒü¿ÒüäÒüåµ│¿µäÅÕûÜÞÁÀÒüùÒüªÒüäÒéï[15]ÒÇéÕîùµÁÀÚüôÒé¬ÒâøÒâ╝ÒâäÒé»þÀÅÕÉêµî»ÞêêÕ▒ÇÒü»ÒÇüµ▓╣µ©® 180┬░Cõ╗Ñõ©èÒüº 4Õêåõ╗Ñõ©èµÅÜÒüÆÒéïÒü«ÒéÆþø«Õ«ëÒü¿ÒüùÒüªÒüäÒéï[17]ÒÇéÒü¬ÒüèÒÇüÒÇî4Õêåõ╗Ñõ©èÒÇìÒü¿ÒüäÒüåÒü«Òü»ÒÇüÕåÀÕçìÒüòÒéîÒüƒþëíÞáúÒü«Þ║½ÒéÆÕìüÕêåÒü½ÞºúÕçìÒüùÒü¬ÒüäÒü¥Òü¥µÅÜÒüÆÒéïÕá┤ÕÉêÒüîÒüéÒéïÒüôÒü¿ÒéÆÞÇâµà«ÒüùÒüƒµò░ÕÇñÒüºÒüéÒéï[15]ÒÇéþ┐╗ÒüùÒüªÞ¿ÇÒüêÒü░ÒÇüÞºúÕçìÒüéÒéïÒüäÒü»ÕåÀÞöÁÒüùÒüªÒüèÒüäÒüƒÒé½Òé¡Òü«Þ║½ÒüºÒüôÒüôÒü¥ÒüºÚòÀÒüŵÅÜÒüÆÒüªÒüùÒü¥ÒüåÒü¿ÒÇüÒâòÒâ®ÒéñÒü«Þí¿ÚØóÒüîþäªÒüÆÒüªÒüùÒü¥ÒüúÒüªþ¥ÄÕæ│ÒüùÒüÅÒü»õ╗òõ©èÒüÆÒéëÒéîÒü¬Òüä[15]ÒÇé ÕÅéÞÇâµûçþî«
Þäܵ│¿µ│¿Úçê
Õç║Õà©
ÚûóÚÇúÚáàþø«ÕñûÚâ¿Òâ¬Òâ│Òé»
|
Portal di Ensiklopedia Dunia