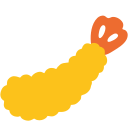„āĘ„āł„Éē„É©„ā§
„āĘ„āł„Éē„É©„ā§ÔľąŤ°®Ť®ėśŹļ„āĆ: „Āā„Āė„Éē„É©„ā§„ÄĀťįļ„Éē„É©„ā§„ÄĀťĮĶ„Éē„É©„ā§ÔľČ„ĀĮ„ÄĀ„āĘ„āł„āíť£üśĚź„Ā®„Āó„Āü„Éē„É©„ā§śĖôÁźÜÔľą„ÉĎ„É≥Á≤Č„ā퍰£„Āę„Āó„ĀüśŹö„ĀíÁȩԾȄĀß„Āā„āč„ÄāŤčĪŤ™ě„Āß„ĀĮ‚ÄúAji Fry‚ÄĚ„Ā™„Ā©„Ā®Ť°®Ť®ė„Āē„āĆ„āč[2][ś≥®ťáą 1]„Äāśėéś≤ĽšĽ•ťôć„Āģśó•śú¨„Āߍ•ŅśīčśĖôÁźÜ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„Ā¶Á訍ᙄĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āüśīčť£ü„Āģ„Ā≤„Ā®„Ā§„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ŚíĆť£ü„Ā®šĹćÁĹģšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč„ĀĽ„Ā©„ÄĀ„Āä„Āč„Āö„ÄĀ„Āä„āĄ„Ā§„ÄĀťÖí„ĀģŤāī„Ā™„Ā©„Ā®„Āó„Ā¶ŚļÉ„ĀŹśôģŚŹä„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā Ť™ŅÁźÜ„ĀĮ„āĘ„āł„Āę„ÉĎ„É≥Á≤Č„Ā™„Ā©„ā횼ė„ĀĎ„Ā¶ś≤Ļ„ĀßśŹö„Āí„āč„Āģ„ĀĆŚüļśú¨„Āß„ÄĀÁīį„Āč„ĀĄŚ∑•Á®č„Āß„ĀĮśßė„ÄÖ„Ā™Ś∑•Ś§ę„ĀĆ„Ā™„Āē„āĆ„āč„Äā„āĶ„āĮ„āĶ„āĮ„Ā®„Āó„ĀüŤ°£„Ā®„ĀĶ„āď„āŹ„āä„Ā®„Āó„Āü„āĘ„āł„ĀĆšĹú„āäŚáļ„Āôť£üśĄü„ĀĆÁČĻŚĺī„Āß„ÄĀ„Āč„ĀĎ„ā荙ŅŚĎ≥śĖô„Āę„āą„Ā£„Ā¶Áēį„Ā™„āčŚĎ≥„āíś•Ĺ„Āó„āÄ„Āď„Ā®„āāŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āč„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀś†Ąť§äťĚĘ„Āß„ĀĮšĹé„āę„É≠„É™„Éľ„ÉĽšĹéÁ≥ĖŤ≥™„Āß„ā®„ā§„ā≥„āĶ„Éö„É≥„āŅ„ā®„É≥ťÖł (EPA) „āĄ„ÉČ„ā≥„āĶ„Éė„ā≠„āĶ„ā®„É≥ťÖł (DHA) „ĀĆŤĪäŚĮĆ„Āß„Āā„āč„Ā®„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āč„Äā śó•śú¨„Āß„ĀĮ„ÄĀŚģ∂Śļ≠śĖôÁźÜ„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹšł≠ť£ü„ÉĽŚ§Ėť£ü„Ā®„Āó„Ā¶„āāśôģŚŹä„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā„Āď„Āģ„ĀĽ„Āč„ÄĀÁĒļ„Āä„Āď„Āó„āĄ„ā≠„É£„É©„āĮ„āŅ„Éľ„Āģť°ĆśĚź„Āę„Āē„āĆ„Āü„āä„ÄĀšŅ≥ŚŹ•„ÉĽ„ā®„ÉÉ„āĽ„ā§„ÉĽśľęÁĒĽ„ÉĽ„ÉČ„É©„Éě„Ā™„Ā©„ĀģšĹúŚďĀŚÜÖ„Āß„āāŚŹĖ„āäšłä„Āí„āČ„āĆ„Āü„āä„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀśó•śú¨śĖáŚĆĖ„Āģšł≠„Āߍ¶™„Āó„Āĺ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āčśĖôÁźÜ„Āß„Āā„āč„Äā ś≠īŚŹ≤ÁôļÁ••  śó•śú¨„Āß„ĀĮ„ÄĀÁłĄśĖáśôāšĽ£„Āč„āČ„āĘ„āł„ĀĆť£ü„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä[5][ś≥®ťáą 2]„ÄĀŚĻ≥ŚģČśôāšĽ£„Āę„ĀĮŤ°Ćšļčť£ü„Ā®„Āó„Ā¶ÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„āč[8]„Ā™„Ā©„ÄĀÁĺéŚĎ≥„Āó„ĀĄť≠ö„Ā®„Āó„Ā¶Áü•„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü[ś≥®ťáą 3]„Äā šłÄśĖĻ„ÄĀśĪüśąłśôāšĽ£„Āģśó•śú¨„Āß„ĀĮ„ÄĀśŹö„ĀíÁČ©„ĀģŤ™ŅÁźÜśĖĻś≥ē„ĀģšłÄ„Ā§„Ā®„Āó„Ā¶Ś§©„Ā∑„āČ„ĀĆŚģöÁĚÄ„Āó„Ā¶„Āä„āä[10]„ÄĀśó•śú¨„ĀģŚ§©„Ā∑„āČ„Āę„ĀĮ„ÄĀś¨ßÁĪ≥„ĀģśŹö„ĀíÁČ©„ĀßšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā™ŚįϝᏄĀģś≤Ļ„āíšĹŅÁĒ®„Āô„ā蜏ö„ĀíśĖĻÔľą„ā∑„É£„É≠„ā¶„ÉĽ„Éē„ā°„ÉÉ„Éą„ÉĽ„Éē„É©„ā§„É≥„āįԾȄĀ®„ĀĮÁēį„Ā™„āä„ÄĀŚ§ßťáŹ„Āģś≤Ļ„āíšĹŅÁĒ®„Āô„ā蜏ö„ĀíśĖĻÔľą„Éá„ā£„Éľ„Éó„ÉĽ„Éē„ā°„ÉÉ„Éą„ÉĽ„Éē„É©„ā§„É≥„āįԾȄāíÁĒ®„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁČĻŚĺī„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü[11]„Äāśėéś≤ĽśôāšĽ£ŚąĚśúü„Āę„Ā™„āč„Ā®„ÉĎ„É≥Á≤Č„ĀĆšľĚśĚ•„Āó[12]„ÄĀ„ā≥„Éľ„Éą„ɨ„ÉÉ„Éą[13][ś≥®ťáą 4]„āĄ„āĮ„É≠„āĪ„ÉÉ„Éą[16]„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„ÄĀ„ÉĎ„É≥Á≤Č„āí„Āĺ„Ā∂„Āó„Ā¶ÁÜĪ„āíťÄö„ĀôŤ•ŅśīčśĖôÁźÜ„ĀĆśó•śú¨„ĀęśĆĀ„Ā°Ťĺľ„Āĺ„āĆ„āč„Äā„Āď„āĆ„Āę„ÄĀŚ§©„Ā∑„āČ„ĀߌüĻ„Ā£„Āüśó•śú¨„Āģ„Éá„ā£„Éľ„Éó„ÉĽ„Éē„ā°„ÉÉ„Éą„ÉĽ„Éē„É©„ā§„É≥„āį„ĀģśäÄŤ°ď„ĀĆŚźą„āŹ„Āē„āä„ÄĀ„ÉĎ„É≥Á≤Č„ā퍰£„Āę„Āó„Ā¶Ś§ßťáŹ„Āģś≤Ļ„ĀßśŹö„Āí„āčśó•śú¨„Āģ„Éē„É©„ā§Ť™ŅÁźÜ[ś≥®ťáą 5]„ĀĆÁĘļÁęč„Āó„Āü[ś≥®ťáą 6]„Äā „Āď„ĀÜ„Āó„Ā¶ÁĒü„Āĺ„āĆ„Āü„Éē„É©„ā§Ť™ŅÁźÜ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÄĀ„ā≥„Éľ„Éą„ɨ„ÉÉ„Éą„ĀĮ„āę„ÉĄ„ɨ„ÉĄ[13]„ÄĀ„āĮ„É≠„āĪ„ÉÉ„Éą„ĀĮ„ā≥„É≠„ÉÉ„āĪ[16]„Ā®„ĀĄ„ĀÜśó•śú¨Á訍ᙄĀģśīčť£ü„Ā®„Āó„Ā¶ŚģĆśąź„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀšłÄśĖĻ„Āß„Éē„É©„ā§Ť™ŅÁźÜ„ĀĮŤ•ŅśīčśĖôÁźÜ„āíťõĘ„āĆ„Ā¶ť≠ö„Āę„āāšłÄŤą¨ÁöĄ„ĀęšĹŅ„āŹ„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„ÄĀ1872ŚĻīÔľąśėéś≤Ľ5ŚĻīԾȄĀꌹ䍰ƄĀē„āĆ„ĀüśúÄŚąĚśúü„ĀģŤ•ŅśīčśĖôÁźÜ„ɨ„ā∑„ÉĒśú¨„Āß„Āā„āč„Ä鍕ŅśīčśĖôÁźÜťÄö„ÄŹ[21]„āĄ„Ä鍕ŅśīčśĖôÁźÜśĆáŚćó„ÄŹ[22]„Āę„ĀĮ„ÄĀť≠ö„Āģ„Éē„É©„ā§„ĀĆśé≤ŤľČ„Āē„āĆ„Āü[20]„Äā„āĘ„āł„Āę„āā„Éē„É©„ā§Ť™ŅÁźÜ„ĀĆšĹŅ„āŹ„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„ÄĀśėéś≤ĽŚąĚśúü„Āģ„ĀÜ„Ā°„Āę„Āô„Āß„Āę„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ[23][24]„Äā śėéś≤Ľśúü„ĀģśČĪ„ĀĄ1895ŚĻīÔľąśėéś≤Ľ28ŚĻīԾȄĀęŚČĶś•≠„Āó„Āüśīčť£üśĖôÁźÜŚļó„ÉĽÁÖČÁﶚļ≠„Āß„ĀĮśßė„ÄÖ„Ā™ť≠öšĽčť°ě„Āģ„Éē„É©„ā§„ĀĆŤ©¶Ť°ĆťĆĮŤ™§„Āē„āĆ„Āü[19]„ĀĆ„ÄĀ„āę„ā≠„Éē„É©„ā§„ÄĀ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„Ā™„Ā©„ĀĆśé°ÁĒ®„Āē„āĆ„Āü„Āģ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮŚźĆŚļó„ĀģšĽ£Ť°®ÁöĄ„Ā™„É°„Éč„É•„Éľ„Āę„ĀĮśĆô„Āí„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ[25]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśė≠ŚíĆŚąĚśúü„ĀęŚČĶś•≠„Āó„ĀüŤĪö„āę„ÉĄ„ÉĽ„Éē„É©„ā§„ĀģŚįāťĖÄŚļó„Āß„Āā„āčŚįŹÁĒįšŅĚ„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀśėéś≤ĽŚąĚśúü„ĀģŤ•ŅśīčśĖôÁźÜśĆáŚćóśõł„Āę„ĀĮ„āę„ā≠„Éē„É©„ā§„āĄ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„ĀģŤ®ėŤľČ„ĀĮ„Āā„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŤ®ėŤľČ„ĀĮ„Ā™„Āč„Ā£„Āü[23]„ÄāŚźĆŚļó„ĀĮ„ÄĀ„Éē„É©„ā§śĖôÁźÜ„ĀĮŚĹďśôāťęėÁīöśĖôÁźÜ„Āß„Āā„āä„ÄĀŚģ∂Śļ≠„Āß„āāšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā†„Ā£„Āü„āĘ„āł„ĀĮťô§Ś§Ė„Āē„āĆ„Ā¶„Āó„Āĺ„Ā£„Āü„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ∂£śó®„Āģśé®śł¨„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[23]„Äā „Āď„āĆ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀÁÖČÁﶚļ≠„ĀģŚČĶś•≠„Ā®ŚźĆ„Āė1895ŚĻī„Āꌹ䍰ƄĀē„āĆ„ĀüŚģ∂Śļ≠ŚźĎ„ĀĎśĖôÁźÜŤß£Ť™¨śõł„ÄéŚģ∂Śļ≠ŚŹĘśõł Á¨¨8Ś∑Ľ Áį°śėďśĖôÁźÜ„ÄŹ„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀ
„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀť≠öť°ě„Āģ„Éē„É©„ā§„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ťß£Ť™¨„Āô„āčšł≠„Āß„ÄĀ„Éē„É©„ā§„ĀęťĀ©„Āó„Āüť≠ö„Ā®„Āó„Ā¶„āŅ„ā§„ÄĀ„Éí„É©„É°„ÄĀ„ÉŹ„āľ„ÄĀ„āĘ„Éä„āī„ÄĀ„āʄɶ„Ā®šł¶„āď„Āß„āĘ„āł„āíšĺčÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[26]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀšłĽŚ©¶„ĀßśĖôÁźÜÁ†ĒÁ©∂Śģ∂„ĀģśĚĎšļēŚ§öŚėČŚ≠źÔľą„Äéť£üťĀďś•Ĺ„ÄŹ„ĀģšĹúŤÄÖ„ÉĽśĚĎšļēŚľ¶śĖé„ĀģŚ¶Ľ[27]ԾȄĀĆ1907ŚĻīÔľąśėéś≤Ľ40ŚĻīԾȄĀč„āČŚĮĺŤęáŚĹĘŚľŹ„ĀßťÄ£ŤľČ„Āó„Āü„Ä錾¶śĖ錧ęšļļ„ĀģśĖôÁźÜŤęá„ÄŹ„Āß„ĀĮ„Āď„ĀÜ„Āā„āč„Äā
„Ā®„āĘ„āł„āíť£üśĚź„Ā®„Āó„ĀüŤ™ŅÁźÜśĖĻś≥ē„ĀĆŤ®ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[28][ś≥®ťáą 7]„Äā śôģŚŹä„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŤ™ŅÁźÜ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā™„ÉĎ„É≥Á≤Č„ĀĮ„ÄĀ1907ŚĻīÔľąśėéś≤Ľ40ŚĻīԾȄĀęśĚĪšļ¨„ÉĽšļ¨ś©č„Āģ„ÉĎ„É≥ŚĪč„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÉĎ„É≥„ĀģÁ≤ČÁ†ēś©ü„ĀĆťĖčÁôļ„Āē„āĆ„Ā¶ś©üśĘįŤ£ĹťÄ†„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āä[30]„ÄĀ1916ŚĻīÔľąŚ§ßś≠£5ŚĻīԾȄĀęśó•śú¨„ĀߌąĚ„āĀ„Ā¶ŚēÜŚďĀŚĆĖ„Āē„āĆ„Āü[31]„ÄāÁ¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶ŚĺĆ„Āģť£üÁ≥ßťõ£„Āęťöõ„Āó„Ā¶ťõĽśįó„ÉĎ„É≥„ĀģśäÄŤ°ď„ĀĆŤĽĘÁĒ®„Āē„āĆ„Ā¶„ÉĎ„É≥Á≤Č„ĀģŚ§ßŤ¶Źś®°ÁĒüÁĒ£„ĀĆ„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä[32]„ÄĀŚ§ßťáŹŚá¶ÁźÜ„ĀęťĀ©„Āó„Āü„Éē„É©„ā§Ť™ŅÁźÜ„ĀĮťõÜŚõ£ÁĶ¶ť£ü„Āę„āāŚŹĖ„āäŚÖ•„āĆ„āČ„āĆ„Āü[33]„ÄāŚ≠¶ś†°ÁĶ¶ť£ü„ĀģŚ§ČťĀ∑„ā횾̄Āą„āčŚ≠¶ś†°ÁĶ¶ť£üś≠īŚŹ≤ť§®„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ≠¶ś†°ÁĶ¶ť£üś≥ēŚą∂ŚģöÁŅĆŚĻī„Āģ1955ŚĻīÔľąśė≠ŚíĆ30ŚĻīԾȄĀģŚ≠¶ś†°ÁĶ¶ť£ü„āĶ„É≥„Éó„Éę„Ā®„Āó„Ā¶„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„āíŚĪēÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[34]„Äā „ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮśó•śú¨ŚõĹŚÜÖ„ĀߌļÉ„ĀŹśôģŚŹä„Āó„ÄĀ„Āä„Āč„Āö„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Āä„āĄ„Ā§[35]„ÄĀťÖí„ĀģŤāī[36]„Ā™„Ā©„Ā®„Āó„Ā¶Ť¶™„Āó„Āĺ„āĆ„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮťõĘšĻ≥ť£üŚģĆšļÜśúüÔľą1ś≠≥„Āč„āČ1ś≠≥ŚćäԾȄĀģ„ɨ„ā∑„ÉĒ„Ā®„Āó„Ā¶„āāśĆô„Āí„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[37]„ÄāŤĶ∑śļź„ĀĮśīčť£ü„Āę„Āā„āč„ĀĆ„ÄĀť£ü„ÉĽÁĒüśīĽŚŹ≤Á†ĒÁ©∂Śģ∂„ĀģťėŅŚŹ§ÁúüÁźÜ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ŚíĆť£ü„Ā®ŚĆĖ„Āó„Āü„Ā®šĹćÁĹģšĽė„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„āč[10]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éě„Éę„ÉŹ„Éč„ÉĀ„É≠„ĀĆ2018ŚĻīÔľąŚĻ≥śąź30ŚĻīԾȄĀꍰƄĀ£„Āü„āĘ„É≥„āĪ„Éľ„Éą„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Äé„Ā䌾ĀŚĹď„Āģ„Āä„Āč„Āö„Āę„Āó„Āü„ĀĄť≠öšĽčśĖôÁźÜ„ÄŹ„Āģ3šĹć„Āę„É©„É≥„āĮ„ā§„É≥„Āó„Āü[38]„Äā Ť™ŅÁźÜś≥ē„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ„ÄĀŚÖ∑śĚź„Āģ„āĘ„āł„āí„Āä„āć„Āó„Ā¶Ôľą„Āē„Āį„ĀĄ„Ā¶ÔľČšłčŚĎ≥„ā횼ė„ĀĎ„ÄĀŚįŹťļ¶Á≤Č„āí„Āĺ„Ā∂„Āó„Ā¶ŚćĶ„āíÁĶ°„Āĺ„Āõ„Ā¶„Āč„āČ„ÉĎ„É≥Á≤Č„āí„Āĺ„Ā∂„Āó„ÄĀś≤Ļ„Āß„Āć„Ā§„Ā≠ŤČ≤„Āę„Ā™„āč„Āĺ„ĀßśŹö„Āí„āč„Āď„Ā®„ĀßšĹú„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč[39][40]„ÄāŚįŹťļ¶Á≤Č„ÉĽŚćĶ„ā횼ė„ĀĎ„āčŚ∑•Á®č„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„Āā„āČ„Āč„Āė„āĀ„Āď„āĆ„āČ„Ā®śįī„ĀčÁČõšĻ≥„āíś∑∑„ĀúŚźą„āŹ„Āõ„Ā¶„Āä„ĀĄ„Āü„Éź„ÉÉ„āŅ„Éľś∂≤„ĀĆšĹŅ„āŹ„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč[41][42]„Äā ŚÖ∑śĚź„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„āĘ„āł„ĀģšłÄÁ®ģ„Āß„Āā„āč„Éě„āĘ„āł„ĀĆšĹŅÁĒ®„Āē„āĆ„āč[43]„Äā„Éě„āĘ„āł„Āę„ĀĮšĹďŤČ≤„Ā™„Ā©„ĀģťĀē„ĀĄ„Āč„āČ„ā≠„āĘ„āł„āĄ„āĮ„É≠„āĘ„āł„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚĆļŚą•„ĀĆ„Āā„āč„ĀĆ„ÄĀÁČĻ„Āę„ā≠„āĘ„āł„ĀĆÁĺéŚĎ≥„Āß„Āā„āč„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[44]„Äā2015ŚĻīśôāÁāĻ„Āß„Éě„āĘ„āł„ĀģśľĀÁć≤ťáŹ„ĀĮśłõŚįĎŚā匟τĀę„Āā„āä„ÄĀŚģöť£üŚļó„Āę„Āä„ĀĎ„āč„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģśŹźšĺõ„Āę„āāŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„Ā¶„ĀĄ„āč[43]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éě„āĘ„āł„ĀģŤŅĎÁłĀÁ®ģ„Āģ„É°„āĘ„āł„ĀĆÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč[45]„Äā „Āē„Āį„ĀćśĖĻ„ĀĮŤÉĆťĖč„Āć„ĀĆšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā†„ĀĆ[46]„ÄĀšłČśěö„Āä„āć„Āó[42]„āĄŤÖĻťĖč„Āć[39]„ĀĆÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč„ÄāŤ°ÄŚźą„ĀĄ„Ā®ŚÜÖŤáď„āí„Āć„āĆ„ĀĄ„ĀꌏĖ„āäŚéĽ„āč„Āď„Ā®„Āߍá≠„ĀŅ„ĀĆ„Ā™„ĀŹŚĎ≥„āą„ĀŹšĽēšłä„ĀĆ„āč„Ā®„Āē„āĆ[47]„ÄĀŚÜÖŤáď„Āģ„ĀĽ„Ā蝆≠„āĄ„Āú„āď„ĀĒÔľą„Āú„ĀĄ„ĀĒ„ÄĀÁ®úťĪóԾȄāāŚŹĖ„āäťô§„ĀŹ[39][40][48]„Äā„ĀĚ„Āģ„ĀĽ„Āč„ÄĀšłčŚá¶ÁźÜ„ĀģśČ蝆܄ɼÁēôśĄŹÁāĻ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśįīśįó„āí„āą„ĀŹŚąá„āč[40][48]„ÄĀť™®śäú„ĀćÁĒ®„Āģ„ÉĒ„É≥„āĽ„ÉÉ„Éą„ĀߌįŹť™®„ā팏Ė„āč[49]„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„āā„Āģ„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„āč„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚĺĆŤŅį„Āģšļ¨„Āį„ĀóśĚ卾™„Āß„ĀĮ„āĘ„āł„āíÁĒü„Āć„Āü„Āĺ„Āĺ„Āē„Āį„Āć„ÄĀŚ°©„āí„Āó„Ā¶10śôāťĖď„ĀĽ„Ā©ŚĮĚ„Āč„Āõ„āč„Āď„Ā®„ĀßšĹôŚąÜ„Ā™śįīŚąÜ„āíŚáļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[50][51]„ÄāšłčŚĎ≥„Āę„ĀĮŚ°©„āĄŤÉ°ś§í„ĀĆšĹŅ„āŹ„āĆ„āč[39][40]„Äā śŹö„Āíś≤Ļ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„āĶ„É©„ÉÄś≤Ļ„āĄ„ĀĒ„Āĺś≤Ļ[50]„ÉĽ„É©„Éľ„ÉČ„āĄ„Éź„āŅ„Éľ[28]„ĀĆÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„ÄĀšļ¨„Āį„ĀóśĚ卾™„Āß„ĀĮ„ā≥„Éľ„É≥„āĶ„É©„ÉÄś≤Ļ„Āę„ĀĒ„Āĺś≤Ļ„āí„ÉĖ„ɨ„É≥„ÉČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[50]„Äā165‚ĄÉ„Ā™„Ā©šĹé„āĀ„Āģśł©Śļ¶„Āß„āÜ„Ā£„ĀŹ„ā䜏ö„Āí„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āĆ„Āį[39]„ÄĀ170‚ĄÉ„Āč„āČ180‚ĄÉ„Āß„Āč„āČ„āä„Ā®śŹö„Āí„ā茆īŚźą„āā„Āā„āč[40]„Äā „Éą„ÉÉ„ÉĒ„É≥„āįÁ≠Č
ŚĎ≥„ÉĽť£üśĄü„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„āí„ĀĮ„Āė„āĀ„Ā®„Āô„āč„Éē„É©„ā§śĖôÁźÜ„Āß„ĀĮ„ÄĀŤ™ŅÁźÜ„ĀģťĀéÁ®č„Āߍ°£„ĀģśįīŚąÜ„ĀĆŤíłÁôļ„Āó„Ā¶„ĀĚ„Āď„ĀęśĶłťÄŹ„Āó„Āüś≤Ļ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŤÜú„ĀĆ„Āß„Āć„ÄĀÁī†śĚź„ĀģśįīŚąÜ„ĀĆŤÜú„ĀģŚÜÖŚĀī„ĀßśįīŤíłśįó„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶Áī†śĚź„āíŤíł„Āóšłä„Āí„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āč[60]„Äā„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀť£üśĚź„Āģśó®„ĀŅ„āíťÄÉ„Āē„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀęŚä†„Āą„ÄĀŤ°£„ĀĮ„āĶ„āĮ„āĶ„āĮ„ÄĀÁī†śĚź„ĀĮ„ĀĶ„āď„āŹ„āä„Ā®„Āó„ĀüšĽēšłä„ĀĆ„āä„Āę„Ā™„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚäĻśěú„ĀĆ„Āā„āč[60]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ„āŅ„Éę„āŅ„Éę„āĹ„Éľ„āĻ„āĄ„ā¶„āĻ„āŅ„Éľ„āĹ„Éľ„āĻ„Ā™„Ā©Ť™ŅŚĎ≥śĖô„āíšĹŅ„ĀĄŚąÜ„ĀĎ„āč„Āď„Ā®„ĀߌĎ≥„ĀģŚ∑ģŚą•ŚĆĖ„āíŚõ≥„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč[61]„Äā „āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ā팕ĹÁČ©„ĀęśĆô„Āí„āč„É©„ā§„āŅ„Éľ„ĀģŚĆóŚįĺ„Éą„É≠„ĀĮ„ÄĀ„āį„Éę„É°ťõĎŤ™Ć„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀÁźÜśÉ≥ÁöĄ„Ā™„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āę„ĀĮ ś†Ąť§äÁī†„Äéśó•śú¨ť£üŚďĀś®ôśļĖśąźŚąÜŤ°®„ÄŹ„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀ100„āį„É©„Ɇ„Āā„Āü„āä„Āģ„āę„É≠„É™„Éľ„ĀĮ270„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„Éľ„Āß„Āā„āč[1]„ÄāŚźĆŤ≥áśĖô„Āß„ĀĮ100„āį„É©„Ɇ„Āā„Āü„āä„Āģ„āę„É≠„É™„Éľ„āí„ÄĀ„Éą„É≥„āę„ÉĄ„ĀĮ„É≠„Éľ„āĻŤāČ429„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„Éľ„ÉĽ„Éí„ɨŤāČ379„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„Éľ„ÄĀ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„ĀĮ236„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„Éľ„Āß„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[66]„ĀĆ„ÄĀ„Éą„É≥„āę„ÉĄ„āĄ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„Ā®śĮĒ„ĀĻ„Ā¶„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āģ„āę„É≠„É™„Éľ„āí„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Āꍩēšĺ°„Āô„ĀĻ„Āć„Āč„ĀĮŤ¶čŤß£„ĀĆŚąÜ„Āč„āĆ„āč„Äā„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āģ1šļļŚČć„āí1Śįĺ„Ā®„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀ224„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„Éľ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„É≠„Éľ„āĻŤāČ„Āģ„Éą„É≥„āę„ÉĄÔľą1śěö463„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„ɾԾȄāĄ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§Ôľą3Śįĺ„Äą„āŅ„Éę„āŅ„Éę„āĹ„Éľ„āĻś∑Ľ„Āą„ÄČ377„ā≠„É≠„āę„É≠„É™„ɾԾȄĀęśĮĒ„ĀĻ„Ā¶šĹé„āę„É≠„É™„Éľ„Āß„Āā„āč„Ā®„Āô„āčÁģ°ÁźÜś†Ąť§äŚ£ę„ĀĆ„ĀĄ„āč[67]„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āģ1šļļŚČć„ĀĮ2ŚįĺÁ®čŚļ¶„Āß„Āā„āč„Ā®„Āó„Āü„ĀÜ„Āą„Āß„ÄĀŚźłś≤ĻÁéá„ĀĮ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„Āģ13„ÉĎ„Éľ„āĽ„É≥„Éą„āĄ„Éą„É≥„āę„ÉĄ„Āģ14„ÉĎ„Éľ„āĽ„É≥„Éą„ĀęŚĮĺ„Āó„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ22„ÉĎ„Éľ„āĽ„É≥„Éą„Ā®ťęė„ĀŹ„ÄĀ„Éą„É≥„āę„ÉĄ1śěöÔľą100„āį„É©„ɆԾȄāą„āä„āāťęė„āę„É≠„É™„Éľ„Āß„Āā„āč„Ā®„Āô„āčÁģ°ÁźÜś†Ąť§äŚ£ę„āā„ĀĄ„āč[68]„Äā „āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮšĹéÁ≥ĖŤ≥™„Ā†„Ā®„Āē„āĆ„āč[9]„Äā„Äéśó•śú¨ť£üŚďĀś®ôśļĖśąźŚąÜŤ°®„ÄŹ„Āę„āą„āč„Ā®100„āį„É©„Ɇ„Āā„Āü„āä„ĀģÁā≠śįīŚĆĖÁČ©„ĀĮ„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĆ7.9„āį„É©„Ɇ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„Éą„É≥„āę„ÉĄ„ĀĮ„É≠„Éľ„āĻŤāČ9.8„āį„É©„Ɇ„ÉĽ„Éí„ɨŤāČ14.9„āį„É©„Ɇ„ÄĀ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„ĀĮ20.3„āį„É©„Ɇ„Āß„Āā„āč[69]„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀÁ≥ĖŤ≥™„āíÁáÉÁĄľ„Āē„Āõ„āč„Éď„āŅ„Éü„É≥B1„ĀĮ100„āį„É©„Ɇ„Āā„Āü„āä0.12„Éü„É™„āį„É©„Ɇ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„Éą„É≥„āę„ÉĄÔľą„É≠„Éľ„āĻŤāČ0.75„Éü„É™„āį„É©„Ɇ„ÄĀ„Éí„ɨŤāČ1.09„āį„É©„ɆԾȄāą„āäŚįĎ„Ā™„ĀĄ[68][70]„Äā „Āĺ„Āü„ÄĀ„āĘ„āł„Āę„ĀĮ„ā®„ā§„ā≥„āĶ„Éö„É≥„āŅ„ā®„É≥ťÖł (EPA) „āĄ„ÉČ„ā≥„āĶ„Éė„ā≠„āĶ„ā®„É≥ťÖł (DHA) „ĀĆŤĪäŚĮĆ„Āꌟę„Āĺ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„Āē„āĆ„āč[46]„ĀĆ„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„ĀĮś≤Ļ„ĀßśŹö„Āí„āč„Ā®śļ∂„ĀĎŚáļ„Āó„Ā¶„Āó„Āĺ„ĀÜ„Ā®ŤŅį„ĀĻ„āčÁģ°ÁźÜś†Ąť§äŚ£ę„āā„ĀĄ„āč[68]„Äā„Äéśó•śú¨ť£üŚďĀś®ôśļĖśąźŚąÜŤ°®„ÄŹ„Āę„āą„āč„Ā®100„āį„É©„Ɇ„Āā„Āü„āä„ĀģEPAŚźęśúȝᏄĀĮ„ÄĀÁĒü„Āģ„āĘ„āł„ĀĆ300„Éü„É™„āį„É©„Ɇ„ĀęŚĮĺ„Āó„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ240„Éü„É™„āį„É©„Ɇ„ÄĀŚźĆ„Āė„ĀŹDHAŚźęśúȝᏄĀĮ„ÄĀÁĒü„Āģ„āĘ„āł„ĀĆ570„Éü„É™„āį„É©„Ɇ„ĀęŚĮĺ„Āó„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ560„Éü„É™„āį„É©„Ɇ„Āß„Āā„āč[71]„Äā šł≠ť£ü„āĄŚ§Ėť£ü„Ā®„Āó„Ā¶ śó•śú¨„Āģ„āĻ„Éľ„ÉĎ„Éľ„Ā™„Ā©„Āß„ĀĮ„ÄĀśÉ£ŤŹúŚēÜŚďĀ„Ā®„Āó„Ā¶Ť™ŅÁźÜ„Āē„āĆ„ĀüÁä∂śÖč„Āߍ≤©Ś£≤„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[72]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚÜ∑Śáćť£üŚďĀ„Ā®„Āó„Ā¶Ť°£„ĀĆ„Ā§„ĀĄ„ĀüÁä∂śÖč„ĀßśĶĀťÄö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„āā„Āģ„āā„Āā„āč[73]„ÄāŚÜ∑Śáćť£üŚďĀ„Āģ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ„ÄĀŤ≥ľŚÖ•ŚĺĆ„Āęś≤Ļ„Āߍ™ŅÁźÜ„Āô„āč„āā„Āģ[73]„ÄĀťõĽŚ≠ź„ɨ„É≥„āł„Āߍ™ŅÁźÜ„Āô„āč„āā„Āģ[74]„ĀĆ„Āā„āč„ÄāŚÜ∑Śáć„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮ„ÄĀťüďŚõĹ[75]„ÄĀšł≠ŚõĹ[76]„ÄĀ„ā™„É©„É≥„ÉÄ[77]„Ā™„Ā©„ÄĀśó•śú¨šĽ•Ś§Ė„ĀģŚõĹ„āíÁĒ£Śúį„Ā®„Āô„āč„āā„Āģ„āā„Āā„āč„Äā Ś§Ėť£ü„Āß„ĀĮ„ÄĀŚģöť£ü„Ā®„Āó„Ā¶„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĆśŹźšĺõ„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āč„ÄāśĚĪšļ¨ťÉĹšł≠Ś§ģŚĆļ„ĀģśĖôÁźÜŚļó„ÉĽšļ¨„Āį„ĀóśĚ卾™„ĀĮ„ÄĀ„É©„É≥„ÉĀ„āŅ„ā§„Ɇ„Āę„ĀĮ70ť£üťôźŚģö„Āģ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§Śģöť£üÁõģŚĹď„Ā¶„Āꍰƌąó„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®„ĀßÁü•„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[59]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀÁČõšłľ„ÉĀ„āß„Éľ„É≥„ĀģŚźČťáéŚģ∂„ĀĮ„ÄĀšłÄśôāśúü„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§Śģöť£ü„Äć„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§šłľ„Äć„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§ŚćėŚďĀ„Äć„āíŤ≤©Ś£≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü[78][79]„Äā śó•śú¨śĖáŚĆĖ„Āģšł≠„Āß ťē∑ŚīéÁúĆśĚĺśĶ¶Śłā„ĀĮ„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŤĀĖŚúį„Äć„Ā®„Āó„Ā¶ÁĒļ„Āä„Āď„Āó„ĀꌏĖ„āäÁĶĄ„āď„Āß„ĀĄ„āč[80]„ÄāŚźĆŚłā„ĀĮ„āĘ„āł„ĀģśįīśŹö„ĀíťáŹ„ĀĆśó•śú¨šłÄ„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ2019ŚĻī„Āę„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŤĀĖŚúįŚģ£Ť®Ä„ā퍰ƄĀĄ„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŤĀĖŚúį„Äć„āíŚēÜś®ôÁôĽťĆ≤„Āó„Āü[81]„Äā„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Éě„ÉÉ„Éó„ĀģšĹúŤ£Ĺ„āĄ„āį„ÉÉ„āļŚĪēťĖč„āā„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[81]„ĀĽ„Āč„ÄĀ2021ŚĻī3śúą„Āę„ĀĮŚłāŚÜÖ„ĀģťĀď„ĀģťßÖ„Ā™„Ā©„ĀęÁČĻÁĒ£ŚďĀ„ĀģťėŅÁŅĀÁü≥„ĀßšĹú„āČ„āĆ„Āü„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āģ„ÉĘ„Éč„É•„É°„É≥„Éą„ā퍮≠ÁĹģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[82][81][ś≥®ťáą 11]„Äā2022ŚĻī3śúą„Āę„ĀĮŚźĆŚłā„ĀģśĚĺśĶ¶ť≠öŚłāŚ†ī„Āę„ÄĀ„ÉĎ„É≥Á≤Č„ā횼ė„ĀĎ„Ā¶ŚÜ∑Śáć„Āē„āĆ„ĀüÁä∂śÖč„Āģ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĆŤ≥ľŚÖ•„Āß„Āć„āčŤá™ŚčēŤ≤©Ś£≤ś©ü„ĀĆŤ®≠ÁĹģ„Āē„āĆ„Āü[84][85]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĮŚźĆŚłā„Āģ„ĀĶ„āč„Āē„Ā®ÁīćÁ®é„ĀģŤŅĒÁ§ľŚďĀ„Āę„āā„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč[86]„Äā„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„āíÁĒ®„ĀĄ„ĀüšłÄťÄ£„ĀģśīĽŚčē„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ť¶≥ŚÖČŚģĘ„ĀƜĕŚĘó„Āó[80]„ÄĀťē∑ŚīéÁúĆ„ĀģŤ¶≥ŚÖČśĆĮŤąą„ĀęŤ≤ĘÁĆģ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀśĚĺśĶ¶Śłā„ĀĮ2021ŚĻī2śúą„Āę„ÄĆÁúĆ„ÉĄ„Éľ„É™„āļ„Ɇ„ÉĽ„āĘ„ÉĮ„Éľ„ÉČ„Äć„ĀßśúÄťęė„Āģ„āį„É©„É≥„Éó„É™„ā팏óŤ≥ě„Āó„Āü[87]„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀ2021ŚĻī10śúą„Āę„ĀĮŚõĹŚúüšļ§ťÄöÁúĀ„ĀĆšłĽŚā¨„Āô„āč„ÄĆŚúįŚüü„Ā•„ĀŹ„ā䍰®ŚĹį„Äć„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ
„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„āíŚĻīťĖď500šłáśěöŤ≤©Ś£≤„Āó[89]„ÄĀ„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„āę„É≥„ÉĎ„Éč„Éľ„Äć„ā퍨≥„ĀÜť≥•ŚŹĖÁúĆŚĘÉśłĮŚłā„ĀģŤßíŚĪčť£üŚďĀ„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀŚļÉ„ĀŹśôģŚŹä„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āę„āāśčė„āČ„Āö„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŚúįšĹć„ĀĮťęė„ĀŹ„Ā™„ĀĄ[24]„Äā„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀŚźĆÁ§ĺ„Āß„ĀĮ„ÄĆÁčô„Ā£„Ā¶„Āĺ„Āô„ÄĀ„ā®„Éď„Éē„É©„ā§„ĀģŚļß„Äā„Äć„āí„ā≠„É£„ÉÉ„ÉĀ„ā≥„ÉĒ„Éľ„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŚúįšĹ挟Ϛłä„ĀꌏĖ„āäÁĶĄ„āď„Āß„ĀĄ„āč[24]„Äā„ĀĚ„ĀÜ„Āó„ĀüśīĽŚčē„ĀģšłÄÁíį„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀśľĘŚ≠ó„Āģ„ÄĆťĮĶÔľą„āĘ„āłÔľČ„Äć„ĀģśóĀ„ĀĆ„ÄĆŚŹā (3)„Äć„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„ÄĆ„Éē„É©„ā§„Äć„ĀģŤ™ěŚĎāŚźą„āŹ„Āõ„Āß„ÄĆ„Éē (2) „É©„ā§ (1)„Äć„Ā®Ť™≠„āĀ„āč„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀŚźĆÁ§ĺ„ĀĮ3śúą21śó•„āí„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āģśó•„Äć„Ā®„Āô„āč„Āď„Ā®„ā휏źŚĒĪ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ2022ŚĻī„Āęśó•śú¨Ť®ėŚŅĶśó•ŚćĒšľö„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ť®ėŚŅĶśó•„Ā®„Āó„Ā¶Ť™ćŚģö„Āē„āĆ„Āü[24]„Äā šĹúŚďĀŚÜÖ„Āß„ĀģśŹŹ„Āč„āĆśĖĻ„āĘ„āł„ĀĮ„ÄĀŚąĚŚ§Ź„Āč„āČŚ§Ź„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„ĀĆśó¨„Ā®„Āē„āĆ[90]„ÄĀšŅ≥ŚŹ•„Ā™„Ā©„Āß„ĀĮ„ÄĆťįļ„Äć„ĀĆŚ§Ź„ĀģŚ≠£Ť™ě„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč[44]„ÄāšŅ≥ŚŹ•„Āę„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ā퍩†„ĀŅŤĺľ„āď„Ā†šĺč„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆťļ¶„ĀģÁßč„ÄćÔľąŚ§Ź„ĀģŚ≠£Ť™ěԾȄāíŚ≠£ť°Ć„Ā®„Āó„Ā¶„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Āę„āĹ„Éľ„āĻ„āí„Āč„ĀĎ„āčśßėŚ≠ź„ā퍩†„āď„Ā†ŤĺĽś°ÉŚ≠ź„Āę„āą„ā茏•„ĀĆ„Āā„āč[91]„ÄāśłÖśįīŚď≤ÁĒ∑„Āę„āą„āĆ„Āį„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹ•„Āę„ĀĮ„ÄĆ„Āē„Āā„ÄĀť£ü„ĀĻ„āč„Āě„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜśįóśĆĀ„Ā°„ĀĆ„āą„ĀŹśŹŹ„Āč„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[91]„Äā „ā®„ÉÉ„āĽ„ā§„Āģť°ĆśĚź„Ā®„Āó„Ā¶„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀĆŚŹĖ„āäšłä„Āí„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āč„ÄāŚÜÖť§®ÁČߌ≠ź„ĀĮ„ÄĀŚÖ•ťôĘÁĒüśīĽ[ś≥®ťáą 12]„Āč„āČ„ĀģŚłįŤ∑Į„ĀęšĹē„ĀĆšłÄÁē™ť£ü„ĀĻ„Āü„ĀĄ„Āč„Ā®ŤÄÉ„Āą„Āü„Ā®„Āć„ÄĀśÄĚ„ĀĄśĶģ„Āč„āď„Ā†„Āģ„ĀĮ ÁČ©Ť™ě„ĀģŚįŹťĀďŚÖ∑„Ā®„Āó„Ā¶ÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„Āüšĺč„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ[95]„ÄĀÁ¶Źśú¨šľłŤ°Ć„ĀģśľęÁĒĽ„ÄéśúÄŚľ∑šľĚŤ™¨ťĽíś≤Ę„ÄŹ„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĀś•ĶÁęĮ„ĀęŚģČ„Ā£„ĀĹ„ĀŹ„āā„Ā™„ĀŹŤĪ™ŤŹĮ„Āô„Āé„Āę„āā„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„ĀģŚļ∂śįĎÁöĄ„Ā™šĹćÁĹģšĽė„ĀĎ„āíÁĒ®„ĀĄ„Āü„ā®„ÉĒ„āĹ„Éľ„ÉČ„ĀĆ„Āā„āč[96]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ÉČ„É©„Éě„ÄéŚ≠§Á訄Āģ„āį„Éę„É°„ÄŹSeason6[97]„ĀģÁ¨¨10Ť©Ī„Āß„ĀĮŚćÉŤĎČÁúĆŚĮĆśī•ŚłāťáĎŤį∑„Āģ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§Śģöť£ü„ĀĆŚŹĖ„āäšłä„Āí„āČ„āĆ„ÄĀśĒĺťÄĀŚĺĆ„Āę„ÄĆ„āĘ„āł„Éē„É©„ā§„Äć„ĀĆTwitter„Āģ„Éą„ɨ„É≥„ÉČ„ĀęŚÖ•„āč„ĀĽ„Ā©„ĀģŤ©Īť°Ć„āíŚĎľ„āď„Ā†[98]„Äā „āĘ„āł„Éē„É©„ā§ťĖĘťÄ£„Āģ„ā≠„É£„É©„āĮ„āŅ„Éľ
ŤĄöś≥®ś≥®ťáą
ŚáļŚÖł
ŚŹāŤÄÉśĖáÁĆģ
|
||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia