مƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€
مƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€ï¼ˆمƒپمƒ‡مƒ³م‚ˆمپڈم‚ٹم‚…مپ†مپکم‚‡م€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€èھ: Kamp Tjideng)مپ¯م€پ第ن؛Œو¬،ن¸–ç•Œه¤§وˆ¦ن¸م€پو—¥وœ¬è»چمپ«م‚ˆمپ£مپ¦م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€é کو±م‚¤مƒ³مƒ‰ï¼ˆçڈ¾هœ¨مپ®م‚¤مƒ³مƒ‰مƒچم‚·م‚¢ï¼‰مپ«ç½®مپ‹م‚Œمپںم€پو•µه›½ن؛؛ه¥³و€§مپ¨هگن¾›م‚’هڈژه®¹مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®وٹ‘ç•™و‰€مپ§مپ‚م‚‹م€‚ ه¤§و—¥وœ¬ه¸ه›½مپ¯1942ه¹´1وœˆ10و—¥مپ«م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€é کو±م‚¤مƒ³مƒ‰مپ¸مپ®ن¾µو”»م‚’é–‹ه§‹مپ—مپںم€‚و—¥وœ¬مپ«م‚ˆم‚‹هچ é کمپ¯1945ه¹´9وœˆمپ®çµ‚وˆ¦مپ¾مپ§ç¶ڑمپچم€پمپمپ®é–“م€پمƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘ç³»مپ®ن؛؛م€…مپ¯وٹ‘ç•™و‰€مپ«é€پم‚‰م‚Œمپںم€‚وٹ‘ç•™مپ•م‚Œمپںمپ®مپ¯ن¸»مپ«م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€ن؛؛مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پم‚¢مƒ،مƒھم‚«ن؛؛م€پم‚¤م‚®مƒھم‚¹ن؛؛م€پم‚ھمƒ¼م‚¹مƒˆمƒ©مƒھم‚¢ن؛؛م‚‚هگ«مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ه…ƒوٹ‘留者مپںمپ،مپ¯و—¥وœ¬مپ®وٹ‘ç•™و‰€م‚’م€Œه¼·هˆ¶هڈژه®¹و‰€م€چمپ‚م‚‹مپ„مپ¯م€Œو¶ˆو¥µçڑ„مپھ絶و»…هڈژه®¹و‰€م€چمپ¨è،¨çڈ¾مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پمپم‚Œمپ¯é£ںو–™م‚„هŒ»è–¬ه“پمپ®ه¤§è¦ڈو¨،مپ‹مپ¤ن¸€è²«مپ—مپںن¾›çµ¦هپœو¢مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پé•·وœںçڑ„مپ«ه¤ڑو•°مپ®هڈژه®¹è€…مپŒو»ن؛،مپ—مپںمپ“مپ¨مپ«èµ·ه› مپ—مپ¦مپ„م‚‹[1][2][3]م€‚ مƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€ مƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€مپ¯م€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€é کو±م‚¤مƒ³مƒ‰مپ®é¦–都مƒگم‚؟مƒ´م‚£م‚¢ï¼ˆçڈ¾هœ¨مپ®م‚¸مƒ£م‚«مƒ«م‚؟)مپ«ن½چç½®مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚ه¸‚مپ®è¥؟部م€پéƒٹه¤–مپ«مپ‚م‚‹مƒپمƒ‡مƒ³مپ®ن¸€éƒ¨مپŒمƒ•م‚§مƒ³م‚¹مپ§ه›²مپ¾م‚Œم€پمƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘ن؛؛مپ®ه¥³و€§مپ¨هگمپ©م‚‚مپںمپ،مپ®وٹ‘ç•™هœ°مپ¨مپ—مپ¦ن½؟用مپ•م‚Œمپںم€‚وˆگن؛؛ç”·و€§م‚„ه¹´é•·مپ®ه°‘ه¹´مپںمپ،مپ¯م€پن»–مپ®هڈژه®¹و‰€م€پن¸»مپ«ن؟ک虜هڈژه®¹و‰€مپ¸مپ¨ç§»é€پمپ•م‚Œمپںم€‚ه±…ن½ڈو–½è¨مپ¯م€پ瓦ه±‹و ¹مپ®مƒ¬مƒ³م‚¬é€ م‚ٹمپ®مƒگمƒ³م‚¬مƒمƒ¼مپ‹م‚‰م€پ竹م‚’用مپ„مپںن¼çµ±çڑ„مپھم‚¸مƒ£مƒ¯ه¼ڈمپ®ه°ڈه±‹مپ¾مپ§مپ•مپ¾مپ–مپ¾مپ§مپ‚مپ£مپں[4]م€‚ ه½“هˆم€پمƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€مپ¯و—¥وœ¬هپ´مپ«م‚ˆم‚ٹم€Œن؟è·هŒ؛م€چمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œم€پو°‘é–“ه½“ه±€مپ®ç®،çگ†ن¸‹مپ«ç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپںمپںم‚پم€پç”ںو´»ç’°ه¢ƒمپ¯مپ¾مپ è€گمپˆم‚‰م‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚مپ£مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—1944ه¹´4وœˆمپ«و—¥وœ¬مپ®è»چه½“ه±€مپŒç›´وژ¥ç®،çگ†م‚’ه¼•مپچ継مپگمپ¨م€پèھ؟çگ†م‚„礼و‹مپ®è¨±هڈ¯مپ¨مپ„مپ£مپں特و¨©مپ¯هچ³ه؛§مپ«ه‰¥ه¥ھمپ•م‚Œمپںم€‚é£ںن؛‹مپ®èھ؟çگ†مپ¯ن¸ه¤®é›†و¨©هŒ–مپ•م‚Œم€پé£ںن؛‹مپ®è³ھمپ¨é‡ڈمپ¯و€¥é€ںمپ«و‚ھهŒ–مپ—مپںم€‚ç”ںو´»ç’°ه¢ƒم‚‚و‚ھهŒ–مپ—م€پن¸‹و°´è¨ه‚™مپ¯ه£ٹم‚Œم€پ飢餓مپ¨ç—…و°—مپŒه؛ƒمپŒمپ£مپںم€‚هŒ»è–¬ه“پم‚„و²»ç™‚مپŒن¸€هˆ‡وڈگن¾›مپ•م‚Œمپھمپ‹مپ£مپںمپںم‚پم€پو»ن؛،者و•°مپ¯ه¢—هٹ مپ—مپںم€‚و„ںوں“ç—‡م‚„و „é¤ٹه¤±èھ؟مپ«م‚ˆم‚‹و»ن؛،مپ¯و—¥ه¸¸çڑ„مپھه‡؛و¥ن؛‹مپ¨مپھمپ£مپںم€‚  و™‚é–“مپ®çµŒéپژمپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€پو—¥وœ¬è»چمپ¯مƒپمƒ‡مƒ³هڈژه®¹و‰€مپ®و•·هœ°م‚’ن½•ه؛¦م‚‚縮ه°ڈمپ—مپ¦مپ„مپ£مپںمپŒم€پمپمپ®ن¸€و–¹مپ§هڈژه®¹و‰€مپ«مپ¯مپ¾مپ™مپ¾مپ™ه¤ڑمپڈمپ®ه›ڑن؛؛م‚’هڈژه®¹مپ™م‚‹م‚ˆمپ†ه¼·هˆ¶مپ—مپںم€‚ه½“هˆم€پهڈژه®¹مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپ®مپ¯ç´„2,000ن؛؛مپ®ه¥³و€§مپ¨هگن¾›مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پوˆ¦ن؛‰وœ«وœںمپ«مپ¯ç´„10,500ن؛؛مپ«مپ¾مپ§ه¢—هٹ مپ—مپںم€‚ن¸€و–¹م€پهڈژه®¹و‰€مپ®é¢ç©چمپ¯ه…ƒمپ®4هˆ†مپ®1مپ«مپ¾مپ§و¸›م‚‰مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ç©؛مپ„مپ¦مپ„م‚‹م‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹مپ¯مپ™مپ¹مپ¦ه¯و‰€مپ¨مپ—مپ¦ن½؟م‚ڈم‚Œم€پن½؟用مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„هڈ°و‰€م‚„و°´مپ®ه‡؛مپھمپ„وµ´ه®¤مپ¾مپ§م‚‚مپŒه¯ه؛ٹمپ«ه……مپ¦م‚‰م‚Œمپںم€‚ 1944ه¹´4وœˆمپ‹م‚‰1945ه¹´6وœˆمپ¾مپ§م€پمƒپمƒ‡مƒ³هڈژه®¹و‰€مپ¯و›½و ¹و†²ن¸€ه¤§ه°‰مپ®وŒ‡وڈ®ن¸‹مپ«ç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚و›½و ¹مپ¯ه¤ڑمپڈمپ®و®‹è™گè،Œç‚؛مپ®è²¬ن»»è€…مپ§مپ‚م‚ٹم€پé£ں糧é…چ給مپ®ه‰ٹو¸›م€په¥³و€§مپںمپ،مپ®é«ھمپ®ه¼·هˆ¶çڑ„مپھه‰ƒé«ھمپ¨وڑ´è،Œم‚’ه‘½مپکمپںم€‚مپ¾مپںم€په¥³و€§م‚„هگن¾›م€پç—…ن؛؛م‚’ç‚ژه¤©ن¸‹مپ«ن½•و™‚é–“م‚‚ç«‹مپںمپ›م‚‹م€Œم‚¯مƒ³مƒ—مƒ©مƒ³ï¼ˆç‚¹ه‘¼ï¼‰م€چم‚’組織مپ—مپںم€‚وˆ¦ه¾Œم€په½¼مپ¯é€®وچ•مپ•م‚Œم€پ1946ه¹´9وœˆ2و—¥مپ«و»هˆ‘هˆ¤و±؛م‚’هڈ—مپ‘مپںم€‚وپ©èµ¦م‚’و±‚م‚پم‚‹هک†é،کمپ¯م€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ®ه‰¯ç·ڈç£مƒ•مƒ¼مƒ™مƒ«مƒˆم‚¥م‚¹مƒ»مƒ•م‚،مƒ³مƒ»مƒ¢مƒ¼م‚¯ï¼ˆHubertus van Mook)مپ«م‚ˆمپ£مپ¦هچ´ن¸‹مپ•م‚Œمپںم€‚مƒ¢مƒ¼م‚¯مپ®ه¦»م‚‚مپ¾مپںو›½و ¹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦وٹ‘ç•™مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚و»هˆ‘مپ¯هگŒه¹´12وœˆ7و—¥م€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€è»چمپ®éٹƒو®؛éڑٹمپ«م‚ˆمپ£مپ¦هں·è،Œمپ•م‚Œمپں[5][6]م€‚ é•·ه´ژمپ¨ه؛ƒه³¶مپ¸مپ®هژں爆وٹ•ن¸‹مپ®ه¾Œم€پو—¥وœ¬مپ¯1945ه¹´9وœˆ2و—¥مپ«é™چن¼ڈمپ—مپںم€‚9وœˆ16و—¥م€په›½éڑ›èµ¤هچپه—社مپ¯مƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€مپ«مپ„مپںه¥³و€§مپںمپ،مپ®وک هƒڈè¨ک録م‚’و’®ه½±مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®وک هƒڈمپ¯هگŒه¹´12وœˆمپ®ç¬¬1週مپ«م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ®وک 画館مپ§مƒمƒھم‚´مƒ¼مƒ³مƒ»مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ¨مپ—مپ¦ن¸ٹوک مپ•م‚Œم€پوˆ¦ه¾Œم€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ§هˆم‚پمپ¦ه…¬é–‹مپ•م‚Œمپںم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€é کو±م‚¤مƒ³مƒ‰مپ«é–¢مپ™م‚‹وک هƒڈمپ¨مپھمپ£مپں[7][8]م€‚ مƒھمƒ¼مƒ‰ï¼م‚³مƒھمƒ³م‚؛ن¸ن½گمپ«م‚ˆم‚‹ه ±ه‘ٹو›¸é€£هگˆè»چمپ®مƒھمƒ¼مƒ‰ï¼م‚³مƒھمƒ³م‚؛ن¸ن½گمپ¯و—¥وœ¬مپ®é™چن¼ڈه¾Œمپ«مپ“مپ®وٹ‘ç•™و‰€مپ«هˆ°ç€مپ—مپںéڑ›م€په›ڑن؛؛مپںمپ،مپ®çٹ¶و³پم‚’ç›´وژ¥ç›®مپ®ه½“مپںم‚ٹمپ«مپ—مپںم€‚م‚³مƒھمƒ³م‚؛مپ®è¦³ه¯ںه†…ه®¹مپ¯م€پمƒ‹مƒ¥مƒ«مƒ³مƒ™مƒ«م‚¯è£پهˆ¤مپٹم‚ˆمپ³و±ن؛¬è£پهˆ¤مپ®و³•ه‹™é،§ه•ڈم‚’ه‹™م‚پمپںم‚¨مƒ‰مƒ¯مƒ¼مƒ‰مƒ»مƒ©مƒƒم‚»مƒ«ç”·çˆµمپ«م‚ˆم‚‹è‘—و›¸م€ژThe Knights of Bushido: A History of Japanese War Crimes During World War IIم€ڈمپ«è¨ک録مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[9]م€‚ م‚³مƒھمƒ³م‚؛مپ¯م€پمپ»مپ¨م‚“مپ©مپ®ه¥³و€§مپŒمپ»مپ¨م‚“مپ©م€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯ه…¨مپڈو„ںوƒ…م‚’ç¤؛مپ•مپھمپ‹مپ£مپںمپ¨ه ±ه‘ٹمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ه½¼مپ¯مپ¾مپںم€پم€Œن¸چهپ¥ه؛·مپھé’白مپ•م€چم‚’ه¸¯مپ³مپںç—©مپ›ç´°مپ£مپںهگمپ©م‚‚مپںمپ،م‚’ç›®مپ«مپ—مپںم€‚ه½¼مپŒè¦–ه¯ںمپ—مپںمپ™مپ¹مپ¦مپ®هڈژه®¹و‰€مپ®ن¸مپ§م€پمƒپمƒ‡مƒ³مپ®ه¥³و€§وٹ‘ç•™و‰€مپŒوœ€م‚‚مپ²مپ©مپ„م‚‚مپ®مپ§مپ‚مپ£مپںمپ¨è؟°مپ¹مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ه½¼مپ¯م€پم‚مƒ£مƒ³مƒ—ه†…مپ®çٹ¶و³پمپ¨مپ¯ه¯¾ç…§çڑ„مپ«م€پمƒگم‚؟مƒ´م‚£م‚¢مپ§مپ¯é£ں糧ن¸چ足مپŒè¦‹م‚‰م‚Œمپھمپ‹مپ£مپںمپ“مپ¨م‚’وŒ‡و‘کمپ—مپںم€‚
ه®¶و—ڈمپ®ه†چن¼ڑ解و”¾ه¾Œم€پو—¥وœ¬مپ®هٹ´هƒچهڈژه®¹و‰€م‚’ç”ںمپچه»¶مپ³مپںç”·و€§مپںمپ،مپ¯م€پè‡ھهˆ†مپںمپ،مپ®ه¦»م‚„هگمپ©م‚‚مپںمپ،م‚’وژ¢مپ—مپ¦م‚„مپ£مپ¦و¥مپںم€‚مپ‚م‚‹ه¤«ه©¦مپ¯ه†چن¼ڑمپ®و§کهگم‚’و¬،مپ®م‚ˆمپ†مپ«èھمپ£مپ¦مپ„م‚‹[10]ï¼ڑ
مپمپ®ه¾Œ و—¥وœ¬مپ®é™چن¼ڈه¾Œم€پوڑ´هٹ›çڑ„مپھم€Œمƒ™مƒ«م‚·م‚¢مƒ—(Bersiap)م€چو™‚وœںمپŒه§‹مپ¾مپ£مپںم€‚م€Œمƒ™مƒ«م‚·م‚¢مƒ—م€چمپ¨مپ¯م‚¤مƒ³مƒ‰مƒچم‚·م‚¢èھمپ§م€Œو؛–ه‚™مپ›م‚ˆم€چم€Œç”¨و„ڈمپ›م‚ˆم€چم‚’و„ڈه‘³مپ™م‚‹è¨€è‘‰مپ§مپ‚م‚‹م€‚و¨©هٹ›مپ®ç©؛白çٹ¶و…‹مپ®ن¸مپ§م€پم‚¹م‚«مƒ«مƒژمپ¯1945ه¹´8وœˆ17و—¥مپ«م‚¤مƒ³مƒ‰مƒچم‚·م‚¢ç‹¬ç«‹ه®£è¨€م‚’ç™؛è،¨مپ—م€پم‚¤مƒ³مƒ‰مƒچم‚·م‚¢ç‹¬ç«‹وˆ¦ن؛‰مپŒه§‹مپ¾مپ£مپںم€‚مپ“مپ®و··ن¹±مپ®مپھمپ‹مپ§م€په¤ڑمپڈمپ®مƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘ç³»مپٹم‚ˆمپ³مƒ¦مƒ¼مƒ©م‚·م‚¢مƒ³مپ®ن؛؛م€…مپŒçڈ¾هœ°م‚¤مƒ³مƒ‰مƒچم‚·م‚¢ن؛؛مپ«م‚ˆمپ£مپ¦و®؛ه®³مپ•م‚Œمپںم€‚مƒ™مƒ«م‚·م‚¢مƒ—مپ«م‚ˆم‚‹م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€ن؛؛و°‘é–“ن؛؛مپ®و»è€…و•°مپ¯وژ¨ه®ڑمپ§3,500ن؛؛مپ‹م‚‰30,000ن؛؛مپ«مپ®مپ¼م‚‹مپ¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ“مپ®و™‚وœںم€پمپ‹مپ¤مپ¦مپ®و—¥وœ¬مپ®وچ•è™œهڈژه®¹و‰€مپ¯م€پوڑ´ه¾’هŒ–مپ—مپںçٹ¶و³پمپ‹م‚‰éپ؟難مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه®‰ه…¨هœ°ه¸¯مپ¨مپ—مپ¦و©ں能مپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپں[11][12][13]م€‚ 1945ه¹´12وœˆم€پو—¥وœ¬مپ®هڈژه®¹و‰€مپ‹م‚‰مپ®ç”ں還者3,800ن؛؛(مپ†مپ،1,200ن؛؛مپ¯هگمپ©م‚‚)مپŒم€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ¸مپ®وœ¬ه›½é€پé‚„مپ®مپںم‚پSSمƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¢مƒ م‚¹مƒ†مƒ«مƒ€مƒ هڈ·مپ«ن¹—船مپ—مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پé•·ه¹´مپ«م‚ڈمپںم‚‹هڈژه®¹ç”ںو´»مپ®ه½±éں؟مپ§هگمپ©م‚‚مپںمپ،مپ¯و¥µه؛¦مپ«è،°ه¼±مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پ船ن¸ٹمپ§é؛»ç–¹مپŒç™؛ç”ںمپ—مپںم€‚و„ںوں“مپ¯ه؛ƒمپŒم‚ٹم€په¤ڑمپڈمپ®هگمپ©م‚‚مپŒه‘½م‚’èگ½مپ¨مپ—مپںم€‚ن؛،مپڈمپھمپ£مپںهگمپ©م‚‚مپںمپ،مپ¯وµ·è‘¬مپ•م‚Œمپںم€‚ 1949ه¹´12وœˆ27و—¥م€پم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€ه¥³çژ‹مƒ¦مƒھم‚¢مƒٹمپ¯م€پم‚¤مƒ³مƒ‰مƒچم‚·م‚¢مپ¸مپ®ن¸»و¨©ç§»è²و،ç´„مپ«ç½²هگچمپ—مپں[14]م€‚ م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€وœ¬ه›½مپ¸مپ®é€پé‚„ م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€é کو±م‚¤مƒ³مƒ‰مپ‹م‚‰مپ®ç§»و°‘مپ®ه¤ڑمپڈمپ¯م€پمپم‚Œمپ¾مپ§ن¸€ه؛¦م‚‚م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€وœ¬ه›½م‚’è¨ھم‚Œمپںمپ“مپ¨مپŒمپھمپ‹مپ£مپںم€‚ه½¼م‚‰مپ¯م€پو—¥وœ¬هچ é کوœںمپ«è²،産م‚’ه¤±مپ£مپںمپ‹م€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯ه¼•مپچوڈڑمپ’مپ®éڑ›مپ«و‰€وœ‰ç‰©م‚’çڈ¾هœ°مپ«و®‹مپ—مپ¦مپچمپ¦مپ„مپںم€‚وˆ¦ه¾Œمپ®م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ¯م€پو·±هˆ»مپھن½ڈه®…ن¸چ足مپ¨ه¤±و¥ه•ڈé،Œمپ«ç›´é¢مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پن¸€éƒ¨مپ®و±م‚¤مƒ³مƒ‰ه‡؛è؛«è€…مپ¯م€پمƒ´م‚§م‚¹مƒ†مƒ«مƒœمƒ«م‚¯é€ڑéپژهڈژه®¹و‰€مپھمپ©م€پ第ن؛Œو¬،ه¤§وˆ¦ن¸مپ®ه¼·هˆ¶هڈژه®¹و‰€مپ«ن¸€و™‚çڑ„مپ«هڈژه®¹مپ•م‚Œمپںم€‚م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€و”؟ه؛œمپ¯ه½“هˆم€پو±م‚¤مƒ³مƒ‰مپ‹م‚‰مپ®ç§»و°‘م‚’وٹ‘هˆ¶مپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپںمپŒم€پو±م‚¤مƒ³مƒ‰çڈ¾هœ°مپ®çٹ¶و³پو‚ھهŒ–مپ«ن¼´مپ„م€پهژ³و ¼مپھو،ن»¶مپ®م‚‚مپ¨مپ§هڈ—مپ‘ه…¥م‚Œم‚’é–‹ه§‹مپ—مپںم€‚و—¥وœ¬è»چمپ«م‚ˆم‚‹هڈژه®¹و‰€ن½“験م‚„مƒ™مƒ«م‚·م‚¢مƒ—وœںمپ®وڑ´هٹ›مپ«م‚ˆم‚‹مƒˆمƒ©م‚¦مƒمپ¯م€پ社ن¼ڑçڑ„مپ«م‚‚ه®¶ه؛ه†…مپ§م‚‚مپ»مپ¨م‚“مپ©èھم‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپھمپ‹مپ£مپں[15][16][17]م€‚ و–‡ه¦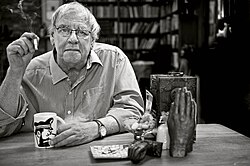 م‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ®ن½œه®¶م‚¤م‚¨مƒ«مƒ¼مƒ³مƒ»مƒ–مƒ©م‚¦مƒ¯مƒ¼م‚؛(Jeroen Brouwers)مپ¯م€پ1986ه¹´مپ®è‡ھن¼çڑ„ه°ڈèھ¬م€ژمپ†م‚ڈمپڑمپ؟مپ®èµ¤ï¼ˆهژںé،Œï¼ڑBezonken Rood)م€ڈمپ«مپٹمپ„مپ¦م€په½¼è‡ھè؛«مپŒوٹ‘ç•™و‰€مپ§éپژمپ”مپ—مپںه°‘ه¹´و™‚ن»£مپ®ن½“験مپ¨م€پمپم‚ŒمپŒه¾Œمپ®ن؛؛ç”ںمپ«هڈٹمپ¼مپ—مپںه½±éں؟م‚’وڈڈمپ„مپ¦مپ„م‚‹م€‚1995ه¹´مپ«مپ¯مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹èھ訳مپŒمƒ•م‚§مƒںمƒٹè³م‚’هڈ—è³مپ—مپںم€‚ م‚¯مƒ©مƒ©مƒ»م‚ھمƒھمƒ³م‚¯مƒ»م‚±مƒھمƒ¼ï¼ˆClara Olink Kelly)مپ®2003ه¹´مپ®è‘—و›¸م€ژمƒ•مƒ©مƒ³مƒœمƒ¤مپ®وœ¨ï¼ˆThe Flamboya Tree)م€ڈمپ¨م€پمƒœم‚¦مƒ‰م‚¦م‚§م‚¤مƒ³مƒ»مƒ•م‚،مƒ³مƒ»م‚ھمƒ¼مƒ«مƒˆï¼ˆBoudewijn van Oort)مپ®2008ه¹´مپ®è‘—ن½œم€ژمƒپمƒ‡مƒ³مپ§مپ®ه†چن¼ڑ(Tjideng Reunion)م€ڈمپ§مپ¯م€پè‡ھè؛«مپ®ه®¶و—ڈمپ¨مپ¨م‚‚مپ«مƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€مپ§éپژمپ”مپ—مپںو—¥م€…مپ¨مپمپ®هٹ£و‚ھمپھç’°ه¢ƒمپ«مپ¤مپ„مپ¦ç¶´م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مƒ•م‚،مƒ³مƒ»م‚ھمƒ¼مƒ«مƒˆمپ®è‘—ن½œمپ§مپ¯م€پوٹ‘ç•™و‰€ç”ںو´»مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په½“و™‚مپ®è»چن؛‹çڑ„مƒ»ه¤–ن؛¤çڑ„背و™¯مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚詳è؟°مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚م‚¢مƒ³مƒھمƒ»م‚·مƒ£مƒ«مƒ«مƒ»م‚·مƒ¥مƒںمƒƒمƒˆï¼ˆHenri Charles Schmid)مپ¯2014ه¹´مپ®è‘—و›¸م€ژScattered Journeyم€ڈمپ§م€پمƒپمƒ‡مƒ³وٹ‘ç•™و‰€مپ«هڈژه®¹مپ•م‚Œمپںو¯چè¦ھمپ®ç”ںو´»م‚’ه›é،§çڑ„مپ«وڈڈمپ„مپ¦مپ„م‚‹م€‚مƒمƒ“مƒ¼مƒچمƒ»م‚¢مƒ³مƒ‰مƒ©م‚¦ï¼ˆRobine Andrau)مپ¯و¯چè¦ھمپ¨ه…±è‘—مپ§2015ه¹´مپ«م€ژBowing to the Emperor: We Were Captives in WWII(çڑ‡ه¸مپ«é م‚’ن¸‹مپ’مپ¦ï¼ڑç§پمپںمپ،مپ¯ç¬¬ن؛Œو¬،ه¤§وˆ¦ن¸مپ®وچ•è™œمپ مپ£مپں)م€ڈم‚’ç™؛è،¨مپ—م€پو¯چه¨کمپ®هڈژه®¹و‰€ن½“験مپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€پ父è¦ھمپŒو—¥وœ¬مپ§وچ•è™œمپ¨مپ—مپ¦éپژمپ”مپ—مپں経験م‚‚وڈڈمپ„مپ¦مپ„م‚‹[18][19]م€‚
وٹ‘ç•™مپ•م‚Œمپںم‚ھمƒ©مƒ³مƒ€مپ®è‘—هگچن؛؛
هڈ‚考و–‡çŒ®
é–¢é€£é …ç›®
ه¤–部مƒھمƒ³م‚¯
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia














