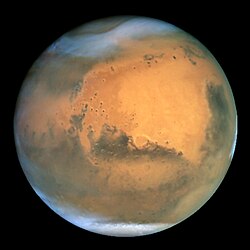パンカム  パノラミック・カメラ(ぱのらみっくかめら、英語: Panoramic Camera)、または略してパンカム(ぱんかむ、英語: Pancam)は、火星探査車(MER)のスピリットおよびオポチュニティに搭載された、2台1組で動作するステレオカメラシステムである[2]。それぞれのカメラに8つのフィルター・スロットを持つホイール・アセンブリが備わっており、異なる波長域の光を撮影できる。パンカム・マスト・アセンブリ(PMA)上のカメラ・バー両端(2台のナビカムの外側)にそれぞれ1台のカメラが据え付けられ、Mini-TESと連携して探査車周囲の撮影に使われた[2][3]。 パンカムは、人間の目の3倍に相当する300マイクロラジアンの角分解能を有している[4] 。2台のカメラを使用することで立体映像を生成し、10ギガビット(非圧縮時)を超える巨大な火星のパノマラを作成できる[4]。火星探査車スピリットは、火星に降り立った2004年時点で、それまでに地球以外の惑星表面で撮影されたものとしては、最高の解像度を持つ画像を撮影した[5]。 光学系パンカムに搭載されているレンズは3枚3群のクック・トリプレット方式、焦点距離43mmである。絞りはf/20固定となっており、無限遠から1.5メートルまで、被写界深度が広くとれる。視野角(FOV)は縦横ともに16度、対角で22.5度であり、35mmフルサイズカメラに109mmの中望遠レンズを装着した場合に近い[6]。2台のカメラは30cm間隔で設置され、マスト内のスペースの都合で2台の上下が反対となる格好で取り付けられている[2]。 イメージセンサーパンカムは1024 x 2048ピクセルのフレーム転送型CCDセンサー(FT-CCD)を使用している。これは、火星探査車に搭載された他のカメラと共通のセンサー(素子)である。素子の半分は読み出し用の蓄積領域として使用するため、露光しないようシールドされている。また、センサーは前面照射型で、反射防止コーティングやUVコーティングは施されていない。メーカーはMitec(現テレダイン・ダルサ)[6]。 信号処理デバイスActel製FPGAのRT1280が信号に関わる処理のすべてを担当し、CCDの出力を12ビット信号にAD変換するほか、他の処理も行う[6]。 フィルターパンカムの左右2台のカメラには、それぞれ8つのスロット(L1~L8、R1~R8)を持つフィルターホルダーが前面に取り付けられている。左のL1スロットにはフィルターが装着されていない(波長739nmを中心とする広域の光が通過する)。左側のL2からL8は、順番に波長753nm、673nm、601nm、535nm、482nm、432nm、440nmの狭帯域パスフィルターが装着されている。右側はR1から順番に436nm、754nm、803nm、864nm、904nm、934nm、1009nm、880nmのフィルターが装着されている。L8およびR8は太陽を直接撮影するためのNDフィルターである。全16スロットのうち、L1、L8、R8を除く13スロットが近赤外線から近紫外線の波長域をカバーし、火星の地質調査用撮影に活用される[7]。また、左右の両側に440nm付近(L7、R1)および750nm付近(L2、R2)のフィルターが用意されており、これらのフィルターを使うことで二色ステレオ映像が得られるようになっている。[6]。各フィルターホイールはステッピングモーター駆動で回転させる。 校正用ターゲット 探査車には、カメラシステムの一部として校正用ターゲットも搭載されている。このターゲットにはいくつかの領域が設けられている。火星の空を反映するように磨かれた領域のほか、内側から順に20%、40%および60%のグレーチャート領域と、四隅に赤、黄、緑および青の色ターゲットが置かれている。色ターゲットは、色を出すための素材にそれぞれ赤鉄鉱、針鉄鉱、酸化クロムおよびアルミン酸コバルトが用いられている[6]。この校正用ターゲットは、日時計アセンブリの一部でもある。 関連項目脚注
外部リンク |
Portal di Ensiklopedia Dunia