µ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπü«σÂìσ┐£µ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπü«σÂìσ┐£πü»πâ¢πéªτ┤áσÃÓσ¡Éπü½τ╡ÉσÉêπüùπüªπüãπé͵▒éµá╕µÇºπü«Θ½Ìπüãσ«ÌΦâ╜σÓ║πüÔµ▒éΘ¢╗σ¡ÉτÜãπü¬τé¡τ┤áπéȵõ╗µÈâπüÕπéÍπüôπü¿πüºΦ╡╖πüôπéÍπÇé╬▒,╬▓-Σ╕ìΘú╜σÈÔπâ¢πéªΘà╕σíÒπéã╬▒Σ╜ìπü½Φã▒Θ¢óσÓ║πéȵÔüπüúπüÓπâ¢πéªΘà╕σíÒπü»σêÁσ¡ÉσÁà1,2-πé╖πâòπâêπü½πéêπüúπüªµ£ÊµÒÓσÓ║πüÔπâ¢πéªτ┤áπüÍπéʵ▒éΘ¢╗σ¡ÉµÇºπü«Θ½Ìπüã╬▒Σ╜ìτé¡τ┤áπü½τº╗σÍòπüùπéãπüÕπüãπÇ鵣ʵÒÓπâ£πâÒπâ│σÔÚσÉêτÊÒπéÈΘà╕σÔÚπéãπâùπâ¡πâêπâÃπâ¬πé╖πé╣πüÕπéÍπüôπü¿πüºπéóπâ½πé│πâ╝πâ½πéãπé½πâ½πâ£πâÍπâ½σÔÚσÉêτÊÒπÇüπéóπâ½πé▒πâ│πÇüπâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚτÊÒπü¬πüÒπüÔσÉêµêÉπüºπüìπéÍ[1]πÇé µªéΦªüµ£ÊµÒÓπâ£πâÒπâ│(Σ╕ÇΦê¼σ╝ÂR3B)πéãπÇüµ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áπéñπé¬πâ│∩╝êΣ╕ÇΦê¼σ╝ÂR4BΓêÈπüºΦí¿πüòπéÔπÇüR3Bπü½RΓêÈπüÔΣ╗Ìσèáπüùπüªσ╛ùπéÊπéÔπéÍ∩╝Êπü»τé¡τ┤á-πâ¢πéªτ┤áτ╡ÉσÉêπéÈπééπüíπÇüπüÙπü«τ╡ÉσÉêπü»τé¡τ┤áπü½σêÁµÑ╡πüùπüªπüãπéÍπÇéπüùπüÓπüÔπüúπüªπÇüτé¡τ┤áπü»πâ¢πéªτ┤áπü½µ▒éµá╕τÜãπü½τ╡ÉσÉêπüùπüªπüèπéè[2]πÇüπâ¢πéªτ┤áπéñπé¬πâ│πüºπü»µ£ÊµÒÓσÓ║(R)πü«πüÁπüíπü«Σ╕ÇπüñπüÔσêÁσ¡ÉσÁàπüºµ▒éΘ¢╗σ¡ÉτÜãπü¬τé¡τ┤áπü½τ╡ÉσÉêπüÕπéÍπÇéπüôπü«σÂìσ┐£πü»σêÁσ¡ÉσÁàπüºΦ╡╖πüôπéÍπüôπü¿πüÔσñÜπüÂπÇüπüÙπü«σá┤σÉêµ▒éµá╕µÇºπü«Θ½Ìπü㵣ʵÒÓσÓ║πüÔ1,2-Φ╗óΣ╜ìπüùπüªπâ¢πéªτ┤áπü½τ╡ÉσÉêπüùπüÓµ▒éΘ¢╗σ¡ÉµÇºπü«Θ½Ìπüãτé¡τ┤áπü½τ╡ÉσÉêπüÕπéÍ[3]πÇéτõÓπüÌπüÓπâ£πâÒπâ│πü»Θà╕σÔÚπü╛πüÓπü»σèáµ░┤σêÁΦºúπüòπéÔπÇüτ¢«τÜãτÊÒπü╕πü¿σñÊσÔÚπüÕπéÍπÇéΣ╕Íπü«σ¢│πü½σÂìσ┐£πü«Σ╛ÍπéÈτñ║πüùπüÓπÇé (1)  πéóπâ½πé▒πâ│πüèπéêπü│πéóπâ½πé¡πâ│πü«πâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπü»πâ£πâÒπâ│πü«σÉêµêÉπü½µ£Êτõ¿πü¬σÂìσ┐£πüºπüéπéÍπÇéπüùπüÍπüùπâ£πâÒπâ│(BH3)πü¬πüãπüùπüÙπü«τ¡ÊΣ╛íΣ╜ôπéÈΣ╜┐πüúπüÓσá┤σÉêπÇüΘà╕σÔÚπüèπéêπü│σèáµ░┤σêÁΦºúπüùπüªπééσàâπü«πé¬πâ¼πâòπéúπâ│πü«33%πüùπüÍσñʵ¢πüòπéÔπüÜπÇüσñÜπüÂπüÔπâ¢πéªτ┤áπéÈσɽπéÇσÊ»τõÓµêÉτÊÒπü¿πü¬πéÍπÇéΘçÂΦ½ÚΘçÂπü«9-BBNπéÈπâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚΦÒªΦÚ¼πü¿πüùπüªτõ¿πüãπéÍπüôπü¿πüºπüôπü«σòÂΘíÔπéÈΦºúµ▒║πüºπüìπéÍ[4]πÇé σÂìσ┐£µÒÓµºÍπü¿τ½ÍΣ╜ôσÔÚσ¡ªΣ╕ÇΦê¼τÜãπü¬σÂìσ┐£µÒÓµºÍπâ£πâÒπâ│Θí₧πü»σìÌτͼπüºπü»µ▒éµá╕µÇºπüÔΣ╜ÃπüãπüÓπéüπéóπâ½πé¡πâ½σÓ║πéȵ▒éΘ¢╗σ¡ÉΣ╕¡σ┐âπü½τº╗σÍòπüòπü¢πéÍπüôπü¿πüÔπüºπüìπü¬πüãπÇéπüùπüÍπüùµ▒éµá╕σÊñπü½πéêπé͵õ╗µÈâπéÈσÂùπüÀπüªτõÓµêÉπüùπüÓπâ¢πéªΘà╕σíÒπü»µ▒éµá╕µÇºπüÔΘ½Ìπüã[3]πÇéµ▒éµá╕σÊñπü«╬▒Σ╜ìπü½Σ╕ìΘú╜σÈÔπü¬σ«ÌΦâ╜σÓ║πéãΦã▒Θ¢óσÓ║πüÔτ╡ÉσÉêπüùπüªπüãπüÓσá┤σÉêπÇüπéóπâ½πé¡πâ½σÓ║πü«Σ╕ÇπüñπüÔπâ¢πéªτ┤áπü½τ╡ÉσÉêπüùπÇüπéóπâ½πé¡πâ½σÓ║πü«Φ▓áΘ¢╗Φì╖πéÈσ«Êσ«ÜσÔÚπüÕπéÍΦâ╜σè¢πüÔΘ½ÌπüÀπéÔπü░µ▒éΘ¢╗σ¡ÉµÇºπü«Θ½Ìπüã╬▒τé¡τ┤áπü╕πü«Φ╗óΣ╜ìπüÔΦ╡╖πüôπéÍπÇéπéóπâ½πé¡πâ½σÓ║πü«Φ▓áΘ¢╗Φì╖σ«Êσ«ÜσÔÚΦâ╜πü»Σ╗ÑΣ╕Íπü«πéêπüÁπü¬ΘáÁπü½πü¬πüúπüªπüãπéÍ πéóπâ½πé¡πâÍπâ½ > πéóπâ¬πâ╝πâ½ ΓÊê πéóπâ½πé▒πâÍπâ½ > 1τ┤Üπéóπâ½πé¡πâ½ > 2τ┤Üπéóπâ½πé¡πâ½ > 3τ┤Üπéóπâ½πé¡πâ½[5]πÇéΦ╗óΣ╜ìσÂìσ┐£πü«ΘÜ¢πü»Φ╗óΣ╜ìσàâπü¿πü¬πéÍτé¡τ┤áπüºπü»σàâπü«τ½ÍΣ╜ôσÔÚσ¡ªπüÔΣ┐ÙµÔüπüòπéÔπéÍ[6]πüÔπÇü Φ╗óΣ╜ìσàêπü«τé¡τ┤áπüºπü»τ½ÍΣ╜ôσÔÚσ¡ªπüÔσÂìΦ╗óπüÕπéÍ∩╝êΦ╗óΣ╜ìσàêπü«τé¡τ┤áπüÔsp3µ╖╖µêÉπüáπüúπüÓσá┤σÉê∩╝Ê[7]πÇéπâôπé╣(πâÃπâ½πâ£πâ½πâÍπâ½)πâ£πâÒπâ│πüèπéêπü│9-BBNπü»πâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπü½πüèπüÀπéÍπâÇπâÓπâ╝σ«ÌΦâ╜σÓ║πü¿πüùπüªτõ¿πüãπéÊπéÔπéÍπÇéπâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπüùπüÓπé¬πâ¼πâòπéúπâ│πüÍπéÊσ╛ùπéÊπéÔπéÍπéóπâ½πé¡πâ½σÓ║πü«πü┐πüÔµ▒éµá╕σÊñπü¿πüùπüªµ┤╗µÇºπéȵÔüπüñπÇé (2)  ╬▒-πâÂπâ¡πé¿πâÃπâÒπâ╝πâêπü»µ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπüÔΘÚóπéÂπéÍσÂìσ┐£πü½πüèπüãπüªσ╣àσ║âπüÂτõ¿πüãπéÊπéÔπé͵▒éµá╕σÊñπüºπüéπéÍπÇéπâ¢πéªτ┤áπü½µ▒éµá╕µõ╗µÈâπüùπüªτõÓµêÉπüÕπéÍπé▒πâêπâ£πâ¡πâ│Θà╕σíÒπü»Φ╗óΣ╜ìπüùπüªΣ╕¡µÇºπü«πé¿πâÃπâ╝πâ½πâ£πâÒπâ│πü½πü¬πéÍπÇéπüôπéÔπéÈσèáµ░┤σêÁΦºúπüÕπéÍπüôπü¿πüºπé½πâ½πâ£πâÍπâ½σÓ║πéȵÔüπüúπüÓσÔÚσÉêτÊÒπüÔσ╛ùπéÊπéÔπéÍ[8]πÇéσÂìσ┐£Σ╕¡ΘÚôΣ╜ôπü«πé¿πâÃπâ╝πâ½πâ£πâÒπâ│πü»µ▒éΘ¢╗σ¡ÉσÊñπüºπé»πé¿πâ│πâüπüòπéÔπéÍπÇé (3)  πéóπâ½πé¡πâÍπâ½πâ£πâÒπâ│πü»πéóπâ½πé¡πâ│πü╕πü«µõ╗µÈâπü¿Φ╗óΣ╜ìπüÔσÉÔµÕéπü½Φ╡╖πüôπéÍπüÓπéüπÇüπé▒πâêπâ│πâ╗πé¬πâ¼πâòπéúπâ│πüãπüÜπéÔπü½πééσñʵ¢πüºπüìπé͵£Êτõ¿πü¬Σ╕¡ΘÚôΣ╜ôπüºπüéπéÍπÇéτõÓµêÉπüÕπéÍπéóπâ½πé▒πâÍπâ½πâ£πâÒπâ│πüºπü»µ▒éΘ¢╗σ¡ÉσÊñπü¿Φ╗óΣ╜ìσÓ║πüÔπâêπâÒπâ│πé╣πü«Σ╜ìτ╜«πü½τ╡ÉσÉêπüÕπéÍπÇéπüôπü«Σ╕¡ΘÚôΣ╜ôπü«σèáµ░┤σêÁΦºúπü½πéêπéèπé¬πâ¼πâòπéúπâ│πüÔτõÓµêÉπüù[9]πÇüπé▒πâê-πé¿πâÃπâ╝πâ½Σ║ÈσñÊτò░µÇºπü½πéêπéèΘà╕σÔÚπüòπéÔπéÍπü¿πé▒πâêπâ│πü½πü¬πéÍ[10]πÇé (4)  σÓ║Φ│¬ΘüÒτõ¿τ»ãσ¢▓πü¿σê╢ΘÕɵ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπéÈτõ¿πüãπüÓµ£ÊµÒÓσÉêµêÉσÂìσ┐£πü½πüèπüÀπéÍσÓ║Φ│¬ΘüÒτõ¿τ»ãσ¢▓∩╝êπé╣πé│πâ╝πâù∩╝Êπü»ΘÙ₧σ╕╕πü½σ║âπüãπÇ鵣ʵÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπü«σÂìσ┐£πüºπü»πéóπâ½πé│πâ╝πâ½πéãπé½πâ½πâ£πâÍπâ½σÔÚσÉêτÊÒπÇüπâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚτÊÒπÇüΘüÃΘà╕σÔÚτÊÒπÇüπéóπâÓπâ│πü¬πüÒµºÌπÇàπü¬σÔÚσÉêτÊÒπéÈσÉêµêÉπüÕπéÍπüôπü¿πüÔπüºπüìπéÍπÇéπüôπüôπüºπü»πéóπâ½πé│πâ╝πâ½πÇüπé½πâ½πâ£πâÍπâ½σÔÚσÉêτÊÒπÇüπâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚτÊÒπü«σÉêµêÉπü½πüñπüãπüªΦ┐░πü╣πéÍπÇé µ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπéÈτõ¿πüãπüÓπéóπâ½πé│πâ╝πâ½πü«σÉêµêÉπü»πé½πâ½πâ£πâÍπâ½σÓ║πü╕πü«µ▒éµá╕σÓ║πü«Φ╗óΣ╜ìπé㵣ʵÒÓπâ£πâÒπâ│πü«Θà╕σÔÚπü½πéêπüúπüªπü¬πüòπéÔπéÍπÇ鵣ʵÒÓπâ£πâÒπâ│πü¿Σ╕ÇΘà╕σÔÚτé¡τ┤áπÇüµ░┤τ┤áσÔÚτÊÒπéÈσÂìσ┐£πüòπü¢πéÍπü¿Σ╕Çτ┤Üπéóπâ½πé│πâ╝πâ½πüÔσ╛ùπéÊπéÔπéÍ[11]πÇé (5)  2πüñπü«τò░πü¬πéÍτ╜«µÂ¢σÓ║πéȵÔüπüñ3τ┤Üπéóπâ½πé│πâ╝πâ½πü»Θà╕πü«σ¡Ìσ£¿Σ╕ÍπÇüπéóπâ½πé¡πâÍπâ½πâ¢πéªΘà╕σíÒπü½2σ¢₧Φ╗óΣ╜ìσÂìσ┐£πéÈπüòπü¢πéÍπüôπü¿πüºσÉêµêÉπüºπüìπéÍ[10]πÇé1σ╜ôΘçÂπü«Θà╕πéÈσÂìσ┐£πüòπü¢πÇüτ╢ÜπüãπüªΘà╕σÔÚπü╛πüÓπü»σèáµ░┤σêÁΦºúπéÈΦíÔπüÁπüôπü¿πüºπüÙπéÔπü₧πéÔπé▒πâêπâ│πÇüπé¬πâ¼πâòπéúπâ│πüÔσ╛ùπéÊπéÔπéÍ∩╝êσÂìσ┐£µÒÓµºÍπü¿τ½ÍΣ╜ôσÔÚσ¡ªπü«πé╗πé»πé╖πâºπâ│πéÈσÂéτàºπü«πüôπü¿∩╝ÊπÇé. (6)  πâ¢πéªΘà╕σíÒπü«πéóπé╖πâ½σÔÚπü»πé½πâ½πâ£πâ│Θà╕πâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚτÊÒπü«σ¡Ìσ£¿Σ╕ÍπüºΘÇ▓ΦíÔπüÕπéÍπÇéπüôπüôπüºπü»πÇüπâ¢πéªΘà╕σíÒπü»πâêπâ¬(πé╖πé»πâ¡πâÜπâ│πâüπâ½)πâ£πâÒπâ│πü¿πâòπéºπâÍπâ½πâ¬πâüπéªπâáπüÍπéÊσÉêµêÉπüòπéÔπéÍπÇé3πüñπü«πé╖πé»πâ¡πâÜπâ│πâüπâ½σÓ║πüÔπâÇπâÓπâ╝πü«σ«ÌΦâ╜σÓ║πü¿πü¬πéèπÇüΦ╗óΣ╜ìσÂìσ┐£πüÔΘÌ╗σ«│πüòπéÔπéÍ[12]πÇé (7)  πâêπâ¬πéóπâ½πé¡πâ½πâ£πâÒπâ│πéÈ╬▒-πâÂπâ¡πé¿πâÃπâÒπâ╝πâêπü¿σÂìσ┐£πüòπü¢πéÍπü¿σ«ÌΦâ╜σÓ║πéÈσ░ÃσàÑπüùπüÓπé▒πâêπâ│πüÔτõÓµêÉπüÕπéÍ[8]πÇéΦ╗óΣ╜ìπüÔτ½ÍΣ╜ôτÊ╣τò░τÜãπü½ΘÇ▓ΦíÔπüÕπéÍ∩╝êΦ╗óΣ╜ìσÓ║πü«τ½ÍΣ╜ôσÔÚσ¡ªπéÈΣ┐ÙµÔüπüùπüñπüñπÇüΦ╗óΣ╜ìσàêπü«╬▒τé¡τ┤áπüºπü»σÂìΦ╗óπüÕπéÍ∩╝ÊπüÓπéüπÇüπüôπü«σÂìσ┐£πü»πé¿πâèπâ│πâüπé¬τÊ╣τò░τÜãπü¬╬▒-πéóπâ½πé¡πâ½πééπüùπüÂπü»╬▒-πéóπâ¬πâ╝πâ½πé▒πâêπâ│πü«σÉêµêÉπü½τõ¿πüãπéÍπüôπü¿πüÔπüºπüìπéÍ[13]πÇé (8) 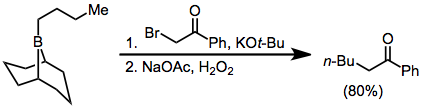 ╬▒-πâÂπâ¡πé¿πé╣πâÁπâ½πé¿πâÃπâÒπâ╝πâêπééπâ£πâÒπâ│πü½Σ╗ÌσèáπüùπÇü╬▒Σ╜ìπüÔσ«ÌΦâ╜σÓ║σÔÚπüòπéÔπüÓτõÓµêÉτÊÒπéÈΣ╕ÃπüêπéÍπÇéπüùπüÍπüùσÂÃτÃçπüÔΦÍÑσ╣▓ΦÉ╜πüíπéÍ[14]πÇéπüôπü«σÂìσ┐£πü½πüèπüãπüªπü»πé╕πéóπé╛πé¿πé╣πâÁπâ½πéãπé╕πéóπé╛πé▒πâêπâ│πééσñÚΘâ¿σíÒσÓ║πü«σ┐àΦªüπü¬πüãσÓ║Φ│¬πü¿πüùπüªτõ¿πüãπéÊπéÔπéÍπüôπü¿πüÔπüéπéÍ[15]πÇé╬▒,╬▒ΓÇÕ-πé╕πâÂπâ¡πé¿πâÃπâÒπâ╝πâêπü»πâ£πâÒπâ│πü¿σÂìσ┐£πüùπÇü╬▒-πâÂπâ¡πé½πâ½πâ£πâÍπâ½σÔÚσÉêτÊÒπéÈΣ╕ÃπüêπéÍπÇéπüôπéÔπü»πüòπéÊπü½╬▒Σ╜ìπü½σ«ÌΦâ╜σÓ║πéÈσ░ÃσàÑπüºπüìπéÍσÔÚσÉêτÊÒπüºπüéπéÍ[16]πÇé (9)  πâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚτÊÒπü»µ£ÊµÒÓπâ£πâÒπâ│πéȵ░┤Θà╕σÔÚτÊÒπü╛πüÓπü»πéóπâ½πé│πé¡πé╖πâÊπüºµ┤╗µÇºσÔÚπüùπüªπüÍπéÊX2πü¿σÂìσ┐£πüòπü¢πéÍπüôπü¿πüºσÉêµêÉπüºπüìπéÍπÇéΘüÃσÊ░πü«σíÒσÓ║πéÈτõ¿πüãπéÍπüôπü¿πüº3πüñπü«πéóπâ½πé¡πâ½σÓ║πü«πüÁπüí2πüñπüÔπâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚπüºπüìπéÍπüÔπÇüπé╕πé╖πéóπâÓπâ½πâ£πâÒπâ│πüºπâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπüÕπéÍπü¿πâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπüùπüÓπé¬πâ¼πâòπéúπâ│πü«πü┐πéÈΘü╕µè₧τÜãπü½πâÂπâ¡πé▓πâ│σÔÚπüºπüìπéÍ as the hydroborating reagent permits the selective halogenation of only the hydroborated olefin.[17] (10)  πéóπâ½πé▒πâÍπâ½πâ£πâÒπâ│πéÈΦç¡τ┤áπéãπâ¿πéªτ┤áπü¿σÂìσ┐£πüòπü¢πéÍπü¿µ£ÊµÒÓσÓ║πü«Σ╕ÇπüñπüÔπâ¢πéªτ┤áπü½τ╡ÉσÉêπüÕπéÍΦ╗óΣ╜ìσÂìσ┐£πüÔΦ╡╖πüìπéÍπÇéπéóπâ½πé¡πâÍπâ½σÓ║πü»Θü╕µè₧τÜãπü½Φ╗óΣ╜ìπüùπÇüΘàóΘà╕πâèπâêπâ¬πéªπâáπü¿ΘüÃΘà╕σÔÚµ░┤τ┤áπüºσçªτÉÁπüÕπéÍπüôπü¿πüºπé¿πâ│πéñπâ│πüÔσ╛ùπéÊπéÔπéÍ[18]πÇé (11)  σÂìσ┐£µÙíΣ╗╢Σ╕ÇΦê¼τÜãπü¬σÂìσ┐£µÙíΣ╗╢σñÜπüÂπü«µ£ÊµÒÓπâ£πâÒπâ│πü»τÒ║µ░ùπü½Σ╕ìσ«Êσ«ÜπüºπÇüµÂ«τÕ║µÇºµ£ÊµÒÓπâ£πâÒπâ│πü»τÒ║µ░ùΣ╕¡πüºπü»σ╝òτü½µÇºπüÔπüéπéÍπÇéσ╛ôπüúπüªπÇüπüôπéÔπéÊπü«ΦÒªΦÚ¼πü»Σ╕ìµ┤╗µÇºπé¼πé╣πü«Θ¢░σ¢▓µ░ùΣ╕ÍπüºσÂìσ┐£πüòπü¢πü¬πüÀπéÔπü░πü¬πéÊπü¬πüãπÇ鵣ʵÒÓπâ£πâÒπâ│πü»µ░┤πéÈσèáπüêπüÓπüáπüÀπüºπü»σÂìσ┐£σü£µ¡óπüùπü¬πüãπüÓπéüπÇüΘüÃΘà╕σÔÚµ░┤τ┤áπü½πéêπüúπüªΘà╕σÔÚπüÕπéÍπüôπü¿πüºπé»πé¿πâ│πâü∩╝êσÂìσ┐£σü£µ¡ó∩╝ÊπüÕπéÍπü«πüÔπéêπüãπÇéµ░┤τ┤áσÔÚπâ¢πéªτ┤áπü»ΘüÃΘà╕σÔÚµ░┤τ┤áπéÈΣ╜┐πüÁσÊìπü½µ░┤πüÍπÇüµ░┤µ║╢µÇºπü«Θà╕πüºπé»πé¿πâ│πâüπüºπüìπéÍπÇ鵣ʵÒÓπâ£πâÒπâ│πü»Σ╕ÇΦê¼τÜãπü½πü»πéóπâ½πé▒πâ│πéãπéóπâ½πé¡πâ│πü«πâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπüºσ╛ùπéÊπéÔπéÍ[19]πÇé σÂìσ┐£πü«ΘÇ▓ΦíÔπü½πü»πâ¢πéªτ┤áµ║Éπü«Θü╕µè₧πüÔΘçìΦªüπüºπüéπéÍπÇé9-BBNπü»µºÌπÇàπü¬σÂìσ┐£πü½πüèπüãπüªπÇüσÂìσ┐£πü½ΘÚóΣ╕Ãπüùπü¬πüãπâÇπâÓπâ╝πü¬σ«ÌΦâ╜σÓ║πü¿πüùπüªσâìπüÂπÇéπü╛πüÓ9-BBNπéÈπâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚΦÒªΦÚ¼πü¿πüùπüªτõ¿πüãπéÍπüôπü¿πüºπé¬πâ¼πâòπéúπâ│πéÈσ«Ôσà¿πü½πâÈπâÊπâ¡πâ¢πéªτ┤áσÔÚπüÕπéÍπüôπü¿πüÔπüºπüìπéÍπÇéTHFπüÔµ£ÊµÒÓπâ¢πéªτ┤áσÔÚσÉêτÊÒπü«σÂìσ┐£πü«µ║╢σ¬Èπü¿πü¬πéÍπüôπü¿πüÔσñÜπüãπüÔπÇüπé»πâ¡πâ¡πâ£πâÒπâ│πü»THFπü¿σ«Êσ«Üπü¬ΘÔ»Σ╜ôπéÈΣ╜£πéÍ[20]πÇéπüôπü«σá┤σÉêπé╕πé¿πâüπâ½πé¿πâ╝πâÁπâ½πü¬πüÒµÑ╡µÇºπü«Σ╜Ãπüãµ║╢σ¬ÈπüÔτõ¿πüãπéÊπéÔπéÍπÇé σ«ÓΘ¿ôµÊ͵│ò(12)  πéêπüÂΣ╣╛τçÑπüòπü¢πüÓ50mLπâèπé╣πâòπâÒπé╣πé│πü½πâ₧πé░πâìπâüπââπé»πé╣πé┐πâ╝πâÒπâ╝πü«µõ¬µÍÔσ¡ÉπéÈσàÑπéÔπÇüπé╗πâùπé┐πâáπüºΦôÍπéÈπüùπüªσÁàΘâ¿πéÈτ¬Èτ┤áτ╜«µÂ¢πüÕπéÍπÇéπâòπâÒπé╣πé│πéÈΓêÈ25°Cπü½σÁ╖σì┤πüùπÇü1.89 g (10 mmol)πü«p-πé»πâ¡πâ¡πâòπéºπâÍπâ½πé╕πé»πâ¡πâ¡πâ£πâÒπâ│πéÈ10 mLπü«πâÁπâêπâÒπâÈπâÊπâ¡πâòπâÒπâ│πü½µ║╢πüÍπüÕπÇéπüôπü«µ║╢µ╢▓πéÈΣ╕ǵ╗┤πüÜπüñπÇü1.25 g (11 mmol)πü«πé╕πéóπé╛ΘàóΘà╕πé¿πâüπâ½πéÈ10 mLπü«πâÁπâêπâÒπâÈπâÊπâ¡πâòπâÒπâ│πü½µ║╢πüÍπüùπüÓµ║╢µ╢▓πü½σàÑπéÔπéÍπÇé(3-5σêÁΘÚôπü½1mL)πüôπéÔπü»τ¬Èτ┤áπü«τÕ║τõÓπéÈτÒÂπéãπüÍπü½πüÕπéÍπüÓπéüπüºπüéπéÍ(τ┤ã1.5µÕéΘÚôπüÍπüÀπüªσÂìσ┐£πüòπü¢πéÍ)πÇéπüôπü«µ╕Òσ║ªπüºµ░┤5 mLπü¿πâíπé┐πâÃπâ╝πâ½5 mLπéÈσèáπüêπéÍπÇéµ£Çσ╛Ôπü½σÁ╖σì┤πâÉπé╣πéÈσÂÚπéèΘÕñπüìπÇüΘú╜σÈÔτé¡Θà╕πâèπâêπâ¬πéªπâáµ░┤µ║╢µ╢▓75 mLπüºσÂìσ┐£σü£µ¡ó∩╝êπé»πé¿πâ│πâü∩╝ÊπüùπüªπüÍπéÊ50mLπü«πé¿πâ╝πâÁπâ½πüº3σ¢₧µè╜σç║πüÕπéÍπÇéτãíµ░┤MgSO4πüºΣ╣╛τçÑπüòπü¢πÇüµ┐âτ╕«πüÕπéÍπü¿ΓÇÕΓÇÕp'ΓÇÕ-πé»πâ¡πâ¡πâòπéºπâÍπâ½ΘàóΘà╕πé¿πâüπâ½πéÈσÂÃΘçÂ1.80 g (σÂÃτÃç91%)πüºσ╛ùπéÍπÇéπüôπü«σÔÚσÉêτÊÒπü«µ▓╕τé╣πü»106ΓÇô107°CπÇü(3.5 mm);Φ₧ìτé╣πü»31ΓÇô32°CπÇü1H NMRπü«╬┤πü»1.34, 3.59, 4.12, 7.21, 7.29πüºπüéπéÍ[21]πÇé Φãܵ│¿
|
Portal di Ensiklopedia Dunia













