цбВцЦЗцЮЭ (5ф╗гчЫо)
5ф╗гчЫо цбВ цЦЗцЮЭя╝ИуБЛуБдуВЙ уБ╢уВУуБЧуАБ1930х╣┤уАИцШнхТМ5х╣┤уАЙ4цЬИ12цЧе[1] - 2005х╣┤уАИх╣│цИР17х╣┤уАЙ3цЬИ12цЧея╝ЙуБпуАБф╕КцЦ╣хЩ║хо╢я╝Иф╕КцЦ╣уБошР╜шкЮхо╢я╝ЙуАВ 6ф╗гчЫочмСчжПф║нцЭ╛щ╢┤уАБ3ф╗гчЫоцбВч▒│цЬЭуАБ3ф╗гчЫоцбВцШехЫгц▓╗уБиф╕жуБ│уАБцШнхТМуБоуАМф╕КцЦ╣шР╜шкЮуБохЫЫхдйчОЛуАНуБишиАуВПуВМуАБшб░щААуБЧуБжуБДуБЯф╕КцЦ╣шР╜шкЮчХМуБох╛йшИИуВТцФпуБИуБЯуАВ цЭецн┤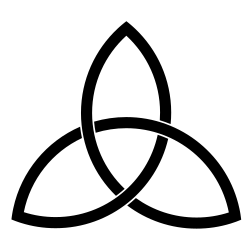 хдзщШкх╕ВхМЧхМ║хдйчеЮцйЛчнЛхЕнф╕БчЫоуБлчФЯуБ╛уВМуВЛуАВчИ╢уБпхоохдзх╖еуБауБгуБЯуБМуАБхдзщШкуБлчз╗ф╜ПуБЧуБжуБЛуВЙуБпшБ╖уВТш╗вуАЕуБиуБЧщАахЕ╡х╗ахЛдхЛЩуБоч╡МщиУуВВуБВуБгуБЯуАВуБоуБбф╕Ахо╢уБпхдзцнгхМ║ф╕Йш╗Тхо╢уБлчз╗уВЛуАВ 1941х╣┤4цЬИуБлуАБхПФчИ╢уБоф╜ПуВАщЗЬх▒▒я╝Их╜УцЩВуБпцЧецЬмуБоцЦ╜цФ┐ф╕Ля╝ЙуБлчз╗уВЛуВВуАБ1943х╣┤4цЬИуБлхдзщШкуБлцИ╗уВКуАБхдзщШкх╕ВчлЛхдйчОЛхп║хХЖценхнжцабуБлхЕехнжуБЩуВЛуАВ1945х╣┤3цЬИуБлуБпуАБчеЮхеИх╖ЭчЬМшЧдц▓вх╕ВуБоц╡╖ш╗НщЫ╗ц╕мхнжцабуБлхЕехнжуБЧуАБх╜УхЬ░уБзцХЧцИжуВТш┐ОуБИуВЛуАВхдйчОЛхп║хХЖценуБлуБпх╛йхнжуБЫуБЪуАБщА▓щзРш╗НуБоцЦ╜шинуБкуБйуБзуВвуГлуГРуВдуГИчФЯц┤╗уВТщАБуВЛуАВ 1947х╣┤цШеуАБхПФчИ╢уБоцЦбцЧЛуБзхдзщШкх╕Вф║дщАЪх▒АуБлх░▒шБ╖уАВх╜УхИЭуБпхдзщШкх╕ВхЦ╢хЬ░ф╕ЛщЙДц╖Ах▒ЛцйЛф╗ох╖еха┤[шжБхЗ║хЕ╕]уБлхЛдхЛЩуАВуБЭуБох╛МхдзщШкх╕ВщЫ╗хдйчОЛхп║ш╗Кх║луБощЫ╗цйЯх╖еха┤уБлщЕНх▒ЮуБХуВМуАБщБЛцРмщГихУбуБауБгуБЯчЯвхАЙцВжхдля╝ИуБоуБбуБо3ф╗гчЫоцбВч▒│ф╣ЛхКйя╝ЙуБохПгуБНуБНуБзуАБш╢гхС│уБош╕КуВКуВТч┐ТуБЖуБЯуВБуАБцЧецЬмшИЮш╕КхЭВцЭ▒ц╡БуБохРНхПЦуБзуВВуБВуБгуБЯ4ф╗гчЫоцбВцЦЗцЮЭуБлхЕещЦАуБЩуВЛуАВ уБЭуБох╛МуБЧуБ░уВЙуБПуБпх╕ВшБ╖хУбуБиуБЧуБжуБоч▒НуВТч╜оуБНуБкуБМуВЙуАБх╕лхМауБМхЗ║ц╝ФуБЩуВЛхпДх╕нуБлщАЪуБгуБжх╝ЯхнРф┐ошбМуВТчйНуБ┐уАБ2ф╗гчЫоцбВуБВуВДуВБя╝ИуАМщШ┐уВДхЕНуАНуБЛуВЙх╜Уф╗гуВИуВКцФ╣чз░я╝ЙуБощлШх║зхРНуВТуВВуВЙуБЖуАВ1947х╣┤5цЬИ2цЧеуАБхдзщШкцЦЗхМЦф╝Ъщдия╝ИуБоуБбуБохдзщШкх╕ВчлЛч▓╛шПпх░Пхнжцабя╝И1995х╣┤3цЬИ31цЧех╗Гцабя╝ЙуБоф╜Нч╜оуБлуБВуБгуБЯя╝ЙуБзхИЭшИЮхП░я╝Иц╝ФчЫоуБпуАМх░ПхАЙшИ╣уАНя╝ЙуАВ1948х╣┤уБлф║дщАЪх▒АуВТщААшБ╖уБЧуАБшР╜шкЮхо╢х░ВценуБиуБкуВЛуАВхРМх╣┤3цЬИуАБцИОцйЛцЭ╛чл╣уБлч╡РщЫЖуБЧуБжуБДуБЯф╕КцЦ╣шР╜шкЮхо╢уБпуАБ5ф╗гчЫочмСчжПф║нцЭ╛щ╢┤уБичв║хЯ╖уВТчФЯуБШуБЯф╕╣ц│вхо╢ф╣ЭщЗМф╕╕уБМ 2ф╗гчЫоцбВцШехЫгц▓╗уВЙуВТшкШуБгуБжц╡кшК▒цЦ░чФЯф╕ЙхПЛц┤╛уВТцЧЧцПЪуБТуБЧуАБх╕лхМауБо4ф╗гчЫоцЦЗцЮЭуВВуБУуВМуБлхРМшк┐уБЧуБЯ[2]уАВуБУуБоуБиуБНуБВуВДуВБуБпчзБц╖СуБЧуБжуБДуБЯцЭ╛щ╢┤уБлуБдуБДуБжхЛЙх╝╖уБЧуБЯуБДуБичФ│уБЧхЗ║уБжцЦЗцЮЭуБицЭ╛щ╢┤уБМчЫ╕шлЗуБЧуБЯч╡РцЮЬуАБуБВуВДуВБуБпц╡кшК▒цЦ░чФЯф╕ЙхПЛц┤╛уБлуБпхКауВПуВЙуБЪуБлцИОцйЛцЭ╛чл╣уБлцоЛуВЛуБУуБиуБлуБкуБгуБЯ[2]уАВхИЖшгВщиТхЛХуБпуАБуБВуВДуВБуВВхКауВПуБгуБжуБДуБЯшЛецЙЛшР╜шкЮхо╢уВ░уГлуГ╝уГЧуАМуБХуБИуБЪуВКф╝ЪуАНуБоф╗ЛхЕеуБлуВИуВКч┤Д1х╣┤уБзхПОцЭЯя╝ИщЦвше┐ц╝ФшК╕хНФф╝ЪуБиуБЧуБжхРИхРМя╝ЙуБЧуБЯуБМ[3]уАБцИОцйЛцЭ╛чл╣уБочХкч╡Дч╖ицИРуБлх╛йх╕░уБЧуБЯф╕╣ц│вхо╢ф╣ЭщЗМф╕╕уБпуАБцЭ╛щ╢┤уБоцн╗хО╗я╝И1950х╣┤я╝ЙуБоуБоуБбуАБшЗкхИЖуБлхРМшк┐уБЧуБкуБЛуБгуБЯуБВуВДуВБуВТуАМцДПш╢гш┐ФуБЧуАНуБиуБЧуБжцИОцйЛцЭ╛чл╣уБЛуВЙч╖ауВБхЗ║уБЧуБЯ[4]уАВуБВуВДуВБуБпуАБцнМшИЮф╝ОуБохЫГхнРцЦ╣я╝Ищ│┤чЙйх╕ля╝ЙуБ╕уБош╗вхРСуВТф╜ЩхДАуБкуБПуБХуВМуАБ хпДх╕нхЫГхнРф╕ЙхС│ч╖ЪцЦ╣уБоц╗ЭщЗОхЕЙхнРуБоч┤╣ф╗ЛуБзщ│┤чЙйуБоцвЕх▒ЛхЛЭф╣Лш╝ФуБлхЕещЦАуАВцвЕх▒ЛхдЪф╕ЙщГОуВТхРНф╣ЧуВЛуАВуБауБМуАБ1951х╣┤уБлшВ║ч╡Рца╕уБМчЩ║шжЪуБЧуАБч┤Д2х╣┤щЦУуБохЕещЩвчФЯц┤╗уВТщАБуВЛя╝И - 1953х╣┤2цЬИя╝ЙуАВх┐лчЩТх╛МуБлшР╜шкЮф╝ЪуБлхЗ║уВЛуБлх╜УуБЯуВКуАБуАМцбВуБВуВДуВБуАНуБзуБпчлЛха┤ф╕КхХПщбМуБМуБВуВЛуБУуБиуБЛуВЙуАБхпДх╕нхЫГхнРцЦ╣уБиуБкуБгуБжуБДуБЯф╕нчФ░уБдуВЛуБШуБМшЗкуВЙуБМхЩ║хо╢уБауБгуБЯцЩВуБощлШх║зхРНуБзуБВуВЛчмСчжПф║нщ╢┤ф║МуВТф╜┐уБЖуВИуБЖуБлшиИуВЙуБДуАБщлШх║зуБлф╕КуБгуБЯ[5]уАВуБУуБохРНхЙНуБзуАМф║МуАБф╕ЙхЫЮуАНшР╜шкЮф╝ЪуБлхЗ║уБЯх╛МуАБф╕нчФ░уБдуВЛуБШуБМ4ф╗гчЫоцЦЗцЮЭуБлуБВуВДуВБуБох╛йх╕░уВТцМБуБбуБЛуБСуБжцЙ┐шл╛уБХуВМуАБ1954х╣┤3цЬИуБл3ф╗гчЫоцбВх░ПцЦЗцЮЭуБлцФ╣хРНуБЧуБжцЬмца╝чЪДуБлх╛йх╕░уБЧуБЯ[5]уАВ 1957х╣┤уБоф╕КцЦ╣шР╜шкЮхНФф╝Ъч╡РцИРцЩВуБлуБпх╣╣ф║ЛуБоф╕Аф║║уБиуБкуВЛ[6]уАВуБУуБощаГуАБх░ПцЦЗцЮЭуБоуБ╗уБЛуАБ4ф╗гчЫочмСчжПф║нцЮЭщ╢┤я╝Их╛МуБо6ф╗гчЫочмСчжПф║нцЭ╛щ╢┤я╝ЙуГ╗3ф╗гчЫоцбВч▒│цЬЭуГ╗2ф╗гчЫоцбВчжПхЬШц▓╗я╝ИуБоуБбуБо3ф╗гчЫоцбВцШехЫгц▓╗я╝ЙуГ╗3ф╗гчЫоцЮЧхо╢цЯУф╕╕уВТхКауБИуБЯ5ф║║уВТуАМф╕КцЦ╣шР╜шкЮф║Фф║║чФ╖уАНуБихС╝уБ╢уВИуБЖуБлуБкуВКуАБуВДуБМуБжцЯУф╕╕уВТщЩдуБДуБжуАМф╕КцЦ╣шР╜шкЮуБохЫЫхдйчОЛуАНуБиуБДуБЖхС╝уБ│цЦ╣уБМуБкуБХуВМуВЛуВИуБЖуБлуБкуБгуБЯ[7]уАВ 1961х╣┤уАБуБУуБох╣┤хзЛуБ╛уБгуБЯNHKуБоуАМф╕КцЦ╣шР╜шкЮуБоф╝ЪуАНуБзуАОхдйчОЛхп║шйгуВКуАПуАОуБЯуБбуБНуВМч╖ЪщжЩуАПуБкуБйуАБуБоуБбуБохНБхЕлчХкуБоуГНуВ┐уБКуВНуБЧуВТуБКуБУуБкуБЖуАВшЗкшСЧуАОуБВуВУуБСуВЙшНШхдЬшй▒уАПуБзуБпуБУуБох╣┤уБлхНГхЬЯхЬ░шИИшбМуБЛуВЙхРЙцЬмшИИценуБлчз╗ч▒НуБЧуБЯуБиуБХуВМуВЛуАВуБЯуБауБЧцЬмф║║уВВшиШцЖ╢уБМшЦДуБДуВИуБЖуБзуАБхРМцЫ╕уБошбичП╛уВВуАМ1961я╜Ю2х╣┤щаГуАНуБицЫЦцШзуБкуВВуБоуБиуБкуБгуБжуБДуВЛуАВ4ф╗гчЫоцбВцЦЗч┤ЕуБоуАОф╕КцЦ╣шР╜шкЮхП▓уАП[шжБхЗ║хЕ╕]уБзуБпхНГцЧехКЗха┤уБо1963х╣┤10цЬИф╕нх╕нуБлхНГхЬЯхЬ░уБошК╕ф║║уБиуБЧуБжхЗ║ц╝ФуБЧуБжуБДуБЯуБиуБошиШш┐░уБМуБВуВКуАБ2ф╗гчЫощЬ▓уБоф║ФщГОхЕ╡шбЫуВВшЗкшСЧуАОф╕КцЦ╣шР╜шкЮуБоуБпуБкуБЧуАПуБоф╕нуБз1964х╣┤уБлхНГхЬЯхЬ░шИИшбМуБлцЙАх▒ЮуБЧуБжуБДуБЯшР╜шкЮхо╢уБоф╕Аф║║уБиуБЧуБжх░ПцЦЗцЮЭуВТцМЩуБТуБжуБДуБЯуАВцЧец▓вф╝╕хУЙуБпшЗкуВЙуБоуГЦуГнуВ░уАМуВЙуБПуБФуБПуВЙ Webч╖иуАНуБлуБКуБДуБжхРЙцЬмшИИценуБош│ЗцЦЩя╝ИщЭЮхЕмшбиуБоф╜ПцЙАщМ▓я╝ЙуБлхРМчд╛хЕечд╛цЧеуБМуАМ1965х╣┤5цЬИ1цЧеуАНуБицШОшиШуБХуВМуБжуБДуБЯуБичЬЯчЫ╕уВТчй╢цШОуБЧуБЯуАВ 1967х╣┤4цЬИ22цЧеуАБхИЭуБочЛмц╝Фф╝ЪуАМх░ПцЦЗцЮЭуБМуВЙуБПуБЯхпДх╕нуАНуВТшВех╛МцйЛуБохдзщШкYMCAуБзщЦЛхВмуАВ 1971х╣┤3цЬИ29цЧеуАБчлЛх╖ЭшлЗх┐ЧуБиуБоф║Мф║║ф╝ЪуАМше┐уБох░ПцЦЗцЮЭуГ╗цЭ▒уБошлЗх┐ЧуАНуВТцЭ▒ф║муГ╗шЩОуГОщЦАуБочЩ║цШОф╝ЪщдиуБзщЦЛхВмуАВхЬиф║муБох░ПцЦЗцЮЭуГХуВбуГ│уБохКкхКЫуБзхоЯчП╛уБЧуБЯшР╜шкЮф╝ЪуБзуАБуБУуВМуБМуБНуБгуБЛуБСуБиуБкуБгуБжуАМцЭ▒ф║мх░ПцЦЗцЮЭуБоф╝ЪуАНуБМшкХчФЯуБЩуВЛуАВуБУуБоф╝ЪуБМцФпцП┤уБЩуВЛх╜вуБз7цЬИ27цЧеуБлуБпцЭ▒ф║муБзхИЭуБочЛмц╝Фф╝ЪуАМхдПхз┐уГ╗х░ПцЦЗцЮЭф╕АхдЬуАНуБМщЦЛхВмуБХуВМуБЯуАВ3уБЛцЬИх╛МуБо10цЬИ29цЧеуБлуБпуАБцЧйуБПуВВцЭ▒ф║муБзф║Мх║жчЫоуБочЛмц╝Фф╝ЪуВТщЦЛуБПуАВ 1984х╣┤1цЬИуАБ3ф╗гчЫоцбВцШехЫгц▓╗уБох╛МуВТхПЧуБСуАБф╕КцЦ╣шР╜шкЮхНФф╝Ъчмм4ф╗гф╝ЪщХ╖уБлх░▒ф╗╗уАВ1994х╣┤уБ╛уБзхЛЩуВБуВЛуАВх░▒ф╗╗уБЧуБжцЬАхИЭуБоф╗Хф║ЛуБМуАБф║дщАЪф║ЛцХЕуБзцАещАЭуБЧуБЯ4ф╗гчЫоцЮЧхо╢х░ПцЯУуБошСмхДАхзФхУбщХ╖уБауБгуБЯ[8]уАВ 1984х╣┤10цЬИ9цЧеуАБцЦЗце╜уБохРЙчФ░ч░СхКйуАБцЦ░хЖЕуБоцЦ░хЖЕцЮЭх╣╕хдкхдлуБиуБоуВ╕уГзуВдуГ│уГИхЕмц╝ФуВТхдзщШкуГ╗х╛бхаВф╝ЪщдиуБзшбМуБЖуАВц╝ФчЫоуБпуАОхдйчеЮх▒▒уАПуАВ 1986х╣┤уАБNHKщАгч╢ЪуГЖуГмуГУх░ПшкмуАОщГ╜уБощвиуАПуБлхЗ║ц╝ФуАВ 1992х╣┤8цЬИ3цЧеуАБ5ф╗гчЫоцбВцЦЗцЮЭуВТше▓хРНуАВхдзщШкуГ╗ф╕нф╣Лх│╢уБоуГнуВдуГдуГлуГЫуГЖуГлуБзцКлщЬ▓уГСуГ╝уГЖуВгуГ╝уВТшбМуБЖуАВше▓хРНцКлщЬ▓хЕмц╝ФуБп8цЬИ22цЧеуБочеЮцИ╕цЦЗхМЦуГЫуГ╝уГлуВТчЪохИЗуВКуБлхдзщШкуГ╗хЫ╜члЛцЦЗце╜хКЗха┤уАБцЭ▒ф║муГ╗цЦ░хо┐цЬлх║Гф║нуБкуБйхЕихЫ╜уБзщЦЛхВмуАВуБУуБоцЩВуВИуВКхЗ║хЫГхнРуВТуБЭуВМуБ╛уБзуБоуАМш╗Тч░╛уАНуБЛуВЙуАМх╗Уф╕╣хЙНуАНуБлцФ╣уВБуВЛуАВ 1996х╣┤ шЗкхПЩф╝ЭуАОуБВуВУуБСуВЙшНШхдЬшй▒уАПуВТхИКшбМуБЩуВЛуАВ 2004х╣┤4цЬИ18цЧеуАБхТМцнМх▒▒чЬМцЦ░хоох╕ВуБоцЦ░хоохЬ░хЯЯшБ╖ценшиУч╖┤уВ╗уГ│уВ┐уГ╝уБзуАБч┤Аф╝Кх▒▒хЬ░уБощЬКха┤уБихПВшйгщБУуБоф╕ЦчХМщБ║чФгчЩ╗щМ▓щБЛхЛХуБищАгцР║уБЧуБЯшЗкф╜ЬуБоцЦ░ф╜ЬшР╜шкЮуАОчЖКщЗОшйгуАПуВТуГНуВ┐ф╕ЛуВНуБЧуАВхРМх╣┤ф╕нуБлхдзщШкуГ╗хЫ╜члЛцЦЗце╜хКЗха┤уАБцЭ▒ф║муГ╗хЫ╜члЛц╝ФшК╕ха┤уБзуВВхПгц╝ФуБЩуВЛуАВ 2005х╣┤3цЬИ12цЧехНИхЙН11цЩВ32хИЖуАБшВ║уБМуВУуБоуБЯуВБф╕ЙщЗНчЬМф╝Кш│Ах╕ВуБочЧЕщЩвуБзцн╗хО╗[9]уАВ74цн│ц▓буАВц│ХхРНуАМхдЪхоЭщЩвхЕЙх╛│цЦЗцЮЭх▒ЕхглуАНуАВхвУцЙАуБпхН░х▒▒хп║уАВцн╗хО╗2уГ╢цЬИхЙНуБохРМх╣┤1цЬИ10цЧеуБохдзщШкуГ╗щлШц┤ехооуБзуБоуАОщлШц┤еуБохпМуАПуБМцЬАх╛МуБохПгц╝ФуБиуБкуБгуБЯуАВ ц▓бх╛М 2006х╣┤3цЬИ26цЧеуАБщлШц┤ехооуБл3ф╗гчЫоцбВцШехЫгц▓╗уБМцПоцплуБЧуБЯ5ф╗гчЫоцбВцЦЗцЮЭуБошиШх┐╡чвСуБМхоМцИРуБЩуВЛуАВ 2008х╣┤10цЬИ29цЧеуАБцЬЭцЧецФ╛щАБф╗ЦхЬищШкц░СцФ╛цЙАшФ╡уБощЯ│ц║РуГ╗цШахГПуВ╜уГ╝уВ╣уБЛуВЙ33х╕нуВТхО│щБ╕уБЧуБЯуАОф║Фф╗гчЫоуААцбВцЦЗцЮЭуАПуБМчЩ║хг▓уБХуВМуБЯ[10]уАВ 2012х╣┤3цЬИуАБуАОх╕лхМауАБф║Фф╗гчЫоцЦЗцЮЭуБ╕уАПуБКуВИуБ│TBSцЙАшФ╡уБоуАОTBSшР╜шкЮчаФчй╢ф╝ЪуАПцШахГПуВ╜уГ╝уВ╣уБЛуВЙ11х╕нуВТхО│щБ╕уБЧуБЯуАОшР╜шкЮчаФчй╢ф╝Ъ ф║Фф╗гчЫо цбВцЦЗцЮЭ хРНц╝ФщЫЖуАПуБМуГкуГкуГ╝уВ╣уБХуВМуВЛуАВ хнРцБпуБпшР╜шкЮхо╢уБлуБпуБкуВЙуБкуБЛуБгуБЯуБМуАБхнля╝Иф╕ЙчФ╖уБохоЯхнРя╝ЙуБМшР╜шкЮхо╢уВТх┐ЧцЬЫуБЧуБжуАБ2015х╣┤уБлцбВуБНуВУцЮЭщЦАф╕ЛуБлхЕещЦА[11]уАБхРМх╣┤6цЬИ13цЧеуАБхдзщШкх╕ВхЯОцЭ▒хМ║уБзшбМуВПуВМуБЯшР╜шкЮф╝ЪуБзцбВх░ПуБНуВУуБохРНуБзуАМчЕохг▓х▒ЛуАНуБзхИЭщлШх║зуВТш╕ПуВУуБа[12]уАВ 2025х╣┤4цЬИ17цЧеуБлхРЫцЮЭхдлф║║уБМ96цн│уБзцн╗хО╗уАВ6ф╗гчЫоцЦЗцЮЭуБМуГЦуГнуВ░уБзцШОуВЙуБЛуБлуБЧуБЯ[13]уАВ цЧецЬмхЫ╜хдЦуБзуБохЕмц╝Фцн┤1980х╣┤ф╗гф╗ещЩНуАБф╜Хх║жуБЛцЧецЬмхЫ╜хдЦуБзхЕмц╝ФуВТуБКуБУуБкуБгуБЯуАВ
хПЧш│Юцн┤
шК╕щвиуГ╗ф║║чЙй х╛МхИЧх╖жуБЛуВЙ2ф║║чЫоуБМцЦЗцЮЭ [ц│и 1] шР╜шкЮуБлуАМуБпуВБуВВуБоуАНуБихС╝уБ░уВМуВЛф╕КцЦ╣шР╜шкЮчЙ╣цЬЙуБоуБКхЫГхнРуБлуВИуВЛщЯ│цЫ▓уВТхПЦуВКхЕеуВМуБЯц╝ФчЫоуВДуАБхе│цАзуВТф╕╗ф║║хЕмуБиуБЧуБЯц╝ФчЫоуВТх╛ЧцДПуБиуБЧуАБшПпуВДуБЛуБзщЩ╜ц░ЧуБкшкЮуВКхПгуБМхдЪуБДуАВ хЗ║хЫГхнРуБпуАМх╗Уф╕╣хЙНуАНуАВх░ПцЦЗцЮЭцЩВф╗гуБпуАМш╗Тч░╛уАНуВТчФиуБДуБжуБДуБЯя╝Их╛МуБлцбВф╕ЙцЮЭуБМч╢ЩцЙ┐уБЧуАБ6ф╗гцЦЗцЮЭше▓хРНуБ╛уБзф╜┐чФия╝ЙуАВ чФЯхЙНуБпхРЙцЬмшИИценуБлцЙАх▒ЮуАВцпОцЧецФ╛щАБуБох░Вх▒ЮуБиуБкуВКуАБуГЖуГмуГУуГ╗уГйуВ╕уВкчХкч╡ДуБлуВВхЗ║ц╝ФуБЧуБЯуАВхРЙцЬмуБзуБпц╝лцЙНф╕нх┐ГуБоуГЧуГнуВ░уГйуГауБоф╕нуБлуБВуВКуБйуБбуВЙуБЛуБиуБДуБИуБ░хЖ╖щБЗуБХуВМуБжуБДуБЯуБМуАБцЬЙцЬЫуБкх╝ЯхнРуВТшВ▓уБжуБжхРЙцЬмуБочЬЛцЭ┐уБлшВ▓уБжуБЯуАВхРЙцЬмуБох╣╣щГиуБзуБВуВЛхпМф║Хч╛йхЙЗуБпуАМцЦЗцЮЭуБХуВУуБлуБпуБКф╕Цшй▒уБлуБкуВКуБ╛уБЧуБЯуАВф╕ЙцЮЭуАБуБНуВУцЮЭуАБцЦЗчПНуАБх░ПцЮЭуБиуБКх╝ЯхнРуБХуВУуБлуБкуВУуБ╝чи╝уБМуБЧуБжуВВуВЙуБгуБЯуВПуБЛуВКуБ╛уБЫуВУуАВуБДуВДхдзцБйф║║уБзуБЩуВИуАВуАНуБишйХф╛буБЧуБжуБДуВЛ[15]уАВ чйПуВДуБЛуБзхДкуБЧуБЛуБгуБЯхПНщЭвуАБшК╕уБлхп╛уБЧуБжуБпхО│уБЧуБПуАБх╝ЯхнРуБлхп╛уБЧуБжуВВщЙДцЛ│уВТуБ╡уВЛуБЖуБУуБиуВВуБВуБгуБЯя╝И4ф╗гцбВх░ПцЦЗцЮЭуБпуАМф┐║уБ╗уБйх╕лхМауБлцо┤уВЙуВМуБЯх╝ЯхнРуБпуБДуБкуБДуАНуБихЫЮцГ│уБЧуБжуБДуВЛуБМуАБцЦЗцЮЭуБпуАМхЕищГиуБох╝ЯхнРуВТуБйуБдуБДуБжуВЛуВПуБСуВДуБкуБДуАВуБНуВУцЮЭуБМшиАуБЖуБУуБиуВТшБЮуБЛуВУуБХуБЛуБДуБлф╕АчХкуБйуБдуБДуБжуВЛуАНуБишкЮуБгуБжуБДуВЛя╝ЙуАВчи╜хПдуБлщЦвуБЧуБжуБпуАБф╛ЛуБИуБ░ф╕КцЦ╣шР╜шкЮуБощЦУуБихТМцнМх▒▒х╝БчЛмчЙ╣уБоуВдуГ│уГИуГНуГ╝уВ╖уГзуГ│уБиуБощЦУуБзшЛжуБЧуВУуБзуБДуБЯцбВцЦЗчжПуВДуАБчФ╖цАзчд╛ф╝ЪуБоф╕нуБзцзЛчпЙуБХуВМуБЯхПдхЕ╕шР╜шкЮуБохгБуБлуБ╢уБдуБЛуБгуБжуБДуБЯхе│ц╡БуБо3ф╗гчЫоцбВуБВуВДуВБуБлцЦ░ф╜ЬшР╜шкЮуВТхЛзуВБуВЛуБкуБйуАБх╝ЯхнРуБочЙ╣х╛┤уВТц┤╗уБЛуБЧуБЯцМЗх░ОуВТшбМуБгуБжуБДуБЯуАВ хРНш╖буБох╖ощЕНуБлщЦвуБЧуБжуАБх╝ЯхнРуБлцбВц┤╛уБохРНш╖буБоше▓хРНуГ╗цФ╣хРНуБпуБВуБ╛уВКхе╜уВУуБзуБДуБкуБЛуБгуБЯуАВщБОхО╗уБлхдзуБНуБкхРНш╖буВТч╢ЩуБДуБзшЛжхК┤уБЧуБжуБДуВЛшР╜шкЮхо╢уВТшжЛуБжуБНуБЯуБЯуВБх╝ЯхнРуБЯуБбуБлуБпшЦжуВБуБкуБЛуБгуБЯуАВф╕АщЦАуБзше▓хРНуГ╗цФ╣хРНуВТшбМуБгуБЯуБоуБпчЫ┤х╝ЯхнРуБзуБпуАМцЮЭхЕЙуАНуАМуБВуВДуВБуАНуАМцЦЗцШЗуАНуАМцЮЭцЫ╛ф╕╕уАНуБУуБо4ф║║уБоуБ┐уБзуАМцЮЭщЫАуАНуАМуБЦуБУуБ░уАНуАМхНЧхЕЙуАНуБиуБДуБгуБЯцбВц┤╛уБлч╕БуБоуБВуВЛхРНхЙНуВВф╕АщЦАуБощБХуБЖч▒│цЬЭф╕АщЦАуБМше▓хРНуБЧуБжуБДуВЛуАВуАМшЧдхЕ╡шбЫуАНуАМхЬУцЮЭуАНуБлщЦвуБЧуБжуВВцЭ▒ф║муБошР╜шкЮхо╢уБМше▓хРНуБЧуБЯуАВх╝ЯхнРуБМчЫ┤уАЕше▓хРНуБЧуБЯуБДуБихРНф╣ЧуВКхЗ║уБжуВВхН┤ф╕ЛуБЧуБжуБДуВЛуАВф╛ЛуБИуБ░уБНуВУцЮЭуБоуАМцЦЗхР╛уАНуВДцЦЗчжПуБоуАМцЦЗх╖жшбЫщЦАуАНчнЙуАВ хдзчЫ╕цТ▓хКЫхглуБощХ╖ш░╖х╖ЭхЛЭцХПя╝Иф╜Рц╕буГ╢х╢╜щГих▒ЛуАБ11ф╗гчЫочзАуГОх▒▒шжкцЦ╣я╝ЙуБиуБпхРМуБШшЛЧхнЧуБиуБДуБЖуБУуБиуБзшжкф║дуБМуБВуВКуАБ3цЬИуБохдзщШкха┤цЙАуБощЪЫуБлуБпщХ╖ш░╖х╖ЭуБпх┐ЕуБЪцЦЗцЮЭхоЕуВТшикуВМуБбуВГуВУуБУуВТцМпшИЮуБгуБжуБДуБЯуАВ ф╕╗уБкц╝ФчЫотА╗ц╝ФщбМуБоф║МщЗНуВлуВоцЛмх╝зуБпчЬБчХеуАВ хПдхЕ╕ф╕ЛшиШуБоуБЖуБбуАБуАОхИ╗уБЖуБйуВУуАПуБлуБдуБДуБжуБпуАБц╝ФшАЕуБМч╡╢уБИуБжуБДуБЯхЩ║уВТуАБхЕГшР╜шкЮхо╢я╝Иф╕ЙщБКф║нщБКф╕ЙщГОя╝ЙуБоц╝лцЙНх╕луГ╗ф║МшСЙхо╢хРЙщЫДуБЛуВЙцЦЗцЮЭуБМф╝ЭуБИуВЙуВМуБжх╛йшИИуБЧуБЯуБиуБДуБЖ[16]уАВ
цЦ░ф╜ЬщБОхО╗уБлхЗ║ц╝ФуБЧуБЯуГЖуГмуГУуГ╗уГйуВ╕уВкчХкч╡ДуГ╗цШачФ╗
CDуГ╗DVD
TBSуБошР╜шкЮчаФчй╢ф╝ЪуБоцШахГПуВТDVDхМЦуАВш▓йхг▓хЕГуБпуВИуБЧуВВуБиуВвуГ╝уГлуГ╗уВвуГ│уГЙуГ╗уВ╖уГ╝уАБчЫгф┐оуБпхЙНчФ░цЖ▓хП╕уАБшзгшкмуБпхЙНчФ░цЖ▓хП╕уАБф║мщаИхБХхЕЕуАБхМЧцЭСшЦлуАБф╕КщЗОщбпя╝ИчЖКщЗОщАЯчОЙхдзчд╛хоохП╕я╝ЙуАБцйШх╖жш┐СуАБцбВф╕ЙцЮЭуАВ
шСЧцЫ╕
х╝ЯхнРхдЪцХ░уБох╝ЯхнРуВТшВ▓уБжуАБуБЭуБохдЪуБПуБМшР╜шкЮхо╢уБауБСуБзуБкуБПуАБуГЖуГмуГУуВ┐уГмуГ│уГИуБиуБЧуБжуВВц┤╗ш║НуБЧуБжуБДуВЛуАВя╝ИхЕещЦАщаЖя╝Й
тА╗хнлх╝ЯхнРуБкуБйуБошй│ч┤░уБпцЦЗцЮЭф╕АщЦАуВТхПВчЕзуАВ шДЪц│иц│ищЗИ
хЗ║хЕ╕
хПВшАГцЦЗчМо
щЦвщАгщаЕчЫо
хдЦщГиуГкуГ│уВп |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal di Ensiklopedia Dunia














