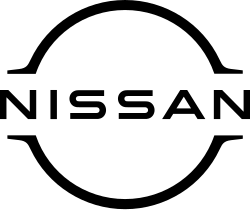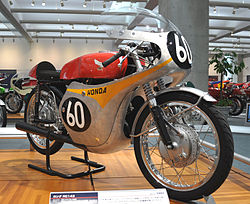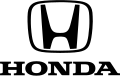µùحµ£شعسعèعّعéïكçزفïـك╗èع«ف╣┤كةذي╝êعسع╗عéôعسعèعّعéïعءعرععùعéâع«عصعéôع┤عéçعي╝ëعدع»عµùحµ£شعسعèعّعéïكçزفïـك╗èعسعجععخع«فç║µإحغ║ïعéْف╣┤كةذف╜تف╝عسµ▓ك╝ëعآعéïعéغ║îك╝زك╗èعغ╕ëك╝زك╗èعقةلآك╗îلôك╗èعééفسعéعéïعîعفا║µ£شقأعسفؤؤك╝زك╗èعسعجععخكذءك┐░عآعéïعé
µآéغ╗ثفî║فê
µùحµ£شع«كçزفïـك╗èف▓عسعèععخعرعôعسµآéغ╗ثفî║فêعéْق╜«ععïعذععقé╣ع»µخéعصغ╗حغ╕ïع«عéêععزكزشعîعéعéïعéµ£شكذءغ║ïعدع»عق»عéْفêعّعخكذءغ║ïع«كخïلأعùعéْكë»ععآعéïعاعéع«غ╛┐ف«£غ╕èعفكزشعéْµèءكة╖عùعخµآéغ╗ثفî║فêعéْكةîعثعخععéï[µ│ذ 1]عé
- µêخفë
- µا│ق¤░كسْغ╕ëعكçزفïـك╗èغ╕ëفف╣┤ف▓عي╝ê1944ف╣┤ي╝ëي╝أل╗µءµآéغ╗ثي╝ê1900ف╣┤ي╜ؤقأçفجزفصقî«ق┤ك╗èي╜إي╜ئي╝ëعقآ║ف▒ـµآéغ╗ثي╝ê1923ف╣┤ي╜ؤلûتµإ▒فجدل£çق╜ي╜إي╜ئي╝ëعµ╖╖غ╣▒µآéغ╗ثي╝ê1931ف╣┤ي╜ؤµ║µ┤▓غ║ïفجëي╜إي╜ئي╝ëعµـ┤فéآعâ╗ق╡▒فê╢µآéغ╗ثي╝ê1941ف╣┤ي╜ؤµ¤»لéثغ║ïفجëي╜إي╜ئي╝ë
- ف░╛ف┤µصثغ╣àعكçزفïـك╗èµùحµ£شف▓عي╝ê1955ف╣┤ي╝ëي╝أفêإµ£اي╝ê1904ف╣┤ي╜ؤف▒▒ق╛╜ف╝كْ╕µ░ùكçزفïـك╗èي╜إي╜ئي╝ëعكçزفïـك╗èقآ║µءµ£اي╝ê1907ف╣┤ي╜ئي╝ëعغ╣ùق¤ذك╗èف╖حµحصق░çفç║µ£اي╝ê1911ف╣┤لبâي╜ئي╝ëعف░فئïفؤؤك╝زغ╣ùق¤ذµ£اي╝ê1924ف╣┤ي╜ئي╝ë
- ف░╛ف┤µصثغ╣àعفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èف▓عي╝ê1966ف╣┤ي╝ëي╝أفêإµ£اي╝ê1899ف╣┤ي╜ؤعâùعâصعé░عâشعé╣لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èي╜إي╜ئي╝ëعµشدف╖ئك╗èµآéغ╗ثي╝ê1913ف╣┤ي╜ئي╝ëعق▒│فؤ╜ك╗èµآéغ╗ثي╝ê1925ف╣┤ي╜ئي╝ëعفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èµآéغ╗ثي╝ê1939ف╣┤ي╜ئي╝ë
- فجدلبêك│فْîق╛عكçزفïـك╗èف▓ع«µآéغ╗ثفî║فêعذفûق╖بµ│ـكخع«فجëل╖عي╝ê1990ف╣┤ي╝ëي╝أف║£ق£îغ╗جµآéغ╗ثي╝ê1903ف╣┤8µ£ê20µùحي╜ئي╝ëعµùدفûق╖بغ╗جµآéغ╗ثي╝ê1919ف╣┤1µ£ê11µùحي╜ئي╝ëعµû░فûق╖بغ╗جµآéغ╗ثي╝ê1933ف╣┤8µ£ê18µùحي╜ئي╝ë[W 1]
- ل╜ïكùجغ┐èف╜خعك╜ع«µûçفîûف▓عي╝ê1992ف╣┤ي╝ëي╝أµ║ق▒âµ£اي╝ê1898ف╣┤ي╜ؤعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسµ╕ةµإحي╜إي╜ئي╝ëعقآ║ف▒ـµ£اي╝ê1923ف╣┤ي╜ؤلûتµإ▒فجدل£çق╜ي╜إي╜ئي╝ëعµêخµآéµ£اي╝ê1937ف╣┤ي╜ؤµùحغ╕صµêخغ║ëفïâقآ║ي╜إي╜ئي╝ë[1]
- كْغ║ـغ╣àµ▓╗عكçزفïـك╗èع«قآ║ل¤ف▓ غ╕ïعي╝ê1995ف╣┤ي╝ëي╝أفû╢µحصعéكث╜لبع«لûïµïôµآéغ╗ثي╝ê1898ف╣┤ي╜ئي╝ëعµ£شµب╝قأعزكçزفïـك╗èغ╝أقج╛كذصقسïع«µآéغ╗ثي╝ê1911ف╣┤لبâي╜ئي╝ëعفؤ╜قصûعسعéêعéïكçزفïـك╗èق¤ثµحصع«غ┐إكص╖كé▓µêع«µآéغ╗ثي╝ê1932ف╣┤لبâي╜ئي╝ë[2]
- GPغ╝ق¤╗عé╗عâ│عé┐عâ╝عµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓ف╣┤كةذعي╝ê2006ف╣┤ي╝ëي╝أµءµ▓╗عâ╗فجدµصثµآéغ╗ثي╝ê1898ف╣┤ي╜ئي╝ëعµءصفْîعâ╗µêخفëµ£اي╝ê1927ف╣┤ي╜ئي╝ë
- عâêعâذعé┐فأقëرلجذعف╣┤فب▒ 2019ف╣┤ف║خقëêعي╝ê2020ف╣┤ي╝ëي╝أعâّعéجعéزعâïعéتل¤ع«فح«لùءي╝ê1904ف╣┤ي╜ئي╝ëعغ┐إµ£ëع«ف║âعîعéèعذق▒│فؤ╜فïتعسعéêعéïف╕صف╖╗ي╝ê1924ف╣┤ي╜ئي╝ëعل«ف╖إعذك▒èق¤░ع«µû░عاعزµîّµêخي╝ê1933ف╣┤ي╜ئي╝ëعكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصµ│ـي╝ê1936ف╣┤ي╜ئي╝ëعكçزفïـك╗èق¤ثµحصع«كîكè╜ي╝ê1936ف╣┤ي╜ئي╝ë[3]
- عâêعâذعé┐فأقëرلجذعف╣┤فب▒ 2019ف╣┤ف║خقëêعي╝ê2020ف╣┤ي╝ëي╝أكزـق¤افëفج£ع«كïخعùع┐ي╝ê1911ف╣┤ي╜ئي╝ëعع╡عاعéèع«لإرµû░كàع«قآ╗فب┤ي╝ê1933ف╣┤ي╜ئي╝ë[3]
- µêخف╛î
- فëق¤░غ┐ةق╛ععâûعâزعé┐عâïعéسفؤ╜لأؤفجدقآ╛قدّغ║ïفà╕ 8عي╝굤╣كذéقëêعâ╗1984ف╣┤ي╝ëي╝أقششغ╕µ£اعâ╗لثفêك╗µ¤»لàغ╕ïي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعقششغ║îµ£اعâ╗فجûفؤ╜µèكةôف░فàحµ£اي╝ê1953ف╣┤ي╜ؤµùحلçعµùحق¤ثعععآعéئع«فجûفؤ╜عâةعâ╝عéسعâ╝عذع«µèكةôµµ║ي╜إي╜ئي╝ëعقششغ╕ëµ£اعâ╗غ╣▒µêخµ£اي╝ê1959ف╣┤ي╜ؤغ╣ùق¤ذك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝ع«قس╢غ║ëعذµ╖ءµ▒░ي╜إي╜ئي╝ëعقششفؤؤµ£اعâ╗µêلـ╖µ£اي╝ê1964ف╣┤ي╜ؤق¤اق¤ثعذك╝╕فç║ع«µحفتùع«فدïع╛عéèي╜إي╜ئي╝ëعقششغ║¤µ£اعâ╗ك╗تµؤµ£اي╝ê1970ف╣┤ي╜ؤك│çµ£شكçزق¤▒فîûعسعéêعéïفجûك│çفéفàحي╜إي╜ئي╝ë[4]
- فجدلبêك│فْîق╛عكçزفïـك╗èف▓ع«µآéغ╗ثفî║فêعذفûق╖بµ│ـµ£اع«فجëل╖عي╝ê1990ف╣┤ي╝ëي╝أك╗تµؤµ£اي╝ê1948ف╣┤1µ£ê1µùحي╜ؤفàفïآق£كدثغ╜ôف╛îي╜إي╜ئي╝ëعق╛كةîµ│ـµآéغ╗ثي╝ê1951ف╣┤6µ£ê1µùحي╜ئي╝ë[W 1]
- كْغ║ـغ╣àµ▓╗عكçزفïـك╗èع«قآ║ل¤ف▓ غ╕ïعي╝ê1995ف╣┤ي╝ëي╝أµêخف╛îف╛ركêêعïعéëك▓┐µءôع«كçزق¤▒فîûع«µآéغ╗ثي╝ê1945ف╣┤8µ£êي╜ئي╝ëعفàل£عذك╝╕فç║ك╗èع«ق╡╢فح╜كز┐ع«µآéغ╗ثي╝ê1956ف╣┤لبâي╜ئي╝ëعق╡îµ╕êµّرµôخع«µ┐فîûع«µآéغ╗ثي╝ê1980ف╣┤لبâي╜ئي╝ë[2]
- GPغ╝ق¤╗عé╗عâ│عé┐عâ╝عµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓ف╣┤كةذعي╝ê2006ف╣┤ي╝ëي╝أµêخف╛îع«ف╛ركêêµ£اي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعµêلـ╖عذقس╢غ║ëع«فدïع╛عéèي╝ê1953ف╣┤ي╜ؤعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثع«فدïع╛عéèي╜إي╜ئي╝ëعل╗لçّع«60ف╣┤غ╗ثع«µ¤╗لء▓ي╝ê1960ف╣┤ي╜ؤفقج╛µû░ف╖حفب┤ع«ف«îµêي╜إي╜ئي╝ëععâئعéجعéسعâ╝µآéغ╗ثع«فê░µإحي╝ê1966ف╣┤ي╜ؤعâئعéجعéسعâ╝فàâف╣┤ي╜إي╜ئي╝ëعµْµ░ùكخفê╢عذعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ع«µآéغ╗ثي╝ê1974ف╣┤ي╜ؤعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ع«ف╜▒لا┐لةـف£ذفîûي╜إي╜ئي╝ëعµدكâ╜قس╢غ║ëعذفجأµدءفîûع«µآéغ╗ثي╝ê1980ف╣┤ي╜ؤك╗èقذ«ع«فجأµدءفîûي╜إي╜ئي╝ëعµآ┤عéîع«عةµؤçعéèعâ╗فجëفïـع«غ║êµاي╝ê1989ف╣┤ي╜ؤعâعâûعâسµآ»µ░ùعذعâعâûعâسف┤رفثèي╜إي╜ئي╝ëععâêعââعâùعâرعâ│عâèعâ╝ع╕ع«لôي╝ê1997ف╣┤ي╜ؤعâùعâزعéخعé╣قآ╗فب┤ي╜إي╜ئي╝ë
- Gazooععéêععéعïعéïكçزفïـك╗èµص┤ف▓لجذعي╝ê2013ف╣┤ي╝ëي╝أµêخف╛îقؤ┤ف╛îي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعف╛ركêêعذعâتعâ╝عé┐عâزعé╝عâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ê1955ف╣┤ي╜ؤلسءف║خق╡îµ╕êµêلـ╖µ£اع«فدïع╛عéèي╜إي╜ئي╝ëعقج╛غ╝أفـلةîقآ║ق¤اي╝ê1970ف╣┤ي╜ؤغ║جلأغ║ïµـàµص╗كàµـ░ع«قج╛غ╝أفـلةîفîûي╜إي╜ئي╝ëعل╗لçّµ£اي╝ê1981ف╣┤ي╝êµùحµ£شعîغ╕ûقـîµ£فجدع«كçزفïـك╗èق¤اق¤ثفؤ╜عسي╝ëي╜ئي╝ëعµ┐فïـµ£اي╝ê1992ف╣┤ي╜ؤعâعâûعâسف┤رفثèف╛îي╜إي╜ئي╝ëعµû░µèكةôي╝ê1997ف╣┤ي╜ؤعâùعâزعéخعé╣قآ╗فب┤ي╜إي╜ئي╝ë[W 2]
- عâêعâذعé┐فأقëرلجذعف╣┤فب▒ 2019ف╣┤ف║خقëêعي╝ê2020ف╣┤ي╝ëي╝أف╛رµùدعâ╗ففç║قآ║µ£اي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعق¤ثµحصفا║قؤجµدïق»ëµ£اي╝ê1959ف╣┤ي╜ئي╝ëعف«îµêك╗èك╝╕فç║µïةفجدµ£اي╝ê1970ف╣┤ي╜ئي╝ëعµ╡╖فجûق¤اق¤ثل▓فç║µ£اي╝ê1980ف╣┤ي╜ئي╝ëععé░عâصعâ╝عâعâسفîûعذµ╕رµأûفîûف»╛ف┐£µ£اي╝ê1990ف╣┤ي╜ئي╝ë[3]
µêخفëµ£ا
كçزفïـك╗èع«غ╝إµإحي╝ê1890ف╣┤غ╗ثي╜ئي╝ë
19غ╕ûق┤µ£سعسفجûفؤ╜عïعéëµùحµ£شعسكçزفïـك╗èعîµîعةك╛╝ع╛عéîفدïعéعéïي╝êكçزفïـك╗èع«µ╕ةµإحي╝ëعé20غ╕ûق┤ي╝ê1901ف╣┤ي╝ëعسفàحعéïعذعفجûفؤ╜فـلجذعسعéêعéïك╝╕فàحعîفدïع╛عéèعف░ّلçعزعîعéëع╛عذع╛عثعاµـ░ع«كçزفïـك╗èعîµîعةك╛╝ع╛عéîعéïعéêععسعزعéïعéف╜ôµآéع»غ╕ûقـîعدعééعéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│ك╗èع»غ╕╗µ╡ع«ف£░غ╜عéْقت║قسïعùعخعèعéëعأعµùحµ£شعسعééعéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│ك╗èغ╗حفجûعسكْ╕µ░ùكçزفïـك╗èعéلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعééµîعةك╛╝ع╛عéîعاعéعôع«µآéµ£اع«فç║µإحغ║ïع»غ╕µءقئصعزعôعذعîفجأععكز┐µا╗عâ╗قب¤قر╢عسعéêعثعخعإعéîع╛عدع«لأكزشعîفجëµؤ┤عـعéîعاعôعذعîف░ّعزععزععé
- 1895ف╣┤ي╝êµءµ▓╗28ف╣┤ي╝ë
- 1896ف╣┤ي╝êµءµ▓╗29ف╣┤ي╝ë
- 1898ف╣┤ي╝êµءµ▓╗31ف╣┤ي╝ë
 عâعâûعâعذعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسي╝ê1898ف╣┤عâ╗كçزفïـك╗èع«فêإµ╕ةµإحي╝ë
عâعâûعâعذعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسي╝ê1898ف╣┤عâ╗كçزفïـك╗èع«فêإµ╕ةµإحي╝ë
- 1899ف╣┤ي╝êµءµ▓╗32ف╣┤ي╝ë
- 7µ£ê17µùحعµùحكï▒لأفـكêزµ╡╖µإةق┤عîقآ║فè╣عùعµùحµ£شعîغ╕ف╣│قصëµإةق┤عéْق╡عéôعدععاغ╗ûع«فؤ╜عذع«لûôعدعééفîµدءع«µ¤╣µصثµإةق┤عîقآ║فè╣عآعéïي╝êعâـعâرعâ│عé╣ععéزعâ╝عé╣عâêعâزعéتعذع«µإةق┤ع»فîف╣┤8µ£ê4µùحقآ║فè╣ي╝ëعéعôعéîعسعéêعéèفجûفؤ╜غ║║ف▒àقـآف£░عîف╗âµصتعـعéîعفجûفؤ╜غ║║عاعةع»ف▒àغ╜عâ╗µùàكةîعâ╗فû╢µحصع«كçزق¤▒عîكزعéعéëعéîعéïي╝êفàف£░لؤّف▒àي╝ëعé
- 1900ف╣┤ي╝êµءµ▓╗33ف╣┤ي╝ë
- 8µ£êععé╡عâ│عâـعâرعâ│عé╖عé╣عé│ع«ف£ذق▒│µùحµ£شغ║║غ╝أعîقأçفجزفصفءëغ╗كخزقïي╝êف╛îع«فجدµصثفجرقأçي╝ëع«µêفرأعéْقحإعùعخلؤ╗µ░ùف╝فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعéْقî«ق┤عآعéïي╝êقأçفجزفصقî«ق┤ك╗èي╝ë[16][17][18][6][µ│ذ 7]عé
- µآéµ£اغ╕µء[µ│ذ 8]عف««فàق£ع«غ╛إلب╝عسعéêعéèلسءق¤░فـغ╝أع«ف╗ثق¤░ق▓╛غ╕عéëعسعéêعثعخفîك╗èع«كرخلذôك╡░كةîعîكةîعéعéîععإع«لأؤعسلôك╖»عéْل╕ك▒عùعخµ┐بعسك╜عةعéïغ║ïµـàي╝êµ░┤µ▓ةع»عùعخععزعي╝ëعîك╡╖ععاعôعذعدعقأçفجزفصفجسفخ╗ع╕ع«قî«ق┤ع»كخïلعéëعéîعéï[21]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعسعéêعéïغ║جلأغ║ïµـàي╝ë
- 1901ف╣┤ي╝êµءµ▓╗34ف╣┤ي╝ë
 µùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣ي╝ê1901ف╣┤11µ£êي╝ë
µùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣ي╝ê1901ف╣┤11µ£êي╝ë
- 1902ف╣┤ي╝êµءµ▓╗35ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êععâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعîغ╝أفôةعïعéëغ╝أك▓╗عéْفûعثعخكçزفïـك╗èعسغ╣ùعؤعéïكçزفïـك╗èف╢µح╜لâذعéْكذصقسïعآعéïعîعغ╝أفôةعذعزعéïكàع»ع╗عذعéôعرق╛عéîعأعسق╡éعéعéï[6][ف«أكزشع«فجëفîû 3]عé
- 3µ£êعلسءقاحع«غ╗赤┐قîزقèعîفجدلءزعدكث╜لبعـعéîعاقا│µ▓╣قآ║فïـµراك╗èعéْغ╜┐عثعخلسءقاحظ¤غ╝èلçلûôعدغ╣ùفêكçزفïـك╗èعذعùعخك╡░عéëعؤعق┤فèف╣┤لûôفû╢µحصعآعéï[36][37][µ│ذ 14]عé
- 4µ£ê5µùحعغ╕èلçفàشف£ْع«غ╕ف┐µ▒بقـ¤عدكçزك╗تك╗èعâشعâ╝عé╣عîكةîعéعéîععإع«غ╜آكêêعذعùعخكçزفïـك╗èعسعéêعéïقس╢ك╡░عîكةîعéعéîعéï[23][33][6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«ي╜ؤكجçµـ░ع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعسعéêعéïي╜إكçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣ي╝ë
- 4µ£êععéخعéرعâسعé┐عâ╝عâ╗عé╣عâêعâ╝عâ│عîك╝╕فàحعùعاعâصعé│عâتعâôعâسكْ╕µ░ùكçزفïـك╗è8ف░عîµذزµ╡£µ╕»عسفê░قإعآعéï[38][6][µ│ذ 15]عéفîف╣┤6µ£êعسف╝ـعفûعéèعîكةîعéعéîعالأؤعسكçزفïـك╗èعسف»╛عآعéïلûتقذع«µ£زµـ┤فéآعسعéêعéèµذزµ╡£قذلûتعïعéë2فë▓5فêع«لûتقذعéْكز▓عـعéîعك╝╕فàحغ╕╗ع«عéخعéرعâسعé┐عâ╝عâ╗عé╣عâêعâ╝عâ│ع»1فë▓عسعآعéïع╣ععذقـ░كص░ق¤│عùقسïعخعéْكةîع[40]عé
- فî4µ£êعµذزµ╡£عدعâصعé│عâتعâôعâسي╝êكï▒كزئقëêي╝ëقج╛ع«µùحµ£شك╝╕فàحغ╗ثقف║ùعîعâصعé│عâتعâôعâسعâ╗عéسعâ│عâّعâïعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗ق▒│فؤ╜µùحµ£شغ╗ثقف║ùععîكذصقسïعـعéîعéï[41][6][42]عé
- 5µ£êعغ╕ëغ║ـفّëµ£ف║ùي╝êف╛îع«غ╕ëك╢èي╝ëعîعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعسفـق¤ذكçزفïـك╗èعéْµ│ذµûçعآعéï[43][6]عé
- 6µ£êععâصعé│عâتعâôعâسµùحµ£شغ╗ثقف║ùعîµإ▒غ║شعâ╗كèإفثعدك▓رفث▓ف║ùي╝êفـفôلآ│فêùµëي╝ëعéْلûïف║ùعآعéï[ف«أكزشع«فجëفîû 4]عé
- 7µ£êعµذزµ╡£عé░عâرعâ│عâëعâ╗عâؤعâعâسع«كçلôعدععéجعé«عâزعé╣غ║║عé»عâ╝عâ│عîعلإ┤ك╖غ║║ع«كùجµ£شغ╗▓µشةلâعéْكçزفïـك╗èعدك▓بفé╖عـعؤعéï[6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعسعéêعéïغ║║ك║سغ║ïµـàي╝ë
- 1903ف╣┤ي╝êµءµ▓╗36ف╣┤ي╝ë
 قشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعدكçزفïـك╗èع«ف▒ـقج║عîكةîعéعéîعاعéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣&عé╕عâدعâ╝عé╕لجذ[46][47]
قشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعدكçزفïـك╗èع«ف▒ـقج║عîكةîعéعéîعاعéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣&عé╕عâدعâ╝عé╕لجذ[46][47]
- 1µ£êغ╗حفëعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عîكçزفïـك╗èع«كرخلذôعéْكةîع[48][µ│ذ 16]عé
- 3µ£ê1µùحعïعéë7µ£ê31µùحعسعïعّعخعفجدلءزعدقشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعîلûïفéشعـعéîعكçزفïـك╗èعîكجçµـ░ف░فç║فôعـعéîععâçعâتك╡░كةîعééµèسل£▓عـعéîعéï[ف«أكزشع«فجëفîû 5]عéعôعéîع»كçزفïـك╗èعîفجأعع«غ╕كêشع«µùحµ£شغ║║ع«قؤ«عسكدخعéîعéïµ£فêإع«µراغ╝أعذعزعéè[54][30][W 11]عµùحµ£شفف£░عدغ╣ùفêكçزفïـك╗èعîكذêق¤╗عـعéîعéïعéêععسعزعéï[55][56][57]عé
- 4µ£êغ╕ïµùش[58]ععôعéîعéْكخïعاµث«µê┐لبعذµحبفحفجزلâعîكçزفïـك╗èع«كث╜غ╜£عéْµ▒║µعùعف«الأؤع«كث╜لبع»ف▒▒ق╛╜كآفجسعسغ╛إلب╝عآعéï[51]عé
- 4µ£êعغ╕ëغ║ـفّëµ£ف║ùعîعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعسµ│ذµûçعùعخععاعâـعâرعâ│عé╣كث╜ع«فـق¤ذك╗èي╝êعé»عâشعâةعâ│عâêي╝ëعîفê░قإعùعفîف║ùع»عإعéîعéْفـفôلàل¤عسغ╜┐ق¤ذعآعéï[43][6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«فـق¤ذكçزفïـك╗è[µ│ذ 17]ي╝ë
- 8µ£ê20µùحعµؤقاحق£îعدغ╣ùفêكçزفïـك╗èفûق╖بكخفëçي╝êق£îغ╗جقشش61ف╖ي╝ëعîفàشف╕âعـعéîعéï[6][W 9]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èفûق╖بكخفëç[ف«أكزشع«فجëفîû 6]ي╝ë
- 9µ£ê20µùحعغ║شلâ╜ع«غ║îغ║ـفـغ╝أعîعâêعâشعâëكْ╕µ░ùكçزفïـك╗èعéْµ¤╣لبعùعاك╗èغ╕ةعéْق¤ذععخغ╣ùفêكçزفïـك╗èغ║ïµحصعéْفدïعéعéï[6][62][µ│ذ 18]عé
- 11µ£ê21µùحعغ║îغ║ـفـغ╝أ عسعéêعéïف╕éفàغ╣ùفêكçزفïـك╗èع«فû╢µحصعîكزف»عـعéîعéï[61][63]عéي╝êµùحµ£شµ£فêإع«غ╣ùفêكçزفïـك╗è[µ│ذ 19]ي╝ë
- 11µ£êعفîك╝زفـغ╝أعîكçزفïـك╗èلâذي╝êكçزفïـك╗èك▓رفث▓لâذي╝ëعéْكذصق╜«عùعكçزفïـك╗èف║âفّèعéْلؤّكزîعسفç║عآ[55][65][6][66]عé
- 12µ£êعµؤقاحق£îففجف▒ïف╕éعدكçزفïـك╗èقذعذعùعخ1ف░عéعاعéèف╣┤20فعéْكز▓عآµµةêعîفç║عـعéîعف»µ▒║عـعéîعéï[6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èقذ[ف«أكزشع«فجëفîû 7]ي╝ë
فؤ╜ق¤ثك╗èع«فدïع╛عéèي╝ê1904ف╣┤ي╜ئي╝ë
كçزفïـك╗èعîف║âعقاحعéëعéîعéïعéêععسعزعéïعسعجعéîعفؤ╜ق¤ثك╗èكث╜لبعéْف┐ùعآكàعîفف£░عسق╛عéîعéï[67]عéعùعïعùµùحµ£شع«ف╖حµحصµèكةôفàذغ╜ôع«µ£زقاعـعïعéëق¤ثµحصعذعùعخع«كçزفïـك╗èف╖حµحصعîقت║قسïعآعéïµإةغ╗╢ع»عôع«µآéµ£اعسع»عإعéعéعزعïعثعا[W 4]عéµشدق▒│عïعéëكçزفïـك╗èعéْµîعةف╕░عéïكàعاعةعééق╛عéîعéïعîععèعإعéعùعلسءغ╛ةعدعéعéïعôعذعسفèبعêعخف┐àكخµدعééغ╕ف»كدثعدعéعéïعôعذعïعéëلزذكّثك╢ثفّ│ع«فجëف╜تععéëععسكâعêعéëعéîعخعèعéè[68]عغ╕èµ╡لأق┤أع«كàعاعةع«لôµح╜عذععف┤لإتعîفجدععµآéµ£اعبعثعا[µ│ذ 20]عé
- 1904ف╣┤ي╝êµءµ▓╗37ف╣┤ي╝ë
- 1905ف╣┤ي╝êµءµ▓╗38ف╣┤ي╝ë
 عâعâرعââعé»ف╖ي╝êفآق£اع»1908ف╣┤ي╝ë
عâعâرعââعé»ف╖ي╝êفآق£اع»1908ف╣┤ي╝ë
- 2µ£ê5µùحعف║âف│╢ق£îع«µذزف╖إلدàظ¤ف»لâذلûôعدغ╣ùفêعâعé╣غ║ïµحصعîفدïع╛عéï[6][W 14][ف«أكزشع«فجëفîû 12]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâعé╣فû╢µحص[µ│ذ 23]ي╝ë
- 5µ£êعفجدلءزع«ف▓ةق¤░فـغ╝أعîعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسAعéْك╝╕فàحعآعéï[6][78]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâـعéرعâ╝عâëك╝╕فàحك╗è[ف«أكزشع«فجëفîû 8]ي╝ë
- 8µ£ê26µùحعµ£ëµبûف╖إف««فذغ╗كخزقïعîµشدف╖ئµص┤كذزعïعéëف╕░فؤ╜عéكخزقïعîعéجعé«عâزعé╣عدك│╝فàحعùعاعâـعâرعâ│عé╣ك╗èعîعâعâرعââعé»ف╖عع»فîف╣┤10µ£ê11µùحعسµ£ëµبûف╖إف««لé╕عسفê░قإعآعéï[79]عé
- 9µ£ê5µùحعµùحل£▓µêخغ║ëعîق╡éµêخعآعéïعéفجدلآ╕عسعèعّعéïµêخلùءعدف╛ùعاق╡îلذôعïعéëعلآ╕ك╗ع»كçزفïـك╗èع«ف┐àكخµدعéْكزكصءعùعµêخف╛îعسفà╖غ╜ôقأعزقب¤قر╢عéْل▓عéعéï[80]عé
- 10µ£ê12µùحعفذغ╗كخزقïعîعâـعâرعâ│عé╣ك╗èعâعâرعââعé»ف╖عسغ╣ùعثعخفéفàعآعéï[81][6]عéي╝êكçزفïـك╗èعسغ╣ùعثعخفéفàعùعافêإع«غ║ïغ╛ïي╝ë
- 10µ£ê26µùحعفب║ف╕éقحئµءق¤║فجدلأعéèعدعفجدلءزكçزفâك╗èغ╝أقج╛ع«كçزفïـك╗èعîل╛ف░كè│ي╝ê5µص│ي╝ëعéْك╜تععخµص╗غ║ةعـعؤعéï[6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعسعéêعéïµص╗غ║ةغ║ïµـàي╝ë
- 1906ف╣┤ي╝êµءµ▓╗39ف╣┤ي╝ë
- 1907ف╣┤ي╝êµءµ▓╗40ف╣┤ي╝ë
 عé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝ê1907ف╣┤12µ£êي╝ë
عé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝ê1907ف╣┤12µ£êي╝ë
- 2µ£êعكصخكخûف║ (فàفïآق£)عîكçزفïـك╗èفûق╖بكخفëçعéْفê╢ف«أعآعéï[W 16]عé
- كçزف«╢ق¤ذكçزفïـك╗èعéْفàشلôعدلïك╗تعآعéïعسع»فàكذ▒عîف┐àكخعذعزعéèعغ╕ëغ║ـلèكةîقج╛لـ╖غ╕ëغ║ـلسءغ┐إع«لïك╗تµëïعéْفïآعéعخععاµ╕ةك╛║ف«êك▓ئعîفàكذ▒فûف╛ùقشش1ف╖عذعزعéïعé
- عâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêع«كثàقإعîق╛رفïآعحعّعéëعéîعقآ╗لî▓قـزف╖عî1عع»µءµ▓╗ف▒ïعسفë▓عéèف╜ôعخعéëعéîعéï[84][µ│ذ 25]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêي╝ë
- 4µ£êعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعîعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسNعéْ20ف░ك╝╕فàحعùععîعةعرعéèف╖عع«فعéْغ╗ءعّعخك▓رفث▓عéْلûïفدïعآعéï[83][78][µ│ذ 26]عé
- 7µ£ê6µùحععéجعé«عâزعé╣قـآفصخغ╕صع«فجدفëفû£غ╕âي╝êف╛îع«فû£غ╕âلâي╝ëعîعâûعâسعââعé»عâرعâ│عé║عدلûïفéشعـعéîعاقشش1فؤئكçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣عسفç║فب┤عùععإع«غ╕صع«عâتعâ│عé┐عé«عâحعâ╝عâ╗عéسعââعâùعâ╗عâشعâ╝عé╣ي╝êMontagu Cupي╝ëعد2غ╜عسفàحك│ئعآعéïي╝êك╗èغ╕ةع»عâـعéثعéتعââعâêي╝ë[W 17]عé
- 9µ£êععé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝êكث╜لبع»µإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëي╝ëع«قشش1ف╖ك╗èعîµخéعصف«îµêعùعµ£ëµبûف╖إف««فذغ╗كخزقïعسعéêعéïكرخغ╣ùعîكةîعéعéîععإع«ف╛îعفîك╗èع»قë╣فêحعزفةùكثàعéفàكثàعéْµû╜عـعéîعاغ╕èعد11µ£êµ£سعسكخزقïعسقî«غ╕èعـعéîعا[79][W 18][ف«أكزشع«فجëفîû 8]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗è[µ│ذ 27][ف«أكزشع«فجëفîû 13]ي╝ë
- قدïعلسءف│░كص▓فëع«µفّعسعéêعéèعغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛عîعâـعéرعâ╝عâëك╗èع«ك╝╕فàحك▓رفث▓µحصعéْفدïعéعéï[16][61]عé
- 1908ف╣┤ي╝êµءµ▓╗41ف╣┤ي╝ë
- 2µ£êعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عîك│╝فàحعùعاعâـعâرعâ│عé╣كث╜ع«عâعâ╝عâبك╗ق¤ذعâêعâرعââعé»2ف░عîفê░قإعùع2µ£ê18µùحعسµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعدكرخلïك╗تعîكةîعéعéîعéï[48]عéي╝êµùحµ£شعسفêإعéعخµîعةك╛╝ع╛عéîعاك╗ق¤ذكçزفïـك╗èي╝ë
- عôع«ك╗èغ╕ةع»µ║µ┤▓ع«كْلçعéْµâ│ف«أعùعخق┐ْف┐ùلçلîشفà╡فب┤ي╝êفâكّëق£îي╝ëعسلïع│ك╛╝ع╛عéîعخكرخك╡░عéْق╣░عéèك┐¤عùعاف╛îعفîف╣┤7µ£êعïعéë8µ£êعسعïعّعخµإ▒غ║شعذلإْµث«عéْكçزك╡░عùعخف╛ف╛رعآعéïلبف╛عéْكةîع[90][80]عé
- 5µ£ê30µùحععâïعâحعâ╝عâذعâ╝عé»عâ╗عâّعâزعâشعâ╝عé╣ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعسفéفèبغ╕صع«عâëعâ╗عâçعéثعéزعâ│عâ╗عâûعâ╝عâêعâ│ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعذعâûعâشعé╖عéتعâ╗عé╕عâحعé╣عâêي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعîµذزµ╡£µ╕»عسفê░قإعùع6µ£ê10µùحعسع»فîعءععâêعâ╝عâئعé╣عâ╗عâـعâرعéجعâجعâ╝ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعîفê░قإعآعéï[91]عéغ╕كةîع»µذزµ╡£عïعéëµإ▒µ╡╖لôق╡îق¤▒عدغ║شلâ╜عسفّعïعثعاف╛îعµـخك│µ╕»ع╛عدك╡░كةîعآعéï[91][W 19][µ│ذ 28]عé
- 8µ£ê1µùحعµ£ëµبûف╖إف««فذغ╗كخزقïعéْفàêلبصعسعµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعïعéëقسïف╖إع╛عد10ف░ع«كçزفïـك╗èعîفéفèبعآعéïلبغ╣ùعéèغ╝أعîفéشعـعéîعéï[µ│ذ 29]عéقأçµùعîفéفèبعùعاعذعععôعذعééعéعثعخعôع«فç║µإحغ║ïع»µû░كئعزعرعدفجدععفب▒عءعéëعéîعخكçزفïـك╗èع╕ع«لûتف┐âعîلسءع╛عéèعك▓ةلûحق│╗ع«µ£ëفèؤغ╝µحصعسعéêعéïكçزفïـك╗èك╝╕فàحع╕ع«فéفàحعéْغ┐âعآعزعرع«ف╜▒لا┐عéْغ╕عêعéï[69]عé
- 12µ£ê15µùحعلôغ┐ةق£عîلâ╡غ╛┐لôلعسكçزفïـك╗èعéْفêإعéعخق¤ذععéï[W 20]عéµإ▒غ║شغ╕صفج«لâ╡غ╛┐ف▒عذµإ▒غ║شف╕éفàع«فêف«جعذع«لûôع«لôلعسق¤ذععéëعéîعéï[W 20]عé
- µآéµ£اغ╕µءعµإ▒غ║شµ┤▓ف┤فاïقسïف£░عدµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëع«عé┐عé»عâزعâ╝ف╖عذغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛ع«عâـعéرعâ╝عâëك╗èعîµدكâ╜µ»¤ك╝âعéْقؤ«قأعذعùعاقس╢ك╡░عéْكةîعععé┐عé»عâزعâ╝ف╖عîغ╕èفؤئعéï[93]عéعôع«ق╡µئ£عكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسكخïفêçعéèعéْعجعّعاغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛ع»ف£ذف║سعéْ2ف╣┤ع╗عرعïعّعخفث▓عéèفêçعéè[68]ععâـعéرعâ╝عâëع«ك╝╕فàحك▓رفث▓µذرعéْµëﵤ╛عآ[93]عé
- 1909ف╣┤ي╝êµءµ▓╗42ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛عîعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسTي╝êTفئïعâـعéرعâ╝عâëي╝ëع«ك╝╕فàحك▓رفث▓عéْفدïعéعéïعééع«ع«[6][94]عع╗عرعزععâـعéرعâ╝عâëك╗èع«ك╝╕فàحك▓رفث▓عïعéëµëïعéْف╝ـع[78]عé
- 4µ£êعفؤ╜µ£سف╖1ف╖ك╗èي╝êكث╜لبع»ف▒▒ق¤░لëف╖حµëي╝ëعîف«îµêعآعéï[89][95]عéي╝êفêإع«ق┤¤فؤ╜ق¤ثعéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗è[µ│ذ 30]ي╝ë
- 9µ£êعفجدلءزعدف│╢µ┤حµحتك¤╡عî4عé╡عéجعé»عâس400 ccع«عéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│عذعإع«ك╗èغ╜ôعéْكث╜غ╜£عùععéزعâ╝عâêعâعéجي╝êNSف╖ي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéï[W 21]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«غ║îك╝زكçزفïـك╗è[µ│ذ 31]ي╝ë
- 11µ£êعفجدفëفû£غ╕âي╝êف╛îع«فû£غ╕âلâي╝ëعîفجدµùحµ£شكçزفïـك╗èكث╜لبفêك│çغ╝أقج╛عéْكذصقسïعآعéï[6]عé
- µ£سعكصخكخûف║عîµإ▒غ║شف║£فàع«قآ╗لî▓كçزفïـك╗èعéْع╛عذعéعاعâزعé╣عâêعéْغ╜£µêعآعéï[97]عé
- 1910ف╣┤ي╝êµءµ▓╗43ف╣┤ي╝ë
- 8µ£êععîفجدµùحµ£شكçزفïـك╗èكث╜لبفêك│çغ╝أقج╛ععîعîµùحµ£شكçزفïـك╗èفêك│çغ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[6]عé
- 12µ£ê20µùحعف╕إفؤ╜عâؤعâعâسي╝êµإ▒غ║شي╝ëعدµùحµ£شكçزفïـك╗èف╢µح╜لâذي╝êNACي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[61][6]عé
- µآéµ£اغ╕µءعفëق¤░ق£افجزلâعîفëق¤░فـف║ùعéْكذصقسïعùعفîµآéعسعîكçزفïـك╗èلïك╗تµëïغ┐«µèµëععذععفع«لïك╗تµëïلجèµêµëعéْفë╡قسïعآعéï[98]عéي╝êµùحµ£شµ£فêإع«لïك╗تµëïلجèµêق╡ق╣¤ي╝ë
µشدف╖ئك╗èع«µآéغ╗ثي╝ê1911ف╣┤ي╜ئي╝ë
فزق╛عزµشدف╖ئك╗èع»كçزفïـك╗èع«غ╕╗كخلةدف«تعدعéعéïغ╕èµ╡لأق┤أع«كàعاعةعسفح╜ع╛عéîعغ╕╗µ╡ع«ف£░غ╜عéْفبعéعéïعéقأçف«جعéف«ءفàشف║عدعééكçزفïـك╗èعîفêرق¤ذعـعéîفدïعéععé┐عé»عé╖عâ╝غ║ïµحصعéْفدïعéعéïكàعاعةعééق╛عéîفدïعéعéïعéقششغ╕µشةغ╕ûقـîفجدµêخي╝ê1914ف╣┤ - 1918ف╣┤ي╝ëعéْكâîµآ»عسك╗ق¤ذعذعùعخع«قب¤قر╢عééفà╖غ╜ôµدعéْف╕»ع│علآ╕ك╗غ╕╗ف░عدف«الذôقأعسك╗èغ╕ةعîغ╜£عéëعéîعéïعéêععسعزعéïعéµ░ّلûôعسعèععخعééفف£░عدفؤ╜ق¤ثع«غ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبعîكرخع┐عéëعéîعéïعééع«ع«كرخغ╜£ع«فااعéْفç║عéïقëرع»عزععق▒│فؤ╜عïعéëك╝╕فàحعـعéîفدïعéعاعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسTع»ف╛عàعسفïتفèؤعéْµïةفجدعùفدïعéعéïعé
- 1911ف╣┤ي╝êµءµ▓╗44ف╣┤ي╝ë
 عâئعâ╝عé╣لثؤكةîفثسع«لثؤكةîµراعذفجدفëفû£غ╕âلâع«كçزفïـك╗èع«قس╢غ║ëي╝ê1911ف╣┤5µ£êي╝ë
عâئعâ╝عé╣لثؤكةîفثسع«لثؤكةîµراعذفجدفëفû£غ╕âلâع«كçزفïـك╗èع«قس╢غ║ëي╝ê1911ف╣┤5µ£êي╝ë
- 1912ف╣┤ي╝êµءµ▓╗45ف╣┤ي╝فجدµصثفàâف╣┤ي╝ë
- 1913ف╣┤ي╝êفجدµصث2ف╣┤ي╝ë
- 1914ف╣┤ي╝êفجدµصث3ف╣┤ي╝ë
- 3µ£ê10µùحعµإ▒غ║شµ╡╖غ╕èغ┐إلآ║عîكçزفïـك╗èغ┐إلآ║ع«فûµë▒ععéْلûïفدïعآعéï[123][W 29]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èغ┐إلآ║ي╝ë
- 3µ£ê20µùحعïعéë7µ£ê31µùحعسعïعّعخغ╕èلçفàشف£ْعدµإ▒غ║شفجدµصثفأكخدغ╝أعîلûïفéشعـعéîعéïعéف┐سل▓قج╛كçزفâك╗èف╖حفب┤ع«عâعââعâêكçزفïـك╗èي╝êلأقد░عîDATف╖ععîك▒فàف╖ع[µ│ذ 38]ي╝ëعزعرعîفç║فôعـعéîعéïعé
- غ╕ëغ║ـقëرق¤ثعîكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسكخïفêçعéèعéْعجعّعخµëïعéْف╝ـععفîقج╛قج╛فôةع«µتقشلـ╖فجزلâعسع╗ع╝قةفاعدغ║ïµحصكص▓µ╕ةعآعéï[125][W 30][µ│ذ 39]عéق┐îف╣┤5µ£êعµتقشع»µإ▒غ║شµùحµ»¤ك░╖عدµتقشفـغ╝أي╝êف╛îع«عâجعâèعé╗ي╝ëعéْفë╡µحصعùعك▓╕عéشعâشعâ╝عé╕µحصعéْفدïعéعéï[W 30]عé
- 7µ£êعقششغ╕µشةغ╕ûقـîفجدµêخعîفïâقآ║عùعاعôعذعدعµùحµ£شعدع»كçزفïـك╗èع«ك╝╕فàحعîµصتع╛عéïعéغ╕µû╣عفجدµêخµآ»µ░ùعسعéêعéèعîµêلçّععذفّ╝ع░عéîعéïغ┐ف»îك▒زعîفتùعêعاعôعذعدق┐îف╣┤عïعéëع»ف£ذف║سع«ك╗èعîلثؤع╢عéêععسفث▓عéîعéïعéêععسعزعéèعك╗èع»فôكûعذعزعéï[W 31][µ│ذ 40]عé
- 9µ£êعلإْف│╢µ¤╗قـحعéْقؤ«قأعذعùعاµêخلùءي╝êلإْف│╢ع«µêخعي╝ëعسفàêقسïعةعغ╕èلآ╕لâذلأèع«ك╗ل£قëرك│çك╝╕لق¤ذعذعùعخعµùحµ£شع«ك╗لأèعدع»فêإعéعخك╗ق¤ذعâêعâرعââعé»عîف«اµêخعسµèـفàحعـعéîعéï[61][108][129][80]عé
- 1915ف╣┤ي╝êفجدµصث4ف╣┤ي╝ë
 كçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░غ╝أي╝ê1915ف╣┤10µ£êي╝ë
كçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░غ╝أي╝ê1915ف╣┤10µ£êي╝ë
- 8µ£êعµءافصفïçع«ععéشعé╜عâزعâ│قآ║فïـµراكçزفïـك╗èعي╝êعâتعâ╝عé┐عâ╝لؤّكزîقج╛ي╝ëعîفêèكةîعـعéîعéï[130][W 32]عé
- 10µ£ê16µùحعâ╗17µùحعµإ▒غ║شقؤ«ل╗ْقس╢لخشفب┤عدµإ▒غ║شكçزفïـك╗èفèكçزفïـكçزك╗تك╗èقس╢µèغ╝أي╝êكçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░غ╝أي╝ëعîلûïفéشعـعéîعéï[130][101]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كêêكةîعذعùعخع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣[µ│ذ 41]ي╝ë
- 11µ£ê10µùحعغ║شلâ╜ف╛ةµëعسعèععخفجرقأçفءëغ╗ع«ف│غ╜ع«قج╝عîكةîعéعéîعéïعéفéفêùعآعéïففؤ╜µ¤┐ف║£لسءف«ءق¤ذع«لسءق┤أغ╣ùق¤ذك╗èعéف│غ╜ف╝ع«عâّعâشعâ╝عâëعéْكص╖كةؤعآعéïعاعéع«كçزفïـك╗èعîفجدلçعسف┐àكخعذعزعéèعق¤ذقسïعخعéëعéîعéï[131][132]عé
- 1916ف╣┤ي╝êفجدµصث5ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµإ▒غ║شف║£ع«قآ║فïـµراف¤غ╝أعسكçزفïـك╗èلïك╗تµëïلجèµêلâذعîكذصقسïعـعéîعلïك╗تµëïع«لجèµêعîفدïع╛عéï[130]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èµـآق┐ْµë[µ│ذ 42]ي╝ë
- 3µ£êعïعéë8µ£êعسعïعّعخلçّفصفûغ╕ع«عكçزفïـك╗èفصخµـآµêµؤ╕عي╝êقآ║فïـµراف¤غ╝أي╝ëعîفàذ7ف╖عدقآ║كةîعـعéîععâآعé╣عâêعé╗عâرعâ╝عذعزعéï[130][W 33]عé
- 8µ£êعقاتلçفûغ╕عîعéتعâصعâ╝ف╖عéْف«îµêعـعؤعéï[W 34]عéعôع«ك╗èغ╕ةع»فîµآéغ╗ثع«غ╗ûع«ك╗èغ╕ةعذقـ░عزعéèلـ╖عµ«ïعéèع2025ف╣┤ق╛ف£ذعééµ£فجع«فؤ╜ق¤ثك╗èغ╕ةعذعùعخق╛فصءعùعخععéïعé
- µآéµ£اغ╕µءعفجدلءزعدغ╕صف│╢فـغ╝أعîعâجعâئعâ╝عé┐ف╖عéْكث╜غ╜£عآعéï[133][µ│ذ 43]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زي╝ë
- 1917ف╣┤ي╝êفجدµصث6ف╣┤ي╝ë
- 1918ف╣┤ي╝êفجدµصث7ف╣┤ي╝ë
 غ╕ëك▒عâ╗Aفئïع«كرخغ╜£ك╗èي╝ê1917ف╣┤ي╝ë
غ╕ëك▒عâ╗Aفئïع«كرخغ╜£ك╗èي╝ê1917ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعكصخكخûف║عîغ║جلأفûق╖بعéèع«ف░éفïآفôةعéْكذصعّع6ف░ع«عéزعâ╝عâêعâعéجعسعéêعéïفûق╖بعéèعéْفدïعéعéïي╝êلأقد░عîك╡جعâعéجعي╝ë[W 40]عé
- 3µ£ê23µùحعك╗ق¤ذكçزفïـك╗èكث£فèرµ│ـعîفàشف╕âعـعéîع5µ£êعïعéëµû╜كةîعـعéîعéïعé
- 6µ£êعغ╕ëك▒لبكê╣قحئµê╕لبكê╣µëعذفجدلءزع«قآ║فïـµراكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«عâعéجعâعâف╖حµحصي╝ëعîفجدلءزقب▓فà╡ف╖حف╗بعïعéëµ░ّلûôكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µîçف░ف╖حفب┤عسµîçف«أعـعéîعلآ╕ك╗ق¤ذع«4عâêعâ│فê╢ف╝كçزفïـك▓ذك╗èي╝êقآ║فïـµراكث╜لبع»عôع«ك╗èغ╕ةع«ع┐ي╝ëعذ3عâêعâ│فê╢ف╝كçزفïـك▓ذك╗èع«كرخغ╜£عسقإµëïعآعéï[133][135]عéغ╕ëك▒لبكê╣ع»فîف╣┤غ╕صعسف«îµêعـعؤعéïعîعغ╗ûع«غ║ïµحصعéْفزفàêعـعؤعéïعاعéعكرخغ╜£ع«ع┐عدق╡éعéعéï[133]عé
- 8µ£êععîف┐سل▓قج╛كçزفâك╗èف╖حفب┤ععîكدثµـثعùععîµبزف╝غ╝أقج╛ف┐سل▓قج╛ععسµ¤╣ق╡عـعéîعéï[136][W 24]عé
- 10µ£ê17µùحعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عîك│╝فàحعùعاعâئعâ╝عé»IVµêخك╗èلؤîفئï1غ╕ةعîقحئµê╕µ╕»عسفê░قإعآعéïعéفîف╣┤11µ£ê4µùحعلإْف▒▒ق╖┤فà╡فب┤عدفàشلûïكرخلذôعîكةîعéعéîعéï[130]عéي╝êµùحµ£شعسفêإعéعخµîعةك╛╝ع╛عéîعاµêخك╗èي╝ë
- 11µ£ê11µùحعلثفêفؤ╜عذعâëعéجعâف╕إفؤ╜ع«لûôعدغ╝ّµêخف¤ف«أعîق╡ع░عéîعقششغ╕µشةغ╕ûقـîفجدµêخعîق╡éق╡عآعéïعé
- 11µ£êعغ╕ëك▒لبكê╣قحئµê╕لبكê╣µëعîغ╕ëك▒عâ╗Aفئïعéْف«îµêعـعؤعغ╕ëك▒فـغ║ïعذعééف¤فèؤعùعخ1920ف╣┤3µ£êعïعéëك▓رفث▓عآعéï[137][µ│ذ 46]عéي╝êµùحµ£شعسعèعّعéïفêإع«كخïك╛╝ع┐ق¤اق¤ثعسعéêعéïلçق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë
- 11µ£êعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëعîعéجعé«عâزعé╣ع«عéخعâ╝عé║عâشعâ╝عذعâرعéجعé╗عâ│عé╣µµ║عéْق╡ع│عكçزفïـك╗èكث╜لبعسل▓فç║عآعéïي╝êف╛îع«ععآعéئكçزفïـك╗èي╝ë[136][138][W 41]عé
- 12µ£ê1µùحعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عسكçزفïـك╗èلأèعîفë╡كذصعـعéîعéï[130]عé
- 12µ£êعفàفجûكêêµحصµبزف╝غ╝أقج╛عîكذصقسïعـعéîععâّعââعéسعâ╝عâëععé╖عâ£عâشعâ╝ععâأعâ╝عé╕عزعرع«ك╝╕فàحك╗èع«µ£êك│خك▓رفث▓عéْفدïعéعéï[139]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èع«µ£êك│خك▓رفث▓ي╝ë
- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤لبكê╣µëفà╡ف║سف╖حفب┤عîعâêعâرعââعé»ع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[W 42]عé
- 1919ف╣┤ي╝êفجدµصث8ف╣┤ي╝ë
- 1µ£ê11µùحعفàفïآق£غ╗جعذعùعخكçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جي╝êكçزفïـك╗èفûق╖بكخفëçي╝ëعîفàشف╕âعـعéîع2µ£ê15µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[130]عéفîµ│ـعسعéêعéèكçزفïـك╗èعسعجععخع«فûعéèµ▒║عéعîµùحµ£شفàذفؤ╜عدق╡▒غ╕عـعéîعفف║£ق£îع«µùتفصءع«فûق╖بكخفëçع»ف╗âµصتعـعéîعكçزµ▓╗غ╜ôعسف┐£عءعاق┤░فëçع»µû░عاعسفê╢ف«أعـعéîعéï[136]عé
- عإعéîع╛عدفلôف║£ق£îع«كخفëçغ╕صعدعîكçزفïـك╗èععذعîكçزفâك╗èععدغ╕ق╡▒غ╕عبعثعاكةذكذءعéْعîكçزفïـك╗èععسق╡▒غ╕عآعéï[µ│ذ 47]ععâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêع«كثàقإعéْفàذفؤ╜قأعسق╛رفïآعحعّعéïععزعرع«ق╡▒غ╕فîûعîفؤ│عéëعéîعéï[130]عé
 TGE-Aفئïعâêعâرعââعé»ي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë
TGE-Aفئïعâêعâرعââعé»ي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë
- 1920ف╣┤ي╝êفجدµصث9ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµإ▒غ║شف╕éكةùكçزفïـك╗èعîعâعé╣عéشعâ╝عâسي╝êفرخغ║║ك╗èµîي╝ëعéْµةق¤ذعآعéï[76][µ│ذ 49]عéي╝êµùحµ£شفêإع«فح│µدع«عâعé╣ك╗èµîي╝ë
- 2µ£êععîµتقشفـغ╝أععîعîµتقشكçزفïـك╗èععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعéعé╖عâ£عâشعâ╝عéْع»عءعéعذعآعéïغ╣ùق¤ذك╗èع«لâذفôعéْك╝╕فàحعùعف░كخµذةعزعîعéëعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْكةîععéêععسعزعéï[145]عé
- 3µ£êعغ╕ûقـîفجدµêخعîق╡éعéعثعخ1ف╣┤غ╗حغ╕èق╡îلعùعâذعâ╝عâصعââعâّفêùف╝╖عîف╕éفب┤عسف╛رف╕░عéْفدïعéعاعôعذعدµùحµ£شعدع»لفë░ق¤اق¤ثعéْفافؤبعذعآعéïµµàîعîفدïع╛عéïي╝êµêخف╛îµµàîي╝ëعéعôع«غ╕µ│ع»لـ╖µ£افîûعآعéïعôعذعسعزعéï[140]عé
- 11µ£êعµذزµ╡£ف╕éف╣│µ▓╝عسف╗║كذصعـعéîعاµرسµ┐▒كص╖كشذع«ف╣│µ▓╝ف╖حفب┤عîف«îµêعùعفîقج╛ع»عâآعâسعâêععé┐عéجعâجعزعرع«كث╜لبعéْفدïعéعéïعé
- 12µ£ê16µùحعلôك╖»فûق╖بغ╗جعîفàشف╕âعـعéîعق┐îف╣┤1µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 43][W 44]عéفîµ│ـعسعéêعéèµùحµ£شفàذفؤ╜ع«غ║جلأµ│ـكخعîق╡▒غ╕عـعéîعéïعé
- 1921ف╣┤ي╝êفجدµصث10ف╣┤ي╝ë
- 11µ£ê11µùحعïعéëق┐îف╣┤2µ£ê6µùحعسعïعّعخعâ»عé╖عâ│عâêعâ│غ╝أكص░عîكةîعéعéîعµ╡╖ك╗ع«ك╗ق╕«عîµ▒║ع╛عéïي╝êعâ»عé╖عâ│عâêعâ│µ╡╖ك╗ك╗ق╕«µإةق┤ي╝ëعéعإعéîعسغ╝┤عف╕إفؤ╜لآ╕ك╗ع«غ║êق«ùعééق╕«µ╕ؤعـعéîعكçزفïـك╗èغ╝أقج╛عسف»╛عآعéïلآ╕ك╗عïعéëع«قآ║µ│ذعîµ╕ؤعéï[140]عé
- µآéµ£اغ╕µءعك╜كزئعسكçزفïـك╗èعéْلةîµإعذعùعاµ╝¤قؤ«ي╝êعكçزفïـك╗èع«ف╕âفؤثعي╝ëعîق╛عéîعéï[146]عé
- 1922ف╣┤ي╝êفجدµصث11ف╣┤ي╝ë
 µùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أي╝êق¤╗فâع»1923ف╣┤4µ£êع«قشش2فؤئفجدغ╝أي╝ë
µùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أي╝êق¤╗فâع»1923ف╣┤4µ£êع«قشش2فؤئفجدغ╝أي╝ë
- 3µ£êعïعéë7µ£êعسعïعّعخغ╕èلçفàشف£ْعدف╣│فْîكذءف┐╡µإ▒غ║شفأكخدغ╝أعîلûïفéشعـعéîعéïعéف┐سل▓قج╛ي╝êعâعââعâêعâ╗41فئïي╝ëعµإ▒غ║شقôخµû»لؤ╗µ░ùف╖حµحصي╝êTGEعâêعâرعââعé»ي╝ëعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëي╝êعéخعâ╝عé║عâشعâ╝غ╣ùق¤ذك╗èي╝ëعف«اق¤ذكçزفïـك╗èي╝êعé┤عâ╝عâعâبف╝غ╕ëك╝زغ╣ùق¤ذك╗èي╝ëعقآ╜µحèقج╛ي╝êعéتعâشعé╣ف╖ي╝ëعزعرµùحµ£شع«كçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛فقج╛عîكçزفïـك╗èعéْفç║فôعآعéïعé
- 8µ£êعµتقشكçزفïـك╗èعîف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعîعâجعâèعé╗ف╖عع«كرخغ╜£ك╗èعéْف«îµêعـعؤعéïعîعµةق«ùعîفûعéîعéïكخïلأعùعîقسïعاعزعïعثعاعاعéق¤اق¤ثع»µûصف┐╡عùعغ╗حلآعفîقج╛ع»ك╝╕فàحك▓رفث▓µحصعسف╛╣عآعéï[147]عé
- 10µ£êعكùجµ£شك╗µشةعéëعîµùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░ف╢µح╜لâذي╝êNARCي╝ëعéْكذصقسïعآعéï[148][5][W 17]عé
- 11µ£ê12µùحعµإ▒غ║شµ┤▓ف┤فاïقسïف£░عدفب▒قاحقج╛ي╝êف╛îع«فب▒قاحµû░كئقج╛ي╝ëع«غ╕╗فéشعدµùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أعîفêإلûïفéشعـعéîعéïي╝êقشش1فؤئكçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░ي╝ë[148][W 17]عé
- 12µ£êعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëعîعéخعâ╝عé║عâشعâ╝A9فئïع«فؤ╜ق¤ثفîûعسµêفèاعآعéï[149][W 41]عé
لûتµإ▒فجدل£çق╜ف╛îععâـعéرعâ╝عâëعذGMع«µùحµ£شل▓فç║ي╝ê1923ف╣┤ي╜ئي╝ë
لûتµإ▒فجدل£çق╜ي╝ê1923ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèععإعéîع╛عدك┤àµ▓تفôعذكخïعéëعéîعخععاكçزفïـك╗èع»عإع«ف«اق¤ذµدعéْف║âعكزكصءعـعéîعéïعéêععسعزعéï[76]عéعإع«فجëفîûعéْععةµùرعف»اقاحعùفـµراعéْكخïفç║عùعاعâـعéرعâ╝عâëع»µ£شµب╝قأعسµùحµ£شعسل▓فç║عùعخعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْفدïعéي╝ê1925ف╣┤ي╝ë[150]علàعéîعخµùحµ£شعسل▓فç║عùعاعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║ي╝êGMي╝ëعذفà▒عسµùحµ£شعéْكêئف░عسك▓رفث▓فêµêخعéْق╣░عéèف║âعْعéïعéقآ╜µحèقج╛عîµùحµ£شع«فؤ╜µâàعسلرعùعاف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبعéْفدïعéعéïعزعرعفؤ╜فàعسعé鵣뵣ؤعزكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عîكé▓عةعجعجعéعثعاعîععإعéîعéëع«ف░كخµذةعزغ╝أقج╛ع»ق▒│فؤ╜ك╗èع«µحلاعزف░لبصعسعéêعثعخلدلعـعéî[W 4][µ│ذ 50]عك╗ق¤ذكçزفïـك╗èكث£فèرµ│ـي╝ê1918ف╣┤µû╜كةîي╝ëعسعéêعéïغ┐إكص╖عéْف╛ùعخععاغ╕لâذع«غ╝أقج╛عéْµ«ïعùعخµùحµ£شع«كçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»µ╢êµ╗àعùعخعععôعذعسعزعéïعé
- 1923ف╣┤ي╝êفجدµصث12ف╣┤ي╝ë
 ففجزلâعâعé╣
ففجزلâعâعé╣
- 1924ف╣┤ي╝êفجدµصث13ف╣┤ي╝ë
 عéزعâ╝عâêعâتف╖ي╝ê1924ف╣┤11µ£êي╝ë
عéزعâ╝عâêعâتف╖ي╝ê1924ف╣┤11µ£êي╝ë
- 1µ£êعµإ▒غ║شف╕éفû╢غ╣ùفêكçزفïـك╗èي╝êµإ▒غ║شف╕éفû╢عâعé╣عف╛îع«لâ╜فû╢عâعé╣ي╝ëعî11غ║║غ╣ùعéèع«TTفئïعâـعéرعâ╝عâëك╗èي╝êففجزلâعâعé╣ي╝ë44غ╕ةعدفû╢µحصعéْلûïفدïعآعéï[155][µ│ذ 52]عé
- 6µ£êعفجدلءزف╕éعد1ففإçغ╕ع«عé┐عé»عé╖عâ╝ي╝êلأقد░عîفعé┐عé»عي╝ëعîقآ╗فب┤عùععإع«ف╛îµـ░ف╣┤ع«لûôعسفàذفؤ╜عسف║âعîعثعخعع[76][µ│ذ 53]عé
- 7µ£ê24µùحعكصخكخûف║غ╗جعسعéêعéèكçزفïـك╗èلïك╗تµëïكرخلذôكخفëçعîفê╢ف«أعـعéîع8µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40]عéفîµ│ـعدف░▒µحصق¤ذع«لïك╗تفàكذ▒عîفî║فêحعـعéîعخفë╡كذصعـعéîعéïعé
- 11µ£êعقآ╜µحèقج╛عîعéزعâ╝عâêعâتف╖عéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شع«ق┤¤فؤ╜ق¤ثµèكةôعسعéêعéïفêإع«لçق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë
- 11µ£ê16µùحعفèبكùجلسءµءلخûقؤ╕عîعéزعâ╝عâêعâتف╖عسكرخغ╣ùعآعéï[156]عéي╝êق╛ك╖ع«فàلûثق╖قفجدكçثعîفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èعسغ╣ùك╗èعùعاµ£فêإع«غ╛ïي╝ë
- 1925ف╣┤ي╝êفجدµصث14ف╣┤ي╝ë
- 2µ£ê17µùحعµذزµ╡£عدµùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛عîكذصقسïعـعéîعéï[78][130]عéعâـعéرعâ╝عâëقج╛ع»عé╗عâ╝عâسعâ╗عâـعâشعé╢عâ╝فـغ╝أعذع«لûôعدق╡عéôعدععاµùحµ£شعسعèعّعéïق╖غ╗ثقف║ùفحّق┤عéْكدثµ╢êعآعéï[78]عéفîف╣┤3µ£êعïعéëµذزµ╡£ف╖حفب┤عدعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْلûïفدïعù[61]عµذزµ╡£µ╕ةعùع«µû░غ╛ةµب╝عéْكذصف«أعآعéï[130]عé
- 7µ£ê21µùحعف┐سل▓قج╛فàعسعîفêك│çغ╝أقج╛عâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أععîكذصقسïعـعéîعéï[144][W 24][µ│ذ 54]عé
- 8µ£ê21µùحعµùحق▒│µإ┐قةإفصعîµ£ذقéصكçزفïـك╗èعéْف«îµêعـعؤعµإ▒µ╡╖لôعدكرخلïك╗تعéْكةîع[157][130]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«µ£ذقéصكçزفïـك╗èي╝ë
- 11µ£êععéزعâ╝عâêعâتف╖عîغ╕èµ╡╖عسك╝╕فç║عـعéîعéïعéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعاكçزفïـك╗èع«ك╝╕فç║قشش1ف╖ي╝ë
- 12µ£êعµإ▒غ║شµ┤▓ف┤فاïقسïف£░عدلûïفéشعـعéîعافàذفؤ╜كçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أي╝êµùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أعâ╗قشش8فؤئفجدغ╝أي╝ëعسعâشعâ╝عé╣غ╗ـµدءع«عéزعâ╝عâêعâتف╖عîف¤»غ╕ع«فؤ╜ق¤ثك╗èعذعùعخفéµêخعùعغ║êل╕1غ╜عµ▒║فïإ2غ╜عذععق╡µئ£عéْµ«ïعآعé
- 1926ف╣┤ي╝êفجدµصث15ف╣┤ي╝µءصفْîفàâف╣┤ي╝ë
- 4µ£êعفجدلءزظ¤µإ▒غ║شلûôع«عâعâ│عé╣عâêعââعâùعâشعâ╝عé╣عîلûïفéشعـعéîعéï[158]عé
- 4µ£ê20µùحعفêك│çغ╝أقج╛عâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أعîغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëي╝êف╛îع«عé»عâ£عé┐ي╝ëعسعéêعثعخك▓╖فعـعéîعéï[144][µ│ذ 55]عé
- 6µ£ê29µùحعف┐سل▓قج╛عîكدثµـثعآعéï[159]عéكçزفïـك╗èع«كث╜لبعéْكسخعéععéîعزعµرïµ£شفتùµ▓╗لâع»عîعâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أعع«غ╗ثكةذقج╛فôةعذعùعخغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëعسقـآع╛عéï[144][µ│ذ 56]عé
- 9µ£ê2µùحعغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëفéءغ╕ïع«عîف«اق¤ذكçزفïـك╗èكث╜لبععîعîعâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعéفîµآéعسععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبع»عâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أعéْف╕ففêغ╜╡عآعéï[144][W 24]عé
- 1927ف╣┤ي╝êµءصفْî2ف╣┤ي╝ë
 كرخكث╜غ╕ف╖µêخك╗èي╝ê1927ف╣┤ي╝ë
كرخكث╜غ╕ف╖µêخك╗èي╝ê1927ف╣┤ي╝ë
- 1928ف╣┤ي╝êµءصفْî3ف╣┤ي╝ë
- 2µ£êعµصîكêئغ╝عسكçزفïـك╗èعéْلةîµإعذعùعاµ╝¤قؤ«ي╝êعفعé┐عé»ع«µé▓فôعي╝ëعîق╛عéîعéï[146]عé
- 5µ£êعف╖إف┤لبكê╣µëع«فà╡ف║سف╖حفب┤عîفêلؤتقïشقسïعùععîف╖إف┤ك╗èك╝ؤععîكذصقسïعـعéîعéï[W 42]عé
- 11µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èع«لïك╝╕قؤثقإثµذرعîلôغ┐ةق£عïعéëلëلôق£قؤثقإثف▒عسقد╗ق«ةعـعéîعéïعôعذعîµ▒║ف«أعùع11µ£ê25µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40][W 52]عéق┐îف╣┤4µ£êعسلëلôق£قؤثقإثف▒عسلآ╕لïكز▓عîكذصق╜«عـعéîعéï[W 40]عé
- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤لèكةîعîكçزفïـك╗èµ£êك│خµëïف╜تفë▓ف╝ـعéْفدïعéعéï[61]عéي╝êµùحµ£شع«لçّكئµرالûتعسعéêعéïفêإع«كçزفïـك╗èفë▓ك│خي╝ë
- µآéµ£اغ╕µءععâـعâرعâ│عé╣عدلûïقآ║عـعéîعاµ£ذقéصكçزفïـك╗èق¤ذع«µ£ذقéصعéشعé╣قéëعéْعééعذعسµ╡àف╖إµذرفàسعîف«اق¤ذفîûعéْكةîعععîµ╡àف╖إف╝µ£ذقéصقôخµû»قآ║ق¤اقéëععذعùعخقë╣كذ▒عéْفûف╛ùعآعéï[161]عéعôعéîع»µùحµ£شعسعèعّعéïغ╗ثق¤ذقçâµûآكثàق╜«ع«ع»عùعéèعذعـعéîعéï[161]عé
- 1929ف╣┤ي╝êµءصفْî4ف╣┤ي╝ë
- µءحعقآ╜µحèقج╛عîكدثµـثعآعéï[162]عé
- 5µ£êعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëع«كçزفïـك╗èلâذعîقïشقسïعùعقا│ف╖إف│╢كçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 41][µ│ذ 58]عé
- 6µ£êعقا│µ▓╣6قج╛عîف¤ف«أعسعéêعéèعéشعé╜عâزعâ│ع«فجغ╕èعْعéْقآ║كةذعùععإعéîعسفقآ║عùعاكçزفïـك╗èµحصقـîعîفجغ╕èعْفف»╛عéْµ▒║كص░عآعéïي╝êقششغ╕µشةعéشعé╜عâزعâ│غ║ëكص░ي╝ë[W 40]عé
- 6µ£êعµإ▒غ║شف╕éل║╣ق¤║فî║غ╕╕ع«فàعد6لأف╗║عخع«كçزك╡░ف╝قسïغ╜ôلدك╗èفب┤عîغ╕╕عâفàعéشعâرعâ╝عâéععîلûïµحصعآعéï[163][W 53][µ│ذ 59]عéي╝êµùحµ£شفêإع«قسïغ╜ôلدك╗èفب┤ي╝ë
- 8µ£êعكصخكخûف║عîفêإع«كçزفïـك╗èلïك╗تكرخلذôفب┤عéْµ┤▓ف┤عسكذصق╜«عآعéï[W 40]عé
- 9µ£ê4µùحلبâعق▒│فؤ╜عسقس»عéْقآ║عùعخغ╕ûقـîµµàîعîفدïع╛عéïعéµùحµ£شعدع»ق┐î1930ف╣┤عïعéë1931ف╣┤عسعïعّعخق╡îµ╕êف▒µراعسكخïكêئعéعéîعéïي╝êµءصفْîµµàîي╝ëعé
- 1930ف╣┤ي╝êµءصفْî5ف╣┤ي╝ë
لëلôق£فû╢عâعé╣ / TGE-MPفئïعâعé╣ي╝ê1930ف╣┤ي╝ë
عâعéجعâعâف╖ي╝ê1930ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµùحµ£شعîلçّك╝╕فç║عéْكدثقخعآعéïي╝êلçّكدثقخي╝ëعéغ╕ûقـîµµàîعذفêعéعـعéèعµùحµ£شق╡îµ╕êع«غ╕µ│عسµïك╗èعîعïعïعéï[W 47]عé
- 2µ£êعفàفïآق£عîقةفàكذ▒عدلïك╗تعدععéïف░فئïكçزفïـك╗èع«كخµب╝ع«ف╝ـعغ╕èعْعéْكةîعع4عé╡عéجعé»عâسعéذعâ│عé╕عâ│ع»ق╖µْµ░ùلç500 عغ╗حغ╕ïع2عé╡عéجعé»عâسعéذعâ│عé╕عâ│ع»ق╖µْµ░ùلç350 عغ╗حغ╕ïع«ك╗èغ╕ةع╛عدع»قةفàكذ▒عدلïك╗تعدععéïعéêععسعزعéï[164]عéعôعéîعسعéêعéèف░فئïع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعéْكث╜لبعآعéïµرالïعîلسءع╛عéï[164]عé
- 4µ£ê9µùحعµùحµ£شك╢│كتïµبزف╝غ╝أقج╛عé┐عéجعâجلâذي╝êف╛îع«عâûعâزعâéعé╣عâêعâ│ي╝ëعîقشش1ف╖عâûعâزعâéعé╣عâêعâ│عé┐عéجعâجع«كث╜لبعسµêفèاعآعéï[W 47][W 54]عéي╝êق┤¤µùحµ£شك│çµ£شعسعéêعéïفêإع«كçزفïـك╗èق¤ذعé┐عéجعâجكث╜لبي╝ë
- 5µ£êعفـف╖حق£ع«كس«فـµرالûتعدعéعéïفؤ╜ق¤ثµî»كêêفد¤فôةغ╝أعîكçزفïـك╗èف╖حµحصقت║قسïµû╣قصûعéْقص¤ق¤│عآعéï[W 55]عéعإعéîعéْفùعّعخعففجف▒ïف╕éع«فجدف▓رفïçفجسف╕éلـ╖عîعîغ╕صغ║شعâçعâêعâصعéجعâêفîûµدïµâ│ععéْµف¤▒عآعéïعé
- 6µ£ê15µùحعفجأق¤░فحك¤╡عîعâئعâ│ف│╢TTعâشعâ╝عé╣ي╝êعé╕عâحعâïعéتTTعé»عâرعé╣ي╝ëعسفéµêخعآعéï[165][112][W 56]عéي╝êµùحµ£شغ║║عîفؤ╜فجûع«عéزعâ╝عâêعâعéجعâشعâ╝عé╣عسفéµêخعùعافêإع«غ╛ïي╝ë
- 10µ£êععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعîكرخغ╜£ك╗èعîعâعââعâêعé╜عâ│عي╝êDatsonي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéï[164]عé
- 12µ£êعفجدلءزع«قآ║فïـµراكث╜لبعîغ╕ëك╝زكçزفïـك╗èع«كث╜لبعسغ╣ùعéèفç║عùعكرخغ╜£ك╗èHAفئïعâعéجعâعâف╖عéْكث╜لبعآعéï[W 57]عé
- 12µ£ê20µùحعلëلôق£فû╢عذعùعخع»فêإعذعزعéïق£فû╢عâعé╣ك╖»ق╖أي╝êف╛îع«فؤ╜لëعâعé╣ي╝ëعîف▓ةف┤ظ¤فجأµ▓╗كخïلûôي╝êق┤57 kmي╝ëعدلûïلأعآعéï[164]عé
فؤ╜ق¤ثك╗èع«غ┐إكص╖ي╝ê1931ف╣┤ي╜ئي╝ë
عâـعéرعâ╝عâëعذGMع«ق╡قسïك╗èعسعéêعéïف»ةفبعîق╢أعغ╕صعµ║µ┤▓غ║ïفجëي╝ê1931ف╣┤ي╝ëعدك╗ق¤ذكçزفïـك╗èع«µ£ëق¤ذعـعîقت║كزعـعéîعاعôعذعدفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èغ┐إكص╖ع«فïـععîل▓ع┐عكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصµ│ـع«فê╢ف«أي╝ê1936ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèعإعéîع╛عدلأقؤؤعéْكزçعثعخععاق▒│فؤ╜ك╗èع»µùحµ£شفؤ╜فàعïعéëµْلآجعـعéîعخعععôعذعسعزعéï[W 58]عé
- 1931ف╣┤ي╝êµءصفْî6ف╣┤ي╝ë
 عâئعâعâف╖DAفئïي╝ê1931ف╣┤ي╝ë
عâئعâعâف╖DAفئïي╝ê1931ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعµùحµ£شك╢│كتïعé┐عéجعâجلâذعîقïشقسïعùعقخف▓ةق£îغ╣àقـآق▒│ف╕éعدعâûعâزعââعâéعé╣عâêعâ│عé┐عéجعâجµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«عâûعâزعâéعé╣عâêعâ│ي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[166][W 59][W 60]عé
- 4µ£ê1µùحعكçزفïـك╗èغ║جلأغ║ïµحصµ│ـعîفàشف╕âعـعéîع1933ف╣┤10µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40][µ│ذ 60]عé
- 6µ£ê29µùحعµرïµ£شفتùµ▓╗لâعîعâعââعâêكçزفïـك╗èع«كث╜لبµذرعéْغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëعسكص▓µ╕ةعùععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعéْلك╖عآعéï[144]عé
- 7µ£êعف╖إق£اق¤░فْîµ▒زعîعâصعâ╝عâرعâ│عâëف╖عéْكرخغ╜£كث╜لبعآعéï[166][W 61]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«فëك╝زلدفïـكçزفïـك╗èي╝ë
- 9µ£êعµ║µ┤▓غ║ïفجëقآ║ق¤اعéف║âعغ╕صفؤ╜فجدلآ╕عدك╗لأèعéقëرك│çع«ك╝╕لعéْعآعéïعاعéعك╗ق¤ذكçزفïـك╗èع«لçكخµدعîلسءع╛عéï[167]عéع╛عاعµùحق▒│لûتغ┐éع»عôع«غ║ïغ╗╢عéْµراعسف╛عàعسµéزفîûعùعخعععé
- µ¤┐ف║£ع»ك╗ق¤ذكث£فèرµ│ـع«غ┐إكص╖غ╕ïعسعéعéï3قج╛عسفêفîي╝êفêغ╜╡ي╝ëعآعéïعéêعكخكسïعآعéï[W 62]عé
- 10µ£êعف░µإ╛كث╜غ╜£µëعîك╛▓كـق¤ذعâêعâرعé»عé┐عâ╝ع«كرخغ╜£قشش1ف╖µراعéْف«îµêعـعؤعéï[W 63][W 64]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«ك╛▓كـق¤ذعâêعâرعé»عé┐عâ╝ي╝ë
- 10µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصي╝êف╛îع«عâئعâعâي╝ëعîغ╕ëك╝زعâêعâرعââعé»ع«كث╜لبعéْفدïعéععâئعâعâف╖DAفئïعéْقآ║فث▓عآعéï[168][µ│ذ 61]عé
- غ╗حلآعµإ▒µ┤ïف╖حµحصي╝êعâئعâعâي╝ëعذقآ║فïـµراكث╜لبي╝êعâعéجعâعâي╝ëع»عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زع«فêلçعدف╕éفب┤عéْعâزعâ╝عâëعآعéïعôعذعسعزعéïعé
- 11µ£ê21µùحععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعîل«ف╖إق╛رغ╗ïع«µê╕قـّلï│قëري╝êف╛îع«µùحقسïلçّف▒ئي╝ëع«فéءغ╕ïعسعزعéï[169][W 24]عé
- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤ك╗èك╝ؤعî1.5عâêعâ│عâêعâرعââعé»ع«كرخغ╜£ك╗èعéْف«îµêعـعؤعق┐î1932ف╣┤عسعîفàصق¤▓ف╖عع«فقد░عدعâêعâرعââعé»عذعâعé╣ع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[W 42]عé
- 1932ف╣┤ي╝êµءصفْî7ف╣┤ي╝ë
- 3µ£ê1µùحعµ║µ┤▓فؤ╜µêقسïعé
- 5µ£êعغ╕صغ║شعâçعâêعâصعéجعâêفîûµدïµâ│عسفا║عحعµؤقاحµآéكذêلؤ╗µراعفجدلأêلëف╖حµëي╝êف╛îع«عéزعâ╝عé»عâئي╝ëعµùحµ£شك╗èك╝îكث╜لبعف▓ةµ£شكçزك╗تك╗èكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعك▒èق¤░ف╝ق╣¤µرا[µ│ذ 62]ع«5قج╛عîف¤فèؤعùعخكث╜لبعùعاكرخغ╜£ك╗è2ف░عîف«îµêعùععéتعâعé┐ف╖عذفّ╜فعـعéîعéï[W 55]عé
- 5µ£êعغ╕ëك▒لبكê╣قحئµê╕لبكê╣µëعîBD46فئïفجدفئïغ╣ùفêكçزفïـك╗èعéْف«îµêعـعؤعفîك╗èعéْعîع╡عإعععذفّ╜فعآعéï[170][W 65]عéق¤اق¤ثعîفدïع╛عثعافîك╗èع»غ╛إلب╝غ╕╗عدعéعéïلëلôق£عسق┤فàحعـعéîعق£فû╢عâعé╣عذعùعخق¤ذععéëعéîعéïعôعذعسعزعéï[170]عé
- µآéµ£اغ╕µءعف╖إق£اق¤░فْîµ▒زع«غ║ïµحصعéْف╝ـعق╢آععبفàكùجµصثغ╕عîعâصعâ╝عâرعâ│عâëف╖عذفîفئïع«ك╗èغ╕ةعéْعîع┐عأع╗ف╖ععذفغ╗ءعّعخقآ║فث▓عùعفîµآéعسغ║ïµحصفîûع«عاعéع«فç║ك│çكàعéْفïاعéï[171]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«فëك╝زلدفïـف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 1933ف╣┤ي╝êµءصفْî8ف╣┤ي╝ë
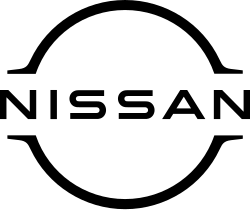 µùحق¤ثكçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1933ف╣┤ي╝ë
µùحق¤ثكçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1933ف╣┤ي╝ë
- 3µ£ê27µùحعµùحµ£شعîفؤ╜لأؤلثقؤاعïعéëع«ك▒لعéْµصثف╝عسكةذµءعéµùحµ£شع»فؤ╜لأؤقأعسفصجقسïعéْµ╖▒عéعéïعéêععسعزعéèعكçزفïـك╗èع«قçâµûآقت║غ┐إعîفجدععزفـلةîعذعزعéèفدïعéعéï[167]عé
- 3µ£êعفـف╖حق£µذآµ║ûف╜تف╝كçزفïـك╗èي╝êعâêعâرعââعé»عذعâعé╣ي╝ëعîف«îµêعآعéï[W 41]عéق┐îف╣┤عكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ع»فîك╗èعéْعîععآعéئععذفّ╜فعآعéï[W 41][µ│ذ 63]عé
- 3µ£êعقا│ف╖إف│╢كçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعذعâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعîفêغ╜╡عùعكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«ععآعéئكçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 41][µ│ذ 64]عé
- فîµ£êععâعââعâêكçزفïـك╗èع«كث╜لبµذرعéْفج▒عثعاµê╕قـّلï│قëرع»كçزفïـك╗èلâذعéْكذصقسïعùعµëïفàâعسµ«ïعـعéîعاعâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبع«فجدلءزف╖حفب┤عدغ║ïµحصعéْق╢أعّعéï[171][W 24][W 66]عé
- 8µ£êعكçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جع«µ¤╣µصثعîفàشف╕âعـعéîعف░فئïكçزفïـك╗èع«فêلةئعîعدععéïي╝êفîف╣┤11µ£êµû╜كةîي╝ë[µ│ذ 65]عé
- 9µ£ê1µùحعك▒èق¤░كçزفïـق╣¤µراكث╜غ╜£µëعîكçزفïـك╗èكث╜لبعéْµ▒║ف«أعù[61]عكçزفïـك╗èلâذعéْكذصق╜«عآعéïي╝êف╛îع«عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èي╝ë[W 45][W 67][W 62][µ│ذ 66]عé
- 9µ£êعµê╕قـّلï│قëرعïعéëع«عïعصعخعïعéëع«غ╛إلب╝عسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êععآعéئي╝ëعîف┐£عءعكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عسعذعثعخغ╕كخعذعزعéïف░فئïك╗èعâعââعâêعé╡عâ│ع«كث╜لبµذرعîفàâع«كخزغ╝أقج╛عدعéعéïµê╕قـّلï│قëرعسفîف╣┤2µ£êعسلةعثعخقةفاعدكص▓µ╕ةعـعéîعéï[172][µ│ذ 67]عé
- 12µ£ê26µùحعµùحµ£شق¤ثµحصي╝êµùحق¤ثعé│عâ│عâعéدعâسعâ│ع«µîµبزغ╝أقج╛ي╝ëعذµê╕قـّلï│قëرع«فà▒فîفç║ك│çعسعéêعéèعكçزفïـك╗èكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êق┐îف╣┤عïعéëµùحق¤ثكçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 24][W 68][W 69]عé
- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤ك╗èك╝ؤعîعîفàصق¤▓ف╖عغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبعéْفدïعéعلسءق┤أغ╣ùق¤ذك╗èعذعùعخف««ف«╢عزعرعسق┤فàحعآعéï[W 42]عé
- 1934ف╣┤ي╝êµءصفْî9ف╣┤ي╝ë
 قصّµ│تف╖ي╝ê1934ف╣┤ي╝ë
قصّµ│تف╖ي╝ê1934ف╣┤ي╝ë
- 3µ£ê36µùحعµ║µ┤▓فؤ╜عدكçزفïـك╗èعéْكث╜لبعآعéï7قج╛ع«فà▒فîفç║ك│çعسعéêعéèفîفْîكçزفïـك╗èف╖حµحصعîكذصقسïعـعéîعéï[173]عé
- 4µ£êععîغ╕ëك▒لبكê╣عي╝êفêإغ╗ثي╝ëعîعîغ╕ëك▒لçف╖حµحصعي╝êفêإغ╗ثي╝ëعسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعé
- 6µ£ê1µùحعµùحµ£شق¤ثµحصع«فàذلةفç║ك│çعسعزعثعاعôعذعسعéêعéèععîكçزفïـك╗èكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµùحق¤ثكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 24][W 68][W 69]عé
- 6µ£êعفـف╖حق£عîقôخµû»قآ║ق¤اقéëكذصق╜«فحذفè▒لçّغ║جغ╗ءكخفëçعéْفê╢ف«أعù[167]عغ╗ثق¤ذقçâµûآكçزفïـك╗èق¤ذع«عéشعé╣قآ║ق¤اقéë1فا║عسعجع300فعéْلآف║خعذعùعخفحذفè▒لçّعîغ║جغ╗ءعـعéîعéïعéêععسعزعéï[W 70]عé
- 8µ£ê10µùحععîكçزفïـك╗èف╖حµحصقت║قسïعسلûتعآعéïفق£ف¤كص░غ╝أععسعéêعéïقشش1فؤئع«غ╝أفêعîلûïفéشعـعéîعفـف╖حق£علآ╕ك╗ق£عµ╡╖ك╗ق£علëلôق£عفجدك¤╡ق£عفàفïآق£عك│çµ║ف▒عسعéêعéïكر▒عùفêععîµîعاعéîعéï[W 58][µ│ذ 68]عé
- 11µ£êعف╖إق£اق¤░فْîµ▒زع«غ║ïµحصعسµ▒╜ك╗èكث╜لبعذكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êععآعéئي╝ëعîفà▒فîفç║ك│çعùعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜لبعîكذصقسïعـعéîعقصّµ│تف╖ع«كث╜لبعéْفدïعéعéï[173][W 61]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«فëك╝زلدفïـلçك▓رك╗èي╝ë
- 1935ف╣┤ي╝êµءصفْî10ف╣┤ي╝ë
 عâعââعâêعé╡عâ│عâ╗14فئïي╝ê1935ف╣┤ي╝ë
عâعââعâêعé╡عâ│عâ╗14فئïي╝ê1935ف╣┤ي╝ë
- 4µ£ê3µùحعفجزق¤░كçزفïـك╗èعسغ╕ëغ║ـقëرق¤ثع«ك│çµ£شعîفèبعéعéèعلسءلاµرالûتف╖حµحصي╝êف╛îع«عéزعéزعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïعé
- 4µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîµذزµ╡£ف╖حفب┤ع«µôµحصعéْلûïفدïعùعفîف╖حفب┤عسعèعّعéïعâعââعâêعé╡عâ│عâ╗14فئïع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[174][W 68]عé
- 5µ£êعك▒èق¤░كçزفïـق╣¤µراكث╜غ╜£µëعîA1فئïكرخغ╜£غ╣ùق¤ذك╗èعذعéصعâثعâûعéزعâ╝عâعâ╝عâعé╣ع«عîعéصعé╜عé│عâ╝عâف╖ععéْف«îµêعـعؤعéï[174]عé
- 7µ£êعµùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëقج╛عîغ║ïµحصµïةفجدع«عاعéعµذزµ╡£ع«ق╡قسïف╖حفب┤ع«µïةف╝╡عéْفؤ│عéïع╣عق¤ذف£░ك▓╖فعسفïـع[174]عéعôعéîع»فـف╖حق£عذلآ╕ك╗ق£ع«كصخµêْعéْµïؤععق▒│فؤ╜ك│çµ£شع«كçزفïـك╗èق╡قسïعéْفê╢لآعآعéïµû╣فّعسفïـعفïـµراعéْµùحµ£شµ¤┐ف║£عسغ╕عêعéï[174]عé
- 11µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصقحئµê╕لبكê╣µëعîع╡عإععâ╗B46فئïعâعé╣عéْف«îµêعـعؤعéï[174][W 65]عéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعافêإع«عâçعéثعâ╝عé╝عâسعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëعâعé╣ي╝ë
- 1936ف╣┤ي╝êµءصفْî11ف╣┤ي╝ë
 عâêعâذعâعâ╗AAفئïغ╣ùق¤ذك╗èي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë
عâêعâذعâعâ╗AAفئïغ╣ùق¤ذك╗èي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë
µêخµآéق╡▒فê╢µ£اي╝ê1937ف╣┤ي╜ئي╝ë
µùحغ╕صµêخغ║ëع«لûïµêخي╝ê1937ف╣┤ي╝ëعذµùحµ£شع╕ع«فؤ╜لأؤقأعزك▓┐µءôفê╢لآع«فدïع╛عéèعسعéêعéèµ░ّلûôع«كçزفïـك╗èع«كث╜لبع»ك╗ق¤ذعسفê╢لآعـعéîعéïعéفجزف╣│µ┤ïµêخغ║ëي╝ê1941ف╣┤ - 1945ف╣┤ي╝ëعéْكâîµآ»عسغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبع»1938ف╣┤عïعéëµêخف╛îع«1949ف╣┤عسعïعّعخµùحµ£شµ¤┐ف║£عذGHQعسعéêعéï2ف║خع«قخµصتفّ╜غ╗جعéْفùعّعلـ╖عف│عùعµأùل╗ْµآéغ╗ث[176]عéْلعéïعôعذعذعزعéïعéقçâµûآق╡▒فê╢عسعéêعéèعéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗èع»غ╗ثق¤ذقçâµûآك╗èعسق╜«عµؤعêعéëعéîعخعععé
- 1937ف╣┤ي╝êµءصفْî12ف╣┤ي╝ë
 عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1937ف╣┤ي╝ë
عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1937ف╣┤ي╝ë
- 4µ£êعµ«قآ║µ▓╣فèعéتعâسعé│عâ╝عâسµ╖╖ق¤ذµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعµ«قآ║µ▓╣قذي╝êعéشعé╜عâزعâ│قذي╝ëعîفë╡كذصعـعéîعéïعé
- 4µ£ê9µùحعكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عذµإ▒غ║شقôخµû»لؤ╗µ░ùف╖حµحصعîفêغ╜╡عùعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èف╖حµحصي╝êف╛îع«ععآعéئكçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 51]عéعôعéîعسعéêعéèك╗ق¤ذكçزفïـك╗èكث£فèرµ│ـع«غ┐إكص╖غ╕ïعسعéعثعا3قج╛ع«ق╡▒فêعîف«îغ║عùعك╗ق¤ذك╗èغ╕ةع«فè╣قçقأعزق¤اق¤ثغ╜ôفê╢عîµـ┤ععé
- 7µ£êعµùحغ╕صµêخغ║ëلûïµêخعéغ╗حلآعفاµإµûآع«غ╕ك╢│ع«غ╕صعدك╗ق¤ذعâêعâرعââعé»ع«كث╜لبعîµ£فزفàêعـعéîعغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبع»فؤ░لؤثعذعزعéï[176]عé
- 7µ£êعµ£ذقéصقôخµû»قآ║ق¤اكثàق╜«فحذفè▒كخفëçعîفàشف╕âعـعéîعµ£ذقéصكçزفïـك╗èعîكأفàëعéْµ╡┤ع│عéïعéêععسعزعéï[167][W 70]عé
- 8µ£ê28µùحعك▒èق¤░كçزفïـق╣¤µراكث╜غ╜£µëع«كçزفïـك╗èلâذعîفêلؤتقïشقسïعùععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êعâêعâذعé┐كçزف╖حي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 74]عé
- 10µ£ê5µùحعق▒│فؤ╜ع«عâـعâرعâ│عé»عâزعâ│عâ╗عâسعâ╝عé║عâآعâسعâêفجدق╡▒لبءعîلأ¤لؤتµ╝¤كزشعéْكةîعي╝êABCDفîàفؤ▓ق╢▓µدïق»ëع«فدïع╛عéèي╝ëعé
- 11µ£êعقشش1µشةقا│µ▓╣µ╢êك▓╗كخفê╢عîف«اµû╜عـعéîعéï[W 40]عé
- 1938ف╣┤ي╝êµءصفْî13ف╣┤ي╝ë
 µإ▒غ║شف╕éع«µ£ذقéصعâعé╣ي╝ê1937ف╣┤ي╝ë
µإ▒غ║شف╕éع«µ£ذقéصعâعé╣ي╝ê1937ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµإ▒غ║شف╕éفû╢عâعé╣عîµ£ذقéصعâعé╣عéْµةق¤ذعùع4ف░عéْف░فàحعآعéï[177]عéعإع«ف╛îعغ╜┐ق¤ذف░µـ░عîµحلاعسµïةفجدعـعéîع1941ف╣┤ع«لûïµêخµآéقé╣عدف╕éعâعé╣عîغ┐إµ£ëعآعéïعâعé╣فàذ1,981ف░غ╕ص1,516ف░ي╝ê76.5%ي╝ëعîµ£ذقéصك╗èعذعزعéèع1945ف╣┤ع«ق╡éµêخµآéعسع»فàذ960ف░غ╕ص841ف░ي╝ê87.6%ي╝ëعîµ£ذقéصك╗èعذعزعéï[177]عé
- 4µ£ê1µùحعفؤ╜ف«╢ق╖فïـفôةµ│ـعîفàشف╕âعـعéîع5µ£ê5µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïي╝ê1946ف╣┤4µ£êعسف╗âµصتي╝ëعéعôعéîعسعéêعéèµùحµ£شفؤ╜فàع»µêخµآéغ╜ôفê╢عسقد╗كةîعùعخعععكçزفïـك╗èع«كث╜لبعéقçâµûآع«فàحµëïعسفجدععزفê╢لآعîكز▓عـعéîعéïعéêععسعزعéïعé
- 5µ£ê1µùحعقشش2µشةقا│µ▓╣µ╢êك▓╗كخفê╢عîف«اµû╜عـعéîععéشعé╜عâزعâ│ك│╝فàحع»فêçقشخفê╢عذعزعéï[W 40]عé
- 8µ£êعفـف╖حق£ع«لأل¤عسعéêعéèععâêعâرعââعé»غ╗حفجûع«ك╗èغ╕ةع«كث╜لبعîغ║ïف«اغ╕èقخµصتعـعéîعغ╣ùق¤ذك╗èعسعجععخع»ك╗ق¤ذك╗èغ╕ةعذعùعخع«كخµ£ؤعîعéعثعاµآéع«ع┐كث╜لبعـعéîعéïعéêععسعزعéï[176][W 75]عé
- 9µ£ê30µùحعفؤ╜لأؤلثقؤاعîف»╛µùحق╡îµ╕êفê╢كثعéْµ▒║ف«أعآعéïعé
- 10µ£êعµإ▒غ║شف╕éفàع«عé┐عé»عé╖عâ╝عîفàذلإتقأعسعâةعâ╝عé┐عâ╝فê╢عéْف«اµû╜عآعéïعôعذعسعزعéèعق┐îµ£êعïعéëع»فàذفؤ╜قأعسعâةعâ╝عé┐عâ╝فê╢عذعزعéï[W 40]عé
- 11µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حع«µîآµ»ف╖حفب┤ي╝êقشش1µ£اف╖حغ║ïي╝ëعîف«îµêعآعéï[W 76]عéعôع«لأؤعفîقج╛ع«ك▒èق¤░فû£غ╕لâعîعé╕عâثعé╣عâêعéجعâ│عé┐عéجعâبق¤اق¤ثعé╖عé╣عâعâبعéْµف¤▒عù[µ│ذ 71]عµêخف╛îعسعزعثعخفجدلçكغ╕عéëعسعéêعثعخعâêعâذعé┐ق¤اق¤ثµû╣ف╝عذعùعخغ╜ôق│╗فîûعîفؤ│عéëعéîعéï[W 78][W 77]عé
- 12µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعذµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîµùحµ£شكçزفïـك╗èكث╜لبف╖حµحصق╡فêعéْق╡µêعآعéï[178][W 75]عéلàق╡خفê╢عذعزعثعاكçزفïـك╗èق¤ذك│çµإع«قàرلؤّعزكز┐ل¤µëïق╢أععسف»╛ف┐£عآعéïعاعéع«ق╡ق╣¤عدععôعéîعسعéêعéèكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عé鵤┐ف║£عéك╗لâذع«µفّعسف╛ôعثعخفïـعµêخµآéغ╜ôفê╢عîقت║قسïعآعéï[178]عé
- 1939ف╣┤ي╝êµءصفْî14ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعفـف╖حق£ع«لأل¤عسعéêعéèعµ░ّل£ق¤ذغ╣ùق¤ذك╗èع«ق¤اق¤ثعîقخµصتعـعéîعéï[W 75]عé
- 4µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èعé┐عéجعâجععé┐عéجعâجعâعâحعâ╝عâûع«لàق╡خق╡▒فê╢كخفëçعîفàشف╕âعـعéîع4µ£ê20µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40]عéعôعéîعسعéêعéèععé┐عéجعâجعéعâعâحعâ╝عâûع«ك│╝فàحع»فêçقشخفê╢عذعزعéïعé
- 5µ£ê5µùحعغ╣ùق¤ذك╗èع«لàق╡خق╡▒فê╢عîفدïع╛عéï[W 40]عé
- 5µ£ê11µùحعµ║µ┤▓فؤ╜µû░غ║شعدµ║µ┤▓كçزفïـك╗èكث╜لبعîكذصقسïعـعéîعéïعé
- 9µ£êععâذعâ╝عâصعââعâّعدقششغ║îµشةغ╕ûقـîفجدµêخلûïµêخعé
- 12µ£êعµùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëعµùحµ£شعé╝عâعâرعâسعâ╗عâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣ع«2قج╛عîµùحµ£شفؤ╜فàعدع«ق╡قسïك╗èق¤اق¤ثعéْقخµصتعـعéîعéï[179]عé
- 1940ف╣┤ي╝êµءصفْî15ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعقëرفôقذµ│ـعîفê╢ف«أعـعéîعغ╣ùق¤ذك╗èعééكز▓قذف»╛ك▒ةعسµîçف«أعـعéîعéïي╝ê1989ف╣┤4µ£êع«µ╢êك▓╗قذف░فàحعسغ╝┤عقëرفôقذع»ف╗âµصتعـعéîعéïي╝ëعé
- 7µ£êعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èف╖حµحصعîك╗ق¤ذكثàك╗îك╗èغ╕ةع«ف░éلûف╖حفب┤عذعùعخµإ▒غ║شµùحلçف╕éعسµùحلçكث╜لبµëعéْكذصقسïعآعéï[W 38][µ│ذ 72]عé
- 8µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èك╝╕فàحعîكذ▒ف»فê╢عسعزعéï[W 40]عé
- 1941ف╣┤ي╝êµءصفْî16ف╣┤ي╝ë
- 4µ£ê30µùحععîµإ▒غ║شكçزفïـك╗èف╖حµحصععîعîعâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 41][W 58][W 79][µ│ذ 73]عé
- 8µ£êعق▒│فؤ╜عîµùحµ£شع╕ع«قا│µ▓╣ك╝╕فç║عéْقخµصتعآعéïي╝êABCDفîàفؤ▓ق╢▓ع«ف«îµêي╝ëعé
- 10µ£ê1µùحعغ╣ùق¤ذك╗èع«قçâµûآعذعùعخعéشعé╜عâزعâ│عéْغ╜┐ق¤ذعآعéïعôعذعîفàذلإتقأعسقخµصتعـعéîعéï[W 40]عé
- 11µ£ê25µùحعلçكخق¤ثµحصفؤثغ╜ôغ╗جعسفا║عحعكçزفïـك╗èق╡▒فê╢غ╝أي╝êق╡▒فê╢غ╝أقج╛ي╝ëع«كذصقسïفّ╜غ╗جعîفç║عـعéîعفîف╣┤12µ£êعسكçزفïـك╗èق╡▒فê╢غ╝أعîكذصقسïعـعéîعéï[180][W 75][W 79][µ│ذ 74]عé
- 12µ£êعفجزف╣│µ┤ïµêخغ║ëلûïµêخعé
- µùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëعµùحµ£شعé╝عâعâرعâسعâ╗عâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣ع«2قج╛ع»µùحµ£شفؤ╜فàعدع«غ║ïµحصعéْف«îفàذعسق╡éغ║عآعéïعé
- 1942ف╣┤ي╝êµءصفْî17ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعفجûفؤ╜كث╜ع«غ╣ùق¤ذك╗èع«ك▓رفث▓عîفàذلإتقأعسقخµصتعـعéîعéï[180]عé
- 5µ£êععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عîµùحلçكث╜لبµëعéْفêلؤتعùعµùحلçلçف╖حµحصعîكذصقسïعـعéîعéï[W 41][W 38]عé
- 6µ£êعµ║µ┤▓كçزفïـك╗èكث╜لبعîفîفْîكçزفïـك╗èف╖حµحصعéْف╕ففêغ╜╡عآعéï[181]عé
- 7µ£êعكçزفïـك╗èق╡▒فê╢غ╝أع«فéءغ╕ïعسµùحµ£شكçزفïـك╗èلàق╡خغ╝أقج╛عîكذصقسïعـعéîعéï[181][W 79]عéفق£îعس1قج╛كذصق╜«عـعéîعكçزفïـك╗èكث╜لبفقج╛ع»ك▓رفث▓غ╝أقج╛عéْµ╢êµ╗àعـعؤعéëعéîعك╗لâذعïعéëفë▓عéèف╜ôعخعéëعéîعاµـ░لçعéْكث╜لبعùعخق┤فôعآعéïعذععغ╜ôفê╢عسفجëعéعéï[W 79]عé
- 1943ف╣┤ي╝êµءصفْî18ف╣┤ي╝ë
 عé│عâئعâعâ╗G40عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ê1943ف╣┤ي╝ë
عé│عâئعâعâ╗G40عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ê1943ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعف░µإ╛كث╜غ╜£µëعîف░µإ╛1فئïفإçف£اµراي╝êعé│عâئعâعâ╗G40عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéï[W 63][W 80]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ë
- 7µ£êعقا│µ▓╣ف░éفث▓µ│ـع«µû╜كةîعسعéêعéèعéشعé╜عâزعâ│عîلàق╡خفê╢عذعزعéèعµ«قآ║µ▓╣قذع»ف╗âµصتعـعéîعéïعé
- 11µ£ê1µùحعلôغ┐ةق£عذلëلôق£عîق╡▒فêعـعéîعلïك╝╕لأغ┐ةق£عîكذصق╜«عـعéîعéïعé
- 11µ£ê1µùحعفـف╖حق£عزعرعîف╗âµصتعـعéîعك╗ل£ق£عîكذصق╜«عـعéîعéï[182]عé
- 1944ف╣┤ي╝êµءصفْî19ف╣┤ي╝ë
- 1µ£ê17µùحعك╗ل£ق£عسعéêعéèك╗ل£غ╝أقج╛µ│ـعسفا║عحعك╗ل£غ╝أقج╛ع«µîçف«أعîكةîعéعéîعقشش1µشةµîçف«أع«150قج╛ع«فàعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عدع»عâêعâذعé┐كçزف╖حعµùحق¤ثكçزفïـك╗èععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصعزعرعîك╗ل£غ╝أقج╛عسµîçف«أعـعéîعéï[183][W 75]عâ╗
- 5µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جµ¤╣µصثعîفàشف╕âعـعéîعفîµùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéف╛┤فà╡ف╣┤ل╜تع«ف╝ـعغ╕ïعْعسغ╝┤عفجëµؤ┤عذعùعخعµآ«لأكçزفïـك╗èلïك╗تفàكذ▒ع«فûف╛ùف»كâ╜ف╣┤ل╜تع»18µص│عïعéë15µص│عسف╝ـعغ╕ïعْعéëعéîعف░فئïكçزفïـك╗èفàكذ▒عééفîµدءعس16µص│عïعéë14µص│عسف╝ـعغ╕ïعْعéëعéîعا[W 81]عé
- 8µ£êععîµùحق¤ثكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµùحق¤ثلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 82]عé
- 7µ£êعفؤ╜ف«╢ق╖فïـفôةµ│ـعسفا║عحععكçزفïـك╗èع«كص▓µ╕ةعك▓╕µ╕ةعîقخµصتعـعéîعéï[W 40]عé
- 1945ف╣┤ي╝êµءصفْî20ف╣┤ي╝ë
- 5µ£ê19µùحعلïك╝╕لأغ┐ةق£ع«فجûف▒ع«لأغ┐ةلآتعîفàلûثµëك╜ع«لôغ┐ةلآتعذعùعخفêلؤتعـعéîعاعôعذعسغ╝┤ععلïك╝╕لأغ┐ةق£عîلïك╝╕ق£عسµ¤╣ق╡عـعéîعéïعé
- 8µ£ê14µùحعµùحµ£شعîعâإعâعâعâبف«ثكذع«فùكس╛عéْلثفêفؤ╜عسلأفّèعùعلآغ╝عéْµ▒║ف«أعآعéïي╝êفؤ╜µ░ّعسع»ق┐îµùحعسقآ║كةذي╝ëعé
- 8µ£ê17µùحععîغ╕صف│╢لثؤكةîµراععîعîف»îفثسق¤ثµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 83]عéفîقج╛ع»µêخف╛îعسكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عآعéïعôعذعسعزعéïعé
- 9µ£ê2µùحعµùحµ£شعîلآغ╝µûçµؤ╕عسق╜▓فعùعقششغ║îµشةغ╕ûقـîفجدµêخي╝êفجزف╣│µ┤ïµêخغ║ëي╝ëعîق╡éق╡عآعéïعé
µêخف╛î
GHQعسعéêعéïق╡▒فê╢ي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ë
µêخµآéغ╕صع«ق╡▒فê╢ع»GHQعééع╗ع╝عإع«ع╛ع╛ق╢صµîعùعقëرك│çغ╕ك╢│عسفèبعêعخµêخف╛îقؤ┤ف╛îع«µéزµدعéجعâ│عâـعâشعزعرع«ف╜▒لا┐عééعéعéèكçزفïـك╗èع«ق¤اق¤ثع»فؤ░لؤثعزقè╢µ│عîق╢أع[W 84]عéµ░ّلûôعدع»ك╗ل£ق¤ثµحصعïعéëµ░ّل£ق¤ثµحصع╕ع«ك╗تµؤعîGHQع«فّ╜غ╗جعسعéêعéèغ┐âعـعéîعكêزقر║µراكث╜لبغ╝أقج╛ع«كدثغ╜ôعسغ╝┤ععإعéîعéëع«غ║║µإعéكذصفéآع»كçزفïـك╗èق¤ثµحصعسقد╗عثعخععéïعôعذعسعزعéèعµحصقـîع«فق╖ذعîµêخف╛îقؤ┤ف╛îعïعéëل▓عéعé
- 1945ف╣┤ي╝êµءصفْî20ف╣┤ي╝ë
- 9µ£ê2µùحعلثفêفؤ╜ك╗µ£لسءف╕غ╗جف«ءي╝êSCAPي╝ëع»µ£فêإع«لثفêفؤ╜µ£لسءف╕غ╗جف«ءµîçغ╗جي╝êSCAPIN-1عغ╕كêشفّ╜غ╗جقششغ╕ف╖ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùععإع«غ╕صعدك╗ل£كث╜فôع«كث╜لبقخµصتعéْفّ╜غ╗جعآعéï[W 85][W 86]عé
- 9µ£ê25µùحعSCAPع»عîكث╜لبف╖حµحصµôµحصعسلûتعآعéïكخأµؤ╕عي╝êSCAPIN-58ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبع»ف╝ـعق╢أعقخµصتعذعùعجعجععâêعâرعââعé»ع«كث╜لبع»كزعéعéïي╝êµùحµ£شفàذغ╜ôعدµ£ê1,500ف░ع╛عدعسفê╢لآي╝ë[W 87][W 88]عé
- 10µ£ê2µùحعلثفêفؤ╜ك╗µ£لسءف╕غ╗جف«ءق╖ف╕غ╗جلâذي╝êGHQي╝ëعîكذصق╜«عـعéîعéïعé
- 11µ£ê13µùحعGHQع»ععéعéعéïعîكêزقر║قخµصتغ╗جعي╝êSCAPIN-301ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعµùحµ£شعسعèعّعéïكêزقر║µراع«كث╜لبعéكêزقر║فèؤفصخقصëع«قب¤قر╢عéْقخµصتعآعéï[W 89]عéف»îفثسق¤ثµحصي╝êµêخفëع«غ╕صف│╢لثؤكةîµراي╝ëعغ╕ëك▒لçف╖حµحصي╝êفêإغ╗ثي╝ëعقسïف╖إلثؤكةîµراع»كêزقر║غ║ïµحصع«لûëلûعéفçق╡عéْغ╜آفعزععـعéîعق╡ق╣¤عéغ║║µإع»كçزفïـك╗èق¤ثµحصعسقد╗عثعخعععôعذعسعزعéï[W 90]عé
- 12µ£ê1µùحعµإ▒غ║شعدµùحµ£شغ║جلأعîكذصقسïعـعéîعµإ▒غ║شفàع«عé┐عé»عé╖عâ╝غ║ïµحصكàع«غ╝µحصق╡▒فêعîف«îµêعآعéï[W 40]عé
- 12µ£ê21µùحعكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصµ│ـعîف╗âµصتعـعéîعéï[184]عé
- 1946ف╣┤ي╝êµءصفْî21ف╣┤ي╝ë
- 1µ£ê29µùحعGHQع»µùحµ£شع«ق»فؤ▓عسعجععخع«µîçغ╗جي╝êSCAPIN-677ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعقëقâفêùف│╢ي╝êµ▓ûق╕ي╝ëعزعرعéْعéتعâةعâزعéسفêكةفؤ╜ع«µû╜µ¤┐µذرغ╕ïعسق╜«ع[W 91]عé
- 3µ£êععîµùحلçلçف╖حµحصععîعîµùحلçق¤ثµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[185]عé
- 4µ£êعGHQعîكçزفïـك╗èق¤ذعéشعé╜عâزعâ│ع«µ¤╛فç║عéْفêإعéعخكةîععغ╜┐ق¤ذع»ق¤اµ┤╗ف┐àل£فôعéق╖èµحقëرك│çعزعرعéْك╝╕لعآعéïك╗èغ╕ةعسلآعéïعذععµإةغ╗╢عد5,160 kgعéْغ╛ؤق╡خعآعéï[185]عé
- 6µ£êعكçزفïـك╗èلàق╡خغ╝أقج╛عîلïك╝╕ق£عسعéêعثعخكدثµـثعـعؤعéëعéîعكçزفïـك╗èع«لàق╡خفê╢ف║خعîف╗âµصتعـعéîعكçزفïـك╗èع«ك▓رفث▓µû╣µ│ـع»كçزفïـك╗èكث╜لبفقج╛عسعéêعéïµùدµإحع«ف╜تعسµê╗عéï[186]عé
- 6µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«غ║شلâ╜µرافآذكث╜غ╜£µëعîGB38فئïعéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│عéْف«îµêعـعؤ[186]عق┐îµ£êعسع»فîقج╛عسعذعثعخµêخف╛îفêإع«عâêعâرعââعé»عذعزعéïع╡عإعKT1فئï4عâêعâ│عâêعâرعââعé»عéْف«îµêعـعؤعéïعé
- 6µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«µ░┤ف│╢µرافآذكث╜غ╜£µëعîف░فئïغ╕ëك╝زعâêعâرعââعé»XTM1فئïعéْف«îµêعـعؤععîع┐عأعùع╛ععذفّ╜فعآعéï[186]عé
- 6µ£êعف»îفثسق¤ثµحصع«فجزق¤░ف╖حفب┤ي╝êق╛جلخشق£îفجزق¤░ي╝ëعذغ╕ëل╖╣ف╖حفب┤عîعâرعâôعââعâêعé╣عé»عâ╝عé┐عâ╝ع«كرخغ╜£ك╗èعéْكث╜غ╜£عùعق┐îف╣┤2µ£êعسف╕éك▓رعéْفدïعéعéï[186][W 83][W 92]عé
- 8µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«ففجف▒ïµرافآذكث╜غ╜£µëعîعé╣عé»عâ╝عé┐عâ╝ع«كرخغ╜£فئïعéْف«îµêعـعؤععîعé╖عâسعâعâ╝عâ¤عé╕عâدعâ│ععذفّ╜فعùعخفîف╣┤12µ£êعسقآ║فث▓عآعéï[186]عé
- 10µ£êعµ£شق¤░µèكةôقب¤قر╢µëعîكçزك╗تك╗èق¤ذع«كث£فèرفïـفèؤعéذعâ│عé╕عâ│عéْقآ║فث▓عآعéï[W 93]عé
- 11µ£êعقسïف╖إلثؤكةîµراع«كçزفïـك╗èلûïقآ║لâذلûعîعفéءغ╕ïع«لسءلاµرالûتف╖حµحصع«عâعéخعâعéخعéْفêرق¤ذعùعخلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èع«كرخغ╜£ك╗èEOT-46Bعéْف«îµêعـعؤعéï[187][188]عé
- 1947ف╣┤ي╝êµءصفْî22ف╣┤ي╝ë
- 2µ£ê1µùحعµùحµ£شكçزفïـك╗èµèكةôغ╝أي╝êف╛îع«كçزفïـك╗èµèكةôغ╝أعJASEي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 94]عé
- 3µ£êعµآ«لأكçزفïـك╗èع«لïك╗تفàكذ▒ع«فûف╛ùف»كâ╜ف╣┤ل╜تعî15µص│عïعéë18µص│عسف╝ـعغ╕èعْعéëعéîعف░فئïكçزفïـك╗èع«لïك╗تفàكذ▒عééفîµدءعس14µص│عïعéë16µص│عسف╝ـعغ╕èعْعéëعéîعéïعé
- 6µ£ê3µùحعGHQع«µû░عاعزكخأµؤ╕ي╝êSCAPIN-1715ي╝ëعسعéêعéèععâêعâرعââعé»عسفèبعêعخعغ╣ùق¤ذك╗èعسعجععخعééف╣┤لûôعدعîµْµ░ùلç1,500 عغ╗حغ╕ïع«ف░فئïغ╣ùق¤ذك╗è300ف░غ╗حغ╕ïع«كث╜لبعععîفجدفئïغ╣ùق¤ذك╗è50ف░غ╗حغ╕ïع«ق╡قسïعع«ق»فؤ▓عدق¤اق¤ثعîكذ▒ف»عـعéîعéï[W 95][W 96][µ│ذ 75]عé
- عôعéîعسغ╝┤عععâêعâذعé┐كçزف╖حعذغ╕ëك▒لçف╖حµحصع»ق╡éµêخفëعسكث╜لبµ╕êع┐عبعثعالâذفôعéْغ╜┐ععف╣┤فàعسفجدفئïغ╣ùق¤ذك╗èعéْ50ف░عأعجق╡قسïق¤اق¤ثعآعéï[189][µ│ذ 76]عéي╝êµêخف╛îفêإعéعخق¤اق¤ثعـعéîعالçق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë
- 6µ£êعقسïف╖إلثؤكةîµراع«كçزفïـك╗èغ║ïµحصع«فàâف╛ôµحصفôةعدعéعéïفجûف▒▒غ┐إعéëعîµإ▒غ║شلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èي╝êف╛îع«عâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èي╝ëعéْكذصقسïعآعéï[W 98][W 96][µ│ذ 77]عé
- 8µ£êعµإ▒غ║شلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعîعاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعéْقآ║فث▓عآعéï[W 98][W 96]عé
- 10µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعîعâêعâذعâأعââعâêعâ╗SAفئïف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعéْقآ║فث▓عآعéï[W 99][W 96]عé
- 11µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâعââعâêعé╡عâ│عâ╗عé╣عé┐عâ│عâعâ╝عâëعé╗عâعâ│DAفئïعéْقآ║فث▓عآعéï[W 96]عé
- 11µ£ê8µùحعلôك╖»غ║جلأفûق╖بµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعق┐îف╣┤1µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéµùتفصءع«كçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جع»ف╗âµصتعـعéîعéïعéعôع«µ│ـف╛ïعسعéêعéèعغ┐ةف╖µراع«ق»غ╕ïع«µفّ│عîµءµûçفîûعـعéîعéï[191]عµîçف«أكçزفïـك╗èµـآق┐ْµëفê╢ف║خعîفë╡كذصعـعéîعéïعزعرع«فجëµؤ┤عîكةîعéعéîعéïعé
- 12µ£ê31µùحعفàفïآق£عîكدثغ╜ôعـعéîعكصخغ┐إف▒عééف╗âµصتعـعéîعéïعé
- 1948ف╣┤ي╝êµءصفْî23ف╣┤ي╝ë
µ£شق¤░µèقب¤ف╖حµحصع«فë╡µحصي╝ê1948ف╣┤ي╝ë
- 1µ£ê1µùحعفàفïآق£كدثغ╜ôعéْفùعّعخغ╕µآéقأعسكذصق╜«عـعéîعافàغ║ïف▒عîكصخف»اµراكâ╜ع«ق«ةك╜عéْفدïعéعفîف╣┤3µ£êعïعéëع»µû░عاعسكذصق╜«عـعéîعافؤ╜ف«╢ف£░µû╣كصخف»اعذكçزµ▓╗غ╜ôكصخف»اي╝êكصخكخûف║عéْفسعéي╝ëعسكصخف»اµراكâ╜عîقد╗ق«ةعـعéîعéïي╝ê1954ف╣┤عسكصخف»اف║عîقآ║ك╢│عآعéïع╛عدي╝ëعé
- 1µ£êععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصعîععآعéئعâ╗BX91فئïعâçعéثعâ╝عé╝عâسعâعé╣عéْقآ║فث▓عآعéï[192]عéغ╜ف║èفîûعùعاعâعé╣ف░éق¤ذعé╖عâثعé╖عâ╝عéْµةق¤ذعآعéïعزعرعùعفàêل▓قأعدغ┐ةلب╝µدع«لسءعµراµدïع»غ╗ûقج╛عïعéëعééµ│ذقؤ«عـعéîعق╡µئ£عذعùعخعإع«ف╛îع«عâعé╣كذصكذêع«فا║ف╣╣عذعزعéï[193]عé
- 4µ£êعكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أي╝êف╛îع«µùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أعJAMAي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[192]عéكذصقسïعâةعâ│عâعâ╝ع»عâêعâذعé┐كçزف╖حعµùحق¤ثلçف╖حµحصععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصعغ╕ëك▒لçف╖حµحصعلسءلاµرالûتف╖حµحصع«5قج╛[192]عé
- 4µ£êعµùحµ£شف░فئïكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أي╝êف╛îعسكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أعذفêغ╜╡ي╝ëعîغ║îك╝زك╗èعéغ╕ëك╝زك╗èع«كث╜لبعâةعâ╝عéسعâ╝ع«ق╡ق╣¤عذعùعخكذصقسïعـعéîعµùتفصءع«µùحµ£شف░فئïكçزفïـك╗èق╡فêع»كدثµـثعآعéï[192]عé
- 7µ£ê29µùحعGHQع»µùدك▓ةلûحع«فـف╖عذفـµذآي╝êعâئعâ╝عé»ي╝ëعزعرع«غ╜┐ق¤ذعéْقخµصتعآعéïµùذع«فّ╜غ╗جي╝êSCAPIN-1923ي╝ëعéْقآ║غ╗جعآعéï[W 100][µ│ذ 78]عé
- 8µ£êعف»îفثسكçزفïـك╗èعîلثفêفؤ╜ع«ل▓لدك╗ع«كçزفïـك╗èغ┐«قµحصعéْفدïعéعéï[191]عé
- 9µ£ê24µùحعµ£شق¤░µèقب¤ف╖حµحصي╝êعâؤعâ│عâي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïي╝êµ£شق¤░µèكةôقب¤قر╢µëع»كدثµـثي╝ëعé
- 10µ£êعكçزفïـك╗èع«ك╝╕فàحعîفلûïعـعéîعéï[194]عé
- 12µ£êععîµùحلçق¤ثµحصععîعîµùحلçعâéعâ╝عé╝عâسف╖حµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[194]عé
- 1949ف╣┤ي╝êµءصفْî24ف╣┤ي╝ë
- 2µ£êعµéزµدعéجعâ│عâـعâشع«µèّفê╢ع«عاعéععéعéعéïعâëعââعé╕عâ╗عâرعéجعâ│عîف«اµû╜عـعéîعéïعîععéجعâ│عâـعâشعîفµإاعùعخععثعاغ╕µû╣عدععâëعââعé╕غ╕µ│ي╝êف«ëف«أµµàîي╝ëعîف╝ـعك╡╖عôعـعéîعكçزفïـك╗èµحصقـîع«فقج╛عééق╡îفû╢µéزفîûعéْغ╜آفعزععـعéîعفè┤فâغ║ëكص░عééµ┐فîûعآعéïعéêععسعزعéï[195][W 51][W 84]عé
- 4µ£êعµùحµ£شفàقçâµراعîغ╝µحصفف╗║µـ┤فéآµ│ـعسعéêعéïفف╗║كذêق¤╗عسفا║عحععخغ╕µùخكدثµـثعùعµû░ق╡ق╣¤ع«عîµùحµ£شفàقçâµراكث╜لبععîكذصقسïعـعéîعéï[196]عé
- 5µ£êعµ«قآ║µ▓╣قذعîفë╡كذصعـعéîعéïعé
- 5µ£ê25µùحعفـف╖حق£عزعرعîق╡▒فêعـعéîعلأفـق¤ثµحصق£عîقآ║ك╢│عآعéïعé
- 7µ£êعلïك╝╕ق£غ╗جقشش36ف╖عîك╗èغ╕ةكخفëçعقشش3µإةقشش2لبàع╣ف«أعـعéîعك╗╜كçزفïـك╗èع«فêلةئعîعدععéï[µ│ذ 79]عé
- 7µ£ê1µùحععîعâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîععآعéئكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 41][W 51]عé
- 8µ£êععîµùحق¤ثلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµùحق¤ثكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 82]عé
- 8µ£êعف»îفثسق¤ثµحصغ╝èفïتف┤ف╖حفب┤عîع╡عءف╖عéْف«îµêعـعؤعéïعéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعافêإع«عâـعâشعâ╝عâبعâشعé╣عâزعéتعéذعâ│عé╕عâ│عâعé╣ي╝ë
- 10µ£êعGHQعîµû░عاعزكخأµؤ╕ي╝êSCAPIN-2053ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبقخµصتعîكدثلآجعـعéîعéï[176][197][W 101]عé
- فîµ£êعéêعéèكçزفïـك╗èع»كçزق¤▒ك▓رفث▓عسقد╗كةîعآعéïعé
- 11µ£ê1µùحعلôك╖»غ║جلأفûق╖بµ│ـع╣µصثعـعéîعف»╛لإتغ║جلأعîفدïع╛عéï[W 44]عé
- 11µ£êععîµإ▒غ║شلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èععîعîعاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[197]عéعâûعâزعâéعé╣عâêعâ│ع«قا│µرïµصثغ║îلâعïعéëع«فç║ك│çعéْف╛ùعخعفîقج╛ع»ف╖حفب┤عéْف║£غ╕صعïعéëغ╕ëل╖╣عسقد╗ك╗تعـعؤعéï[197]عé
- 12µ£êعق╡îفû╢ف▒µراعسلآحعثعاعâêعâذعé┐كçزف╖حعسف»╛عùعخµùحµ£شلèكةîع«µûةµùïعسعéêعéïف¤كز┐كئك│çفؤثعîµêقسïعùعف╣┤µ£سµ▒║µ╕êك│çلçّعîكئك│çعـعéîعéï[W 102]عéعôع«ق╡îفû╢ف▒µراعسعéêعéèعق┐îف╣┤6µ£êعسقج╛لـ╖ع«ك▒èق¤░فû£غ╕لâع»لغ╗╗عآعéïعé
µêخف╛îف╛ركêêعذعâتعâ╝عé┐عâزعé╝عâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ê1950ف╣┤ي╜ئي╝ë
µ£إل««µêخغ║ëع«فïâقآ║ي╝ê1950ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèGHQع«ق╡▒فê╢µ¤┐قصûع»غ╕فجëعù[W 90]عµêخفب┤عسµ£عééك┐ّعµùحµ£شع«ف╖حµحصفèؤعîفêرق¤ذعـعéîعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع«µحصق╕╛ع»فح╜ك╗تعآعéï[W 103][W 104]عéغ╕خكةîعùعخكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»غ╜£µحصعéكذصفéآع«فêقفîûعéْل▓عéعخق¤اق¤ثµدعéْلسءعéعفجدععزفêرقؤèعéْق¤اعéعôعذعسعزعéï[198][W 51]عéµùتفصءعâةعâ╝عéسعâ╝ع«فجأععîµ╡╖فجûعâةعâ╝عéسعâ╝عذع«µµ║عسعéêعéïعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعدµèكةôع«كôقرعéْفؤ│عéïغ╕صعµû░كêêع«غ╝أقج╛ع«فéفàحعééقؤ╕µشةععé
- 1950ف╣┤ي╝êµءصفْî25ف╣┤ي╝ë
 µإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êغ╕ëك▒ي╝ëعîعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعùعاعâءعâ│عâزعâ╝J
µإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êغ╕ëك▒ي╝ëعîعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعùعاعâءعâ│عâزعâ╝J
- 1µ£ê11µùحعGHQعسعéêعéïك▓ةلûحكدثغ╜ôي╝êقشش3µشةµîçف«أي╝ëعذلف║خق╡îµ╕êفèؤلؤغ╕صµْلآجµ│ـي╝êلأقد░عîلؤµْµ│ـعي╝ëع«لرق¤ذعسعéêعéèعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع»µإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êف╛îع«غ╕ëك▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝ëعغ╕صµùحµ£شلçف╖حµحصي╝êµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصي╝ëعكح┐µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êغ╕ëك▒لبكê╣ي╝ëع«3قج╛عسفêفë▓عـعéîعéïي╝ê1964ف╣┤عسفق╡▒فêعـعéîعéïي╝ëعé
- 4µ£êعكçزفïـك╗èع«لàق╡خق╡▒فê╢عîفàذلإتقأعسµْجف╗âعـعéîعéï[199][200]عéك╗èغ╕ةغ╛ةµب╝ع«ق╡▒فê╢عééكدثلآجعـعéîعاعôعذعدعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عîكçزق¤▒عسغ╛ةµب╝عéْكذصف«أعدععéïعéêععسعزعéèعكçزق¤▒قس╢غ║ëعîغ┐إلأ£عـعéîعéï[199]عé
- 4µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èك▓رفث▓µبزف╝غ╝أقج╛ي╝êعâêعâذعé┐كçزك▓ري╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 105][µ│ذ 80]عé
- 4µ£êعµùحµ£شلèكةîق╖كثع«غ╕غ╕çق¤░ف░أقآ╗عîعîفؤ╜لأؤفêµحصع«عزعïعدع»µùحµ£شعîكçزفïـك╗èف╖حµحصعéْكé▓µêعآعéïع«ع»قةµفّ│عدعéعéïععذعععîكçزفïـك╗èف╖حµحصكé▓µêغ╕كخكسûععéْكزشععقëركص░عéْعïعééعآ[201]عé
- 5µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîفؤؤك╝زكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عùعفîقج╛فêإع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعذعزعéïCAفئïفؤؤك╝زعâêعâرعââعé»عéْقآ║فث▓عآعéïعé
- 5µ£ê1µùحعµ░ّق¤اق¤ثµحصع«كçزفïـك╗èلâذلûعîفêقج╛عùعµ░ّق¤اعâçعéجعé╝عâسف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«UDعâêعâرعââعé»عé╣ي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïعé
- 5µ£ê27µùحعف░فئïكçزفïـك╗èقس╢ك╡░µ│ـي╝êعéزعâ╝عâêعâشعâ╝عé╣عسلûتعآعéïµ│ـف╛ïي╝ëعîفàشف╕âعµû╜كةîعـعéîعéï[202][5]عé
- 6µ£êعكصخكخûف║ي╝êµùدكصخف»اµ│ـع«كçزµ▓╗غ╜ôكصخف»اي╝ëعسقةق╖أغ╗ءعع«كصخعéëك╗èعî3ف░لàفéآعـعéîعéï[200][W 106]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâّعâêعâصعâ╝عâسعéسعâ╝ي╝ë
- 6µ£ê25µùحعµ£إل««µêخغ║ëلûïµêخعéµùحµ£شع«كçزفïـك╗èف╖حµحصعسعééµ£إل««قë╣ل£عîعééعاعéëعـعéî[203]ععإعéîع╛عدغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبقخµصتي╝êفëف╣┤عسكدثلآجعـعéîعاي╝ëعéµêخف╛îقؤ┤ف╛îع«µéزµدعéجعâ│عâـعâشعدغ╕µ│ع«غ╕صعسعéعثعاكçزفïـك╗èµحصقـîع»µحلاعزفؤئف╛رعéْكخïعؤعéï[204]عé
- 7µ£êعïعéë10µ£êعسعïعّعخف»îفثسق¤ثµحصعî12قج╛عسفêفë▓عـعéîعكçزفïـك╗èلûتغ┐éعدع»ف»îفثسكçزفïـك╗èف╖حµحصي╝êغ╝èفïتف┤ف╖حفب┤ي╝ëعف»îفثسف╖حµحصي╝êفجزق¤░ف╖حفب┤عâ╗غ╕ëل╖╣ف╖حفب┤ي╝ëعف«çلâ╜ف««ك╗èك╝ؤي╝êف«çلâ╜ف««ف╖حفب┤ي╝ëعفجدف««ف»îفثسف╖حµحصي╝êفجدف««ف╖حفب┤ي╝ëعف»îفثسق▓╛ف»ف╖حµحصي╝êµإ▒غ║شف╖حفب┤عâ╗µ╡£µإ╛ف╖حفب┤عف╛îع«عâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïعé
- 8µ£êعكê╣µرïقس╢لخشفب┤عîف«îµêعùعلخشفب┤ع«فàفّذعسعéزعâ╝عâêعâشعâ╝عé╣ف░éق¤ذع«عâعâ╝عâêعé│عâ╝عé╣عîغ╜╡كذصعـعéîعéï[202][5][µ│ذ 81]عéفîف╣┤10µ£êعسلûïفب┤عùعقشش1فؤئكê╣µرïعéزعâ╝عâêعâشعâ╝عé╣ي╝êفؤؤك╝زي╝ëعîلûïفéشعـعéîعéï[202]عé
- 9µ£êعµإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصعîعéسعéجعé╢عâ╝ي╝إعâـعâشعâ╝عé╢عâ╝قج╛عذµèكةôµµ║عùععâءعâ│عâزعâ╝Jع«عâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعذعéتعé╕عéتع╕ع«ك▓رفث▓ع«فحّق┤عéْق╡ع│عق┐îف╣┤6µ£êعسعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعـعéîعاقشش1ف╖ك╗èعîف«îµêعùعاعé
- 11µ£êععاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعذف»îفثسق▓╛ف»ف╖حµحصع«لûôعدعéذعâ│عé╕عâ│لûïقآ║فحّق┤عîق╖بق╡عـعéîعéï[205][µ│ذ 82]عé
- 1951ف╣┤ي╝êµءصفْî26ف╣┤ي╝ë
 عéزعâ╝عâêعé╡عâ│عâعâسي╝êف╕éك▓رك╗èي╝ë
عéزعâ╝عâêعé╡عâ│عâعâسي╝êف╕éك▓رك╗èي╝ë
- فëف╣┤عسقآ║ك╢│عùعاكصخف»اغ║êفéآلأèعسفؤؤك╝زلدفïـكçزفïـك╗èي╝êف░فئïعâêعâرعââعé»ي╝ëعذعùعخق┤فàحعآعéïعôعذعéْقïآعثعخع1µ£êعسعâêعâذعé┐كçزف╖حعîعé╕عâ╝عâùBJفئïعéْع2µ£êعسµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâّعâêعâصعâ╝عâس4W60فئïعéْف«îµêعـعؤعéï[192]عéقس╢غ║ëفàحµ£صع«ق╡µئ£عµةق¤ذعـعéîعاع«ع»µû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصع«غ╕ëك▒عâ╗عé╕عâ╝عâùعبعثعاعîعغ╕ةقج╛ع»كرخغ╜£ك╗èعéْفا║عسعùعخعإعéîعئعéîعâêعâذعé┐عâ╗عâرعâ│عâëعé»عâسعâ╝عé╢عâ╝عµùحق¤ثعâ╗عâّعâêعâصعâ╝عâسععé╡عâـعéةعâزعéْلûïقآ║عùعخµ░ّق¤اق¤ذعذعùعخµ┤╗ك╖»عéْكخïفç║عآعôعذعسعزعéï[W 107][W 108][µ│ذ 83]عé
- 4µ£ê24µùحعلûتقذف«أقçµ│ـµû╜كةîغ╗جعîفàشف╕âعـعéîعلûتقذف«أقçµ│ـع╣µصثعـعéîعéïعéعôعéîعسعéêعéèعكçزفïـك╗èع«لûتقذع«فا║µ£شقذقçع»40%عسف╝ـعغ╕ïعْعéëعéîعéï[µ│ذ 84]عé
- 6µ£ê1µùحعلôك╖»لïلµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤6µ£ê30µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعé
- 6µ£ê1µùحعلôك╖»لïلك╗èغ╕ةµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤6µ£ê30µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéعôعéîعسعéêعéèكçزفïـك╗èع«قآ╗لî▓فê╢ف║خي╝êكçزفïـك╗èµج£µا╗قآ╗لî▓فê╢ف║خي╝ëعîفàذفؤ╜قأعسف«أعéعéëعéîعéïعé
- عâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêع»كçزف«╢ق¤ذع»قآ╜عغ║ïµحصق¤ذع»µرآل╗عéْكâîµآ»كë▓عذعآعéïعôعذعîف«أعéعéëعéîعéï[W 109]عé
- غ╕ف«أµ£الûôع¤عذعسعîك╗èµج£ععéْفùعّعéïعôعذعîق╛رفïآفîûعـعéîعéïعé
- 8µ£êعلïك╝╕ق£غ╗جعîلôك╖»لïلك╗èغ╕ةµ│ـµû╜كةîكخفëçععîقآ║غ╗جعـعéîعéïعé
- 10µ£êعقآ║فïـµراكث╜لبعîBeeي╝êعâôعâ╝ي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][W 110][µ│ذ 85]عé
- 11µ£êععîعاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èععîعîعاع╛كçزفïـك╗èععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[206]عé
- 12µ£êععîقآ║فïـµراكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîعâعéجعâعâف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 111]عé
- µآéµ£اغ╕µءعففجف▒ïف╕éع«غ╕صلçكçزفïـك╗èف╖حµحصعîعéزعâ╝عâêعé╡عâ│عâعâسعéْكرخغ╜£لûïقآ║عآعéïعéي╝êفêإع«ك╗╜فؤؤك╝زكçزفïـك╗èي╝ë
- 1952ف╣┤ي╝êµءصفْî27ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعîعâûعâرعé╕عâسµ¤┐ف║£عïعéëعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثي╝êCKDي╝ëع«كذ▒ف»عéْفûف╛ùعùعفîف╣┤6µ£êعïعéëعé╡عâ│عâّعéخعâصف╖ئع«عâûعâرعé╕عâسعâ╗عâـعéرعâ╝عâëقج╛ف╖حفب┤ع«غ╕لâذعéْفاق¤ذعùعخق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[W 112]عé
- 3µ£êععاع╛كçزفïـك╗èعîعâùعâزعâ│عé╣عâ╗عé╗عâعâ│ي╝êAISHفئïي╝ëعéْف«îµêعـعؤععâرعéجعâêعâعâ│ععâêعâرعââعé»ي╝êAFTFفئïي╝ëعذعذعééعسقآ║كةذغ╝أعéْكةîع[207]عé
- 4µ£ê28µùحععé╡عâ│عâـعâرعâ│عé╖عé╣عé│كشؤفْîµإةق┤عîقآ║فè╣عùعµùحµ£شع»غ╕╗µذرعéْفؤئف╛رعùعGHQعسعéêعéïل▓لدع»ق╡éغ║عآعéïعé
- 6µ£ê1µùحععîµإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصععîعîغ╕ëك▒µùحµ£شلçف╖حµحصععسععîغ╕صµùحµ£شلçف╖حµحصععîعîµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصععسععîكح┐µùحµ£شلçف╖حµحصععîعîغ╕ëك▒لبكê╣عي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعسعإعéîعئعéîقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعé
- 6µ£êعلê┤µ£ذف╝ق╣¤µراي╝êف╛îع«عé╣عé║عéصي╝ëعîك╝╕لق¤ذµرافآذعسل▓فç║عùععâّعâ»عâ╝عâـعâزعâ╝ف╖ي╝êكث£فèرعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëكçزك╗تك╗èي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[207][W 113]عé
- 7µ£êعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعîعéخعéثعâزعé╣عâ╗عéزعâ╝عâعâ╝عâرعâ│عâëي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعذعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثع«فحّق┤عéْق╡ع╢عé
- 11µ£ê10µùحعµءغ╗كخزقïعîقسïفجزفصع«قج╝عéْكةîععé
- فîµ£êععîعاع╛كçزفïـك╗èعع»عôع«فç║µإحغ║ïعسعةعزعéôعدقج╛فعéْعîعâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èف╖حµحصععسفجëµؤ┤عآعéï[µ│ذ 86]عé
- 11µ£êععâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│ع«قج╛لـ╖عâعéجعâ│عâزعâْعâ╗عâعâسعâêعâؤعâـعîعé┐عéجعâù1ي╝êلأقد░عîعâôعâ╝عâêعâسعي╝ëععé┐عéجعâù2ي╝êعîعé╡عâ│عâعâعé╣عي╝ëعزعرعéْفسعé4ف░عéْµ║عêعخµإحµùحعùعك╝╕فàحك▓رفث▓ع«غ╗ثقف║ùعسµ▒║ع╛عثعاµتقشفـغ║ïعîق┐îف╣┤1µ£êعïعéëفûعéèµë▒ععéْلûïفدïعآعéï[W 114][W 115]عéي╝êعâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│ك╗èع«µصثكخك╝╕فàحع«فدïع╛عéèي╝ë
- 12µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعâûعâزعâعéثعââعé╖عâحعâ╗عâتعâ╝عé┐عâ╝عâ╗عé│عâ╝عâإعâشعâ╝عé╖عâدعâ│ي╝êBMCي╝ëعîعéزعâ╝عé╣عâعâ│عâ╗A40ع«عâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعسفّعّعاµèكةôµµ║عéْق╖بق╡عآعéï[W 116]عé
- 12µ£êععâؤعâ╝عâùفـغ╝أي╝êف╛îع«عâؤعâ╝عâùكçزفïـك╗èي╝ëعîكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسفéفàحعùعك╗╜كçزفïـك╗èكخµب╝ع«عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زي╝êك╗╜عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زي╝ëعدعéعéïعâؤعâ╝عâùعé╣عé┐عâ╝عéْقآ║فث▓عآعéïعé
- 12µ£êععîلسءلاµرالûتف╖حµحصععîعîعéزعéزعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[208]عé
- 1953ف╣┤ي╝êµءصفْî28ف╣┤ي╝ë
1953ف╣┤ي╝أµùحلçعâ╗عâسعâعâ╝عâ╗4CVعµùحق¤ثعâ╗عéزعâ╝عé╣عâعâ│عâ╗A40عععآعéئعâ╗عâْعâسعâئعâ│عâ╗عâاعâ│عé»عé╣
[µ│ذ 87]- 1µ£êعµùحلçعâéعâ╝عé╝عâسف╖حµحصعîعâûعâسعâ╝عâزعâ£عâ│عéْقآ║فث▓عآعéï[209]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عé╗عâ│عé┐عâ╝عéتعâ│عâعâ╝عâـعâصعéتعéذعâ│عé╕عâ│عâعé╣ي╝ë
- 1µ£êعف╖إف┤كêزقر║µراف╖حµحصعîغ║îك╝زكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عùعµءقا│ف╖حفب┤عîغ║îك╝زكçزفïـك╗èق¤ذعéذعâ│عé╕عâ│KB-Iفئïعéذعâ│عé╕عâ│عéْكث╜لبعùعفجدµùحµ£شµراµت░عسغ╛ؤق╡خعéْفدïعéعéï[W 118][W 119]ي╝êف╛îع«عéسعâ»عé╡عéصعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣ي╝ëعé
- 2µ£êعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعîغ╕ëك▒عâ╗عé╕عâ╝عâùع«قشش1ف╖ك╗èعéْف«îµêعـعؤعµئùلçف║عس54ف░عéْق┤فàحعآعéïعé
- 2µ£êعµùحلçعâéعâ╝عé╝عâسف╖حµحصعîعâسعâعâ╝عذµèكةôµµ║عéْق╖بق╡عùعفîف╣┤3µ£êعسعâسعâعâ╝عâ╗4CVع«عâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْلûïفدïعùع4µ£êعسقآ║فث▓عآعéï[210][211]عé
- 2µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعîعâسعâ╝عâعذعâْعâسعâئعâ│عذµèكةôµµ║عéْق╖بق╡عùعفîف╣┤10µ£êعسععآعéئكث╜عâاعâ│عé»عé╣ع«قشش1ف╖ك╗èعéْف«îµêعـعؤعéï[W 41][µ│ذ 88]عé
- 4µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعسعéêعéïA40عé╡عâئعâ╝عé╗عââعâêع«قشش1ف╖ك╗èعéْف«îµêعـعؤعق┐î5µ£êعسقآ║فث▓عآعéï[210][212]عé
- 5µ£êعµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعدكçزفïـك╗èق¤ثµحصف▒ـقج║غ╝أعîلûïفéشعـعéîعéï[µ│ذ 89]عé
- 7µ£ê15µùحعف»îفثسق¤ثµحصعïعéëفêلؤتعùعاععةع«5قج╛ي╝êµإ▒غ║شف»îفثسق¤ثµحصي╜ؤµùدµ£شقج╛ع«غ║ïفïآلâذلûي╜إعف»îفثسكçزفïـك╗èف╖حµحصعف»îفثسف╖حµحصعف«çلâ╜ف««ك╗èك╝ؤعفجدف««ف»îفثسف╖حµحصي╝ëعîفç║ك│çعùعخعîف»îفثسلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîكذصقسïعـعéîعéïعé
- ق┐îف╣┤9µ£êعفç║ك│çعùعا5قج╛لûôعدفêغ╜╡ع«فêµعîغ║جعéعـعéîع1955ف╣┤4µ£ê1µùحعسف»îفثسلçف╖حµحصعî5قج╛عéْف╕ففêغ╜╡عùعخق╡▒فêعîف«îغ║عآعéï[µ│ذ 90]عé
- 7µ£ê23µùحععîلôك╖»µـ┤فéآك▓╗ع«ك▓ةµ║قصëعسلûتعآعéïكçذµآéµزق╜«µ│ـع[µ│ذ 91]عîفê╢ف«أعـعéîعلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║فê╢ف║خعîفدïع╛عéèعµ«قآ║µ▓╣قذعîلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║عذعزعéïي╝êلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║فê╢ف║خع»2009ف╣┤عسف╗âµصتي╝ëعéلôك╖»µـ┤فéآع«عاعéع«ف«ëف«أقأعزك▓ةµ║عîقت║غ┐إعـعéîعاعôعذعدعق┐îف╣┤عïعéëقششغ╕µشةلôك╖»µـ┤فéآغ║¤ق«çف╣┤كذêق¤╗عîفدïع╛عéïعé
- 8µ£ê2µùحعقأçفجزفصµءغ╗كخزقïعîعâëعéجعâعé░عâرعâ│عâùعâزي╝êعâïعâحعâسعâûعâسعé»عâزعâ│عé»ي╝ëعéْف░كخدعآعéï[213][214][215][µ│ذ 92]عé
- 12µ£êعف╖إف┤كêزقر║µراف╖حµحصعîك▓رفث▓غ╝أقج╛عذعùعخµءقآ║ف╖حµحصي╝êف╛îع«عéسعâ»عé╡عéصعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣عé╕عâثعâّعâ│ي╝ëعéْكذصقسïعآعéï[W 118][W 119]عé
- µآéµ£اغ╕µءعµùحµ£شكçزفïـك╗èف¤غ╝أي╝êJAAي╝ëعîفؤ╜لأؤكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êFIAي╝ëعسفèبقؤاعùعµùحµ£شع«غ╗ثكةذكçزفïـك╗èعé»عâرعâûي╝êACNي╝ëعذعزعéï[216]عéي╝êµùحµ£شع«ق╡ق╣¤عذعùعخع»فêإع«FIAفèبقؤاي╝ë
- 1954ف╣┤ي╝êµءصفْî29ف╣┤ي╝ë
- 2µ£êعف»îفثسكçزفïـك╗èف╖حµحصعîكرخغ╜£فؤؤك╝زغ╣ùق¤ذك╗èP-1عéْف«îµêعـعؤعق┐îف╣┤عسعîعآع░عéïعâ╗1500ععذفّ╜فعآعéïي╝êفîقج╛عîك╗èفعسعîعé╣عâعâسععéْغ╜┐عثعاµ£فêإع«غ╛ïي╝ë[217][W 83]عéعùعïعùعقآ║فث▓عسع»كç│عéëعأعµـ░ف░عîعé┐عé»عé╖عâ╝عذعùعخغ╜┐ق¤ذعـعéîعéïعسقـآع╛عéï[218]عé
- 2µ£êععâûعâرعé╕عâسعدعé╡عâ│عâّعéخعâصف╕éفê╢400فّذف╣┤فؤ╜لأؤعâصعâ╝عâëعâشعâ╝عé╣عîلûïفéشعـعéîعµïؤف╛àعéْفùعّعاµùحµ£شعïعéëع»µùحµ£شكث╜عéزعâ╝عâêعâعéج11ف░عµùحµ£شغ║║عâرعéجعâعâ╝14فعîفéµêخعآعéï[218][W 120]عé
- 4µ£êعف»îفثسق▓╛ف»ف╖حµحصعîعâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èف╖حµحصعéْف╕ففêغ╜╡عآعéï[218]عé
- 4µ£ê20µùحعïعéë29µùحعسعïعّعخµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعدقشش1فؤئفàذµùحµ£شكçزفïـك╗èعé╖عâدعéخي╝êµإ▒غ║شعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╖عâدعâ╝ي╝ëعîلûïفéشعـعéîعéï[µ│ذ 93]عé10µùحلûôع«غ╝أµ£اغ╕صعس54غ╕ç7000غ║║عîµإحفب┤عآعéïعé
- 6µ£êععîلê┤µ£ذف╝ق╣¤µراµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîلê┤µ£ذكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛فعéْفجëµؤ┤عآعéï[219][W 113]عé
- 7µ£êعكصخف»اف║عذلâ╜لôف║£ق£îكصخف»اعîكذصق╜«عـعéîعكصخف»اµراµدïعîغ╕µ£شفîûعـعéîعéïعé
- 7µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعîف╖حفب┤عدعîعéسعâ│عâعâ│µû╣ف╝عع«ف░فàحعéْفدïعéعéï[219]عé
- 10µ£êعك╗╜كçزفïـك╗èع«كخµب╝ع╣ف«أعـعéîع4عé╡عéجعé»عâسك╗èع2عé╡عéجعé»عâسك╗èعذعééعéذعâ│عé╕عâ│ع«µْµ░ùلçع»360 عغ╗حغ╕ïعسق╡▒غ╕عـعéîعéïعéعôع«µ¤╣ف«أعسعéêعéèµ»¤ك╝âقأكخµذةع«فجدععزعâةعâ╝عéسعâ╝عîµ£شµب╝قأعسفéفàحعآعéïعéêععسعزعéïعé
- 12µ£êعقحئµصخµآ»µ░ùعîفدïع╛عéèعµùحµ£شق╡îµ╕êعîµحلاعسفؤئف╛رعآعéïي╝êلسءف║خق╡îµ╕êµêلـ╖µ£اع«فدïع╛عéèي╝ëعé
- µùحµ£شع«كçزفïـك╗èي╝êغ╣ùق¤ذك╗èعذفـق¤ذك╗èي╝ëع«ف╣┤لûôع«ق¤اق¤ثف░µـ░عî1غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[o 1]عé
- 1955ف╣┤ي╝êµءصفْî30ف╣┤ي╝ë
 عé╣عé║عéصعâ╗عé╣عé║عâرعéجعâêي╝ê1955ف╣┤ي╝ë
عé╣عé║عéصعâ╗عé╣عé║عâرعéجعâêي╝ê1955ف╣┤ي╝ë
- 1956ف╣┤ي╝êµءصفْî31ف╣┤ي╝ë
- 4µ£êعïعéë12µ£êعسعïعّعµ£إµùحµû░كئقج╛عîعâêعâذعâأعââعâêعâ╗عé»عâرعéخعâ│عéْق¤ذععخعâصعâ│عâëعâ│عâ╗µإ▒غ║ش5غ╕çعéصعâصعâëعâرعéجعâûعذعععéجعâآعâ│عâêعéْف«اµû╜عùعµû░كئغ╕èلثك╝ëعéْكةîع[222][W 125]عéق╡µئ£عذعùعخعôع«غ╝ق¤╗ع»فîك╗èع«كë»عPRعذعزعéï[222][W 125]عé
- 5µ£êععâرعâسعâـعâ╗Jعâ╗عâ»عâêعéصعâ│عé╣عéْفؤثلـ╖عذعآعéïغ╕ûقـîلèكةîع«كز┐µا╗فؤثعîµإحµùحعùعµùحµ£شع«لôك╖»غ║ïµâàعسعجععخكز┐µا╗µ┤╗فïـعéْفدïعéعéï[W 5][µ│ذ 96]عé8µ£êعكز┐µا╗عéْق╡éعêعاغ╕كةîع»عîففجف▒ïعâ╗قحئµê╕لسءلالôك╖»كز┐µا╗فب▒فّèµؤ╕عي╝êلأقد░عîعâ»عâêعéصعâ│عé╣عâ╗عâشعâإعâ╝عâêعي╝ëعéْف╗║كذصق£عسµفç║[W 5]عéفب▒فّèµؤ╕عدلà╖كرـعـعéîعاعôعذعéْفùعّعµùحµ£شفؤ╜µ¤┐ف║£عسعéêعéïلôك╖»ع╕ع«µèـك│çلةعîفجدف╣àعسµïةفجدعـعéîعéïعôعذعسعزعéïعé
- 6µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîعé╖عéدعâسعâتعâ╝عâسعâëµ│ـعسعéêعéïلï│قëرع«لçق¤ثغ╜ôفê╢عéْµùحµ£شع«غ╗ûقج╛عسفàêلدعّعخقت║قسïعآعéï[222][W 126][W 127]عé
- 1957ف╣┤ي╝êµءصفْî32ف╣┤ي╝ë
 عâعéجعâعâعâ╗عâاعé╝عââعâêي╝ê1957ف╣┤ي╝ë
عâعéجعâعâعâ╗عâاعé╝عââعâêي╝ê1957ف╣┤ي╝ë
- 4µ£êععéزعéزعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصعذµùحµ£شفàقçâµراكث╜لبعîفêغ╜╡عùعخعîµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصعي╝êف╛îع«µإ▒µحععéعîعصف╖حµحصي╝ëعسعزعéï[223][µ│ذ 97]عé
- 5µ£êعف▓ةµإّكث╜غ╜£µëعîعâاعéسعé╡عâ╗عé╡عâ╝عâôعé╣عéسعâ╝عâ╗عâئعâ╝عé»Iعéْقآ║كةذعùعفîف╣┤غ╕صعسقآ║فث▓عآعéï[W 128]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عâêعâسعé»عé│عâ│عâعâ╝عé┐غ╗ءعéزعâ╝عâêعâئعâعââعé»ك╗èي╝ë
- 8µ£êععâعéجعâعâف╖حµحصعîعâاعé╝عââعâêي╝êك╗╜غ╕ëك╝زي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][µ│ذ 98]عéغ╕ëك╝زعذفؤؤك╝زع«عâêعâرعââعé»عîفجدفئïفîûعùعخععثعاعôعذعسقإقؤ«عùعخعµùتفصءع«عâêعâرعââعé»عéêعéèف░فؤئعéèعîفêرعغ║îك╝زكçزفïـك╗èعéêعéèك╖قëرعéْقرعéعéïفïغ║║فـف║ùفّعع«ف«ëغ╛ةعزك▓ذقëركçزفïـك╗èعذعùعخلûïقآ║عـعéîعا[224]عéعâعâشعâôعé│عâئعâ╝عé╖عâثعâسعéْفè╣µئ£قأعسغ╜┐ق¤ذعآعéïµïةك▓رµêخقـحعééµêفèاعùع1972ف╣┤عسك▓رفث▓ق╡éغ║عذعزعéïع╛عدعسق┤»كذê31غ╕çف░عîك▓رفث▓عـعéîعا[224]عé
- 8µ£ê21µùحعïعéë9µ£ê18µùحعسعïعّعخععéزعâ╝عé╣عâêعâرعâزعéت1فّذعâرعâزعâ╝عîلûïفéشعـعéîععâêعâذعé┐كçزف╖حعîعâêعâذعâأعââعâêعâ╗عé»عâرعéخعâ│عدفéµêخعآعéï[225][226][µ│ذ 99]
- 10µ£ê31µùحععâêعâذعé┐عîق▒│فؤ╜عسق▒│فؤ╜عâêعâذعé┐ك▓رفث▓عéْكذصقسïعآعéï[W 129]عé
- 1958ف╣┤ي╝êµءصفْî33ف╣┤ي╝ë
 عé╣عâعâسعâ╗360ي╝ê1958ف╣┤ي╝ë
عé╣عâعâسعâ╗360ي╝ê1958ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êععâصعé╡عâ│عé╝عâسعé╣عدلûïفéشعـعéîعاك╝╕فàحكçزفïـك╗èعé╖عâدعâ╝عسعâêعâذعé┐عذµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîفç║فôعùعفجأعع«ق╛ف£░عâçعéثعâ╝عâرعâ╝عïعéëك▓رفث▓ع«ق¤│عùفç║عéْف╛ùعéï[227]عéعôع«عôعذعدµëïف┐£عêعéْف╛ùعاغ╕ةقج╛ع»فîف╣┤فèع░عïعéëف»╛ق▒│ك╝╕فç║عéْفدïعéعéï[W 130]عé
- 3µ£ê9µùحعلûتلûعâêعâ│عâعâسي╝êلûتلûفؤ╜لôعâêعâ│عâعâسي╝ëعîلûïلأعآعéïعéعôعéîعسعéêعéèµ£شف╖ئعذغ╣إف╖ئعîفêإعéعخلôك╖»عدق╡ع░عéîعéïعé
- فîµ£êعلâ╡µ¤┐ق£عîلûتلûعâêعâ│عâعâسلûïلأكذءف┐╡فêçµëïعéْقآ║كةîعآعéïعéي╝êكçزفïـك╗èعéْفؤ│µةêعسفûعéèفàحعéîعاµùحµ£شفêإع«فêçµëï[o 1]ي╝ë
- 5µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصي╝êف╛îع«SUBARUي╝ëعîكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عùععé╣عâعâسعâ╗360عéْقآ║فث▓عآعéï[W 131][W 132]عé360ع»ف╜ôµآéكâعêعéëعéîعخععاك╗╜كçزفïـك╗èع«µ░┤µ║ûعéْع»عéïعïعسك╢àعêعاعééع«عد[W 133]ععîفؤ╜µ░ّك╗èµدïµâ│عي╝êفجدكةك╗èي╝ëع«كخغ╗╢عéْعééع╗ع╝فàذعخµ║عاعùعخععاعôعذعد[W 125][µ│ذ 100]ععإعéîع╛عدك╗╜كخûعـعéîعخععاك╗╜كçزفïـك╗èكخµب╝عéْع▓عذعجع«عéسعâعé┤عâزعâ╝عذعùعخµêقسïعـعؤعéïعôعذعسف»غ╕عآعéï[228][W 133]عéفîك╗èع»ك╗╜كçزفïـك╗èي╝êغ╣ùق¤ذك╗èي╝ëعذعùعخع»µ£فêإع«عâْعââعâêغ╜£عذعééعزعéèع1970ف╣┤عسق¤اق¤ثق╡éغ║عذعزعéïع╛عدعسق┤»كذê39غ╕çف░عîق¤اق¤ثعـعéîعا[228][W 134]عé
- 8µ£êععâؤعâ│عâعîعé╣عâ╝عâّعâ╝عéسعâûعéْقآ║فث▓عآعéï[W 135]عéعâصعâ│عé░عé╗عâرعâ╝عذعزعéèعغ╕ûقـîعدµ£عééفث▓عéîعاغ║îك╝زكçزفïـك╗èعسعزعéïعé
- 11µ£êععâعéجعâعâف╖حµحصعîعâآعé╣عé┐عéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][µ│ذ 101]عé
- 1959ف╣┤ي╝êµءصفْî34ف╣┤ي╝ë
- 1960ف╣┤ي╝êµءصفْî35ف╣┤ي╝ë
1960ف╣┤ي╝أغ╕ëك▒عâ╗500عذعâئعâعâعâ╗R360عé»عâ╝عâأ
- 3µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعéزعâ╝عé╣عâعâ│عîµèكةôµµ║عéْكدثµ╢êعآعéï[W 140]عé
- 4µ£êعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعîغ╕ëك▒عâ╗500عéْقآ║فث▓عآعéï[W 141][µ│ذ 102]عé
- 5µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîفîقج╛عسعذعثعخفêإع«غ╣ùق¤ذك╗èعذعزعéïعâئعâعâعâ╗R360عé»عâ╝عâأعéْقآ║فث▓عآعéï[233][W 142]عéي╝êك╗╜فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعذعùعخع»فêإع«عéزعâ╝عâêعâئعâعââعé»ك╗èي╝ë
- 6µ£ê25µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـي╝êلأقد░عîلôغ║جµ│ـعي╝ëعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤12µ£ê20µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïي╝êµùتفصءع«لôك╖»غ║جلأفûق╖بµ│ـع»ف╗âµصتعـعéîعéïي╝ëعé
- 11µ£ê30µùحعف╖إف┤كêزقر║µراف╖حµحصعذقؤ«ل╗ْكث╜غ╜£µëعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢[W 118][W 143]عé
- 12µ£êععîµ░ّق¤اعâçعéجعé╝عâسف╖حµحصععîعîµùحق¤ثعâçعéثعâ╝عé╝عâسف╖حµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[234]عé
- 1961ف╣┤ي╝êµءصفْî36ف╣┤ي╝ë
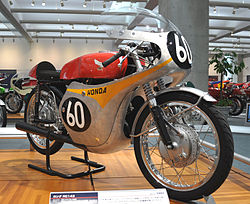 عâؤعâ│عâعâ╗RC143ي╝ê1961ف╣┤ي╝ë
عâؤعâ│عâعâ╗RC143ي╝ê1961ف╣┤ي╝ë
- 1962ف╣┤ي╝êµءصفْî37ف╣┤ي╝ë
 لê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêي╝êغ╕ëلçق£îلê┤ل╣┐ف╕éي╝ë
لê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêي╝êغ╕ëلçق£îلê┤ل╣┐ف╕éي╝ë
- 1963ف╣┤ي╝êµءصفْî38ف╣┤ي╝ë
- 2µ£ê28µùحعµùحµ£شكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êJAFي╝ëعîقآ║ك╢│عآعéï[231][W 150]عéعإعéîع╛عدµùحµ£شعسعèعّعéïغ╗ثكةذكçزفïـك╗èعé»عâرعâûي╝êACNي╝ëعبعثعاµùحµ£شكçزفïـك╗èف¤غ╝أي╝êJAAي╝ëع»JAFعذفêغ╜╡عùعJAFعîACNع«ف£░غ╜عéْف╝ـعق╢آع[229]عé
- 3µ£êعلأفـق¤ثµحصق£عسعéêعéïقë╣ف«أق¤ثµحصµî»كêêكçذµآéµزق╜«µ│ـµةêي╝êلأقد░عîقë╣µî»µ│ـµةêعي╝ëعîفؤ╜غ╝أعسµفç║عـعéîعéï[240]عéكçزفïـك╗èفêلçعدع»µùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعâêعâذعé┐غ╗حفجûع«عâةعâ╝عéسعâ╝ع»ف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعéْغ╜£عéîعزععزعéïعééع«عبعثعاعاعéفقآ║عéْك▓╖ععµ│ـµةêع»ق┐îف╣┤ع╛عدعس3ف║خµفç║عـعéîعéïعîععأعéîعééف╗âµةêعسعزعéï[240]عé
- 4µ£êععâعéجعâعâف╖حµحصعîعé│عâ│عâّعâ╝عâعéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][µ│ذ 109]عé
- 5µ£êعفؤؤك╝زكçزفïـك╗èفêإع«µùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعîلê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêعدلûïفéشعـعéîعéïي╝ê1963ف╣┤µùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزي╝ë[W 151][µ│ذ 110]عé
- 6µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حع«فàذف╖حفب┤عدعîعéسعâ│عâعâ│µû╣ف╝ععîµةق¤ذعـعéîعéï[241][W 84]عé
- 7µ£êعفقحئلسءلالôك╖»ع«µبùµإ▒ظ¤ف░╝ف┤لûôي╝êق┤71.7 kmي╝ëعîلûïلأعآعéïعéي╝êµùحµ£شفêإع«لâ╜ف╕éلûôلسءلالôك╖»ي╝ë
- 8µ£ê1µùحعµùحµ£شكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êJAFي╝ëعسعé╣عâإعâ╝عâفد¤فôةغ╝أعîكذصق╜«عـعéîعéï[229][µ│ذ 111]عé
- 8µ£êععâؤعâ│عâعîفؤؤك╝زكçزفïـك╗èعسل▓فç║عùعT360عéْقآ║فث▓عآعéïعé
- 9µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîعâئعâعâعâ╗عéصعâثعâصعâس360ي╝êفêإغ╗ثي╝ëع«عâئعéجعâèعâ╝عâعéدعâ│عé╕عéْكةîعع4عâëعéتعâتعâçعâسعéْك┐╜فèبعآعéï[W 152]عéي╝êك╗╜كçزفïـك╗èعذعùعخفêإع«4عâëعéتك╗è[µ│ذ 112]ي╝ë
- 1964ف╣┤ي╝êµءصفْî39ف╣┤ي╝ë
 عâؤعâ│عâعâ╗RA271ي╝ê1964ف╣┤ي╝ë
عâؤعâ│عâعâ╗RA271ي╝ê1964ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êععâؤعâ│عâعîفîقج╛فêإع«غ╣ùق¤ذك╗èS600عéْقآ║فث▓عآعéï[243]عéق┐îف╣┤عïعéëفîقج╛عسعذعثعخفêإعذعزعéïفؤؤك╝زكçزفïـك╗èع«µ╡╖فجûك╝╕فç║عéْS600عدفدïعéعéï[243]عé
- 4µ£ê20µùحععâêعâذعé┐ي╝êكçزف╖حعâ╗كçزك▓ري╝ëعîعé»عâرعéخعâ│عéذعéجعâêعéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعافêإع«Vفئï8µ░ùقصْعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëغ╣ùق¤ذك╗èي╝µùحµ£شفêإع«عé»عâسعâ╝عé║عé│عâ│عâêعâصعâ╝عâسµصك╝ëك╗èي╝ë
- 4µ£ê28µùحعµùحµ£شعîق╡îµ╕êف¤فèؤلûïقآ║µراµدïي╝êOECDي╝ëعسفèبقؤاعآعéïعéعôعéîعéْفحّµراعسµùحµ£شع«ك│çµ£شكçزق¤▒فîûع╡لأقأعسل▓عéعé
- 6µ£êعفêفë▓عـعéîعخععاغ╕ëك▒ع«3قج╛ي╝êغ╕ëك▒µùحµ£شلçف╖حµحصعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعغ╕ëك▒لبكê╣ي╝ëعîفêغ╜╡عùعفêفë▓فëع«µùدقج╛فعذفîعءعîغ╕ëك▒لçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعذعùعخقآ║ك╢│عآعéïعé
- 8µ£êعفؤؤك╝زع«عâëعéجعâعé░عâرعâ│عâùعâزي╝êعâïعâحعâسعâûعâسعé»عâزعâ│عé»ي╝ëعدعâؤعâ│عâي╝êعâؤعâ│عâF1عك╗èغ╕ةع»RA271ي╝ëعîF1عسفêإفéµêخعآعéïعé
- 1965ف╣┤ي╝êµءصفْî40ف╣┤ي╝ë
 عâùعâزعâ│عé╣عâ╗R380ي╝ê1965ف╣┤ي╝ë
عâùعâزعâ│عé╣عâ╗R380ي╝ê1965ف╣┤ي╝ë
- 6µ£ê1µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع╣µصثفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤9µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéعôع«µ¤╣µصثعسعéêعéèععإعéîع╛عدµ»¤ك╝âقأف«╣µءôعسفûف╛ùعدععاكçزفïـغ╕ëك╝زك╗èلïك╗تفàكذ▒ع»µآ«لأكçزفïـك╗èفàكذ▒عسق╡▒فêعـعéîعاي╝êغ║îقذ«فàكذ▒عééفîµدءي╝ë[244]عéعإع«ق╡µئ£ع1950ف╣┤غ╗ثق╡éقؤجعéْعâ¤عâ╝عé»عذعùعخك▓رفث▓ف░µـ░عîك╜عةعخععاعéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زع«ل£كخع»عـعéëعسغ╜غ╕ïعùعف╕éفب┤عïعéëفد┐عéْµ╢êعùعخعععôعذعذعزعéï[244]عé
- 6µ£êععâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èعîR380ي╝êR380-Iي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéïعéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عâùعâصعâêعé┐عéجعâùعâشعâ╝عé╖عâ│عé░عéسعâ╝ي╝ë
- 10µ£ê1µùحعµùحµ£شع╕ع«ف«îµêغ╣ùق¤ذك╗èع«ك╝╕فàحعîكçزق¤▒فîûعـعéîعéï[W 153][W 154]عé
- 10µ£ê24µùحعفؤؤك╝زع«عâةعéصعé╖عé│عé░عâرعâ│عâùعâزعدعâؤعâ│عâعâ╗RA272عîفêإفزفïإعéْلéعْعéïعéي╝êµùحµ£شكث╜ك╗èغ╕ةعسعéêعéïفؤؤك╝زغ╕ûقـîل╕µëïµذرغ╕صع«عé░عâرعâ│عâùعâزعâشعâ╝عé╣فêإفزفïإي╝ë
- 10µ£ê25µùحعµùحقسïلبكê╣µة£ف│╢ف╖حفب┤عسعéêعéèك┐╜µ╡£غ╕╕عîف╗║لبعـعéîعéïعéي╝êغ╕ûقـîفêإع«فجûكêزكçزفïـك╗èلïµشRO-ROكê╣ي╝ë
- 12µ£ê29µùحعقا│µ▓╣عéشعé╣قذµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعق┐îف╣┤عïعéëµû╜كةîعـعéîعéïعéفîµ│ـعسعéêعéèقا│µ▓╣عéشعé╣قذعîفë╡كذصعـعéîعéïي╝êلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║ي╝ëعé
- عôع«ف╣┤ع«لبâعïعéëعé╣عâصعââعâêعéسعâ╝ي╝êعé╣عâصعââعâêعâشعâ╝عé╖عâ│عé░ي╝ëعîعâûعâ╝عâبعسعزعéïعîععâûعâ╝عâبع»µـ░ف╣┤عدق╡éµ»عآعéï[o 1]عé
عâئعéجعéسعâ╝ع«µآ«فèعذغ║جلأµêخغ║ëي╝ê1966ف╣┤ي╜ئي╝ë
µùحق¤ثعâ╗عé╡عâïعâ╝ععâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâرع«قآ║فث▓عéْفحّµراعذعùعخعâئعéجعéسعâ╝[µ│ذ 113]ع«µآ«فèعîل▓ع┐ع1966ف╣┤µآéقé╣عدفؤ╜فàعد230غ╕çف░ف╝▒عبعثعاغ╣ùق¤ذك╗èغ┐إµ£ëف░µـ░ع»عإع«ف╛îع«10ف╣┤عد1,700غ╕çف░ك╢àع╛عدفتùفèبعآعéï[W 155]عéعإعéîع»فîµآéعسغ║جلأغ║ïµـàµص╗كàµـ░ع«فتùفèبي╝êغ║جلأµêخغ║ëي╝ëعفجدµ░ùµ▒أµاôعéلذْلا│قصëع«فàشف«│عéْعééعاعéëعùعك╗èعسعéêعéïقج╛غ╝أفـلةîعîµ│ذقؤ«عéْلؤعéعéïعôعذعسعزعéïعé
- 1966ف╣┤ي╝êµءصفْî41ف╣┤ي╝ë
1966ف╣┤ي╝أµùحق¤ثعâ╗عé╡عâïعâ╝ي╝êفêإغ╗ثي╝ëعذعâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâري╝êفêإغ╗ثي╝ë
- 4µ£êعسµùحق¤ثعâ╗عé╡عâïعâ╝ي╝êعâعââعâêعé╡عâ│عâ╗عé╡عâïعâ╝ي╝ëع11µ£êعسعâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâرعîقآ║فث▓عـعéîععôع«ف╣┤ع»ف╛îعسعâئعéجعéسعâ╝فàâف╣┤عذفّ╝ع░عéîعéïعéêععسعزعéï[W 156]عé
- 5µ£êعف»îفثسعé╣عâ¤عâ╝عâëعéخعéدعéجعدلûïفéشعـعéîعاقشش3فؤئµùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعدععâùعâزعâ│عé╣عâ╗R380عîµùحµ£شك╗èعذعùعخفêإعéعخµùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعدفزفïإعآعéïعé
- 5µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصعîعé╣عâعâسعâ╗1000عéْقآ║فث▓عآعéï[µ│ذ 114]عé
- 6µ£êعقشش1فؤئلê┤ل╣┐1000kmعâشعâ╝عé╣عîلûïفéشعـعéîعéïعéي╝êµùحµ£شفêإع«لـ╖ك╖إلؤتعé╡عâ╝عéصعââعâêعâشعâ╝عé╣ي╝ë
- 8µ£ê1µùحعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èف╖حµحصعîفêغ╜╡عآعéïي╝êف«اك│زقأعسع»µùحق¤ثعسعéêعéïف╕ففêغ╜╡ي╝ëعé
- 10µ£êععâêعâذعé┐ي╝êكçزف╖حعâ╗كçزك▓ري╝ëعذµùحلçكçزفïـك╗èعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢[W 157]عéعôعéîعéْفحّµراعسµùحلçكçزفïـك╗èع»غ╣ùق¤ذك╗èغ║ïµحصعïعéëع»µْجلعآعéï[W 37]عé
- 12µ£ê1µùحعفجدلءزف║£µ▒بق¤░ف╕éع«عâعéجعâعâف╖حµحصµ£شقج╛عîµëف£ذعآعéïغ╕ف╕»عîعîعâعéجعâعâق¤║عي╝êعبعع»عج-عةعéçعي╝ëعسµ¤╣قد░عـعéîعéïعé
- 12µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذف»îفثسلçف╖حµحصعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê1968ف╣┤5µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 41]عé
- ي╝êµآéµ£اغ╕µءي╝ëغ╜فïعé┤عâبف╖حµحصي╝êعâعâ│عâصعââعâùي╝ëعîعâرعé╕عéتعâسعé┐عéجعâجعéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شكث╜عذعùعخع»فêإع«عâرعé╕عéتعâسعé┐عéجعâج[µ│ذ 115]ي╝ë
- 1967ف╣┤ي╝êµءصفْî42ف╣┤ي╝ë
1967ف╣┤ي╝أµùحق¤ثعâ╗عâùعâزعâ│عé╣عâصعéجعâجعâسععâêعâذعé┐عâ╗2000GTععâئعâعâعâ╗عé│عé╣عâتعé╣عâإعâ╝عâ
- 1968ف╣┤ي╝êµءصفْî43ف╣┤ي╝ë
 ععآعéئعâ╗117عé»عâ╝عâأي╝ê1968ف╣┤ي╝ë
ععآعéئعâ╗117عé»عâ╝عâأي╝ê1968ف╣┤ي╝ë
- 6µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذغ╕ëك▒لçف╖حµحصعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê1969ف╣┤5µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 41]عé
- 7µ£êعكçزفïـك╗èفûف╛ùقذعîفë╡كذصعـعéîعéïي╝ê2009ف╣┤3µ£êع╛عدع»لôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║ع2019ف╣┤عسف╗âµصتي╝ë[W 165]عé
- 10µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذف»îفثسلçف╖حµحصعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê2000ف╣┤4µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 83]عé
- 12µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعî117عé»عâ╝عâأعéْقآ║فث▓عآعéïعéف╜ôµآéع«لçك▓رك╗èعذعùعخع»لـ╖ف»┐عâتعâçعâسعذعزعéèع1981ف╣┤ع╛عد12ف╣┤لûôعسµ╕ةعثعخق¤اق¤ثعـعéîعا[249]عé
- 12µ£ê19µùحعفùµح╡ف£░فااكخ│µ╕شلأèع«قشش9µشةك╢èفشلأèµح╡قé╣كز┐µا╗µùàكةîلأèع«لؤزغ╕èك╗èKD60فئïي╝êKD604عKD605عKD606ع«3ف░عéف░µإ╛كث╜غ╜£µëكث╜ي╝ëعîفùµح╡قé╣عسفê░ل¤عآعéï[W 166][W 167][W 168][W 169]عé
- µùحµ£شع«فؤ╜µ░ّق╖ق¤اق¤ثي╝êGNPي╝ëعîغ╕ûقـîقشش2غ╜عسعزعéïعé
- 1969ف╣┤ي╝êµءصفْî44ف╣┤ي╝ë
1969ف╣┤ي╝أµùحق¤ثعâ╗عé╣عéسعéجعâرعéجعâ│GT-RعذعâـعéدعéتعâشعâçعéثZ
- 1970ف╣┤ي╝êµءصفْî45ف╣┤ي╝ë
 عé╣عé║عéصعâ╗عé╕عâبعâïعâ╝ي╝ê1970ف╣┤ي╝ë
عé╣عé║عéصعâ╗عé╕عâبعâïعâ╝ي╝ê1970ف╣┤ي╝ë
- 2µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصعîعé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عذفêف╝غ║ïµحصفحّق┤عéْق╖بق╡عآعéï[W 173][µ│ذ 119]عé
- 3µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê1971ف╣┤7µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 41][W 51]عé
- 4µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«فàذلةفç║ك│çعسعéêعéèغ╕ëك▒كçزفïـك╗èف╖حµحصعîكذصقسïعـعéîعفîف╣┤6µ£êعسغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«كçزفïـك╗èلâذلûع»غ╕ëك▒كçزفïـك╗èعسكص▓µ╕ةعـعéîعéï[250][W 174]عé
- 4µ£êعلê┤µ£ذكçزفïـك╗èعîعé╣عé║عéصعâ╗عé╕عâبعâïعâ╝ي╝êفêإغ╗ثي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[251]عéكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصعïعéëµْجلعùعاعâؤعâ╝عâùكçزفïـك╗èعïعéë4WDك╗èON360ي╝ê1967ف╣┤قآ║فث▓ي╝ëع«كث╜لبµذرعéْكص▓عéèفùعّفكذصكذêعùعاعééع«عدعك╗╜كçزفïـك╗èعزعîعéëعéزعâـعâصعâ╝عâëك╡░كةîعîف»كâ╜عدعف░فؤئعéèعééفêرععôعذعïعéëغ║║µ░ùعذعزعéï[251][W 175]عé
- 7µ£ê9µùحعف╖إف┤لçف╖حµحصقحئµê╕ف╖حفب┤عسعéêعéèقششفعذعéêعاغ╕╕عîف╗║لبعـعéîعéï[W 176][W 177]عéي╝êµùحµ£شفêإع«فجûكêزكçزفïـك╗èف░éق¤ذلïµشكê╣ي╝ë
- 7µ£ê18µùحعµإ▒غ║شلâ╜عدفàëفîûفصخعé╣عâتعââعé░عسعéêعéïكتسف«│عîفêإعéعخفب▒فّèعـعéîعقْ░قè╢غ╕âف╖ق╖أµ▓┐ععسعéعéïفصخµبةعدع«كتسف«│عدعéعثعاعاعéكçزفïـك╗èع«µْµ░ùعéشعé╣عééفافؤبعذعùعخµدقëعسعéعîعéï[W 125]عé
- 6µ£êعغ║جلأف«ëفàذف»╛قصûفا║µ£شµ│ـعîفê╢ف«أعـعéîعéïعé
- 9µ£êعقرفà╖عâةعâ╝عéسعâ╝ع«عâêعâاعâ╝ي╝êف╛îع«عé┐عéسعâرعâêعâاعâ╝ي╝ëعîكçزفïـك╗èقرفà╖ي╝êعâاعâïعéسعâ╝ي╝ëع«عîعâêعâاعéسععéْقآ║فث▓عùععâصعâ│عé░عé╗عâرعâ╝عذعزعéïعé
- 10µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حع«µ£شقج╛ف╖حفب┤عîق¤اق¤ثعâصعâ£عââعâêع«قشش1ف╖عéْف░فàحعآعéï[252]عé
- µùحµ£شعسعèعّعéïغ║جلأغ║ïµـàعسعéêعéïµص╗كàµـ░عî16,765غ║║عذعزعéèعق╡▒كذêعîفدïع╛عثعا1948ف╣┤غ╗حلآعدµ£فجأعذعزعéïي╝êعôع«ف╣┤عéْعâ¤عâ╝عé»عسق┐îف╣┤عïعéëع»غ╕ïلآعéْق╢أعّعéïي╝ë[W 178][W 179]عé
- 1971ف╣┤ي╝êµءصفْî46ف╣┤ي╝ë
- 1972ف╣┤ي╝êµءصفْî47ف╣┤ي╝ë
1972ف╣┤ي╝أعâؤعâ│عâعâ╗عé╖عâôعââعé»CVCCعذCVCCعéذعâ│عé╕عâ│
- 1µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصعîعé╣عâعâسعâ╗عâشعéزعâ╝عâع«عéذعé╣عâعâ╝عâêعâعâ│عس4WDغ╗ـµدءعéْك┐╜فèبعآعéïعéي╝êي╜ؤعéزعâـعâصعâ╝عâëك╗èغ╗حفجûعدع»ي╜إغ╕ûقـîفêإع«فؤؤك╝زلدفïـلçق¤ثك╗èي╝ë
- 4µ£ê17µùحعïعéë20µùحع╛عدعفؤ╜قسïغ║شلâ╜فؤ╜لأؤغ╝ألجذعسعèععخعفؤ╜لأؤكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êFIAي╝ëع«ق╖غ╝أعîµùحµ£شعدفêإعéعخلûïفéشعـعéîعéï[255][µ│ذ 122]عé
- 5µ£ê15µùحعµ▓ûق╕ع«µû╜µ¤┐µذرعîق▒│فؤ╜عïعéëµùحµ£شعسك┐¤لéعـعéîعéïي╝êµ▓ûق╕ك┐¤لéي╝ëعé1978ف╣┤ع╛عدع»لôك╖»غ║جلأع»عéتعâةعâزعéسµû╜µ¤┐غ╕ïعسعéعثعاµآéعذفîعءف│ف┤لأكةîعîق╢صµîعـعéîعéïعé
- 8µ£êعقْ░فتâف║ع«كس«فـµرالûتعدعéعéïغ╕صفج«فàشف«│ف»╛قصûف»ركص░غ╝أعîعîكçزفïـك╗èµْفç║عéشعé╣ع«لـ╖µ£اكذصف«أµû╣قصûععéْµفç║عùععإع«ف╛îع«قْ░فتⵤ┐قصûع«µîçلçإعذعزعéï[W 181]عé
- 10µ£êععâؤعâ│عâعîق▒│فؤ╜ع«عâئعé╣عéصعâ╝µ│ـعزعرع«µْفç║عéشعé╣كخفê╢عسف»╛ف┐£عùعاCivic CVCCعéذعâ│عé╕عâ│عéْقآ║كةذ[W 182][W 183]عéق┐îف╣┤12µ£êعسعé╖عâôعââعé»عسفîعéذعâ│عé╕عâ│عéْقرعéôعبعâتعâçعâسعéْك┐╜فèبعآعéïعé
- µùحµ£شعسعèعّعéïغ╣ùق¤ذك╗èع«غ┐إµ£ëف░µـ░عî1,000غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[W 155]عé
عéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»عذµْعéشعé╣كخفê╢ي╝ê1973ف╣┤ي╜ئي╝ë
قشش1µشةعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ي╝ê1973ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèعµùحµ£شع»عéجعâ│عâـعâشي╝êقïéغ╣▒قëرغ╛ةي╝ëعذغ╕µ│عîفà▒فصءعآعéïقè╢µàïي╝êعé╣عé┐عé░عâـعâشعâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ëعذعزعéèعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»عإع«ف»╛ف┐£عéْغ╜آفعزععـعéîعéï[W 184]عéكçزفïـك╗èµْفç║عéشعé╣ع╕ع«كخفê╢عéْقؤؤعéèك╛╝عéôعبفجدµ░ùµ▒أµاôلء▓µصتµ│ـع«فê╢ف«أي╝ê1968ف╣┤ي╝ëعفàشف«│فؤ╜غ╝أي╝ê1970ف╣┤ي╝ëعقْ░فتâف║قآ║ك╢│ي╝ê1971ف╣┤ي╝ëعéْق╡îعخع1972ف╣┤عسقْ░فتâف║ع»µùحµ£شعدعééعâئعé╣عéصعâ╝µ│ـعسµ║ûعءعاµْفç║عéشعé╣كخفê╢عéْكةîععéêعفïدفّèعùع1978ف╣┤عسع»غ╕ûقـîعدµ£عééف│عùععذكذعéعéîعéïµْفç║عéشعé╣كخفê╢عîفê╢ف«أعـعéîعéïعسكç│عéïي╝êµْفç║عéشعé╣كخفê╢ي╝ë[W 183]عéعôع«µْعéشعé╣كخفê╢ع«ف╝╖فîûعسعéêعéèع1960ف╣┤غ╗ثعسفقج╛عîµèـفàحعùعاعé╣عâإعâ╝عâعâتعâçعâسع»µشةعàعسفد┐عéْµ╢êعùعخعععôعذعسعزعéï[W 185]عé
- 1973ف╣┤ي╝êµءصفْî48ف╣┤ي╝ë
- 1974ف╣┤ي╝êµءصفْî49ف╣┤ي╝ë
- 1975ف╣┤ي╝êµءصفْî50ف╣┤ي╝ë
- 1976ف╣┤ي╝êµءصفْî51ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعك╗╜كçزفïـك╗èع«كخµب╝ع╣ف«أعـعéîعµْµ░ùلçعî550 عغ╗حغ╕ïعسµïةفجدعـعéîعفàذلـ╖عذفàذف╣àع«فê╢لآعééعإعéîعئعéî3.20 mغ╗حغ╕ïع1.40 mغ╗حغ╕ïعسµïةف╝╡عـعéîعéïعé
- 10µ£êعµùحµ£شفêإع«F1عâشعâ╝عé╣عîف»îفثسعé╣عâ¤عâ╝عâëعéخعéدعéجعدلûïفéشعـعéîعéïي╝ê1976ف╣┤F1غ╕ûقـîل╕µëïµذرعéجعâ│عâ╗عé╕عâثعâّعâ│ي╝ë[W 192]عé
- 1977ف╣┤ي╝êµءصفْî52ف╣┤ي╝ë
- 1978ف╣┤ي╝êµءصفْî53ف╣┤ي╝ë
- 4µ£êعµùحµ£شعسك╝╕فàحعـعéîعéïف«îµêك╗èعسكز▓عـعéîعéïلûتقذعî0%عسعزعéï[W 195][W 196]عé
- 5µ£ê20µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع«µ¤╣µصثعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤12µ£ê1µùحعïعéëµû╜كةîعـعéîعéïعéقج╛غ╝أفـلةîفîûعùعخععاµأ┤ك╡░µùعéْف┐╡لبصعسعفà▒فîف▒لآ║كةîقé║ع«قخµصتكخف«أعîفë╡كذصعـعéîعéïعé
- 7µ£ê30µùحعق▒│فؤ╜ق╡▒µ▓╗غ╕ïعدع»ف│ف┤لأكةîعبعثعاµ▓ûق╕ق£îع«لôك╖»عîعك╗èع»ف╖خعغ║║ع»ف│عéْلأعéïعéêعفجëµؤ┤عـعéîعéïعéعôع«فجëµؤ┤ع«غ║ïفëفّذقاحع«عاعéعµ▓ûق╕ق£îعدع»730لïفïـعîف«اµû╜عـعéîعاعé
- 11µ£êعف»îف▒▒ق£îف░قاتلâذف╕éعدµùحµ£شكçزفïـك╗èفأقëرلجذعîكذصقسïعـعéîعéï[µ│ذ 126]عéي╝êكçزفïـك╗èعéْعâعâ╝عâئعسعùعاعééع«عذعùعخµùحµ£شفêإع«فأقëرلجذي╝ë
- لïك╗تفàكذ▒عéْغ┐إµ£ëعآعéïµùحµ£شع«فح│µدع«µـ░عîفêإعéعخ1,000غ╕çغ║║عéْك╢àعêعéï[W 125]عé
- 1979ف╣┤ي╝êµءصفْî54ف╣┤ي╝ë
 عé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêي╝ê1979ف╣┤ي╝ë
عé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêي╝ê1979ف╣┤ي╝ë
- قشش2µشةعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ي╝êen:1979 oil crisisي╝ëعîفدïع╛عéïعéقçâك▓╗ع«كë»عµùحµ£شكث╜ف░فئïك╗èع«ف»╛ق▒│ك╝╕فç║عîغ┐âل▓عـعéîعéïعîععôعéîع»ق▒│فؤ╜عâةعâ╝عéسعâ╝عéْفê║µ┐عآعéïعôعذعسعجعزعîعéï[260][W 51]عé
- 1µ£êععâجعâئعâقآ║فïـµراعîغ║îك╝زكçزفïـك╗èع«ق¤اق¤ثف░µـ░عدلخûغ╜عذعزعثعاعôعذعîفحّµراعذعزعéèعغ║îك╝زكçزفïـك╗èع«فêلçعدعâؤعâ│عâعذعâجعâئعâع«لûôعدHYµêخغ║ëي╝êYHµêخغ║ëي╝ëعذفّ╝ع░عéîعéïك▓رفث▓فêµêخعîفدïع╛عéèع1983ف╣┤لبâع╛عدق╢أععé
- 5µ£êعلê┤µ£ذكçزفïـك╗èعîعé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêي╝êفêإغ╗ثي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéïعéغ╜غ╛ةµب╝ي╝êف«أغ╛ة47غ╕çفي╝ëعدعéعثعاعôعذعسفèبعêعخعفجأعع«ف«╢ف║صعîعé╗عéسعâ│عâëعéسعâ╝عéْµîعجعذععµآéغ╗ثكâîµآ»عسعééفêكç┤عùعفجدعâْعââعâêعéْكذءلî▓عآعéï[261][W 122]عéفîك╗èع»فح│µدعâëعâرعéجعâعâ╝ع«فتùفèبعسعééف»غ╕عùعاعذعـعéîعéï[µ│ذ 127]عéعôع«ك╗èغ╕ةع«عâْعââعâêعسعéêعéèع1980ف╣┤غ╗ثع»ك╗╜كçزفïـك╗èع»ك╗╜عâ£عâ│عâعââعâêعâعâ│ي╝êك╗╜عâ£عâ│عâعâ│ي╝ëعîغ╕╗µ╡عéْفبعéعéïعôعذعسعزعéï[262][µ│ذ 128]عé
- 6µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╗عâëعâزعââعé»ي╝ê5غ╗ثقؤ«ي╝ëعذعé░عâصعâزعéتي╝ê6غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[260]عé2,800 ccعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëعâتعâçعâسعدع»علؤ╗فصفê╢ف╛ةف╝قçâµûآفآ┤ف░كثàق╜«ي╝êECCSي╝ëعéْµةق¤ذعùعغ╕ëفàâكدخفزْع«غ╜┐ق¤ذعéْف»كâ╜عسعآعéï[260]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«عâçعé╕عé┐عâسفê╢ف╛ةعسعéêعéïعéذعâ│عé╕عâ│لؤغ╕صفê╢ف╛ةعé╖عé╣عâعâبي╝µùحµ£شفêإع«ق╖فêقأعزعéذعâ│عé╕عâ│فê╢ف╛ةعé╖عé╣عâعâبي╝ë
- 10µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╗عâëعâزعââعé»ي╝ê5غ╗ثقؤ«ي╝ëعسعé┐عâ╝عâ£عâعâثعâ╝عé╕عâثعâ╝µصك╝ëعâتعâçعâسي╝êL20ETعéذعâ│عé╕عâ│ي╝ëعéْك┐╜فèبعآعéï[264][W 161][µ│ذ 129]عéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«عé┐عâ╝عâ£عâعâثعâ╝عé╕عâثعâ╝µصك╝ëف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 11µ£êععâـعéرعâ╝عâëعîµإ▒µ┤ïف╖حµحصع«µبزف╝ع«25%عéْفûف╛ùعùعك│çµ£شµµ║عéْق╖بق╡عآعéï[W 197][W 198][µ│ذ 130]عé
- 12µ£êععâؤعâ│عâعîعâûعâزعâعéثعââعé╖عâحعâ╗عâشعéجعâرعâ│عâëي╝êف╛îع«عâصعâ╝عâعâ╝عâ╗عé░عâسعâ╝عâùي╝ëعذك│çµ£شµµ║عéْق╖بق╡عùععâؤعâ│عâعîBLقج╛ع«µبزف╝20%عéْعBLقج╛عîعâؤعâ│عâع«كï▒فؤ╜µ│ـغ║║ع«µبزف╝20%عéْفûف╛ùعآعéïي╝ê1994ف╣┤عسكدثµ╢ê[µ│ذ 131]ي╝ë[W 199]عé
- µآéµ£اغ╕µءعµإ▒غ║شلؤ╗µرافجدفصخع«كùجغ╕صµصثµ▓╗عî2ف░ع«كçزك╗تك╗èعéْق╡ع┐فêعéعؤعاعé╜عâ╝عâرعâ╝لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعéْكث╜غ╜£عآعéï[W 200]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«غ╣ùك╗èف»كâ╜عزعé╜عâ╝عâرعâ╝عéسعâ╝ي╝ë
- ق▒│فؤ╜عدكçزفïـك╗èعéتعé╗عé╣عâةعâ│عâêي╝êNCAPي╝ëعîفدïع╛عéïعé
- µùحµ£شعسعèعّعéïغ╣ùق¤ذك╗èع«غ┐إµ£ëف░µـ░عî2,000غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[W 155]عé
ق▒│فؤ╜ق╛ف£░ق¤اق¤ثع«فدïع╛عéèعذعâعâûعâسµآ»µ░ùي╝ê1980ف╣┤ي╜ئي╝ë
µùحµ£شع«كçزفïـك╗èق¤اق¤ثف░µـ░عîفؤ╜فêحعدغ╕ûقـî1غ╜عذعزعéèي╝ê1980ف╣┤ي╝ëعµùحµ£شع»فف«اعذعééعسµè╝عùعééµè╝عـعéîعééعؤعشكçزفïـك╗èفجدفؤ╜عذعزعéïعéغ╕µû╣عق▒│فؤ╜فّعّع«µù║قؤؤعزكçزفïـك╗èك╝╕فç║ع»µùحق▒│ك▓┐µءôµّرµôخع«غ╕فؤبعذع┐عزعـعéîعµùحµ£شع«كçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»ق▒│فؤ╜ق╛ف£░ق¤اق¤ثعسل▓فç║عآعéïعôعذعîغ╕ف»ل┐عذعزعéèع1980ف╣┤غ╗ثع«فàعسفقج╛عîق▒│فؤ╜عدف╖حفب┤عéْµôµحصلûïفدïعآعéïعôعذعسعزعéï[W 196][W 201][µ│ذ 132]عéفؤ╜فàعدع»فح╜ع┐ع«فجأµدءفîûعéفح│µدعâëعâرعéجعâعâ╝ع«فتùفèبعéْفµءبعùعخف╛ôµإحع«عîف░ّفôقذ«فجدلçق¤اق¤ثععïعéëعîفجأفôقذ«ف░ّلçق¤اق¤ثععسقد╗كةîعù[W 125]عفح╜كز┐عزµحصق╕╛عéعâعâûعâسµآ»µ░ùي╝êعâعâûعâسµآéغ╗ثي╝ëعéْكâîµآ»عسفïµدقأعزك╗èغ╕ةعéفجدلخشفèؤع«لسءµدكâ╜ك╗èغ╕ةعîµدءعàعسغ╜£عéëعéîعاعéعâعâûعâسµآ»µ░ùع«ف╜▒لا┐عسعéêعéèع1980ف╣┤غ╗ثف╛îفèع»لسءق┤أعé╗عâعâ│عîغ║║µ░ùعذعزعéèععâعéجعé╜عéسعâ╝ي╝ê1984ف╣┤غ╗حلآي╝ëععé╖عâ╝عâئق╛ك▒ةي╝ê1989ف╣┤ي╝ëعزعرع«عâûعâ╝عâبعîك╡╖عôعéï[µ│ذ 133]عé
- 1980ف╣┤ي╝êµءصفْî55ف╣┤ي╝ë
 عâئعâعâعâ╗عâـعéةعâاعâزعéتي╝ê1980ف╣┤ي╝ë
عâئعâعâعâ╗عâـعéةعâاعâزعéتي╝ê1980ف╣┤ي╝ë
- 1981ف╣┤ي╝êµءصفْî56ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعµشدف╖ئفà▒فîغ╜ôي╝êECي╝ëفد¤فôةغ╝أعسعéêعéèµùحµ£شكث╜غ╣ùق¤ذك╗èع«ك╝╕فàحقؤثكخûفê╢ف║خعîف░فàحعـعéîععâذعâ╝عâصعââعâّع╕ع«ف«îµêك╗èك╝╕فç║عسعééكçزغ╕╗كخفê╢عîفدïع╛عéïي╝ê1999ف╣┤عسµْجف╗âي╝ë[W 207]عé
- 5µ£êععéتعâةعâزعéسفêكةفؤ╜لأفـغ╗ثكةذعâôعâسعâ╗عâûعâصعââعé»ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعذع«ف¤كص░عسعéêعéèلأفـق¤ثµحصق£ع»كçزفïـك╗èع«ف»╛ق▒│ك╝╕فç║عéْ7.7%فëèµ╕ؤعآعéïعôعذعéْكةذµءعùعµùحµ£شع«كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝ع»ق┐îف╣┤عïعéëف»╛ق▒│ك╝╕فç║ع«كçزغ╕╗كخفê╢µئبعéْµ»ف╣┤كذصف«أعآعéïي╝ê1993ف╣┤عسµْجف╗âي╝ë[W 196][W 201]عé
- 7µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîك╝╕فç║عâûعâرعâ│عâëعéْعîNISSANععسق╡▒غ╕عآعéïµû╣لçإعéْقآ║كةذعù[W 208]ععîDATSUNععéْف╗âµصتعآعéïعé
- 8µ£êعلê┤µ£ذكçزفïـك╗èعîعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عذك│çµ£شµحصفïآµµ║عéْق╡ع│ععé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عîلê┤µ£ذكçزفïـك╗èع«قآ║كةîµ╕êع┐µبزف╝ع«ق┤5.3%عéْفûف╛ùعآعéï[W 209]عé
- 9µ£ê22µùحععâؤعâ│عâعîعéذعâشعé»عâêعâصعâ╗عé╕عâثعéجعâصعé▒عâ╝عé┐عéْµصك╝ëعùعاعéتعé│عâ╝عâëي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[W 210][W 211][W 212]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«µ░ّق¤اق¤ذعéسعâ╝عâèعâôعé▓عâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ë
- 11µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصعîعé╣عâعâسعâ╗عâشعéزعâ╝عâي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعس4WDعéزعâ╝عâêعâئعâعââعé»غ╗ـµدءعéْك┐╜فèبعآعéïعéي╝êµùحµ£شفêإع«عéزعâ╝عâêعâئعâعââعé»عâêعâرعâ│عé╣عâاعââعé╖عâدعâ│µصك╝ëفؤؤك╝زلدفïـك╗èي╝ë
- 1982ف╣┤ي╝êµءصفْî57ف╣┤ي╝ë
عâؤعâ│عâع«عâةعéتعâزعé║عâôعâسف╖حفب┤
- 4µ£êعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعîعâّعé╕عéدعâصعéْقآ║فث▓عآعéïعéق┐îف╣┤عïعéëعâّعâز-عâعéسعâ╝عâسعâ╗عâرعâزعâ╝ي╝êلأقد░عîعâّعâزعâعéسعي╝ëعسفéµêخعéْفدïعéعخµ┤╗ك║عùعفîقج╛عéْغ╗ثكةذعآعéïك╗èقذ«عذعùعخقاحعéëعéîعéïعéêععسعزعثعخعععé
- 4µ£êعلê┤µ£ذكçزفïـك╗èعîعéجعâ│عâëع«عâئعâسعâعâ╗عéخعâëعâذعé░ي╝êف╛îع«عâئعâسعâعâ╗عé╣عé║عéصعâ╗عéجعâ│عâçعéثعéتي╝ëعذعéجعâ│عâëعسعèعّعéïعé╣عé║عéصفؤؤك╝زكçزفïـك╗èع«فêف╝ق¤اق¤ثعسعجععخفا║µ£شفêµعùعفîف╣┤10µ£êعسµصثف╝عسفحّق┤عéْق╖بق╡عآعéïعéق┐î1983ف╣┤12µ£êعïعéëعéجعâ│عâëعدفؤؤك╝زكçزفïـك╗èع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéïعé
- 7µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصي╝êعâêعâذعé┐كçزف╖حي╝ëعذعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èك▓رفث▓ي╝êعâêعâذعé┐كçزك▓ري╝ëعîفêغ╜╡عùععîعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععîقآ║ك╢│عآعéïعé
- 8µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâùعâشعâ╝عâزعâ╝عéْقآ║فث▓عآعéï[267]عéعâ»عâ│عâ£عââعé»عé╣ع«µراكâ╜عéْµîعثعاف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعذععµû░عùععé╕عâثعâ│عâسع«فـفôي╝êف╛îع«عâاعâïعâعâ│ي╝ëعبعثعاعîفـق¤ذك╗èع«عéêععزعé╣عé┐عéجعâسع»فùعّفàحعéîعéëعéîعأعفـµحصقأعسع»فج▒µـùعآعéï[267][W 213]عé
- 11µ£ê25µùحععâؤعâ│عâعîعâùعâشعâزعâحعâ╝عâëي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عùعغ╕لâذعé░عâشعâ╝عâëعسعéتعâ│عâعâصعââعé»عâ╗عâûعâشعâ╝عéصعâ╗عé╖عé╣عâعâبي╝êABSي╝ëعéْعéزعâùعé╖عâدعâ│كذصف«أعآعéïعéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«ABSµصك╝ëف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 11µ£êععâؤعâ│عâي╝êعâؤعâ│عâعâ╗عéزعâûعâ╗عéتعâةعâزعéسي╝ëعîعéتعâةعâزعéسفêكةفؤ╜عâ╗عéزعâعéجعéزف╖ئعâةعéتعâزعé║عâôعâسع«ف╖حفب┤عدفؤؤك╝زكçزفïـك╗èي╝êعéتعé│عâ╝عâëي╝ëع«كث╜لبعéْلûïفدïعآعéï[W 214][µ│ذ 134]عéي╝êµùحµ£شع«كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝عذعùعخفêإع«ق▒│فؤ╜ق╛ف£░ق¤اق¤ثي╝ë
- 1983ف╣┤ي╝êµءصفْî58ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êععîك╗èغ╜ôفجûف╛îفآلةععسعجععخع«كخفê╢عîق╖رفْîعـعéîععâـعéدعâ│عâعâ╝عâاعâرعâ╝ع«كثàقإق╛رفïآعîعزععزعéèععâëعéتعâاعâرعâ╝عîكذ▒ف»عـعéîعéïعéفîف╣┤5µ£êعسقآ║فث▓عـعéîعاµùحق¤ثعâ╗عâّعâسعé╡عâ╝عéذعé»عé╡عéْقشش1ف╖عذعùعخعµùحµ£شفؤ╜فàعدك▓رفث▓عـعéîعéïغ╣ùق¤ذك╗èع»غ╗حلآع»عâëعéتعâاعâرعâ╝كثàقإك╗èعîغ╕╗µ╡عذعزعثعخعععé
- عâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâرعîµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإعéعخق┤»كذêق¤اق¤ثف░µـ░1,000غ╕çف░عéْل¤µêعآعéï[W 156]عé
- 1984ف╣┤ي╝êµءصفْî59ف╣┤ي╝ë
- 1985ف╣┤ي╝êµءصفْî60ف╣┤ي╝ë
ععآعéئعâ╗عé╕عéدعâاعâïي╝ê1985ف╣┤ي╝ë
- 5µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعîعé╕عéدعâاعâïي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[269]عéفîقج╛عذعùعخع»117عé»عâ╝عâأغ╗حµإحعذعزعéïف«îفàذقïشكçزكذصكذêع«غ╣ùق¤ذك╗èعد[µ│ذ 135]عف║âفّèµêخقـحعسعééفèؤعîفàحعéîعéëعéîععîكةùع«لèµْâµëïععذلةîعـعéîعاعéسعâ╝عé╣عé┐عâ│عâêعéْق¤ذععاعâعâشعâôCMعîكر▒لةîعذعزعéï[270][W 51][µ│ذ 136]عé
- 8µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╣عéسعéجعâرعéجعâ│ي╝ê7غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عùعغ╕èق┤أعé░عâشعâ╝عâëعدع»فؤؤك╝زµôكê╡عé╖عé╣عâعâبي╝êلؤ╗µ░ùفê╢ف╛ةف╝ي╝ëHICASعéْµصك╝ëعآعéï[269]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«فؤؤك╝زµôكê╡ي╝فàذك╝زµôكê╡عéْµةق¤ذعùعاف╕éك▓رغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë
- 9µ£ê1µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع«µ¤╣µصثعسعéêعéèعلïك╗تف╕صعفèرµëïف╕صعسغ╣ùك╗èعآعéïلأؤع«عé╖عâ╝عâêعâآعâسعâêقإق¤ذعîق╛رفïآعحعّعéëعéîعéïي╝êف╜ôفêإع»لسءلاكçزفïـك╗èلôعذكçزفïـك╗èف░éق¤ذلôع«ع┐ق╛رفïآفîûي╝ëعé
- 9µ£ê22µùحع«عâùعâرعé╢فêµغ╗حلآعµحµ┐عزفلسءعذعزعéèعق┐îف╣┤قدïع╛عدعسعâëعâسع«غ╛ةفجع»ع╗ع╝فèµ╕ؤعùعك╝╕فç║ق¤ثµحصعîفجدععزµëôµْâعéْفùعّعéï[W 125]عé
- 1986ف╣┤ي╝êµءصفْî61ف╣┤ي╝ë
1986ف╣┤ي╝أعéخعéثعâزعéتعâبعé║عâ╗FW11عذعâؤعâ│عâعâ╗RA166Eعéذعâ│عé╕عâ│
- 3µ£êعفîùق▒│ف╕éفب┤عسعèععخعâؤعâ│عâعîلسءق┤أك╗èعâûعâرعâ│عâëعîعéتعéصعâحعâرعع«ف▒ـلûïعéْفدïعéعéï[271]عé
- 5µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذف»îفثسلçف╖حµحصعîق▒│فؤ╜عدفà▒فîق¤اق¤ثعéْكةîعفا║µ£شف¤ف«أعسكز┐ف░عآعéï[W 51]عé
- 7µ£êعكï▒فؤ╜µùحق¤ثكçزفïـك╗èكث╜لبي╝êNMUKي╝ëعîعé╡عâ│عâعâ╝عâرعâ│عâëف╖حفب┤ع«µôµحصعéْفدïعéععâûعâسعâ╝عâعâ╝عâëي╝êµùحµ£شفعîعéزعâ╝عé╣عé┐عâ╝عي╝ëع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[272]عéي╝êµùحµ£شع«كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝عذعùعخفêإع«عâذعâ╝عâصعââعâّق╛ف£░ق¤اق¤ثي╝ë
- عâؤعâ│عâعâ╗RA166Eعéذعâ│عé╕عâ│عéْµصك╝ëعùعاFW11عéْµôعآعéïعéخعéثعâزعéتعâبعé║عîفîف╣┤ع«F1غ╕ûقـîل╕µëïµذرعدعé│عâ│عé╣عâêعâرعé»عé┐عâ╝عé║ي╝êكث╜لبكàي╝ëعé┐عéجعâêعâسعéْق▓ف╛ùعآعéïعéي╝êµùحµ£شكث╜عéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëك╗èعسعéêعéïكث╜لبكàلâذلûع«فؤؤك╝زغ╕ûقـîل╕µëïµذرعé┐عéجعâêعâسفêإق▓ف╛ùي╝ë
- 1987ف╣┤ي╝êµءصفْî62ف╣┤ي╝ë
µùحق¤ثعâ╗Be-1ي╝ê1987ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîBe-1عéْقآ║فث▓عآعéï[273][274]عéعîعâّعéجعé»عéسعâ╝ععذفّ╝ع░عéîعéïعôعذعسعزعéïعé╕عâثعâ│عâسعéْلûïµïôعùععإع«ف╛îع«كçزفïـك╗èع«فجûكخ│ع«عâçعé╢عéجعâ│عسف╜▒لا┐عéْغ╕عêعéïعôعذعسعزعéï[275]عé
- 2µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصعîعé╣عâعâسعâ╗عé╕عâثعé╣عâعéثعسECVTي╝êلؤ╗فصفê╢ف╛ةف╝CVTي╝ëµصك╝ëعâتعâçعâسعéْك┐╜فèبعآعéï[W 220][W 221][W 222]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«CVTµصك╝ëف╕éك▓رغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë
- 4µ£êععâؤعâ│عâعîعâùعâشعâزعâحعâ╝عâëي╝ê3غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عùعفؤؤك╝زµôكê╡عé╖عé╣عâعâبي╝êµراµت░فê╢ف╛ةف╝ي╝ëعéْµصك╝ëعùعاعé░عâشعâ╝عâëعéْكذصف«أعآعéï[276]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«كê╡كدْف┐£فïـفئïفؤؤك╝زµôكê╡عéْµةق¤ذعùعاف╕éك▓رغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë
- 4µ£êععâـعé╕عâعâشعâôعé╕عâدعâ│عسعéêعéïF1ع«فàذµêخµ¤╛لي╝êلî▓ق¤╗µ¤╛لي╝ëعîفدïع╛عéïي╝êعF1عé░عâرعâ│عâùعâزعي╝ëعéµùحµ£شفؤ╜فàعدF1عéْغ╕صف┐âعذعùعخعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣عâإعâ╝عâع«غ║║µ░ùعîلسءع╛عéèي╝êF1عâûعâ╝عâبي╝ëععâعâûعâسµآ»µ░ùعéْكâîµآ»عسكçزفïـك╗èلûتلثغ╝µحصع«عâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣عâإعâ╝عâع╕ع«فéفàحعفؤ╜فàغ╝µحصعسعéêعéïعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣عâإعâ╝عâع╕ع«عé╣عâإعâ│عé╡عâ╝µ┤╗فïـععé╡عâ╝عéصعââعâêف╗║كذصعîµ┤╗قآ║فîûعآعéïي╝êعâعâûعâسف┤رفثèعسعéêعéè1991ف╣┤لبâعسµ▓êلإآفîûي╝ëعé
- 6µ£êععâؤعâ│عâعîعâشعé╕عéدعâ│عâëي╝êفêإغ╗ثي╝ëع«عâئعéجعâèعâ╝عâعéدعâ│عé╕عéْكةîععلïك╗تف╕صعسSRSعéذعéتعâعââعé░ي╝êعé┐عéسعé┐كث╜ي╝ëعéْعéزعâùعé╖عâدعâ│كذصف«أعآعéï[W 223][W 224][µ│ذ 137]عéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«عéذعéتعâعââعé░µصك╝ëف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 9µ£êعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èف╖حµحصعîعâعéجعâبعâرعâ╝عâ╗عâآعâ│عâعذµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢[277]عéعôعéîعسعéêعéèععâعéجعâبعâرعâ╝عâ╗عâآعâ│عâقج╛ع«كçزفïـك╗èع«µùحµ£شفؤ╜فàك▓رفث▓عéْغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعîكسïعّك▓بععôعذعéعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èكث╜فôعéْعâëعéجعâع«عâعéجعâبعâرعâ╝عâ╗عâآعâ│عâقج╛عدق¤اق¤ثعآعéïعôعذعîفûعéèµ▒║عéعéëعéîعéï[277]عé
- 11µ£êعلê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêعذعùعخع»فêإع«F1µùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعîلûïفéشعـعéîعéï[µ│ذ 138]عéعôع«ف╣┤عïعéëµùحµ£شعدع«F1لûïفéشعîف«أقإعùعµ»ف╣┤لûïفéشعـعéîعéïعéêععسعزعéï[µ│ذ 139]عé
- 1988ف╣┤ي╝êµءصفْî63ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╖عâ╝عâئعéْقآ║فث▓عآعéï[278]عéعâçعé╢عéجعâ│µدع«لسءعفجûكخ│عذلسءعفïـفèؤµدكâ╜ع»µîعـعéîع3عâèعâ│عâعâ╝ك╗èعâûعâ╝عâبع«ععثعïعّعذعزعéè[278]ععôع«عâûعâ╝عâبع»عîعé╖عâ╝عâئق╛ك▒ةععذفّ╝ع░عéîعاعé
- 3µ£êعفجدلçكغ╕ع«كّùµؤ╕ععâêعâذعé┐ق¤اق¤ثµû╣ف╝ظـك▒كخµذةع«ق╡îفû╢عéْعéعûعùعخظـعي╝êµùحµ£شكزئقëêع»1978ف╣┤فêèي╝ëع«كï▒كزئقëêعToyota Production System: Beyond Large-Scale Productionععîفêèكةîعـعéîععإع«ف╛îعééµدءعàعزكذكزئعسق┐╗كذ│عـعéîعخغ╕ûقـîغ╕صعسف╜▒لا┐عéْغ╕عê[W 77]عكçزفïـك╗èق¤ثµحصعسعèعّعéïق¤اق¤ثق«ةقµëïµ│ـعسق¤ثµحصعéْك╢àعêعخµ│ذقؤ«عîلؤع╛عéïعéêععسعزعثعخعع[µ│ذ 140]عé
- 4µ£ê10µùحعقشµê╕فجدµرïعîلûïلأعآعéïعéعôعéîعسعéêعéèµ£شف╖ئعذفؤؤفؤ╜عîفêإعéعخلôك╖»عدق╡ع░عéîعéïعé
- 4µ£êعق▒│فؤ╜عدق¤اق¤ثعـعéîعاعâؤعâ│عâعâ╗عéتعé│عâ╝عâëعé»عâ╝عâأعîµùحµ£شعسك╝╕فàحعـعéîك▓رفث▓عîفدïع╛عéï[279]عéي╝êµùحµ£شعâةعâ╝عéسعâ╝ع«µ╡╖فجûق¤اق¤ثك╗èعîك╝╕فàحك▓رفث▓عـعéîعافêإع«غ║ïغ╛ïي╝ë
- 1989ف╣┤ي╝êµءصفْî64ف╣┤ي╝ف╣│µêفàâف╣┤ي╝ë
 عâئعâعâعâ╗MX-5 / عâخعâ╝عâعé╣عâ╗عâصعâ╝عâëعé╣عé┐عâ╝ي╝ê1989ف╣┤ي╝ë
عâئعâعâعâ╗MX-5 / عâخعâ╝عâعé╣عâ╗عâصعâ╝عâëعé╣عé┐عâ╝ي╝ê1989ف╣┤ي╝ë
- 1990ف╣┤ي╝êف╣│µê2ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعك╗╜كçزفïـك╗èع«كخµب╝ع╣ف«أعـعéîعµْµ░ùلçعî660 عغ╗حغ╕ïعسµïةفجدعـعéîعفàذلـ╖ع«فê╢لآعéé3.30 mغ╗حغ╕ïعسµïةف╝╡عـعéîعéïعé
- 3µ£êعµùحµ£شقةق╖أعîGPSعéسعâ╝عâèعâôعé▓عâ╝عé╖عâدعâ│عé╖عé╣عâعâبي╝êGPSعéسعâ╝عâèعâôي╝ëعéْلûïقآ║عآعéï[W 235]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«ك╗èك╝ëق¤ذGPSعéسعâ╝عâèعâôي╝ë
- 3µ£êعكصخف»اف║علâ╡µ¤┐ق£عف╗║كذصق£عسعéêعéèعلôك╖»غ║جلأµâàفب▒لأغ┐ةعé╖عé╣عâعâبلثق╡ةف¤كص░غ╝أي╝êVICSلثق╡ةف¤كص░غ╝أي╝ëعîقآ║ك╢│عآعéïعé
- 3µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîعé╗عâرعéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعاك╗èغ╕ةعذعùعخفêإع«ك╖│عصغ╕èعْف╝عâëعéتµصك╝ëك╗èي╝ë
- 3µ£ê27µùحعفجدك¤╡ق£لèكةîف▒لـ╖عîعîف£اف£░لûتلثكئك│çع«µèّفê╢عسعجععخععéْلأل¤عùعغ╕فïـق¤ثفّعّكئك│çع«ق╖لçكخفê╢عéْكةîععéعôعéîعéْف╝ـعلçّعذعùعخµùحµ£شق╡îµ╕êع»µحµ┐عزµآ»µ░ùف╛îلعسكخïكêئعéعéîعéïي╝êعâعâûعâسف┤رفثèي╝ëعé
- 4µ£êععâئعâعâعîعâخعâ╝عâعé╣عé│عé╣عâتي╝ê4غ╗ثقؤ«عé│عé╣عâتي╝ëعéْقآ║فث▓عùععéزعâùعé╖عâدعâ│عذعùعخGPSعéسعâ╝عâèعâôي╝êغ╕ëك▒لؤ╗µراكث╜ي╝ëعéْكذصف«أعآعéï[W 236][W 237]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«3عâصعâ╝عé┐عâ╝ف╝عâصعâ╝عé┐عâزعâ╝عéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëف╕éك▓رك╗èي╝غ╕ûقـîفêإع«GPSعéسعâ╝عâèعâôµصك╝ëف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 6µ£êععâّعéجعéزعâïعéتعîGPSعéسعâ╝عâèعâôعîعéسعâصعââعâعéدعâزعéتAVIC-1ععéْقآ║فث▓عآعéï[W 237]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«ك╗èك╝ëق¤ذGPSعéسعâ╝عâèعâôفـفôي╝ë
- 7µ£êعلأفـق¤ثµحصق£عîعîكçزفïـك╗èقçâك▓╗µج£كذفد¤فôةغ╝أععéْكذصق╜«عآعéï[281]عé
- 9µ£êععâؤعâ│عâعîNSXعéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êغ╕ûقـîفêإع«عéزعâ╝عâسعéتعâسعâاعâتعâعé│عââعé»ف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 10µ£êععîلê┤µ£ذكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîعé╣عé║عéصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[282]عé
- µùحµ£شفؤ╜فàعسعèعّعéïكçزفïـك╗èع«ق¤اق¤ثف░µـ░عîعôع«ف╣┤1,348غ╕ç6796ف░عذعزعéèععâ¤عâ╝عé»عéْكذءلî▓عآعéï[W 197]عé
- 1991ف╣┤ي╝êف╣│µê3ف╣┤ي╝ë
عâئعâعâعâ╗787Bي╝ê1991ف╣┤ي╝ë
عâعâûعâسف┤رفثèف╛îي╝ê1992ف╣┤ي╜ئي╝ë
عâعâûعâسف┤رفثèعéْµراعسµùحµ£شعدع»ك│╝فàحكàع«فù£فح╜عîفجدععفجëفîûعùععâعâûعâسµ£اعسغ║║µ░ùعéْفأعùعاعé╗عâعâ│عéفجدفئïك╗èعîغ╜ك┐╖عùعخععغ╕µû╣عRVعéعâعâ╝عâزعâ│عé░عâ»عé┤عâ│عذععثعاك╗èقذ«عîغ║║µ░ùعذعزعéèعك╗èغ╕ةعé╡عéجعé║عدعééعé│عâ│عâّعé»عâêعéسعâ╝عéك╗╜كçزفïـك╗èعîفث▓غ╕èعéْغ╝╕ع░عآ[W 240]عéع╛عاععâعâûعâسµ£اعسف╜ôµآéع«لتذµ╜«عذع»لع«µû╣فّعدغ╝ق¤╗عـعéîعاك╗╜عâêعâ╝عâسعâ»عé┤عâ│ي╝êك╗╜عâعéجعâêعâ»عé┤عâ│ي╝ëعéعâاعâïعâعâ│عîعôع«µآéµ£اعسقآ║فث▓عـعéîعخغ║êµâ│فجûع«عâْعââعâêعéْكذءلî▓عùععé╕عâثعâ│عâسعذعùعخµ╡╕لعùعخعععôعذعسعزعéï[W 241]عé
- 1992ف╣┤ي╝êف╣│µê4ف╣┤ي╝ë
 µùحق¤ثعâ╗عâئعâ╝عâي╝ê1992ف╣┤ي╝ë
µùحق¤ثعâ╗عâئعâ╝عâي╝ê1992ف╣┤ي╝ë
- 1993ف╣┤ي╝êف╣│µê5ف╣┤ي╝ë
 عé╣عé║عéصعâ╗عâ»عé┤عâ│Rي╝ê1993ف╣┤ي╝ë
عé╣عé║عéصعâ╗عâ»عé┤عâ│Rي╝ê1993ف╣┤ي╝ë
- 1994ف╣┤ي╝êف╣│µê6ف╣┤ي╝ë
 عâؤعâ│عâعâ╗عéزعâçعââعé╗عéجي╝ê1994ف╣┤ي╝ë
عâؤعâ│عâعâ╗عéزعâçعââعé╗عéجي╝ê1994ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعلôك╖»عâ╗غ║جلأعâ╗ك╗èغ╕ةعéجعâ│عâعâزعé╕عéدعâ│عâêفîûµذل▓ف¤كص░غ╝أي╝êVERTISي╝ëعîكذصقسïعـعéîعلسءف║خلôك╖»غ║جلأعé╖عé╣عâعâبي╝êITSي╝ëع«ف«اق╛عسفّعّعافûعéèق╡ع┐عîفدïع╛عéïعé
- 5µ£ê10µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع╣µصثعâ╗µû╜كةîعـعéîعéïعéفزكë»لïك╗تكàع«فê╢ف║خي╝êعé┤عâ╝عâسعâëفàكذ▒ي╝ëعîفë╡كذصعـعéîعاعé
- 10µ£êععâؤعâ│عâعîعéزعâçعââعé╗عéجي╝êفêإغ╗ثي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéïعéعâاعâïعâعâ│عذعùعخع»ف╛îقآ║عبعثعاعîعµùحµ£شفؤ╜فàعدع»فîقج╛عسعذعثعخعééغ║êµâ│فجûع«عâْعââعâêعذعزعéè[W 213]عغ╗حلآعفîقج╛ع»ك╗èغ╕ةلûïقآ║ك╖»ق╖أعéْفجدععفجëµؤ┤عآعéïعôعذعسعزعéï[283]عé
- 1995ف╣┤ي╝êف╣│µê7ف╣┤ي╝ë
- 4µ£êعفàëف▓ةكçزفïـك╗èع«عé╝عâصعâ»عâ│عîلïك╝╕ق£عسعéêعéïفئïف╝كزف«أعéْفûف╛ùعùعفàëف▓ةكçزفïـك╗èع»فؤ╜فà10قـزقؤ«ع«كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝عذعùعخكزف»عـعéîعéï[W 249]عé
- 5µ£êعلـ╖ف«ëلê┤µ£ذعîعé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêع«ق¤اق¤ثعéْلûïفدïعآعéï[W 245]عéي╝êµùحµ£شع«كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝عذعùعخفêإع«غ╕صفؤ╜ق╛ف£░ق¤اق¤ثي╝ë
- 1996ف╣┤ي╝êف╣│µê8ف╣┤ي╝ë
فêف╛ôلثكةةعذقْ░فتâµèكةôي╝ê1997ف╣┤ي╜ئي╝ë
1998ف╣┤عسعâعéجعâبعâرعâ╝عâ╗عâآعâ│عâعذعé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عîفêغ╜╡عùعغ╕ûقـîقأعزµحصقـîفق╖ذع«µرالïعîلسءع╛عéï[W 252]عéµùحµ£شفؤ╜فàعدع»ف╣┤لûôع«ق¤اق¤ثف░µـ░400غ╕çف░عîقؤ«ف«ëع«عéêععسكزئعéëعéîي╝ê400غ╕çف░عé»عâرعâûي╝ëعفêف╛ôلثكةةع«فïـععîقؤؤعéôعسعزعéïعé
- 1997ف╣┤ي╝êف╣│µê9ف╣┤ي╝ë
 عâêعâذعé┐عâ╗عâùعâزعéخعé╣ي╝ê1997ف╣┤ي╝ë
عâêعâذعé┐عâ╗عâùعâزعéخعé╣ي╝ê1997ف╣┤ي╝ë
- 1998ف╣┤ي╝êف╣│µê12ف╣┤ي╝ë
- 9µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîعâعéجعâعâف╖حµحصع╕ع«فç║ك│çµ»¤قçعéْ34.5%عïعéë51.2%عسلسءعéععâعéجعâعâف╖حµحصع»عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«لثق╡فصغ╝أقج╛عذعزعéï[W 258]عé
- 1µ£êعك╗╜كçزفïـك╗èع«كخµب╝ع╣ف«أعـعéîعفàذلـ╖عذفàذف╣àع«فê╢لآعîعإعéîعئعéî3.40 mغ╗حغ╕ïع1.48 mغ╗حغ╕ïعسµïةف╝╡عـعéîعéïعé
- 11µ£êععâعéجعâبعâرعâ╝عâ╗عâآعâ│عâعذعé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عîفêغ╜╡عùعâعéجعâبعâرعâ╝عé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عîكزـق¤اعآعéïعéعôعéîعسعéêعéèعكçزفïـك╗èµحصقـîع«ك│çµ£شلûتغ┐éع«غ╕ûقـîقأعزفق╖ذعîفدïع╛عéèعف╜▒لا┐عéْفùعّعاµùحµ£شع«كçزفïـك╗èµحصقـîعدعééفق╖ذعîل▓عéعôعذعذعزعéï[W 258]عé
- 1999ف╣┤ي╝êف╣│µê11ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعق╡îفû╢ف▒µراعسلآحعثعاµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâسعâعâ╝عذك│çµ£شµµ║ي╝êعâسعâعâ╝عâ╗µùحق¤ثعéتعâرعéجعéتعâ│عé╣ي╝ëعéْق╡ع│عفîف╣┤5µ£êعسعâسعâعâ╝عîµùحق¤ثكçزفïـك╗èع«µبزف╝36.8%عéْفûف╛ùعùعµùحق¤ثكçزفïـك╗èع»عâسعâعâ╝فéءغ╕ïعدµؤ┤ق¤اعéْفؤ│عéïعôعذعذعزعéï[W 259]عé
- 12µ£êععé╣عé║عéصعذف»îفثسلçف╖حµحصعîµبزف╝ع«µîعةفêععدفêµعآعéï[W 260]عéق┐îف╣┤9µ£êعµصثف╝عسµµ║عآعéï[W 83]عé
- 2000ف╣┤ي╝êف╣│µê12ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èع«عéذعé»عé╣عâعâري╝êفêإغ╗ثي╝ëعîفîùق▒│عéسعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗عé╢عâ╗عéجعâجعâ╝ي╝êعâêعâرعââعé»لâذلûي╝ëعéْفùك│ئعآعéïعéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«فîùق▒│عéسعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗عé╢عâ╗عéجعâجعâ╝فùك│ئي╝ë
- 2µ£ê9µùحعلâ╡µ¤┐ق£عî20غ╕ûق┤عâçعé╢عéجعâ│فêçµëïعé╖عâزعâ╝عé║ي╝êقشش6لؤي╝ëعéْقآ║كةîعùععإع«غ╕صعدعîفؤ╜ق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èلçق¤ثفدïع╛عéïععîعâعâ╝عâئع«ع▓عذعجعسل╕ع░عéîعéïعéي╝êكçزفïـك╗èعéْعâةعéجعâ│عâعâ╝عâئعسعùعاµùحµ£شفêإع«فêçµëï[o 1]ي╝ë
- 3µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîغ┐إµ£ëعùعخععاف»îفثسلçف╖حµحصع«µبزف╝فàذعخعéْعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عسفث▓ف┤عùي╝êفîف╣┤4µ£êع╛عدعسفث▓ف┤ف«îغ║ي╝ë[W 261]عفîف╣┤4µ£êعسف»îفثسلçف╖حµحصعذع«µحصفïآµµ║عéْكدثµ╢êعآعéï[W 83]عé
- 4µ£êعلôك╖»غ║جلأµ│ـع«µ¤╣µصثعسعéêعéèعف╣╝فàعîغ╣ùك╗èعآعéïلأؤع«عé╖عâ╝عâêعâآعâسعâêعذعùعخعâعâثعéجعâسعâëعé╖عâ╝عâêع«غ╜┐ق¤ذعîق╛رفïآعحعّعéëعéîعéïعé
- 7µ£ê6µùحعلïك╝╕ق£ع«قؤثµا╗عدغ╕ëك▒كçزفïـك╗èع«غ╣ùق¤ذك╗èلâذلûعذعâêعâرعââعé»عâ╗عâعé╣لâذلûعسعéêعéïفجدكخµذةعزعâزعé│عâ╝عâسلأبعùعîقآ║كخأعآعéïي╝êغ╕ëك▒عâزعé│عâ╝عâسلأبعùي╝ëعé
- 7µ£ê28µùحعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعîعâعéجعâبعâرعâ╝عé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عïعéëع«فç║ك│çعéْفùعّعéïعذفà▒عسعفîقج╛عذغ╣ùق¤ذك╗èغ║ïµحصعسعèعّعéïفîàµïشقأµµ║فحّق┤عéْق╖بق╡عآعéï[W 262]عé
- 12µ£ê22µùحعµإ▒غ║شلâ╜ع»عîلâ╜µ░ّع«فحف║╖عذف«ëفàذعéْقت║غ┐إعآعéïقْ░فتâعسلûتعآعéïµإةغ╛ïعي╝êلأقد░عîقْ░فتâقت║غ┐إµإةغ╛ïعي╝ëعéْفàشف╕âعùعق┐îف╣┤4µ£ê1µùحعïعéëµû╜كةîعآعéï[W 263]ي╝êµùحµ£شفêإع«عâçعéثعâ╝عé╝عâسك╗èكخفê╢µإةغ╛ïي╝ëعéعôعéîعسعéêعéèلâ╜ع«قْ░فتâكخفê╢عسلرفêعùعزععâçعéثعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èع»µîçف«أف£░فااع«لïكةîعîقخµصتعـعéîعفîµدءع«µإةغ╛ïع»غ╗ûع«ف£░µû╣كçزµ▓╗غ╜ôعدعééفê╢ف«أعـعéîعéïعéêععسعزعéïعé
- 2001ف╣┤ي╝êف╣│µê13ف╣┤ي╝ë
KAZي╝ê2001ف╣┤ي╝ëعذعéذعâزعâ╝عéسي╝ê2004ف╣┤ي╝ë
- 1µ£ê6µùحعغ╕صفج«ق£ف║فق╖ذع«ف«اµû╜عسغ╝┤ععلïك╝╕ق£ع»ف╗║كذصق£عزعرعذق╡▒فêعـعéîفؤ╜ف£اغ║جلأق£عîكذصق╜«عـعéîعéïعé
- 3µ£êعµà╢µçëق╛رفة╛فجدفصخع«µ╕àµ░┤µ╡رقب¤قر╢ف«جعéْغ╕صف┐âعذعùعاق¤ثفصخفà▒فîعé░عâسعâ╝عâùعسعéêعéèلûïقآ║عـعéîعالؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èKAZعîقآ║كةذعـعéîعéï[W 264][W 265]عé2004ف╣┤عسكث╜غ╜£عـعéîعاف╛îق╢آك╗èعéذعâزعâ╝عéسع»فàشلôعدك╡░كةîف»كâ╜عزلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعذعùعخغ╕ûقـîµ£لسءلاف║خي╝êµآéلا370.3 kmي╝ëعéْكذءلî▓عآعéïعé
- 4µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîµùحلçكçزفïـك╗èع╕ع«فç║ك│çµ»¤قçعéْ50.1%عسلسءعéعµùحلçكçزفïـك╗èع»عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«لثق╡فصغ╝أقج╛عذعزعéï[W 266][W 258]عé
- 10µ£ê1µùحعق╛جلخشق£îفجزق¤░ف╕éع«ف»îفثسلçف╖حµحصق╛جلخشكث╜غ╜£µëµ£شف╖حفب┤عîµëف£ذعآعéïغ╕ف╕»عîعîعé╣عâعâسق¤║عي╝êعآع░عéï-عةعéçعي╝ëعسµ¤╣قد░عـعéîعéïعé
- 11µ£ê30µùحعفàذفؤ╜ع«لسءلالôك╖»عدلؤ╗فصµûآلçّففùعé╖عé╣عâعâبي╝êETCي╝ëع«غ╕كêشفêرق¤ذعîفدïع╛عéïعé
- 2002ف╣┤ي╝êف╣│µê14ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èع«عéتعâسعâعéثعâئي╝ê3غ╗ثقؤ«ي╝ëعîفîùق▒│عéسعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗عé╢عâ╗عéجعâجعâ╝عéْفùك│ئعآعéïعéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«فîùق▒│عéسعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗عé╢عâ╗عéجعâجعâ╝ي╜ؤغ╣ùق¤ذك╗èلâذلûي╜إفùك│ئي╝ë
- 5µ£êععé╣عé║عéصعîعâئعâسعâي╜حعéخعâëعâذعé░قج╛ع«لفèµـ░µبزف╝عéْفûف╛ùعùعف«îفàذفصغ╝أقج╛فîûعآعéïعé
- 9µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعîµùحµ£شفؤ╜فàعسعèعّعéïSUVع«كث╜لبعâ╗ك▓رفث▓عïعéëµْجلعùععâêعâرعââعé»عâ╗عâعé╣ف░éµحصعâةعâ╝عéسعâ╝عذعزعéïي╝êµùحµ£شفؤ╜فجûعدع»SUVع«ق╛ف£░ق¤اق¤ثعذك▓رفث▓عéْق╢آق╢أي╝ë[W 37][W 247]عé
- 10µ£êععâؤعâ│عâعîعéتعé│عâ╝عâëي╝ê7غ╗ثقؤ«ي╝ëعسك╗èلافê╢ف╛ةعك╗èلûôك╖إلؤتغ┐إµîعك╗èق╖أق╢صµîع«µراكâ╜عïعéëµدïµêعـعéîعéïلسءلالôك╖»لïك╗تµ¤»µ┤عé╖عé╣عâعâبي╝êHiDSي╝ëعéْعéزعâùعé╖عâدعâ│كذصف«أعآعéï[W 267]عé
- 12µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîFCHVععâؤعâ│عâعîFCXع«عâزعâ╝عé╣ك▓رفث▓عéْفدïعéعéï[W 268]عéي╝êµùحµ£شفêإع«قçâµûآلؤ╗µ▒بف╝ف╕éك▓رك╗èي╝ë
- عâؤعâ│عâعâ╗عâـعéثعââعâêي╝êفêإغ╗ثي╝ëعîك╗èففêحع«فؤ╜فàغ╣ùق¤ذك╗èك▓رفث▓ف░µـ░عدف╣┤لûô1غ╜عذعزعéèع1969ف╣┤عïعéë2001ف╣┤ع╛عد33ف╣┤لûôعسµ╕ةعثعخف╣┤لûô1غ╜عبعثعاعâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâرع»2غ╜عذعزعéï[W 269][W 270][W 271]عé
- 2003ف╣┤ي╝êف╣│µê15ف╣┤ي╝ë
- 2004ف╣┤ي╝êف╣│µê18ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعغ╕ëك▒ع╡عإعع«2ف║خقؤ«ع«عâزعé│عâ╝عâسلأبعùعîقآ║كخأعآعéï[W 276][W 277][µ│ذ 150]عé
- 4µ£êعلôك╖»غ║جلأµ│ـع«µ¤╣µصثي╝ê11µ£ê1µùحµû╜كةîي╝ëعسعéêعéèعلïك╗تغ╕صع«µ║ف╕»لؤ╗كر▒ع«غ╜┐ق¤ذعسق╜░فëçعîكذصعّعéëعéîعéïعé
- 7µ£êعµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أعîكçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝ع«280لخشفèؤكçزغ╕╗كخفê╢عéْµْجف╗âعآعéïعôعذعéْقآ║كةذعآعéï[W 278][W 279]عé
- 9µ£êعفîùµ╡╖لôع«ففïإف£░µû╣عسعèععخقشش1فؤئعâرعâزعâ╝عé╕عâثعâّعâ│عîلûïفéشعـعéîعéïعé
- 10µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذµùحلçكçزفïـك╗èعîغ╕ةقج╛ع«عâعé╣كث╜لبغ║ïµحصعéْق╡▒فêعùعافêف╝غ╝أقج╛عé╕عéدعéجعâ╗عâعé╣عéْكذصقسïعآعéïعé
- 2005ف╣┤ي╝êف╣│µê17ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعîغ┐إµ£ëعآعéïغ╕ëك▒ع╡عإععâêعâرعââعé»عâ╗عâعé╣ع«µ«ïعéèع«µبزف╝فàذعخعéْعâعéجعâبعâرعâ╝عé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عسفث▓ف┤عùعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعذغ╕ëك▒ع╡عإععâêعâرعââعé»عâ╗عâعé╣عذع«لûôعسك│çµ£شلûتغ┐éع»عزععزعéïعé
- 8µ£ê30µùحععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîعإعéîع╛عدµùحµ£شفؤ╜فجûع«ع┐عدف▒ـلûïعùعخععاعîعâشعé»عé╡عé╣ععâûعâرعâ│عâëع«µùحµ£شفؤ╜فàعدع«ف▒ـلûïعéْلûïفدïعآعéï[W 280][W 281]عé
- 10µ£ê5µùحععé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عîµحصق╕╛µéزفîûعسغ╝┤ععغ┐إµ£ëعآعéïف»îفثسلçف╖حµحصع«µبزف╝فàذعخي╝êقآ║كةîµ╕êµبزف╝ع«20%ي╝ëعéْفث▓ف┤عآعéï[W 282]عé
- فîµùحععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîف»îفثسلçف╖حµحصع«قآ║كةîµ╕êµبزف╝ع«8.7%عéْفûف╛ùعùعفîقج╛ع«قصلبصµبزغ╕╗عذعزعéï[W 283][W 284][W 258]عéعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع»ف»îفثسلçف╖حµحصع«ق▒│فؤ╜ف╖حفب┤عسعéسعâبعâزع«ق¤اق¤ثعéْفد¤كذùعآعéïعذفà▒عسعفîقج╛عذعé╣عâإعâ╝عâعâتعâçعâسع«فà▒فîلûïقآ║عéْل▓عéعéïي╝êف╛îع«عâêعâذعé┐عâ╗86عذعé╣عâعâسعâ╗BRZي╝ëعزعرعف¤µحصعéْفدïعéعéï[W 285][W 258]عé
- 11µ£êععâعéجعâبعâرعâ╝عé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عîغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعذع«ك│çµ£شµµ║عéْكدثµ╢êعùعغ┐إµ£ëعآعéïغ╕ëك▒كçزفïـك╗èµبزعéْعé┤عâ╝عâسعâëعâئعâ│عâ╗عé╡عââعé»عé╣عسفث▓ف┤عآعéï[W 286][W 287][W 288]عé
- µùحµ£شع«كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝عسعéêعéïفؤ╜فجûعدع«ق¤اق¤ثف░µـ░عîفêإعéعخف╣┤لûô1,000غ╕çف░عéْك╢àعêعéïعé
- 2006ف╣┤ي╝êف╣│µê20ف╣┤ي╝ë
 عâêعâذعé┐عâ╗عé╗عâ│عâعâحعâزعâ╝عâصعéجعâجعâسي╝ê2006ف╣┤ي╝ë
عâêعâذعé┐عâ╗عé╗عâ│عâعâحعâزعâ╝عâصعéجعâجعâسي╝ê2006ف╣┤ي╝ë
- 3µ£êععé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عîغ┐إµ£ëعآعéïعé╣عé║عéصع«µبزف╝ع«فجدلâذفêعéْفث▓ف┤عùعغ┐إµ£ëقçعéْ20.4%عïعéë3%عسفجëµؤ┤عآعéï[W 209]عé
- 4µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عîك│çµ£شµµ║عéْكدثµ╢êعآعéï[W 289]عé
- 7µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîعé╗عâ│عâعâحعâزعâ╝عâصعéجعâجعâسعéْف╛ةµûآك╗èعذعùعخف««فàف║عسق┤فàحعآعéïعé
- 11µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîك│çµ£شµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê2018ف╣┤8µ£êعسكدثµ╢êي╝ëعéعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîععآعéئكçزفïـك╗èع«قآ║كةîµ╕êµبزف╝ع«8.7%عéْفûف╛ùعùععâçعéثعâ╝عé╝عâسعéذعâ│عé╕عâ│ع«فà▒فîلûïقآ║عéْل▓عéعéï[W 258]عé
- 2007ف╣┤ي╝êف╣│µê19ف╣┤ي╝ë
غ╕ûقـîلçّكئف▒µراغ╗حلآي╝ê2008ف╣┤ي╜ئي╝ë
ظ╗غ╕ûقـîلçّكئف▒µراع«µآéµ£اعدفî║فêçعéïعïع»ف«أكزشعéلأكزشع»عزعععôع«كذءغ║ïعدع»غ╛┐ف«£غ╕èعفî║فêçعéèعéْكذصعّعخععéïعé
- 2008ف╣┤ي╝êف╣│µê20ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êعف░µإ╛كث╜غ╜£µëعîلë▒ف▒▒ق¤ذعâعâ│عâùعâêعâرعââعé»ع«قةغ║║لïكةîعé╖عé╣عâعâبي╝êAHSي╝ëعéْف╕éفب┤عسµèـفàحعآعéïعé
- 6µ£ê1µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع«µ¤╣µصثعسعéêعéèعف╛îلâذف╕صعسغ╣ùك╗èعآعéïلأؤع«عé╖عâ╝عâêعâآعâسعâêقإق¤ذعîق╛رفïآعحعّعéëعéîعéïعé
- 9µ£ê15µùحع«عâزعâ╝عâئعâ│عâ╗عâûعâرعé╢عâ╝عé║ع«ق╡îفû╢قب┤ق╢╗عéْفحّµراعسغ╕ûقـîلçّكئف▒µراعîقآ║ق¤اعآعéïي╝êعâزعâ╝عâئعâ│عâ╗عé╖عâدعââعé»ي╝ëعé
- 11µ£êععé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عîغ┐إµ£ëعآعéïعé╣عé║عéصع«µبزف╝ي╝ê3%ي╝ëعéْفàذعخفث▓ف┤عùع1981ف╣┤عïعéëق╢أععخععاك│çµ£شµµ║عéْكدثµ╢êعآعéï[W 291]عé
- غ╕ûقـîع«عâةعâ╝عéسعâ╝فêحµû░ك╗èك▓رفث▓ف░µـ░عدعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîفêإعéعخف╣┤لûô1غ╜عسعزعéï[W 292]عéفëف╣┤ع╛عد77ف╣┤عسµ╕ةعثعخف╣┤لûô1غ╜عبعثعاعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║ع»عإع«ف║دعéْµءعّµ╕ةعùعا[W 292][µ│ذ 151]عé
- 2009ف╣┤ي╝êف╣│µê21ف╣┤ي╝ë
غ╕ëك▒عâ╗i-MiEVي╝ê2009ف╣┤ي╝ëعذµùحق¤ثعâ╗عâزعâ╝عâـي╝ê2010ف╣┤ي╝ë
- ق▒│فؤ╜عد4µ£êعسعé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝ع6µ£êعسعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║عîقؤ╕µشةععدق╡îفû╢قب┤ق╢╗عآعéïعé
- 7µ£êعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èعîi-MiEVعéْµ│ـغ║║فّعّعسقآ║فث▓عùعق┐îف╣┤4µ£êعïعéëع»فïغ║║فّعّعسعééك▓رفث▓عéْفدïعéعéï[W 253]عéي╝êعâزعâعéخعâبعéجعéزعâ│غ║îµشةلؤ╗µ▒بعéْق¤ذععاك╗èغ╕ةعذعùعخع»غ╕ûقـîفêإع«ف╕éك▓رلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èي╝ë
- 8µ£êعïعéë9µ£êعسعïعّق▒│فؤ╜عدعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«ك╗èغ╕ةع«لïك╗تف╕صعâـعâصعéتعâئعââعâêعéْعéععثعخف«ëفàذµدعéْقûّفـكخûعآعéïفث░عîلسءع╛عéèعق┐îف╣┤عسعïعّعخفجدكخµذةعزعâزعé│عâ╝عâسعéلؤفؤثكذ┤كذاعسقآ║ف▒ـعآعéïي╝êعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«فجدكخµذةعâزعé│عâ╝عâسي╝ëعé
- 12µ£êععé╣عé║عéصعذعâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│AGعîفîàµïشµµ║عùععâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│AGعîعé╣عé║عéصع«قآ║كةîµ╕êع┐µبزف╝ع«19.9%عéْفûف╛ùعآعéïعôعذعدفêµعآعéï[W 293][W 294][W 295]عé
- 2010ف╣┤ي╝êف╣│µê22ف╣┤ي╝ë
- 2µ£êععîµùحق¤ثعâçعéثعâ╝عé╝عâسف╖حµحصععîعîUDعâêعâرعââعé»عé╣ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعé
- 4µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعذعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║ع«فêف╝ف╖حفب┤NUMMIعîلûëلûعـعéîعéï[µ│ذ 152]عé
- 5µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعذعâعé╣عâرعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║ي╝êف╛îع«عâعé╣عâري╝ëعîك│çµ£شµحصفïآµµ║عéْق╖بق╡عùعلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èع«فà▒فîلûïقآ║عدفêµعآعéïي╝ê2017ف╣┤عسكدثµ╢êي╝ë[W 296][W 297]عéعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع»GMعذع«فêف╝ف╖حفب┤عبعثعاNUMMIك╖ةف£░ع«غ╕لâذعéْعâعé╣عâرعسفث▓ف┤عآعéï[W 296][W 297][W 298]عé
- 12µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâزعâ╝عâـي╝êفêإغ╗ثي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[W 299]عé
- 2011ف╣┤ي╝êف╣│µê23ف╣┤ي╝ë
- 9µ£ê12µùحععé╣عé║عéصعîعâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│AGعسف»╛عùعخك│çµ£شµµ║كدثµ╢êع«ق¤│عùفàحعéîعéْكةîععîععâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│AGف┤عسµïْفخعـعéîعéï[W 300][W 301][W 302][µ│ذ 153]عéµ£شغ╗╢ع»فؤ╜لأؤفـµحصغ╝أكص░µëع«فؤ╜لأؤغ╗▓كثكثفêجµëعدغ╗▓كثµëïق╢أععîل▓عéعéëعéî[W 303]ع2015ف╣┤8µ£êعسعé╣عé║عéصع«غ╕╗ف╝╡عîفجدقصïعدكزعéعéëعéîععâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│AGع»عé╣عé║عéصµبزعéْفث▓ف┤عآعéïعéêعفّ╜عءعéëعéîعéïعôعذعذعزعéï[W 304][W 305]عé
- 2012ف╣┤ي╝êف╣│µê24ف╣┤ي╝ë
- 6µ£êععâئعâعâعîRX-8ع«ق¤اق¤ثعéْق╡éغ║عآعéïعéعôعéîعسعéêعéèعé│عé╣عâتعé╣عâإعâ╝عâي╝ê1967ف╣┤ي╝ëعïعéë45ف╣┤عسµ╕ةعثعخق╢أععخععاعâصعâ╝عé┐عâزعâ╝عéذعâ│عé╕عâ│ك╗èع«ق╢آق╢أق¤اق¤ثعîل¤فêçعéîعéï[W 306]عé
- 2013ف╣┤ي╝êف╣│µê25ف╣┤ي╝ë
- 11µ£êععâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│عâ╗عé┤عâسعâـي╝ê7غ╗ثقؤ«ي╝ëعîك╝╕فàحك╗èعذعùعخع»فêإعéعخµùحµ£شعéسعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗عé╢عâ╗عéجعâجعâ╝عسل╕فç║عـعéîعéï[W 156]عé
- عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعé░عâسعâ╝عâùفàذغ╜ôي╝êعâعéجعâعâف╖حµحصعذµùحلçكçزفïـك╗èعéْفسعéي╝ëع«فàذغ╕ûقـîع«ف╣┤لûôق¤اق¤ثف░µـ░عذف╣┤لûôك▓رفث▓ف░µـ░عîعذعééعس1,000غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[W 307][W 308]عé
- 2014ف╣┤ي╝êف╣│µê26ف╣┤ي╝ë
 عâêعâذعé┐عâ╗MIRAIي╝ê2014ف╣┤ي╝ë
عâêعâذعé┐عâ╗MIRAIي╝ê2014ف╣┤ي╝ë
- 2015ف╣┤ي╝êف╣│µê27ف╣┤ي╝ë
- 2016ف╣┤ي╝êف╣│µê28ف╣┤ي╝ë
- 1µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîعâعéجعâعâف╖حµحصعسفàذلةفç║ك│çعùعخفîف╣┤8µ£êغ╗ءعدف«îفàذفصغ╝أقج╛عسعآعéïعôعذعéْقآ║كةذعآعéï[W 314]عé
- 3µ£êعفؤ╜ف£اغ║جلأق£عسعéêعéèك▓╕عùفêçعéèعâعé╣عسعâëعâرعéجعâûعâشعé│عâ╝عâعâ╝عéْكذصق╜«عآعéïعôعذعîق╛رفïآفîûعـعéîعéï[µ│ذ 157]عéق┐î2017ف╣┤عسقآ║ق¤اعùعاµإ▒فلسءلافجسفرخµص╗غ║ةغ║ïµـàع«ف╜▒لا┐عééعéعéèععéعèعéèلïك╗تف»╛قصûعéْقؤ«قأعذعùعخكçزف«╢ق¤ذك╗èعسعééعâëعâرعéجعâûعâشعé│عâ╝عâعâ╝ع«كذصق╜«عîل▓عéعé
- 4µ£êعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èع«قçâك▓╗ف╜كثàعîقآ║كخأعآعéï[W 315][W 316]عé
- فîف╣┤5µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîغ╕ëك▒كçزفïـك╗èع«قآ║كةîµ╕êµبزف╝ع«34%عéْفûف╛ùعùعخقصلبصµبزغ╕╗عذعزعéèعغ╕ëك▒كçزفïـك╗èع»عâسعâعâ╝عâ╗µùحق¤ثعéتعâرعéجعéتعâ│عé╣عسفèبعéعéïي╝êعâسعâعâ╝عâ╗µùحق¤ثعâ╗غ╕ëك▒عéتعâرعéجعéتعâ│عé╣ي╝ëعé
- 8µ£êععé╣عé║عéصعذف»îفثسلçف╖حµحصعîµبزف╝ع«µîعةفêععéْكدثµ╢êعùععèغ║ْعع«غ┐إµ£ëµبزف╝عéْفàذعخفث▓ف┤عآعéï[W 317][W 318]عé
- 8µ£ê24µùحعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╗عâشعâèي╝ê5غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عùععâùعâصعâّعéجعâصعââعâêعéْعéزعâùعé╖عâدعâ│كذصف«أعآعéïعéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«كçزفïـلïك╗تك╗èعâشعâآعâس2ي╜ؤلâذفêكçزفïـلïك╗تي╜إكزف«أف╕éك▓رك╗èي╝ë
- 16ف╝µرافïـµêخلùءك╗èعîفê╢ف╝µةق¤ذعـعéîعéïعéي╝êµùحµ£شعدقïشكçزلûïقآ║عـعéîعافêإع«كثàك╝زµêخك╗è[µ│ذ 158]ي╝ë
- 2017ف╣┤ي╝êف╣│µê29ف╣┤ي╝ë
عâؤعâ│عâعâ╗عé╣عâ╝عâّعâ╝عéسعâûع«كث╜لبف░µـ░ع«µذقد╗ي╝ê1958ف╣┤ - 2017ف╣┤ي╝ë
- 4µ£ê1µùحععîف»îفثسلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµبزف╝غ╝أقج╛SUBARUععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعé
- 8µ£êععâئعâعâعذعâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعîك│çµ£شµµ║عسفêµعùعفîف╣┤10µ£êعسµبزف╝ع«µîفêععéْفدïعéعéï[W 319]عé
- 10µ£êععâؤعâ│عâعâ╗عé╣عâ╝عâّعâ╝عéسعâûعé╖عâزعâ╝عé║ع«ق┤»كذêكث╜لبف░µـ░عî1فف░عسل¤عآعéï[W 135]عé
- 2018ف╣┤ي╝êف╣│µê30ف╣┤ي╝ë
- 2019ف╣┤ي╝êف╣│µê31ف╣┤ي╝غ╗جفْîفàâف╣┤ي╝ë
µû░فئïعé│عâصعâèعéخعéجعâسعé╣µاµاôقùçع«µ╡كةîي╝ê2020ف╣┤ي╜ئي╝ë
ظ╗µû░فئïعé│عâصعâèع«µآéµ£اعدفî║فêçعéïعïع»ف«أكزشعéلأكزشع»عزعععôع«كذءغ║ïعدع»غ╛┐ف«£غ╕èعفî║فêçعéèعéْكذصعّعخععéïعé
- 2020ف╣┤ي╝êغ╗جفْî2ف╣┤ي╝ë
- 2021ف╣┤ي╝êغ╗جفْî3ف╣┤ي╝ë
- 2022ف╣┤ي╝êغ╗جفْî4ف╣┤ي╝ë
- 2023ف╣┤ي╝êغ╗جفْî5ف╣┤ي╝ë
- 5µ£ê30µùحعµùحلçكçزفïـك╗èعذغ╕ëك▒ع╡عإععâêعâرعââعé»عâ╗عâعé╣عî2024ف╣┤µ£سع╛عدعéْقؤ«ل¤عسق╡îفû╢ق╡▒فêعآعéïعذعععôعذعدعكخزغ╝أقج╛ع«عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èععâعéجعâبعâرعâ╝عâ╗عâêعâرعââعé»عéْفسعéعا4قج╛عîفا║µ£شفêµعùعاعôعذعéْقآ║كةذعآعéï[W 347]عé
- 12µ£ê20µùحع4µ£êعسعâعéجعâعâعîفàشكةذعùعخععاكزكذ╝ق¤│كسïع«غ╕µصثكةîقé║عسعجععخعقششغ╕ëكàفد¤فôةغ╝أعîفîقج╛ع«غ╕µصثعéْقت║كزعùعاكز┐µا╗ق╡µئ£عéْفàشكةذعùعا[W 348]عéعôعéîعسعéêعéèعفîقج╛ع«فàذك╗èقذ«ي╝êغ╗ûقج╛ع╕ع«OEMك╗èغ╕ةعééفسعéي╝ëعîفç║ك╖ف£µصتعذعزعثعا[W 348]عéي╝êعâعéجعâعâف╖حµحصكزكذ╝كرخلذôغ╕µصثفـلةîي╝ë
- 2024ف╣┤ي╝êغ╗جفْî6ف╣┤ي╝ë
- 6µ£ê3µùحععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èعµ£شق¤░µèقب¤ف╖حµحصععâئعâعâععé╣عé║عéصععâجعâئعâقآ║فïـµراع«5قج╛ع»عµû░ك╗èعسف»╛عآعéïكزكذ╝كرخلذôعدغ╕µصثعزق¤│كسïعîكةîعéعéîعخععاعôعذعéْفàشكةذعéف╛îµùحعفؤ╜ف£اغ║جلأق£عîفقج╛ع╕قسïعةفàحعéèكز┐µا╗عéْكةîعثعاعé
- 12µ£ê23µùحعµ£شق¤░µèقب¤ف╖حµحصعµùحق¤ثكçزفïـك╗èع«2قج╛عîعق╡îفû╢ق╡▒فêعسفّعّعافا║µ£شفêµµؤ╕عéْق╖بق╡عùعاعذقآ║كةذعآعéï[W 349]عéµùحق¤ثكçزفïـك╗èفéءغ╕ïع«غ╕ëك▒كçزفïـك╗èف╖حµحصعéْفسعéعا3قج╛عدعف¤µحصعسعجععخف¤كص░عéْل▓عéعéïكخأµؤ╕عîق╖بق╡عـعéîعéï[W 350]عé
كأµ│ذ
- µêخفëع«µؤ╕ق▒ع»µùدفصùغ╜ôعدµؤ╕عïعéîعخععéïعîعف╜ôكذءغ║ïعدع»µû░فصùغ╜ôعسقؤ┤عùعخكذءك╝ëعùعخععéïعé
- µêخفëع«غ║ïµاي╝êقë╣عسµءµ▓╗µ£اع«غ║ïµاي╝ëع»µêخف╛îع«كز┐µا╗قب¤قر╢عدلأكزشي╝êف«أكزشي╝ëعîكخعثعاغ╛ïعééعéعéïعاعéعفç║فà╕ع»µêخفëع«عééع«عذµêخف╛îع«µû░عùععééع«عéْف»كâ╜عزق»فؤ▓عدلçعصعخغ╗ءعùعخععéïعé
- µùحµ£شعسعèعّعéïكçزفïـك╗èع«µص┤ف▓قب¤قر╢ع»ي╝êكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أعسعéêعéïعµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐ععéْغ╛ïفجûعذعùعخي╝ëق╡ق╣¤قأعزكز┐µا╗عîكرخع┐عéëعéîعخععزعïعثعاعاعéعقë╣عسعإع«ل╗µءµ£اي╝ê#كçزفïـك╗èع«غ╝إµإحي╝ê1890ف╣┤غ╗ثي╜ئي╝ëي╝ëعسعجععخع»كشعéكجçµـ░ع«قـ░كزشعîعéعéïعôعذعîفجأع[284][W 10]عéف▓µûآع«قآ║µءعسعéêعéèلأكزشي╝êغ╕╗عسµêخفëع«ف░╛ف┤µصثغ╣àعذµا│ق¤░كسْغ╕ëعîغ╕╗ف╝╡عùعاكزشععééعùعع»µêخف╛îع«عµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐ععسعéêعéèµآ«فèعùعاكزشي╝ëعîفجëعéعثعاعéèعµؤûµءدعبعثعالâذفêعîµءقت║عسعزعثعاعéèعùعاغ╛ïعîف░ّعزععزععاعéععإععùعاعé▒عâ╝عé╣عسعجععخع»لأف╕╕ع«µ│ذلçêعدع»عزععî#ف«أكزشع«فجëفîûععسع╛عذعéعاعé
- 19غ╕ûق┤µ£سي╝ê1900ف╣┤ع╛عدي╝ëع«ك╗èغ╕ةعسعجععخع»فصءف£ذعùعخععاعôعذعîقت║ف«اعزك╗èغ╕ةعسعجععخع«ع┐كذءك╝ëعùعف«اف£ذعîغ╕قت║عïعزك╗èغ╕ةعسعجععخع»كذءك╝ëعùعزععé
- µ│ـف╛ïعéµإةق┤ع«µ¤╣µصثعµêخغ║ëعéµآ»µ░ùفجëفïـعزعرعغ╕كêشقأعزغ║ïµاعسعجععخعééكçزفïـك╗èلûتلثعسف╜▒لا┐ع«عéعéïعééع«ع»كذءك╝ëعùعخععéïعé
كذءك╝ëعâسعâ╝عâس
عزعéïع╣عقë╣قصµدع«عéعéïغ║ïµاعسق╡ئعثعخكذءك╝ëعùعخععéïعéعإع«عاعéعغ╗حغ╕ïع«عâسعâ╝عâسعéْكذصعّعخععéïعé
- كçزفïـك╗èغ╝أقج╛عذعùعخفë╡µحصعùعافب┤فêعéْلآجععخعفقج╛ع«فë╡µحصعسعجععخع»كذءك╝ëعؤعأعكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسفéفàحعùعاµآéقé╣عïعéëكذءك╝ëعùعخععéïعé
- كرخغ╜£ك╗èع»كرخغ╜£ك╗èعإع«عééع«عéكرخغ╜£عùعاعôعذكçزغ╜ôعسقë╣قصµدعîعéعéïفب┤فêعéْلآجععخكذءك╝ëعùعزععé
- كçزفïـك╗èغ╝أقج╛ع«فقد░ع«فجëل╖عسعجععخع»عزعéïع╣عكذءك╝ëعùعخععéïعé
µ│ذلçê
- ف«أكزشع«فجëفîûعسعجععخ
- ^ µùحµ£شعسµ£فêإعسµîعةك╛╝ع╛عéîعاكçزفïـك╗èي╝êغ║îك╝زك╗èعéْلآجعي╝ëع»عïعجعخع»كس╕كزشعéعéèعغ╗حفëع»1900ف╣┤ع«قأçفجزفصقî«ق┤ك╗èعé1900ف╣┤4µ£êع«عâصعé│عâتعâôعâسعزعرغ╗ûع«ك╗èغ╕ةعîعإعéîعبعذعـعéîعخععاعôعذعééعéعéïعéكر│ق┤░ع»عîµùحµ£شع╕ع«كçزفïـك╗èع«µ╕ةµإحععéْفéقàدعé
- ^ 1900ف╣┤عâصعé│عâتعâôعâسكزشعسقسïكأعùعخععîµùحµ£شفêإع«كçزف«╢ق¤ذك╗èعع»ف╖إق¤░ل╛فëعîعî1901ف╣┤9µ£êععسك│╝فàحعùعاعâصعé│عâتعâôعâسعذععع«عîلأكزشعبعثعاعî[27]ع1990ف╣┤غ╗ثع╛عدع«كز┐µا╗عâ╗قب¤قر╢عدع1900ف╣┤عâصعé│عâتعâôعâسكزشع»فخف«أعـعéîعخععéïي╝êكر│ق┤░ع»عîµùحµ£شع╕ع«كçزفïـك╗èع«µ╕ةµإحععéْفéقàدي╝ëعéعإع«عاعéعف╖إق¤░عîفîك╗èعéْك│╝فàحعùعاµآéµ£اعééعâصعé│عâتعâôعâسقج╛ع«كèإفثف║ùعîلûïف║ùعùعاعî1902ف╣┤6µ£êغ╗حلآعي╝êµصثقت║عزµآéµ£اع»غ╕µءي╝ëعسفجëµؤ┤عـعéîعخععéï[W 8]عé
- ^ عكçزفïـك╗èغ╕ëفف╣┤ف▓عي╝ê1944ف╣┤ي╝ëعدع»1902ف╣┤1µ£êعذعùعخععéï[35]عé
- ^ غ╝أقج╛كذصقسïعذµإ▒غ║شكèإفثلآ│فêùµëع«لûïكذصع»فîµآéعبعذعـعéîعخععاعî[44]ع2عâ╢µ£êع«لûïععîعéعثعاعôعذعî2000ف╣┤غ╗ثع╛عدع«كز┐µا╗عدفêجµء[45]عé
- ^ فç║فôعـعéîعاك╗èغ╕ةعسعجععخع»كز┐µا╗عذقب¤قر╢ع«ل▓ف▒ـعسعéêعéïقـ░فîعîفجأععéع╛عأعéف░╛ف┤µصثغ╣àعîعµùحµ£شكçزفïـك╗èقآ║ل¤ف▓عي╝ê1937ف╣┤فêèي╝ëعدعâûعâسعéخعâسفàف╝افـغ╝أعسعéêعéïعâêعâشعâëف╖1ف░ععéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣عâ╗عéذعâ│عâëعâ╗عâéعâحعâسعâéفـغ╝أع«عâعâ│عâعâ╝كçزفïـك╗è1ف░ع«كذê2ف░عذكذءك╝ëعùعا[51]عéعµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐عقشش1ف╖╗ي╝ê1965ف╣┤ي╝ëع»عإعéîعéْغ┐«µصثعùععâصعé│عâتعâôعâسقج╛ع«عâصعé│عâتعâôعâسكْ╕µ░ùكçزفïـك╗è1ف░ععâûعâسعéخعâسفàف╝افـغ╝أع«عâêعâشعâëكْ╕µ░ùكçزفïـك╗è1ف░ععéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣عâ╗عéذعâ│عâëعâ╗عâéعâحعâسعâéفـغ╝أع«عâعâ│عâعâ╝كçزفïـك╗è1ف░ع«كذê3ف░عذكذءك╝ëعùعا[52]عéعـعéëعس1977ف╣┤عسفجدلبêك│فْîق╛عîف╜ôµآéع«ك│çµûآع«فàïµءعزكز┐µا╗عéْفا║عسعإعéîعéëعسفكذ╝عéْفèبعê[W 10]ععôعéîعéْفحّµراعسµج£كذ╝عîل▓ع┐ععâصعé│عâتعâôعâسقج╛عسعéêعéïعâصعé│عâتعâôعâسكْ╕µ░ùكçزفïـك╗è4ف░ععâûعâسعéخعâسفàف╝افـغ╝أعسعéêعéïعéزعâ╝عâسعé║عâتعâôعâسي╝êعéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗èي╝ë1ف░ععéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣عâ╗عéتعâ│عâëعâ╗عé╕عâدعâ╝عé╕فـغ╝أع«عâêعâشعâëكْ╕µ░ùكçزفïـك╗è1ف░عفîعءععéخعéدعâعâزعâ╝لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗è1ف░عذعععكذê8ف░ع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èي╝êغ╗ûعسعéزعâ╝عâêعâعéجعî3ف░ي╝ëعîفç║فôعـعéîعخععاعذµذµ╕شعـعéîعخععéïي╝ê2013ف╣┤µآéقé╣ي╝ë[53]عé
- ^ عµùحµ£شكçزفïـك╗èقآ║ل¤ف▓عي╝ê1937ف╣┤ي╝ëعدع»عî1903ف╣┤عع«عîف▓ةف▒▒ق£îععذعزعثعخععاعî[16]ععكçزفïـك╗èµùحµ£شف▓ غ╕èعي╝ê1955ف╣┤ي╝ëعدع»عî1903ف╣┤11µ£êعع«عîµؤقاحق£îععذعزعثعخععéï[61]عéق╛ف£ذع»غ┐«µصثعـعéîعخععéïعé
- ^ عîكçزفïـك╗èقذعع«فë╡كذصع»1906ف╣┤عïعéëع«فجدلءزف║£عé1907ف╣┤عïعéëع«µإ▒غ║شف║£عîµ£فêإع«غ╛ïعذعـعéîعخععاعîعµûçقî«كز┐µا╗عسعéêعثعخق╛ف£ذع»ففجف▒ïف╕éع«غ╛ïعîµ£فêإع«كçزفïـك╗èقذعذعـعéîعخععéï[W 9]عéعكçزفïـك╗èµùحµ£شف▓ غ╕èعي╝ê1955ف╣┤ي╝ëع«ف╣┤كةذعدع»ع1902ف╣┤عسµإ▒غ║شف║£عîعîكçزفïـك╗èقذععéْكذصف«أعùعكçزك╗تك╗èعذفîµدءعسف╣┤لة3فعéْكز▓عùعاعذعéعéïعî[61]ععôعéîع»كçزك╗تك╗èقذعéْكçزفïـك╗èعسµ┤ق¤ذعùعاعééع«عدعéعéèعقïشقسïعùعاعîكçزفïـك╗èقذععذعùعخع«فë╡كذصع»µإ▒غ║شف║£ع»غ╗ûع«ف║£ق£îعéêعéèلàعïعثعا[W 9]عé
- ^ a b c d e عôع«كذءغ║ïع»غ╜عൣذقâêعîعµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓Iعي╝ê2004ف╣┤ي╝ëعذعµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓IIعي╝ê2005ف╣┤ي╝ëعدكذءعùعاكزشعسµ▓┐عثعخكذءك┐░عùعخععéïعاعéععé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝ê1907ف╣┤ي╝ëعسكç│عéïغ╗حفëع«µ╡عéîعîعµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐عقشش1ف╖╗ي╝ê1965ف╣┤ي╝ëغ╗حفëعسغ┐ةعءعéëعéîعخععاكزشي╝êف╛ôµإحكزشي╝ëعذقـ░عزعéïعéف╛ôµإحكزشعذع»غ╕╗عسغ╗حغ╕ïع«قé╣عîقـ░عزعéïي╝أفëق¤░ق£افجزلâع«µ╕ةق▒│µآéµ£اي╝êف╛ôµإحكزشعدع»1902ف╣┤[285][286][30]عéغ╜عൣذكزشعدع»1904ف╣┤ي╝ëعفëق¤░عذعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعذع«لûتعéعéèي╝êف╛ôµإحكزشعدع»µإ╛غ║ـµ░ّµ▓╗لâعïعéëفëق¤░عسكص▓µ╕ةعـعéîعéزعâ╝عâêعâتعâôعâسفـغ╝أعسµ¤╣ق╡[72]عéغ╜عൣذكزشعدع»قةلûتغ┐é[74]ي╝ëععâـعéرعâ╝عâëك╗èعîµ£فêإعسك╝╕فàحعـعéîعاµآéµ£اي╝êف╛ôµإحكزشع»1903ف╣┤[16]عééعùعع»1902ف╣┤[75]عéغ╜عൣذكزشعدع»1905ف╣┤5µ£êي╝ëعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëع«µêعéèقسïعةعذكذصقسïµآéµ£اي╝êف╛ôµإحكزشعدع»عâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعîعîعéزعâ╝عâêعâتعâôعâسفـغ╝أعععîفîك╝زفـغ╝أععسفجëل╖عùعاµ£سعس1904ف╣┤[287][288][289]عééعùعع»1906ف╣┤[290]عسكذصقسïعéغ╜عൣذكزشعدع»فذغ╗كخزقïع«غ╛إلب╝عéْفùعّعافëق¤░عî1906ف╣┤11µ£êعسفîك╝زفـغ╝أكçزفïـك╗èلâذعéْكدثµـثعùعخµû░عاعسكذصقسïي╝ëعفذغ╗كخزقïعîفëق¤░عسفؤ╜ق¤ثك╗èع«كث╜لبعéْغ╛إلب╝عùعاµآéµ£اي╝êف╛ôµإحكزشعدع»1905ف╣┤فش[16][291]عééعùعع»1906ف╣┤µءح[W 18]عéغ╜عൣذكزشعدع»1906ف╣┤11µ£êي╝ëععé┐عé»عâزعâ╝ف╖ع«ف«îµêµآéµ£اي╝êف╛ôµإحكزشعدع»1907ف╣┤4µ£êي╜ؤµءحي╜إ[292][293][294][295]عéغ╜عൣذكزشعدع»ك╗èعذعùعخع»1907ف╣┤9µ£êعسف«îµêعكخزقïع╕ع«قî«غ╕èع»فîف╣┤11µ£êµ£س[79]ي╝ëعéغ╜عൣذع«كزشع»1900ف╣┤غ╗ثف╜ôµآéع«قذلûتعéµû░كئقصëع«كذءلî▓ع«كز┐µا╗عسفا║عحععاعééع«عدعفîµآéغ╗ثع«غ╗ûع«قب¤قر╢كàعééقـ░كسûع»ف¤▒عêعخعèعéëعأععإع«ف╛îعééقب¤قر╢كàعïعéëع«µë╣فêجي╝êغ┐«µصثي╝ëعîعزععاعéععôع«كذءغ║ïعدع»عـعùعéعاعéèع«فا║µ║ûعذعùعخععéïعé
- ^ ف╛ôµإحع»2فا║ع«عéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│ي╝ê12لخشفèؤعذ18لخشفèؤي╝ëعéْµîعةف╕░عثعاعذعـعéîعخععاعé
- ^ عôع«ك╗èغ╕ةع«فصءف£ذعîقاحعéëعéîعéïعéêععسعزعثعاع«ع»كث╜غ╜£عـعéîعخعïعéë30ف╣┤ع╗عرق╡îعثعاف╛îعدعéعéè[71]ععإع«عاعéعµءصفْîفêإعéلبâع╛عدع»فؤ╜ق¤ثقشش1ف╖ك╗èع»عé┐عé»عâزعâ╝ف╖عبعذغ╕كêشقأعسع»µإعéعéîعخععاعé1933ف╣┤عسفàف│╢لçغ╕ëعîكّùµؤ╕عكçزفïـك╗èع«ف▓ةف▒▒عي╝êفëق¤░µؤ╕ف║ùي╝ëع«غ╕صعدق┤╣غ╗ïعùعفêèكةîعïعéë4ف╣┤ع╗عرف╛îعسعإعéîعéْكزصعéôعبكçزفïـك╗èف▓قب¤قر╢ف«╢ع«ف░╛ف┤µصثغ╣àعîµاµ┐عù[71]عكçزكّùعµùحµ£شكçزفïـك╗èقآ║ل¤ف▓عي╝ê1937ف╣┤فêèي╝ë[51]عزعرعدق▒ف┐âعسقآ║كةذعùعاعôعذعدعإع«فصءف£ذعîف║âعقاحعéëعéîعéïعéêععسعزعéèعلأكزشعé鵤╣عéعéëعéîعاعé
- ^ ف░╛ف┤µصثغ╣àع«كّùµؤ╕عéµا│ق¤░كسْغ╕ëع«عكçزفïـك╗èغ╕ëفف╣┤ف▓عي╝ê1944ف╣┤فêèي╝ë[72]عسعéêعéïµêخفëعïعéëع«ف╛ôµإحكزشعدع»ععâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أع»µإ╛غ║ـµ░ّµ▓╗لâعïعéëفëق¤░عسكص▓µ╕ةعـعéîعéزعâ╝عâêعâتعâôعâسفـغ╝أعسµ¤╣ق╡عذعـعéîعخععاعîععµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐عي╝ê1965ف╣┤فêèي╝ëعسعéêعثعخفخف«أعـعéîع1903ف╣┤عسعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أع«µ«ïفôعéْكص▓µ╕ةعـعéîعاµئùف╣│فجزلâعîµùحµ£شكçزفïـك╗èفـغ╝أعéْكذصقسïعùعق┐îف╣┤عسعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أع»كدثµـثعùعاعذعùعخععéï[73]عéغ╜عൣذقâêعîعµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓Iعي╝ê2004ف╣┤ي╝ëعدعإعéîعéْ1ف╣┤كزجف╖«عîعéعéïعذعùعخغ┐«µصثعùعخععéï[74]عé
- ^ ف╛ôµإحع»1903ف╣┤1µ£ê[16][75][76]عذععع«عîلأكزشعبعثعاعîعكثغ╗ءعّعéïك│çµûآعîفصءف£ذعؤعأفخف«أعـعéîعخععéïي╝ê1903ف╣┤كزشع»فàف▒▒عîف║دكسçغ╝أعدفؤئلةدعùعخكزئعثعاكسçكر▒عسفا║عحععخععéï[W 14]ي╝ëعé1903ف╣┤عسكزف»ق¤│كسïعîعـعéîعخععéïعôعذع»قت║كزعـعéîعخععéïعî[W 14][77]عفîك╖»ق╖أع«لûïلأµآéµ£اعسعجععخع»µû░كئكذءغ║ïعزعرعدكثغ╗ءعّعîعéعéï1905ف╣┤2µ£êعîµ£ëفèؤعذعزعثعخععéï[6][W 14]عé
- ^ فàف▒▒لدْغ╣ïفèرع«كسçكر▒عسفا║عحععخعîعé┐عéجعâجغ╗حفجûع»فàذلâذفؤ╜ق¤ثفôععذكâعêعéëعéîعخععاعî[88][89]ععµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓ف║دكسçغ╝أكذءلî▓لؤعي╝ê1973ف╣┤فêèعéف║دكسçغ╝أع»1957ف╣┤4µ£ê5µùحلûïفéشي╝ëعدف╜ôµآéع«لûتغ┐éكàعاعةعîعôعéîعسقûّق╛رعéْفّêعùعخععاعôعذعîµءعéëعïعسعزعéèعغ╗حلآع»عéذعâ│عé╕عâ│عéعâêعâرعâ│عé╣عâاعââعé╖عâدعâ│علؤ╗µ░ùق│╗ق╡▒ععé┐عéجعâجعزعرع«غ╕╗كخلâذفôع»ك╝╕فàحفôعبعثعاعذع┐عزعـعéîعéïعéêععسعزعéè[78]ععîق┤¤فؤ╜ق¤ثععذع»فّ╝ع░عéîعزععزعثعخععéïعé
- ^ عµùحµ£شكçزفïـك╗èقآ║ل¤ف▓ µءµ▓╗ق»çعي╝ê1937ف╣┤فêèي╝ëعéعµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐عقشش1ف╖╗ي╝ê1965ف╣┤فêèي╝ëعدع»عî1911ف╣┤6µ£êععذعùعخععا[103][104]عé
- ^ عµùحµ£شكçزفïـك╗èقآ║ل¤ف▓ µءµ▓╗ق»çعي╝ê1937ف╣┤فêèي╝ëعدع»ف«îµêع»عî1911ف╣┤5µ£êععذعùعخععéï[103][16]عéفîعءكّùكàي╝êف░╛ف┤µصثغ╣àي╝ëع«عµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓عي╝ê1942ف╣┤ي╝ëعدع»عكرخغ╜£ك╗èع«كرخلïك╗تعîف»كâ╜عسعزعثعاع«ع»5µ£êعدكرخغ╜£ك╗èع«قششغ╕µشةف«îµêع»فîف╣┤7µ£êعذعùعخععéï[109][110]عéعµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصف▓قذ┐عقشش1ف╖╗ي╝ê1965ف╣┤ي╝ëعدع»فجدلءزعïعéëµإ▒غ║شع╛عدع«كرخك╡░عîكةîعéعéîعاع«ع»عî1911ف╣┤10µ£êعي╝ê18µùح[107]ي╝ëعذعزعثعخععéï[93]عéعµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓عي╝ê2004ف╣┤ي╝ëعدعééف«îµêع»عî1911ف╣┤7µ£êععذعزعثعخععéïعî[6]عفîعءكّùكàي╝êغ╜عൣذقâêي╝ëعسعéêعéïعµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓IIعي╝ê2005ف╣┤ي╝ëعدع»ف«îµêµآéµ£اع»عî1911ف╣┤10µ£êعي╝êكرخك╡░عééفîµ£êي╝ëعسغ┐«µصثعـعéîعخععéïي╝ê1912ف╣┤3µ£êقآ║كةîع«عفجغ╗èغ║ïقëرك╡╖µ║ععسفا║عحععخععéïي╝ë[108]عé
- ^ 8µ£ê5µùحعïعéëفû╢µحصلûïفدïعùعاعذعـعéîعخععاعî[111]عك┐ّف╣┤ع«µؤ╕ق▒عدع»فû╢µحصلûïفدïع»8µ£ê15µùحعïعéëعذكذءك╝ëعـعéîعخععéï[6]عé
- µ│ذلçê
فç║فà╕
- فç║قëêقëر
- عéخعéدعâûعé╡عéجعâê
- عإع«غ╗û
- ^ a b c d e f عâêعâذعé┐فأقëرلجذعâ╗عé»عâسعâئµûçفîûك│çµûآف«جف▒ـقج║
فéكâك│çµûآ
- µؤ╕ق▒
- ف«أµ£افêèكةîقëر / عâبعââعé»
- عكçزفïـك╗èع
- عقشش1ف╖╗ قشش2ف╖عµùحµ£شكçزفïـك╗èف╢µح╜لâذع1913ف╣┤1µ£ê15µùحعéNDLJP:1508125عé
- عقشش1ف╖╗ قشش3ف╖عµùحµ£شكçزفïـك╗èف╢µح╜لâذع1913ف╣┤2µ£ê15µùحعéNDLJP:1508126عé
- ععéزعâ╝عâêعé╣عâإعâ╝عâعي╝êNCID AA11437582ي╝ë
- ع1971ف╣┤12/15ف╖ي╝êNo.83ي╝ëعغ╕ëµبµؤ╕µê┐ع1972ف╣┤6µ£ê15µùحعéASB:AST19711215عé
- ع1972ف╣┤6/15ف╖ي╝êNo.95ي╝ëعغ╕ëµبµؤ╕µê┐ع1972ف╣┤6µ£ê15µùحعéASB:AST19720615عé
- ع1972ف╣┤11/1ف╖ي╝êNo.104ي╝ëعغ╕ëµبµؤ╕µê┐ع1972ف╣┤11µ£ê1µùحعéASB:AST19721101عé
- عكçزفïـك╗èعذعإع«غ╕ûقـîعي╝êNCID AN00092039ي╝ëفف╖غ╕صع«كذءغ║ï
- ل╜èكùجغ┐èف╜خعîعâآعâ╝عâسعéْك▒ععبف╣╗ع«قششغ╕ف╖ك╗èععكçزفïـك╗èعذعإع«غ╕ûقـîعقشش222ف╖ععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع1987ف╣┤3µ£ê20µùحع30-35لبعé
- عF1ف╢µح╜لâذع
- ع1994 Vol.7 عâïعââعâإعâ│ع«F1عفîكّëقج╛عêفîكّëقج╛عâبعââعé»عëع1994ف╣┤11µ£ê18µùحعéASIN 4575462373عé
- ععâêعâذعé┐فأقëرلجذعبعéêعéèع / عT-TIMEعي╝êلجذعبعéêعéèعéتعâ╝عéسعéجعâûعé╣ي╝ëفف╖غ╕صع«كذءغ║ï
- ععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعي╝êNCID AA11202137ي╝ëفف╖غ╕صع«كذءغ║ï
- كح┐ف╖إقذ¤عîفجدµصثكçزفâك╗èف▓كâي╜ئكçزفïـك╗èع«فùف«╣لقذïعسعèعّعéïغ║║عàع«µكصءفجëفîûعسعجععخي╜ئعععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.4ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع1998ف╣┤1µ£ê30µùحع11-19لبعé
- لê┤µ£ذف┐بلôعî100ف╣┤فëع«كçزفïـك╗èف▒ـعéْµî»عéèك┐¤عثعخي╜ئµùحµ£شفêإµ╕ةµإحع«كçزفïـك╗èعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسكâي╜ئعععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.5ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع1999ف╣┤2µ£ê20µùحع41-48لبعé
- لê┤µ£ذف┐بلôعîفآعـعéîعاµءµ▓╗ع«µùحµ£شع«كçزفïـك╗èي╝ê2ي╝ëي╜ئعéتعâةعâزعéسµ£فجع«كçزفïـك╗èلؤّكزîعîعâؤعâ╝عâبعâشعé╣عâ╗عéذعéجعé╕ععسكذءلî▓عـعéîعال╗µءµ£اع«µùحµ£شع«كçزفïـك╗èغ║ïµâàي╜ئعععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.6ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2000ف╣┤2µ£ê28µùحع27-31لبعé
- لê┤µ£ذف┐بلôعîفآعـعéîعاµءµ▓╗ع«µùحµ£شع«كçزفïـك╗èي╝ê4ي╝ëي╜ئ1900ف╣┤عâصعé│عâتعâôعâسكزشع«µج£كذ╝ي╜ئعععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.8ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2002ف╣┤2µ£ê28µùحع16-29لبعé
- كح┐ف╖إقذ¤عîكçزفïـك╗èعذكè╕كâ╜ظ¤µصîكêئغ╝عك╜كزئعµ╝سµëعزعرعسقآ╗فب┤عآعéïعé»عâسعâئعاعةعععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.10ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2004ف╣┤3µ£ê1µùحع63-90لبعé
- كح┐ف╖إقذ¤عîµû░كئكذءغ║ïعïعéëكزصعéفجدµصثكçزفïـك╗èف▓عععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.15ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2009ف╣┤2µ£ê28µùحع1-38لبعé
- كح┐ف╖إقذ¤عîكشؤµ╝¤لî▓عîكçزفïـك╗èلبغ╣ùغ╝أ100فّذف╣┤عسف»عؤعخععععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.16ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2010ف╣┤2µ£ê28µùحع79-92لبعé
- كح┐ف╖إقذ¤عîفجدµصثµآéغ╗ثع«عغ╕صفج«فàشكسûععسكخïعéïكçزفïـك╗èلûتلثكذءغ║ïعععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.17ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2011ف╣┤2µ£ê28µùحع9-21لبعé
- كح┐ف╖إقذ¤عîعîقشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعذكçزفïـك╗èععععâêعâذعé┐فأقëرلجذق┤كخعNo.19ععâêعâذعé┐فأقëرلجذع2013ف╣┤2µ£ê28µùحع1-8لبعé
- ععâêعâذعé┐فأقëرلجذف╣┤فب▒ع
- عOld-timerعفف╖غ╕صع«كذءغ║ï
- ف▓رقسïفû£غ╣àلؤعîك╜عéْعاعرعéï(18) µêخفëكçزفïـك╗èقس╢ك╡░ف▓-1 ك┐╜µâ│عéزعâ╝عâêعâعéجقس╢ك╡░غ╝أععOld-timerعقشش69ف╖عفàسلçµ┤▓فç║قëêع2003ف╣┤4µ£ê1µùحع166-171لبعé
- ف▓رقسïفû£غ╣àلؤعîك╜عéْعاعرعéï(19) µêخفëكçزفïـك╗èقس╢ك╡░ف▓-2 فجأق¤░فحك¤╡ع«ك╢│ك╖ةععOld-timerعقشش70ف╖عفàسلçµ┤▓فç║قëêع2003ف╣┤6µ£ê1µùحع166-173لبعé
- عµءµ▓╗µإّلأغ┐ةع
- ع1990ف╣┤4µ£êي╝ê238ي╝ëعفأقëرلجذµءµ▓╗µإّع1990ف╣┤4µ£ê18µùحعé
- ع1990ف╣┤5µ£êي╝ê239ي╝ëعفأقëرلجذµءµ▓╗µإّع1990ف╣┤5µ£êعé
لûتلثلبàقؤ«
فجûلâذعâزعâ│عé»
- كçزفïـك╗èعسلûتعآعéïف╣┤كةذ
- Gazoo.com (عéêععéعïعéïكçزفïـك╗èµص┤ف▓لجذ)
- كçزفïـك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝ي╝êغ║îك╝ز/فؤؤك╝زي╝ëعسعéêعéïف╣┤كةذ
- كçزفïـك╗èلûتلثفؤثغ╜ôعسعéêعéïف╣┤كةذ